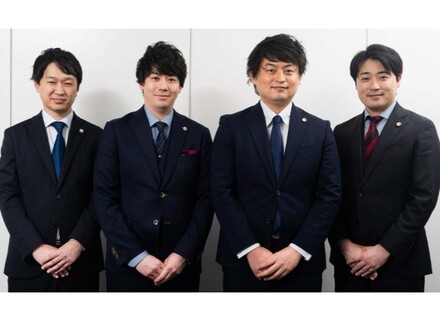交通事故の診断書に書かれた日数の意味とは?診断書の種類や作成期間の目安も解説

交通事故に遭ったら、医療機関で作成される診断書を作成してもらうことが大切です。
診断書には治療期間の目安が記載されていますが、治療日数について以下のような不安を感じる方は多いでしょう。
- 「交通事故後の治療は診断書に記載の日数しか受けられないの?」
- 「交通事故の治療に通っているけど、治療はいつまで受けられる?」
また、「全治2週間」などの記載が損害賠償や今後の手続きにどんな影響があるのか、不安に思う方も少なくありません。
本記事では、交通事故に遭ったときにもらうべき診断書の3つの種類や、発行される診断書に書かれた日数の意味、作成までの期間についてなどを解説します。
交通事故の診断書に書かれた日数の意味とは?
診断書には、治療期間として「全治2週間」「加療2週間を要する」などと書かれることほとんどです。
これは、実際の治療期間ではなく治療の見込み期間であり、記載の日数以上は治療を受けられないという意味ではありません。
診断書に記載されている日数よりも、実際の治療の日数のほうが多い場合、加害者側の任意保険会社から受け取れる損害賠償金が少なくなるのではないかと不安になる方も少なくありません。
しかし、診断書の治療期間は、あくまでも医師が大まかな診断結果を証明しているものです。
記載された日数よりも長く治療を受けても問題はなく、受け取れる損害賠償金は実際の治療期間から算定されるため心配はありません。
交通事故の診断書に「2週間程度」と書かれることが多い理由
交通事故に遭ったときに必要な診断書は、主に3種類あります。
- 警察へ提出する診断書
- 加害者側の任意保険会社に提出する診断書
- 後遺障害等級認定のために提出する診断書
それぞれ書式は異なりますが、警察へ提出する診断書については書式が決まっているわけではありません。
そのため、病院やクリニックごとに独自に用意されているものを提出することになります。
病院やクリニックごとの診断書には、治療期間の目安として「約2週間の治療を要する見込みである」と記載されたり、2週間後の日付が記載され「◯月◯日まで治療見込み」と書かれたりします。
なお、この期間は目安であるため、実際の治療期間ではありません。
交通事故の場合、医療機関は治療の見込み期間を「2週間」にすることがほとんどです。
これは、治療見込み期間が長いほど加害者の違反点数が高くなるためです。
被害者のための診断書ではありますが、加害者側への配慮も欠かすことはできません。
加害者にも守られるべき人権がありますし、実際よりも長く記載してしまい、加害者に免許停止などの処分が科されてしまうと、医療機関と加害者側で法的なトラブルに発展しかねないからです。
受け取れることができる損害賠償金は、実際の治療期間から算定されます。
診断書に「2週間」と書かれていても気にせず、必要な治療を受けましょう。
交通事故の診断書の中で日数が書かれている部分
交通事故に遭ったら、警察へ提出する診断書・加害者側の任意保険会社に提出する診断書が必要です。
また、後遺障害が残る場合には、後遺障害等級認定のために提出する診断書も必要になります。
ここでは、それぞれの診断書の目的と、治療期間の日数が書かれている部分について解説します。
1.警察提出用の診断書の場合
交通事故に遭ったら、事故処理を担当した警察署に医療機関で発行された診断書を提出しなければなりません。
これは、人身事故として処理してもらうためです。
義務ではありませんが、提出がなされなければ警察が事故の捜査をスムーズに進めることができません。
捜査への協力として速やかに提出することが求められます。
また、被害者として十分な補償を得るためにも、警察への診断書提出は重要です。
診断書が提出されなければ、物損事故として処理されてしまいます。
物損事故と人身事故では、受け取れる賠償金や慰謝料の請求可否などが大きく異なるのです。
たとえば、自賠責保険は物損事故では適用されませんが、人身事故なら上限額までは適用されます。
また、物損事故の場合は加害者に慰謝料を請求することは基本的に難しいでしょう。
しかし、人身事故なら慰謝料請求も可能です。
さらに、損害の証拠を証明しなければならない場合、証拠の証明責任は物損事故では被害者側にありますが、人身事故なら加害者側が証明しなければなりません。
治療期間の日数が書かれている部分
警察へ提出する診断書は書式が決まってないため、医療機関ごとに用意されているものを使用します。
多くの場合「診断書」という表題の下に患者の氏名や病名が書かれ、その下に症状や治療期間の目安が3行〜5行程度で書かれる形式です。
日数については、文章の冒頭や文章内に「約2週間の治療を要する見込みである」「◯月◯日まで治療見込み」などと書かれます。
2.自賠責様式の診断書の場合
自賠責様式の診断書は、適切な損害賠償金を請求するために必要な書類です。
自賠責保険請求用の診断書に書かれている内容によって、加害者側の任意保険会社から受け取れる損害賠償の内容が決まるため、非常に重要な書類といえます。
自賠責保険請求用の診断書は書式が決まっています。
しかし、病院に備え付けていない場合が多いので、保険会社から取り寄せなければなりません。
窓口に連絡してみましょう。
治療期間の日数が書かれている部分
自賠責様式の診断書では、「診断書」という表題の下に患者の氏名・住所・性別・生年月日が書かれています。
そのすぐ下に「傷病名」と「治療開始日」が書かれ、同じ行に「治ゆまたは治ゆ見込日」を記載する欄があります。
自賠責様式の診断書には、そのほかにも症状の経過などを詳しく書く欄があり、受傷部位を示すための人体のイラストなども掲載されています。
3.後遺障害診断書の場合
後遺障害診断書は、後遺障害等級を受けるために必要な書類です。
後遺障害等級を受けなければ、後遺障害についての適切な損害賠償を請求することができません。
後遺障害診断書には、残ってしまった後遺症についての症状などを医師が記載します。
医師のみが作成でき、整骨院の柔道整復師などには作成できません。
そのため、事故によって後遺症が残る不安がある場合は、必ず病院やクリニックに通院しましょう。
後遺障害診断書の作成費用は医療機関により5,000円〜1万円程度です。
大きな病院では数万円程度かかるところもあります。
なお、後遺障害診断書の作成費用も、後遺障害が認定されれば保険会社に請求することができます。
治療期間の日数が書かれている部分
後遺障害診断書は、様式が決まっています。
「自動車損害賠償責任保険後遺障害診断書」という表題の下に、患者の氏名・性別・年齢・生年月日・住所・職業・受傷日時・症状固定日が書かれます。
そのすぐ下に「当院入院期間」と「当院通院期間」の欄が設け荒れています。
ここに治療期間の目安日数が書かれています。
交通事故の診断書に書かれた日数に関するよくある誤解
交通事故の診断書に書かれている日数については、「それ以上通院できない」「記載されている日数しか治療費などを受け取れない」と考えている方が多いです。
しかし、それは誤解です。
以下では、診断書に記載された日数に関するよくある誤解を紹介します。
1.「診断書に書かれた日数しか通院できない」は間違い
交通事故の診断書には、一般的に「全治2週間」などと日数が記載されています。
しかし、この日数はその期間しか治療を受けられないという意味ではありません。
診断書に書かれた日数は、治療にかかるだいたいの日数を示すための目安です。
その期間内しか治療を受けられないわけではないのです。
そのため、診断書に書かれている日数を過ぎたからといって、治療をやめる必要はありません。
医師が通院の必要がないと実際に判断するまで、きちんと通院して治療を続けましょう。
2.「診断書に書かれた日数しか治療費・慰謝料が支払われない」は間違い
診断書の治療期間は、あくまでも目安です。
それは相手側の任意保険会社も理解しています。
そのため、日数を過ぎて通院した治療費や慰謝料が支払われなくなるということはありません。
診断書の日数と実際の治療日数が違っていても、損害賠償の金額は実際の治療期間から算定されるので安心してください。
ただし、診断書に記載されている治療期間は参考にされます。
記載期間が過ぎたタイミングで相手側の任意保険会社から治療費の打ち切りを告げられることは少なくありません。
その場合は同意をせずに、治療を続けなければいけないことを伝えましょう。
もしも、治療が必要であるにも関わらず継続して支払いができないと言われてしまったら、医師や弁護士に相談してください。
交通事故の診断書の作成にかかる日数の目安
診断書は、必ずしも即日で受け取れるものではありません。
医療機関によって作成にかかる期間は異なります。
警察への提出用などの簡易なものであれば当日作成してくれるケースも少なくありませんが、後遺障害等級認定で使用するものは記入項目が多いため、2週間〜3週間程度かかるのが通常です。
診断書が必要になる日が決まっているときは、期限を伝えておきましょう。
さいごに|交通事故の診断書に関する疑問点や不安は弁護士に相談を!
交通事故における診断書には、治療の見込み日数が記載されていますが、その日数はあくまで目安です。
損害賠償額は、実際の治療期間に基づいて算出がなされるのが通常です。
しかし、診断書の内容によっては十分な損害賠償がもらえないなどの影響のおそれがあります。
交通事故における損害賠償請求について、診断書を含めて不安や疑問がある方は弁護士に相談することをおすすめします。
医師は診察や治療のプロであり、損害賠償請求や後遺障害等級認定の専門家ではありません。
そのため、医師だけの判断では法的な解決が十分にできない可能性があります。
最適な治療を受けてきちんと賠償してもらえるよう、ぜひ弁護士を頼ってください。
交通事故における法的手続きに精通した弁護士を探すなら「ベンナビ交通事故」の活用がおすすめです。
ベンナビ交通事故には、実績豊富な弁護士を抱える法律事務所が多数登録しており、住んでいる地域や相談内容を指定して信頼できる弁護士を探すことができます。
初回無料で受け付けている法律事務所も多いので、迷わず相談してください。
弁護士に相談するかお悩みの方へ
下のボタンからあなた当てはまるものを選んで悩みを解消しましょう。
弁護士費用特約があれば 実質0円で依頼できます!

多くの保険会社では、被害者1名につき最大300万円までの弁護士費用を負担してくれます。特約があるか分からない方でも、お気軽にご相談ください。弁護士と一緒にご確認した上で依頼の有無を決めて頂けます。
特約を利用して弁護士に相談する交通事故問題を依頼する弁護士の選び方にはポイントがあります。
- 過去の解決事例を確認する
- 料金体系が明確である弁護士を選ぶ
- 交通事故問題が得意な弁護士から選ぶ
等です。
詳しくは以下の記事を読んで、正しい弁護士の選び方を理解した上で弁護士に相談しましょう。
弁護士の選び方について詳しくみる
【元警察官(警部補)弁護士が経験を活かした交渉を】「怪我で通院している」「御家族が交通事故で亡くなった」など【LINE、WEB、電話で完結】【相談料無料】【着手金0円/365日対応】
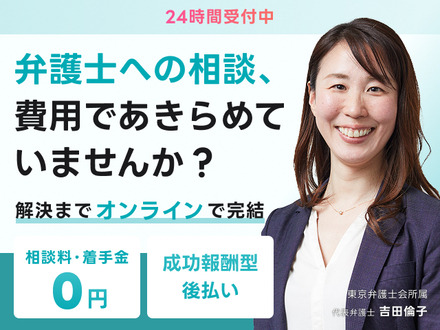
相談料・着手金0円、費用倒れの心配なし。大手より低価格な料金体系で増額実績多数。交通事故専門チームが後遺障害認定から交渉まで強力サポート。LINE完結・来所不要で全国対応。
事務所詳細を見る当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡

治療の受け方・入通院慰謝料に関する新着コラム
-
交通事故後の通院は、最後まで継続しなければ症状が悪化してしまうおそれがあるほか、適切な補償を受け取れなくなるリスクがあります。そのため、原則としては医師と相談の...
-
交通事故で通院することになったものの、病院の治療方法や医師との相性が合わないと感じている方もいるのではないでしょうか。医療機関に通っている方のうち転院を検討して...
-
交通事故に遭ったら、医療機関で作成される診断書を作成してもらうことが大切です。本記事では、交通事故に遭ったときにもらうべき診断書の3つの種類や、発行される診断書...
-
交通事故で体にダメージを受けた場合、遅くとも2~3日以内には病院へ行くべきです。極端に遅くなると、症状と交通事故との因果関係を疑われ、慰謝料請求が難しくなるリス...
-
「人身にすると手続きが面倒になる」という思いから、診断書を出さないでおこうかな?と考えている人は少なくありません。本記事では、交通事故に遭った際に診断書を提出し...
-
本記事では、交通事故後の通院やめるタイミングを知りたい方に向けて、やめるタイミングに関する基礎知識、症状別の通院をやめるタイミング、自己判断で通院をやめるべきで...
-
交通事故による怪我の治療でリハビリ通院する場合、慰謝料算出においてリハビリ期間は考慮されるのでしょうか?この記事では、リハビリ通院する際の慰謝料に関する知ってお...
-
この記事では交通事故の慰謝料に通院日数の少なさが与える影響を中心に解説しています。通院日数の少なさは入通院慰謝料と後遺障害慰謝料に影響を与えます。 この記事を...
-
この記事では交通事故での入通院慰謝料算出の際、ギプス固定期間や骨折の程度に関する考慮についての具体的な考え方について解説します。 この記事を読んで骨折した際の...
治療の受け方・入通院慰謝料に関する人気コラム
-
「人身にすると手続きが面倒になる」という思いから、診断書を出さないでおこうかな?と考えている人は少なくありません。本記事では、交通事故に遭った際に診断書を提出し...
-
交通事故に遭ったら、医療機関で作成される診断書を作成してもらうことが大切です。本記事では、交通事故に遭ったときにもらうべき診断書の3つの種類や、発行される診断書...
-
交通事故で体にダメージを受けた場合、遅くとも2~3日以内には病院へ行くべきです。極端に遅くなると、症状と交通事故との因果関係を疑われ、慰謝料請求が難しくなるリス...
-
交通事故後の通院は、最後まで継続しなければ症状が悪化してしまうおそれがあるほか、適切な補償を受け取れなくなるリスクがあります。そのため、原則としては医師と相談の...
-
本記事では、交通事故後の通院やめるタイミングを知りたい方に向けて、やめるタイミングに関する基礎知識、症状別の通院をやめるタイミング、自己判断で通院をやめるべきで...
-
この記事では交通事故での入通院慰謝料算出の際、ギプス固定期間や骨折の程度に関する考慮についての具体的な考え方について解説します。 この記事を読んで骨折した際の...
-
交通事故で通院することになったものの、病院の治療方法や医師との相性が合わないと感じている方もいるのではないでしょうか。医療機関に通っている方のうち転院を検討して...
-
交通事故による怪我の治療でリハビリ通院する場合、慰謝料算出においてリハビリ期間は考慮されるのでしょうか?この記事では、リハビリ通院する際の慰謝料に関する知ってお...
-
この記事では交通事故の慰謝料に通院日数の少なさが与える影響を中心に解説しています。通院日数の少なさは入通院慰謝料と後遺障害慰謝料に影響を与えます。 この記事を...
治療の受け方・入通院慰謝料の関連コラム
-
交通事故後の通院は、最後まで継続しなければ症状が悪化してしまうおそれがあるほか、適切な補償を受け取れなくなるリスクがあります。そのため、原則としては医師と相談の...
-
交通事故による怪我の治療でリハビリ通院する場合、慰謝料算出においてリハビリ期間は考慮されるのでしょうか?この記事では、リハビリ通院する際の慰謝料に関する知ってお...
-
「人身にすると手続きが面倒になる」という思いから、診断書を出さないでおこうかな?と考えている人は少なくありません。本記事では、交通事故に遭った際に診断書を提出し...
-
この記事では交通事故での入通院慰謝料算出の際、ギプス固定期間や骨折の程度に関する考慮についての具体的な考え方について解説します。 この記事を読んで骨折した際の...
-
交通事故に遭ったら、医療機関で作成される診断書を作成してもらうことが大切です。本記事では、交通事故に遭ったときにもらうべき診断書の3つの種類や、発行される診断書...
-
本記事では、交通事故後の通院やめるタイミングを知りたい方に向けて、やめるタイミングに関する基礎知識、症状別の通院をやめるタイミング、自己判断で通院をやめるべきで...
-
交通事故で体にダメージを受けた場合、遅くとも2~3日以内には病院へ行くべきです。極端に遅くなると、症状と交通事故との因果関係を疑われ、慰謝料請求が難しくなるリス...
-
この記事では交通事故の慰謝料に通院日数の少なさが与える影響を中心に解説しています。通院日数の少なさは入通院慰謝料と後遺障害慰謝料に影響を与えます。 この記事を...
-
交通事故で通院することになったものの、病院の治療方法や医師との相性が合わないと感じている方もいるのではないでしょうか。医療機関に通っている方のうち転院を検討して...
治療の受け方・入通院慰謝料コラム一覧へ戻る


























 慰謝料・損害賠償
慰謝料・損害賠償
 示談
示談
 過失割合
過失割合
 死亡事故
死亡事故
 後遺障害
後遺障害
 むちうち
むちうち
 自転車事故
自転車事故
 自動車事故
自動車事故
 人身事故
人身事故
 バイク事故
バイク事故