- 交通事故の慰謝料がいくら貰えるか不安…
- 慰謝料をできるだけ多くもらいたい!
- 慰謝料の計算方法が難しくて分からない…
そんな方にオススメなのが、ベンナビ交通事故の『慰謝料計算ツール』です。
【実際の利用画面】

適切な慰謝料額を簡単に計算できる上、近くの弁護士を探してくれるので、事故の被害にあって困っている方にぴったりのサービスなんです。
交通事故で損をしないためにも、まずは適正な慰謝料を調べてみましょう。
\弁護士にも相談できる!/
今すぐ適正な慰謝料を調べてみる▶

交通事故で被害者が亡くなった場合、加害者に対して死亡慰謝料を請求することができます。
被害者の命はお金では代え難いものがありますが、せめて加害者から適正な補償を得るためにも慰謝料請求・損害賠償請求の手続きを進めましょう。
交通事故の死亡慰謝料には3種類の計算基準があり、どの計算基準を用いるのかによって金額が大きく変動します。
自力で慰謝料請求することも可能ですが、適切に対応できるか不安な場合は弁護士への依頼を検討しましょう。
本記事では、交通事故の死亡慰謝料の相場や計算方法、慰謝料が増額されるケース・減額されるケース、慰謝料請求の流れや弁護士に依頼するメリットなどを解説します。
死亡慰謝料とは、交通事故で被害者が死亡したことにより受けた精神的苦痛への補償のことです。
死亡事故が発生した場合、被害者遺族は加害者に対して死亡慰謝料を請求することができます。
死亡慰謝料は「被害者本人の慰謝料」と「被害者遺族固有の慰謝料」の2つに分類され、請求権は被害者本人と被害者遺族に認められます。
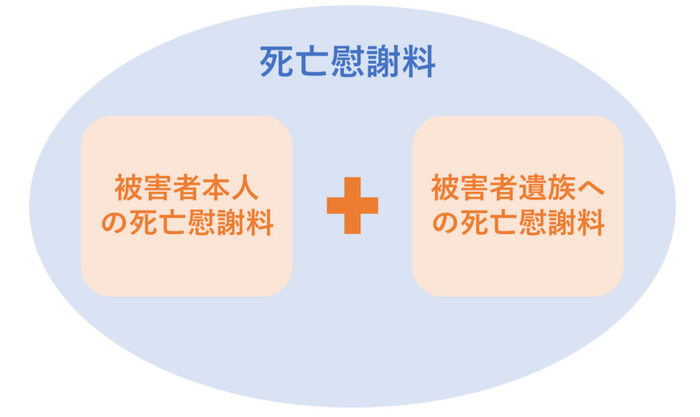
交通事故の被害に遭って亡くなった本人の精神的苦痛は計り知れないものがあり、当然被害者本人には慰謝料を求める権利があります。
しかし、被害者本人は死亡しているため、代わりに相続人である被害者遺族が権利を行使することになります。
死亡事故では家族を失った被害者遺族の精神的苦痛も相当なものがあるため、被害者本人が被った精神的苦痛とは別に、被害者遺族が被った固有の精神的苦痛についても慰謝料請求が可能です。
多くの場合、交通事故の死亡慰謝料とは「被害者本人の精神的苦痛に対する慰謝料」と「被害者遺族固有の精神的苦痛に対する慰謝料」を合わせたものを指します。
交通事故の死亡慰謝料には、以下のように3種類の算出基準があります。
|
計算基準 |
概要 |
適用されるケース |
|
自賠責基準 |
自賠責保険が慰謝料計算の際に用いる基準で、最も低額になりやすい |
加害者が任意保険未加入の場合 |
|
任意保険基準 |
任意保険会社が慰謝料計算の際に用いる基準で、自賠責基準よりは高額になりやすい |
加害者が任意保険に加入している場合 |
|
弁護士基準(裁判所基準) |
弁護士や裁判所が慰謝料計算の際に用いる基準で、最も高額になりやすい |
弁護士に慰謝料請求を依頼する場合 |
死亡慰謝料の金額は適用される計算基準によって異なり、なかでも弁護士基準が最も高額になりやすい傾向にあります。
ここでは、死亡慰謝料の相場や計算方法について、計算基準ごとに解説します。
自賠責基準の場合、「被害者本人の慰謝料」と「被害者遺族固有の慰謝料」に分けて算出・合算し、「被害者遺族固有の慰謝料」は請求権者の数が多いほど高額になります。
なお、民法第711条により、死亡慰謝料の請求権は被害者の父母・配偶者・子どもなどに認められています。
第七百十一条 他人の生命を侵害した者は、被害者の父母、配偶者及び子に対しては、その財産権が侵害されなかった場合においても、損害の賠償をしなければならない。
(責任能力)
引用元:民法第711条
自賠責基準における死亡慰謝料の計算方法は以下のとおりです。
|
自賠責基準の慰謝料算出表 |
||
|
被害者本人の慰謝料 |
400万円 |
|
|
被害者遺族固有の慰謝料 |
被害者に扶養されていた場合 |
被害者に扶養されていなかった場合 |
|
請求権者が1名の場合 |
750万円 |
550万円 |
|
請求権者が2名の場合 |
850万円 |
650万円 |
|
請求権者が3名以上の場合 |
950万円 |
750万円 |
たとえば「被害者が死亡して慰謝料の請求権者が3名おり、被害者に扶養されていた」というケースでは、以下のように計算できます。
|
死亡慰謝料の合計:400万円(被害者本人の慰謝料)+950万円(被害者遺族固有の慰謝料)=1,350万円 |
任意保険基準は、加害者が加入する任意保険会社が慰謝料を算出する際に用いる計算基準です。
任意保険基準に関しては、各保険会社で計算方法が異なり非公開となっていますが、一般的な相場としては「自賠責基準と弁護士基準の中間程度」といわれています。
基本的に生前の被害者の立場によって金額が変わりますが、あくまでも以下は推定額です。
|
生前の被害者の立場 |
任意保険基準の慰謝料額(推定) |
|
一家の支柱 |
1,500万円~2,000万円程度 |
|
配偶者・専業主婦(主夫) |
1,300万円~1,600万円程度 |
|
子ども |
1,200万円~1,500万円程度 |
|
高齢者 |
1,100万円~1,400万円程度 |
|
上記以外 |
1,300万円~1,600万円程度 |
任意保険基準の場合、被害者本人の慰謝料と被害者遺族固有の慰謝料に分けず、まとめて計算するのが一般的です。
弁護士基準は、過去の判例から統計的に分析・構築されていて訴訟手続を前提とした計算基準であり、最も高額になりやすい傾向にあります。
弁護士に依頼すれば、弁護士基準を用いて加害者側との示談交渉を進めてくれます。
生前の被害者の立場によって金額が変わり、相場は以下のとおりです。
|
生前の被害者の立場 |
弁護士基準の慰謝料相場 |
|
一家の支柱 |
2,800万円程度 |
|
配偶者・母親 |
2,500万円程度 |
|
上記以外 |
2,000万円~2,500万円程度 |
弁護士基準の場合も、被害者本人の慰謝料と被害者遺族固有の慰謝料に分けず、まとめて計算するのが一般的です。
当サイト「ベンナビ交通事故」の慰謝料計算ツールなら、相手側がいくら提示してきそうか、弁護士に依頼するといくら増額できそうかを計算できます。
けがの状態・治療状況・年齢・連絡先などを入力すれば診断結果がすぐに出てくるので、「とりあえずいくらもらえるのか知っておきたい」という方は利用してみましょう。
診断結果ページでは、付近の法律事務所もあわせて確認でき、スムーズに相談できます。
そんな方にオススメなのが、ベンナビ交通事故の『慰謝料計算ツール』です。
【実際の利用画面】

適切な慰謝料額を簡単に計算できる上、近くの弁護士を探してくれるので、事故の被害にあって困っている方にぴったりのサービスなんです。
交通事故で損をしないためにも、まずは適正な慰謝料を調べてみましょう。
\弁護士にも相談できる!/
今すぐ適正な慰謝料を調べてみる▶

交通事故の死亡慰謝料の金額は「交通事故の死亡慰謝料の相場・計算方法」で解説したとおりですが、これは絶対的なものではありません。
事案によっては、一般的な相場よりも死亡慰謝料が高くなることもあります。
たとえば、以下のようなケースでは死亡慰謝料が増額される可能性があります。
「被害者が長期入院して治療を続けたものの、亡くなってしまった」という場合、被害者には死亡前の入院治療について相当程度の精神的苦痛を認めることができます。
「苦しい治療期間を経ても結果的に助からなかった」という状況は、ある意味即死の場合よりも精神的苦痛が大きいといえるかもしれません。
したがって、死亡前の精神的苦痛を加味して、通常の死亡事故よりも死亡慰謝料が増額される可能性があります。
加害者が意図的に死亡事故を起こしたり、酒酔い運転・無免許運転・著しいスピード違反・ひき逃げなどの重過失があったりした場合、死亡慰謝料が増額される可能性があります。
ほかにも、以下のように「事故内容が悪質な場合」や「加害者側の態度が不誠実な場合」なども、死亡慰謝料の増額が認められる可能性があります。
一方、なかには死亡慰謝料などの獲得金額が減ってしまうケースもあります。
過失割合とは「交通事故の当事者双方の責任を割合で表したもの」のことです。
被害者にも事故の過失がある場合は過失相殺がおこなわれ、過失が大きいほど加害者に対して請求できる金額が減ってしまいます。
過失割合の判断はケースによって異なりますが、たとえば「被害者が信号無視をした」「安全確認を怠った」などの場合は被害者側にも過失が認められる可能性があります。
また、被害者に持病や既往症などがあった場合は、素因減額がおこなわれて獲得金額が減ってしまうこともあります。
死亡事故では、死亡慰謝料だけでなく、死亡逸失利益や葬儀関係費用なども請求可能です。
ここでは、死亡逸失利益や葬儀関係費用の概要や計算方法について解説します。
死亡逸失利益とは、被害者の死亡によって本来獲得できたはずの収入が失われたことに対する補償のことを指します。
死亡逸失利益の計算式は以下のとおりです。
|
死亡逸失利益=1年あたりの基礎収入×(1-生活費控除率)×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数 |
以下では、各項目の求め方について解説します。
1年あたりの基礎収入は、生前の被害者の立場に応じて算出方法が異なります。
基本的には以下のような方法で算出します。
|
生前の被害者の立場 |
算出方法 |
|
給与所得者 |
事故に遭う前年度の給与年額(賞与含む) |
|
事業所得者・自営業者 |
事故に遭う前年度の申告所得・固定費 |
|
専業主婦・(主夫) |
厚生労働省がその年に発表した賃金センサスの性別ごとの全年齢平均年収 |
|
学生・生徒・幼児など |
厚生労働省がその年に発表した賃金センサスの性別ごとの全年齢平均年収 |
死亡逸失利益を計算する際は、「被害者が亡くなっていなければ発生するはずだった生活費」を控除する必要があります。
生活費控除率は、被害者の立場によって以下のように異なります。
|
生前の被害者の立場 |
生活費控除率 |
|
一家の支柱 |
30%~40% |
|
女性(独身・幼児を含む) |
30%~40% |
|
男性(独身・幼児を含む) |
50% |
労働能力喪失期間については「67-死亡時の年齢」で計算するのが一般的です。
ライプニッツ係数とは「中間利息を控除するために用いられる指数」のことで、以下のように労働能力喪失期間ごとに設定されています。
|
労働能力喪失期間(年) |
ライプニッツ係数 |
労働能力喪失期間(年) |
ライプニッツ係数 |
|
1 |
0.971 |
18 |
13.754 |
|
2 |
1.913 |
19 |
14.324 |
|
3 |
2.829 |
20 |
14.877 |
|
4 |
3.717 |
21 |
15.415 |
|
5 |
4.580 |
22 |
15.937 |
|
6 |
5.417 |
23 |
16.444 |
|
7 |
6.230 |
24 |
16.936 |
|
8 |
7.020 |
25 |
17.413 |
|
9 |
7.786 |
26 |
17.877 |
|
10 |
8.530 |
27 |
18.327 |
|
11 |
9.253 |
28 |
18.764 |
|
12 |
9.954 |
29 |
19.188 |
|
13 |
10.635 |
30 |
19.600 |
|
14 |
11.296 |
31 |
20.000 |
|
15 |
11.938 |
32 |
20.389 |
|
16 |
12.561 |
33 |
20.766 |
|
17 |
13.166 |
34 |
21.132 |
|
労働能力喪失期間(年) |
ライプニッツ係数 |
労働能力喪失期間(年) |
ライプニッツ係数 |
|
35 |
21.487 |
52 |
26.166 |
|
36 |
21.832 |
53 |
26.375 |
|
37 |
22.167 |
54 |
26.578 |
|
38 |
22.492 |
55 |
26.774 |
|
39 |
22.808 |
56 |
26.965 |
|
40 |
23.115 |
57 |
27.151 |
|
41 |
23.412 |
58 |
27.331 |
|
42 |
23.701 |
59 |
27.506 |
|
43 |
23.982 |
60 |
27.676 |
|
44 |
24.254 |
61 |
27.840 |
|
45 |
24.519 |
62 |
28.000 |
|
46 |
24.775 |
63 |
28.156 |
|
47 |
25.025 |
64 |
28.306 |
|
48 |
25.267 |
65 |
28.453 |
|
49 |
25.502 |
66 |
28.595 |
|
50 |
25.730 |
67 |
28.733 |
|
51 |
25.951 |
|
|
死亡事故では、通夜や葬儀などにかかった費用も請求することが可能です。
ただし、計算基準ごとに上限があり、それぞれの上限額は以下のとおりです。
|
自賠責基準の場合 |
弁護士基準の場合 |
|
|
葬儀関係費用の上限額 |
原則100万円まで |
原則150万円まで |
死亡事故で死亡慰謝料を請求する場合、基本的には以下のような流れで手続きを進めます。
ここでは、死亡交通事故の慰謝料を受け取るまでの流れについて解説します。
被害者が死亡した場合、まずは死亡届の提出や葬儀などの手続きが必要です。
さらに、亡くなった被害者の遺産について親族同士で遺産分割協議をおこない、どのように分配するのか決定しなければいけません。
死亡事故ではさまざまな手続きに対応しなければならないため、加害者との示談交渉は四十九日法要後に始めるのが一般的です。
被害者の死亡後の手続きが一通り完了したら、示談交渉を始めます。
示談交渉では、加害者が加入している任意保険会社の担当者から、慰謝料などの金額が提示されるのが一般的です。
示談交渉の注意点として、示談成立後に合意内容を変更することは原則できません。
加害者側から提示を受けた際は安易に受け入れず、提示内容が本当に妥当かどうかをよく考えて、もし納得のいかない部分がある場合はしっかり主張することが大切です。
双方の主張がぶつかって示談交渉での解決が難しい場合は、民事調停や民事裁判に移行して解決を図ります。
民事調停とは、簡易裁判所にて調停委員が間に入って話し合いをおこない、解決を目指す手続きのことです。
調停委員が提示する解決案に双方が合意すれば調停成立となりますが、合意しなかった場合は民事裁判に移行することになります。
民事裁判では、裁判所にて双方が証拠などを用いて主張立証をおこない、最終的には裁判官によって決着がつけられます。
死亡慰謝料などについて合意できた場合は、示談成立後1週間~2週間ほどで支払いがおこなわれます。
多くの場合、指定の銀行口座に一括で支払われます。
ここでは、死亡事故が起きた際に弁護士に依頼するメリットについて解説します。
死亡事故の場合、被害者遺族としては家族を失った悲しみが続く状況のなか、相手方と不慣れな示談交渉に対応することになります。
示談交渉は原則としてやり直しができないため、慰謝料額や過失割合などについて慎重に判断しなければならず、素人にとっては大きな負担となります。
弁護士なら、示談交渉などの事故後手続を一任することが可能です。
依頼後は相手方と直接やり取りすることもなくなるため、身体的負担・精神的負担を大幅に軽減できます。
弁護士基準を用いて慰謝料請求する際は法律知識が必要であり、素人が自力で対応するのは困難です。
また、被害者の死亡に伴う損失を確定させる際も相応の知識・経験が必要となります。
十分な知識や経験なく損害賠償請求を進めてしまうと、本来受け取るべき適正額に満たない金額で終結してしまうことにもなりかねません。
弁護士に依頼すれば、適切な損害賠償額を算出し、弁護士基準での慰謝料請求も的確に進めてくれるため、自力で対応するよりも獲得金額の増額が期待できます。
なお、弁護士に依頼する場合は弁護士費用がかかるのがデメリットですが、被害者が自動車保険の弁護士費用特約に加入していた場合は自己負担0円で済むこともあります。
保険会社によって補償範囲・補償内容は異なりますが、最大300万円まで負担してくれるケースもあり、事故が起きた際は被害者の契約状況を確認しておきましょう。
ここでは、交通事故の死亡慰謝料に関するよくある質問について解説します。
死亡事故の被害者が子どもの場合、死亡慰謝料は高額になりやすい傾向にあります。
特に「たった一人の子どもが亡くなってしまった」というようなケースでは、被害者遺族が被った精神的苦痛は通常の死亡事故よりも大きいと判断される可能性があります。
実際のところはケースバイケースでの判断となるため、詳しくは弁護士にご相談ください。
死亡事故の被害者が高齢の場合も、ほかのケースと同様に死亡慰謝料を獲得できます。
たとえば、任意保険基準が適用された場合は1,100万円~1,400万円程度、弁護士基準の場合は2,000万円~2,500万円程度の獲得が望めます。
死亡慰謝料の相場としては「被害者が一家の支柱だった(弁護士基準)」というケースが最も高額で、約2,800万円となります。
ただし、被害者が長期入院したのち亡くなった場合や、加害者側に故意や重過失があった場合など、状況によってはさらに高額になることもあります。
死亡事故で受け取れる死亡慰謝料は、弁護士基準を用いて請求することで高額になる可能性があります。
ただし、法律知識のない素人が弁護士基準を用いて請求するのは難しく、弁護士のサポートが必要不可欠です。
弁護士なら、法律知識や交渉ノウハウを生かして的確に対応してくれますし、相手方とのやり取りを一任できて身体的負担・精神的負担も大幅に軽減できます。
当サイト「ベンナビ交通事故」では、交通事故トラブルが得意な全国の弁護士を掲載しています。
初回相談無料の法律事務所も多くあり、信頼できる弁護士に相談したい方は以下のリンクから探してみましょう。
弁護士に相談するかお悩みの方へ
下のボタンからあなた当てはまるものを選んで悩みを解消しましょう。
弁護士費用特約があれば 実質0円で依頼できます!

多くの保険会社では、被害者1名につき最大300万円までの弁護士費用を負担してくれます。特約があるか分からない方でも、お気軽にご相談ください。弁護士と一緒にご確認した上で依頼の有無を決めて頂けます。
特約を利用して弁護士に相談する交通事故問題を依頼する弁護士の選び方にはポイントがあります。
等です。
詳しくは以下の記事を読んで、正しい弁護士の選び方を理解した上で弁護士に相談しましょう。
弁護士の選び方について詳しくみる
【来所不要・交通事故の被害者は初回相談料0円】◆豊富な解決実績◆示談金の大幅な増額実績多数◆交通事故専門チームが丁寧に対応します。まずは無料でご相談ください。【「錦糸町駅」南口から徒歩9分】
事務所詳細を見る
【初回相談0円|分割払い可】軽傷~後遺障害・死亡事故◆コンシェルジュ役として、事故直後から総合的にサポート◎適切な示談金・早期の日常復帰を目指し、チームで貴方を支えます《メディア出演多数┃当事務所のこだわりはコチラ》
事務所詳細を見る
【初回相談0円】〈弁護士特約の利用で自己負担0〉軽傷~重篤・死亡事故まで◆損害賠償や後遺障害など、医療機関との連携で納得の解決を目指す〈賠償金: 3,000万の獲得実績〉【オンライン相談│休日夜間◎】
事務所詳細を見る
交通事故で家族を亡くした直後は、深い悲しみの中で何をすべきか判断が難しくなります。本記事では、死亡事故直後に遺族が行うべき手続きや警察・保険会社への対応、示談交...
死亡事故では、遺族が被害者に代わって示談交渉を進めることになりますが、それだけでなく通夜や葬儀などにも対応しなければなりません。スムーズに事故後の対応を済ませる...
タクシーとの事故でご家族が亡くなってしまった遺族に向けて、事故発生から解決までの流れ、損害賠償請求のポイント、示談を弁護士に依頼すべき理由などについて解説してい...
交通事故により被害者が死亡した場合、生存していた場合に得られた収入を補填するために死亡逸失利益が請求できます。この記事では被害者の年齢や社会的立場に合わせた計算...
交通事故の死亡慰謝料の相場は400万円~2,800万円程度で、適用される計算基準や生前の被害者の立場などによって大きく変動します。本記事では、交通事故の死亡慰謝...
交通事故の死亡者は毎年3,000人以上にものぼり、損傷部位によって死因はそれぞれ異なります。また死亡事故では、損害賠償請求や通夜・葬儀などの対応も必要となるため...
死亡事故が発生し、精神的にも追い込まれた状況のなかで、示談交渉や事務手続きを進めていくのは困難です。すみやかに、交通事故問題を得意とする弁護士に相談してください...
被害者が死亡している死亡事故では、交渉時に不利な状況になってしまうことも多々あります。せめて少しでも多くの補償を受けるためにも、遺族としては適切に事故後対応を進...
死亡事故では、遺された遺族が事故対応を進めなければなりません。まだ気持ちの整理がつかない方も多いでしょうが、せめて適切な額の賠償金を受け取るためにも、事故対応の...
交通事故により未成年が死亡した場合、将来を考慮し高額になるケースがあります。逆に、未成年が死亡事故を起こした場合、たとえ被害者が死亡したとしても、加害者本人に慰...
被害者が死亡している死亡事故では、交渉時に不利な状況になってしまうことも多々あります。せめて少しでも多くの補償を受けるためにも、遺族としては適切に事故後対応を進...
交通事故の死亡者は毎年3,000人以上にものぼり、損傷部位によって死因はそれぞれ異なります。また死亡事故では、損害賠償請求や通夜・葬儀などの対応も必要となるため...
交通事故により未成年が死亡した場合、将来を考慮し高額になるケースがあります。逆に、未成年が死亡事故を起こした場合、たとえ被害者が死亡したとしても、加害者本人に慰...
死亡事故では、遺された遺族が事故対応を進めなければなりません。まだ気持ちの整理がつかない方も多いでしょうが、せめて適切な額の賠償金を受け取るためにも、事故対応の...
死亡事故では、遺族が被害者に代わって示談交渉を進めることになりますが、それだけでなく通夜や葬儀などにも対応しなければなりません。スムーズに事故後の対応を済ませる...
交通事故により被害者が死亡した場合、生存していた場合に得られた収入を補填するために死亡逸失利益が請求できます。この記事では被害者の年齢や社会的立場に合わせた計算...
交通事故の死亡慰謝料の相場は400万円~2,800万円程度で、適用される計算基準や生前の被害者の立場などによって大きく変動します。本記事では、交通事故の死亡慰謝...
死亡事故が発生し、精神的にも追い込まれた状況のなかで、示談交渉や事務手続きを進めていくのは困難です。すみやかに、交通事故問題を得意とする弁護士に相談してください...
タクシーとの事故でご家族が亡くなってしまった遺族に向けて、事故発生から解決までの流れ、損害賠償請求のポイント、示談を弁護士に依頼すべき理由などについて解説してい...
交通事故で家族を亡くした直後は、深い悲しみの中で何をすべきか判断が難しくなります。本記事では、死亡事故直後に遺族が行うべき手続きや警察・保険会社への対応、示談交...
被害者が死亡している死亡事故では、交渉時に不利な状況になってしまうことも多々あります。せめて少しでも多くの補償を受けるためにも、遺族としては適切に事故後対応を進...
交通事故で家族を亡くした直後は、深い悲しみの中で何をすべきか判断が難しくなります。本記事では、死亡事故直後に遺族が行うべき手続きや警察・保険会社への対応、示談交...
交通事故の死亡慰謝料の相場は400万円~2,800万円程度で、適用される計算基準や生前の被害者の立場などによって大きく変動します。本記事では、交通事故の死亡慰謝...
交通事故の死亡者は毎年3,000人以上にものぼり、損傷部位によって死因はそれぞれ異なります。また死亡事故では、損害賠償請求や通夜・葬儀などの対応も必要となるため...
死亡事故では、遺された遺族が事故対応を進めなければなりません。まだ気持ちの整理がつかない方も多いでしょうが、せめて適切な額の賠償金を受け取るためにも、事故対応の...
タクシーとの事故でご家族が亡くなってしまった遺族に向けて、事故発生から解決までの流れ、損害賠償請求のポイント、示談を弁護士に依頼すべき理由などについて解説してい...
死亡事故では、遺族が被害者に代わって示談交渉を進めることになりますが、それだけでなく通夜や葬儀などにも対応しなければなりません。スムーズに事故後の対応を済ませる...
交通事故により被害者が死亡した場合、生存していた場合に得られた収入を補填するために死亡逸失利益が請求できます。この記事では被害者の年齢や社会的立場に合わせた計算...
交通事故により未成年が死亡した場合、将来を考慮し高額になるケースがあります。逆に、未成年が死亡事故を起こした場合、たとえ被害者が死亡したとしても、加害者本人に慰...
死亡事故が発生し、精神的にも追い込まれた状況のなかで、示談交渉や事務手続きを進めていくのは困難です。すみやかに、交通事故問題を得意とする弁護士に相談してください...

