交通事故の加害者・被害者どちらも労災は使える?任意保険との併用は可能?

仕事中または通勤中に、交通事故に遭ってけがをした労働者は、労災認定を申請して労災保険給付を受給できます。
労災保険給付は、労災の認定要件を満たしている限り、交通事故の被害者・加害者のいずれの立場でも受給可能です。
弁護士のアドバイスを受けながら、交通事故による損害について適正な補償を受けつつ、トラブルの早期解決を目指しましょう。
本記事では交通事故によるけがについて労災認定を受けるための要件、交通事故加害者による労災保険給付の受給の可否、労災保険と任意保険(自動車保険)の併用などについて解説します。
仕事中や通勤中に交通事故を起こしてしまった方は、本記事を参考にしてください。
交通事故の加害者・被害者どちらの立場でも労災保険は使える?
業務上の原因により、または通勤中にけがをした労働者は、労災保険の給付金(=労災保険給付)を受給できます。
仕事中または通勤中に発生した交通事故によるけがも、労災保険給付の対象です。
交通事故の加害者も、原則として被害者と同様に、労災保険給付を受給することができます。
治療費・休業損害・後遺症による逸失利益などの補償を受けられるので、該当する労災保険給付を漏れなく請求しましょう。
ただし、故意に交通事故を起こした加害者は、労災保険給付を受給できません(労働者災害補償保険法12条の2の2第1項)。
また、交通事故を発生させたことについて加害者に重大な過失がある場合や、正当な理由なく治療を受けなかった場合などにも、加害者は労災保険給付を受給できないことがあるので注意が必要です(同条2項)。
交通事故について労災保険が適用される条件
交通事故について労災保険の適用を受けるための条件は、被害者・加害者どちらの立場でも同じです。
「業務災害」または「通勤災害」の要件を満たしていれば、労災保険給付(労災認定)の対象となります。
仕事中に交通事故を起こしてしまった(遭った)場合の適用条件
運送業ドライバー(トラック・タクシーなど)による運転業務や、緊急用務のため休日に呼出しを受けて緊急出動する際の運転など、業務としての性質を有する運転の最中に発生した交通事故については、「業務災害」として労災保険給付を受給できる可能性があります。
けがの原因となった交通事故について、以下の要件をすべて満たす場合は業務災害に該当し、被災労働者は労災保険給付を受給できます。
- 業務遂行性:労働者が使用者の支配下にある状態において交通事故が発生したこと
- 業務起因性:会社の業務と、交通事故によって生じた労働者のけがの間に相当因果関係があること
基本的には、運転業務が会社の指示によるものである場合には、その運転中に発生した交通事故について労災保険給付を受給できる可能性が高いと考えられます。
通勤中に交通事故を起こしてしまった(遭った)場合の適用条件
通勤のための運転の最中に発生した交通事故については、「通勤災害」として労災保険給付を受給できる可能性があります。
けがの原因となった交通事故について、以下の要件をすべて満たす場合は通勤災害に該当し、被災労働者は労災保険給付を受給できます。
- 以下のいずれかの移動中に交通事故が発生したこと
・住居と就業場所の間の往復
・就業場所から他の就業場所への移動
・単身赴任先住居と帰省先住居の間の移動 - 交通事故が発生した際の移動が、以下の日におこなわれたこと
・住居と就業場所の間の往復
→就業(予定)日の当日
・就業場所から他の就業場所への移動
→就業(予定)日の当日
・単身赴任先住居と帰省先住居の間の移動
→就業(予定日)の前日・当日・翌日 - 交通事故が発生した際の移動が、合理的な経路・方法によるものであること
- 交通事故が発生した際の移動が、業務の性質を有するものでないこと
※移動が業務としての性質を有する場合は、業務災害として労災保険給付を受けられることがあります。
仕事中・通勤中の交通事故について、労災保険・自動車保険の併用は可能 | 覚えておくべきポイントは?
仕事中または通勤中の交通事故によって生じたけがについては、労災保険給付とともに、事故の相手方が加入している自賠責保険および任意保険(自動車保険)からも保険金を受け取ることができます。
漏れのないように補償を受けるため、労災保険と自賠責保険・任意保険を併用する際には、以下の各点に留意しておきましょう。
- 労災保険では慰謝料は補償対象外|自賠責保険・任意保険では慰謝料も補償される
- 労災保険給付でカバーされないその他の損害も、任意保険ではカバーされる
- 労災保険と自動車保険から二重取りすることはできない|支給調整がおこなわれる
- 労災保険からは特別支給金を受け取れる|特別支給金は支給調整の対象外
- 労災保険は示談交渉の進捗に関わらず補償を受けられる
労災保険では慰謝料は補償対象外|自賠責保険・任意保険では慰謝料も補償される
交通事故によって受けた精神的損害を補填する慰謝料は、労災保険によっては一切カバーされません。
これに対して、自賠責保険および任意保険では慰謝料も補償されます。
自賠責保険には支給限度額が設けられていますが、任意保険では客観的な精神的損害に相当する慰謝料全額が補償されます。
慰謝料について補償を受けるためには、労災保険給付だけでなく、自賠責保険および任意保険の保険金も請求しましょう。
労災保険給付でカバーされないその他の損害も、任意保険ではカバーされる
労災保険給付では、慰謝料以外にも補償されない損害があります。
たとえば、休業損害については60%相当額(+特別支給金として20%相当額)しか補償されません。
後遺症による逸失利益についても、必ずしも全額が補償されるわけではありません。
また、車の修理費などの物損については、労災保険給付の対象外です。
労災保険給付によっては補償されない損害も、自賠責保険および任意保険では補償される場合があります。
特に任意保険では、対人・対物ともに無制限の補償がおこなわれるのが一般的です。
保険会社との交渉などの結果によりますが、休業侵害・後遺障害逸失利益・物損なども含めて、労災保険給付よりも幅広い補償を受けられる可能性があることを知っておきましょう。
労災保険と自動車保険から二重取りすることはできない|支給調整がおこなわれる
交通事故が労災に該当する場合でも、労災保険と自動車保険(自賠責保険・任意保険)の保険金を二重取りすることはできません。
損害賠償に対応する給付については、労災保険と自動車保険の間で支給調整がおこなわれるためです。
具体的には、以下の労災保険給付と損害賠償項目が支給調整の対象となります。
| 支給調整の対象となる労災保険給付 | 保険金による損害賠償の項目 |
|---|---|
| 療養(補償)給付 | 療養費(治療費など) |
|
休業(補償)給付 傷病(補償)年金 障害(補償)給付 遺族(補償)給付 |
逸失利益 |
| 葬祭料(葬祭給付) | 葬祭費用 |
先に自賠責保険または任意保険から保険金の支払いを受けた場合は、後に受給できる労災保険給付が減額されます。
反対に、先に労災保険給付を受給した場合は、後に請求できる自賠責保険・任意保険の保険金が減額されます。
この場合、被災労働者は労災保険給付を請求する際に、労働基準監督署に対して「第三者行為災害届」などを提出しなければなりません。
政府は交通事故の相手方(または保険会社)に対して、控除すべき労災保険給付に相当する金額を求償することになります。
労災保険からは特別支給金を受け取れる|特別支給金は支給調整の対象外
交通事故が労災保険給付の対象となる場合、被災労働者は損害賠償に対応する給付に加えて「特別支給金」を受給できることがあります。
特別支給金の種類および内容は、下表のとおりです。
| 労災保険給付の種類 | 特別支給金の種類 | 特別支給金の内容 |
|---|---|---|
| 休業(補償)給付 | 休業特別支給金 | 休業4日目以降、給付基礎日額の20%相当額 |
| 傷病(補償)年金 | 傷病特別支給金 |
傷病等級に応じて、以下の額の一時金 第1級:114万円 第2級:107万円 第3級:100万円 |
| 傷病特別年金 |
傷病等級に応じて、以下の額の年金 第1級:算定基礎日額の313日分 第2級:算定基礎日額の277日分 第3級:算定基礎日額の245日分 |
|
| 障害(補償)給付 | 障害特別支給金 | 障害等級に応じて、342万円(第1級)~8万円(第14級)の一時金 |
| 障害特別年金 |
障害等級に応じて、算定基礎日額の313日分(第1級)~131日分(第7級)の年金 ※障害等級第1級~第7級の場合 |
|
| 障害特別一時金 |
障害等級に応じて、算定基礎日額の503日分(第8級)~56日分(第14級)の一時金 ※障害等級第8級~第14級の場合 |
|
| 遺族(補償)給付 | 遺族特別支給金 | 300万円(一時金) |
| 遺族特別年金 |
遺族の人数などに応じて、算定基礎日額の153日分~245日分の年金 ※死亡した被災労働者と生計を同じくする、一定の要件を満たす遺族のみ受給可能 |
|
| 遺族特別一時金 |
算定基礎日額の1,000日分の一時金 ※遺族(補償)年金を受けることができる遺族がいない場合などに限って受給可能 |
特別支給金については、自賠責保険または任意保険との間で支給調整がおこなわれません。
したがって、自賠責保険または任意保険によって受けられる補償に加えて、特別支給金を上乗せ的に受給できます。
特別支給金を受給するため、自賠責保険・任意保険だけでなく、労災保険給付も併せて請求しましょう。
労災保険は示談交渉の進捗に関わらず補償を受けられる
任意保険の保険金は、保険会社との示談交渉や訴訟などが終わってからでなければ、治療費などを除いて支払われません。
これに対して労災保険給付は、保険会社との示談交渉などが終わっていなくても、労働基準監督署などへの請求によって受給できます。
速やかに補償を受けたい場合は、先に労災保険給付を請求するとよいでしょう。
なお自賠責保険の保険金については、被害者自ら請求すれば、保険会社との示談交渉などが終わっていなくても受給可能です(=被害者請求)。
労災保険給付の請求と併せて、自賠責保険の被害者請求も検討しましょう。
労災に当たる交通事故に関して、弁護士への相談・依頼を推奨する理由
仕事中または通勤中に交通事故に遭ってしまった場合は、弁護士に相談・依頼することをおすすめします。
仕事中・通勤中の交通事故について、弁護士に相談・依頼するのがよい主な理由は、以下のとおりです。
- 損をしない保険の活用法や手続きなどをアドバイスしてもらえる
- 煩雑な交渉・訴訟などの代行を依頼できる
- 適正な後遺障害等級の認定を受けられる
- 【被害者の場合】相手に対して適正額の損害賠償を請求できる
- 【任意保険に加入していない加害者の場合】適正額を超える損害賠償を拒否できる
損をしない保険の活用法や手続きなどをアドバイスしてもらえる
弁護士に相談すれば、労災保険や自賠責保険・任意保険の仕組みに加えて、それぞれの保険の効果的な活用方法をアドバイスしてもらえます。
複雑な支給調整のルールについても教えてもらえるので、保険の活用に関して損をすることを避けられるでしょう。
また、各保険の請求手続きについても、弁護士に相談すればアドバイスを受けられます。
特に自賠責保険の被害者請求については、交通事故の当事者が自らおこなうのは多くの手間がかかります。
弁護士に依頼すれば、被害者請求の手続きを代行してもらえるので、労力を大幅に軽減できるでしょう。
煩雑な交渉・訴訟などの代行を依頼できる
交通事故の被害者や、任意保険に加入していなかった加害者は、損害賠償請求について相手方との示談交渉をおこなうことになります。
示談交渉がまとまらなければ、裁判所における訴訟に発展する可能性が高いです。
示談交渉や訴訟について、自ら対応するのは非常に大変です。
準備に多大な労力がかかりますし、専門的な検討や書類の作成などを含めて、すべての対応を適切におこなうのは困難でしょう。
弁護士には、交通事故に関する示談交渉や訴訟などの対応を依頼できます。
弁護士に対応を一任すれば労力を大幅に軽減できますし、適正な形で交通事故トラブルを解決できる可能性が高まります。
適正な後遺障害等級の認定を受けられる
交通事故によるけがが完治せずに後遺症が残った場合は、相手方の自賠責保険の保険会社を通じて、後遺障害等級の認定を申請しましょう。
認定される後遺障害等級に応じて、慰謝料および逸失利益を請求できます。
適正な後遺障害等級の認定を受けるためには、認定要件を満たすことが分かる後遺障害診断書を提出するなど、事前の準備が大切になります。
弁護士に依頼すれば、後遺障害等級認定の申請に関するサポートを受けられます。
弁護士が主治医と連携して準備を整えれば、適正な後遺障害等級の認定を受けられる可能性が高まるでしょう。
【被害者の場合】相手に対して適正額の損害賠償を請求できる
交通事故の被害者が適正額の損害賠償を受けるためには、客観的な損害額につき、漏れなく適正な基準で積算して請求することが大切です。
弁護士に依頼すれば、主要なものから細かいものまで、交通事故に関する損害額を漏れなく見積もってもらえます。
また、過去の裁判例に基づいて策定された「弁護士基準(裁判所基準)」に基づき、被害者に生じた客観的な損害額を適切に計算してもらえます。
弁護士によるこれらの対応は、適正額による損害賠償の獲得に繋がるでしょう。
【任意保険に加入していない加害者の場合】適正額を超える損害賠償を拒否できる
交通事故の時点において任意保険に加入していなかった加害者は、被害者との示談交渉や訴訟などにつき、自ら対応しなければなりません。
被害者側の請求が妥当であるかどうかは、被害者に生じた客観的な損害額の把握・計算や、過失相殺(民法722条2項)に関する検討をおこなった上で判断する必要があります。
弁護士に相談・依頼すれば、これらの対応・検討を適切におこなってもらえます。
その上で、被害者側の請求額が妥当であるかどうかを適切に判断し、適正額を超える部分については支払いを拒否することができます。
交通事故について、相手方から多額の損害賠償を請求された場合には、速やかに弁護士へ相談しましょう。
さいごに | 加害者・被害者どちらの立場でも、労災に当たる交通事故は弁護士へ相談を
業務の一環として、または通勤のために運転をしている最中に交通事故に遭ったら、弁護士へ相談しましょう。
加害者・被害者いずれの立場でも、適正な形でトラブルを解決するためのアドバイスを受けることができます。
「ベンナビ交通事故」には、交通事故案件を豊富に取り扱う弁護士が多数登録されています。
相談内容や地域に応じて、スムーズに弁護士を検索できるのでたいへん便利です。
無料相談ができる弁護士も数多く登録されているので、交通事故に遭ってしまった方は、「ベンナビ交通事故」を通じて速やかに弁護士へご相談ください。
弁護士に相談するかお悩みの方へ
下のボタンからあなた当てはまるものを選んで悩みを解消しましょう。
弁護士費用特約があれば 実質0円で依頼できます!

多くの保険会社では、被害者1名につき最大300万円までの弁護士費用を負担してくれます。特約があるか分からない方でも、お気軽にご相談ください。弁護士と一緒にご確認した上で依頼の有無を決めて頂けます。
特約を利用して弁護士に相談する交通事故問題を依頼する弁護士の選び方にはポイントがあります。
- 過去の解決事例を確認する
- 料金体系が明確である弁護士を選ぶ
- 交通事故問題が得意な弁護士から選ぶ
等です。
詳しくは以下の記事を読んで、正しい弁護士の選び方を理解した上で弁護士に相談しましょう。
弁護士の選び方について詳しくみる
【初回相談0円&弁護士特約で自己負担0円】軽微な事故から死亡事故まで幅広く対応◎町の板金屋さんや自動車整備共同組合から多くのご相談いただき交通事故の対応経験が豊富◆事故に遭ってしまったらすぐにご相談を
事務所詳細を見る
【田町駅&三田駅好アクセス】【初回相談 60分0円|オンライン相談対応◎】【来所せずご依頼可能】治療中のお悩み/保険会社との交渉など、実績豊富な弁護士が対応いたします ◤弁護士特約対応◢ お気軽にご相談ください【カード決済可】
事務所詳細を見る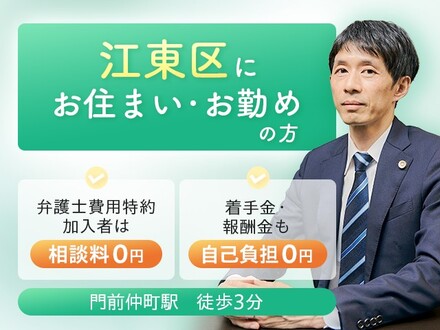
【弁護士費用特約があれば、実質費用負担なくご依頼可能】 人身事故・後遺障害・死亡事故を強力サポート!治療費打ち切り等の解決策も面談にて提示します。事故直後から、まずは一人で悩まずご相談を。 【出張相談可※応相談】
事務所詳細を見る当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡

交通事故後の対応に関する新着コラム
-
接触がない「非接触事故」は、過失割合の判断が難しい事故です。非接触事故における過失割合の基本的な考え方、車対歩行者・車対車・車対バイクといった典型的なケース別の...
-
非接触事故で後日警察から連絡が来るかどうかは、一概には言えません。連絡が来る時期も、事故の種類や相手の診断書の提出時期、被害者のけがの程度により異なります。場合...
-
本記事では、交通事故の被害に遭った方に向けて、交通事故用の示談書の簡単な書き方と流れ、交通事故用の示談書を簡単に書くために押さえておくべき4つのコツ、示談書の作...
-
本記事では、自転車と自動車間の過失割合がどのように設定されるかや、自転車と自動車間の交通事故が起きたときの対処法・注意点を解説します。
-
非接触事故で転倒がなくても、後で怪我に気づくことがあります。適切な対処法を理解せずに立ち去ると問題になる可能性があるため、本記事では転倒なしの非接触事故における...
-
交通事故トラブルを抱えるなかで、弁護士だけでなく行政書士にも対応してもらえることを知り、主に費用面が気になっている方も多いのではないでしょうか。本記事では、行政...
-
本記事では、レンタカーを運転していて交通事故に遭った場合、相手が100%悪くてもレンタカー会社へお金を支払わなければならない理由やレンタカー会社からお金を請求さ...
-
本記事では、交通事故の被害に遭った方に向けて、被害者が利用できる保険(自賠責保険・任意保険)の種類、加害者の自賠責保険と被害者の任意保険を使用する順番、加害者側...
-
交通事故によるけがで仕事を休む場合、いつ頃復帰するのが適切なのでしょうか?本記事では、交通事故が原因で仕事を休む場合の一般的な休業期間や、休業した場合にもらえる...
-
交通事故に遭った場合、会社から診断書の提出を求められることがあります。しかし、費用の問題などからためらっている方も多いのではないでしょうか。本記事では、交通事故...
交通事故後の対応に関する人気コラム
-
当て逃げに遭ってしまった方へ、少しでも解決に近づけるための対処法をご紹介します。
-
物損事故とは、怪我人や死亡者がなく車両などに損害が出たにとどまる交通事故のことです。物損事故では相手方と示談交渉で揉めてしまう可能性もありますので、ポイントをお...
-
交通事故発生後は、警察に連絡・治療(人身事故の場合)・保険会社との交渉と進んでいきます。本記事では、各場面の詳しい対応や、いつ連絡が来るのかなどの期間についても...
-
交通事故が起きて被害者となった場合、「自分は被害者だから、待っているだけで何もする必要はない」と考えているなら、それは大きな間違いだと言えます。
-
交通事故が起きたら、物損事故・人身事故問わず警察へ届け出なければいけません。これは法律で義務付けられており、報告を怠ると法律違反として処罰を受ける可能性もありま...
-
交通事故のうち3割は駐車場で起こっているといわれています。駐車場は私有地になるため、事故が起こったあとの対処が一般道路とは異なる部分があります。本記事では、駐車...
-
事故後の対応や手続きを適切におこなうことで、その後の補償や示談交渉をスムーズに進められます。本記事では、交通事故にあった際に最初にとるべき行動、その後の手続きの...
-
車でおかまをほられた(後ろから追突された)ときに、どのように対処すればよいかご存知でしょうか。この記事では、車でおかまをほられた際の流れと対処法、示談金などを紹...
-
接触事故とは、走行中の自動車が車両・物・人などに接触して、損害や傷害が生じた事故のことです。接触事故では「怪我の有無」で賠償金の内容が異なりますので、事故後の流...
-
ひき逃げ事故は、その後の人生を大きく左右する重大な問題です。本記事では、ひき逃げ事故に遭われた被害者の方、そしてひき逃げ事故を起こしてしまった加害者の方が、事故...
交通事故後の対応の関連コラム
-
交通事故の加害者は、被害者に対して損害賠償責任を負うほか、自らもケガや車の破損などによって大きな損害を受けることがあります.。 交通事故を起こしてしまい、大き...
-
物損事故が発生した場合、加害者または任意保険会社に損害賠償請求することになります。物損事故の被害に遭った際に不利な状況にならないためにも、この記事にて示談成立ま...
-
通勤中に交通事故を起こしてしまい、労災保険を使えるのかどうか気になっている方もいるでしょう。労災保険は、一定の条件を満たせば加害者も利用できます。本記事では、加...
-
交通事故(追突事故)にあったら警察に事故報告をした後に病院で検査を受ける必要がありますが、その時に受け取る診断書は損害賠償請求をするための重要な役割を担っていま...
-
交通事故の相手方からしつこく電話がかかってくるために、プレッシャーを感じて悩んでいる方もいらっしゃるかと思います。本記事では、交通事故の相手方がしつこく電話をか...
-
本記事では、レンタカーを運転していて交通事故に遭った場合、相手が100%悪くてもレンタカー会社へお金を支払わなければならない理由やレンタカー会社からお金を請求さ...
-
交通事故の治療は接骨院や整骨院でも受けられますが、保険会社に損害賠償を請求するための診断書は『正式な医師』でないと作成できないといった問題があります。交通事故の...
-
本記事では、交通事故を理由に解雇されることがあるのかを解説します。解雇が認められるケースや解雇された場合の対処法なども紹介するので、交通事故のけがが原因で解雇さ...
-
交通事故における供述調書(きょうじゅつちょうしょ)とは、警察が事故の様子を記録する為に作成する書類のことで、事故の状況を明らかにする実況見分書とセットで作成され...
-
交通事故が起きたら、物損事故・人身事故問わず警察へ届け出なければいけません。これは法律で義務付けられており、報告を怠ると法律違反として処罰を受ける可能性もありま...
-
交通事故が起きた際に警察へ電話をすることは法律で義務付けられており、これを怠ることによって様々なリスクが生じる恐れがあります。今回は、交通事故時に警察へ電話をす...
-
交通事故に巻き込まれた際は、できるだけ早く弁護士に相談することが大切です。支払ってもらえる保険金額や逸失利益を計算したい場合もあるでしょう。本記事では、後遺障害...
交通事故後の対応コラム一覧へ戻る


























 慰謝料・損害賠償
慰謝料・損害賠償
 示談
示談
 過失割合
過失割合
 死亡事故
死亡事故
 後遺障害
後遺障害
 むちうち
むちうち
 自転車事故
自転車事故
 自動車事故
自動車事故
 人身事故
人身事故
 バイク事故
バイク事故




























