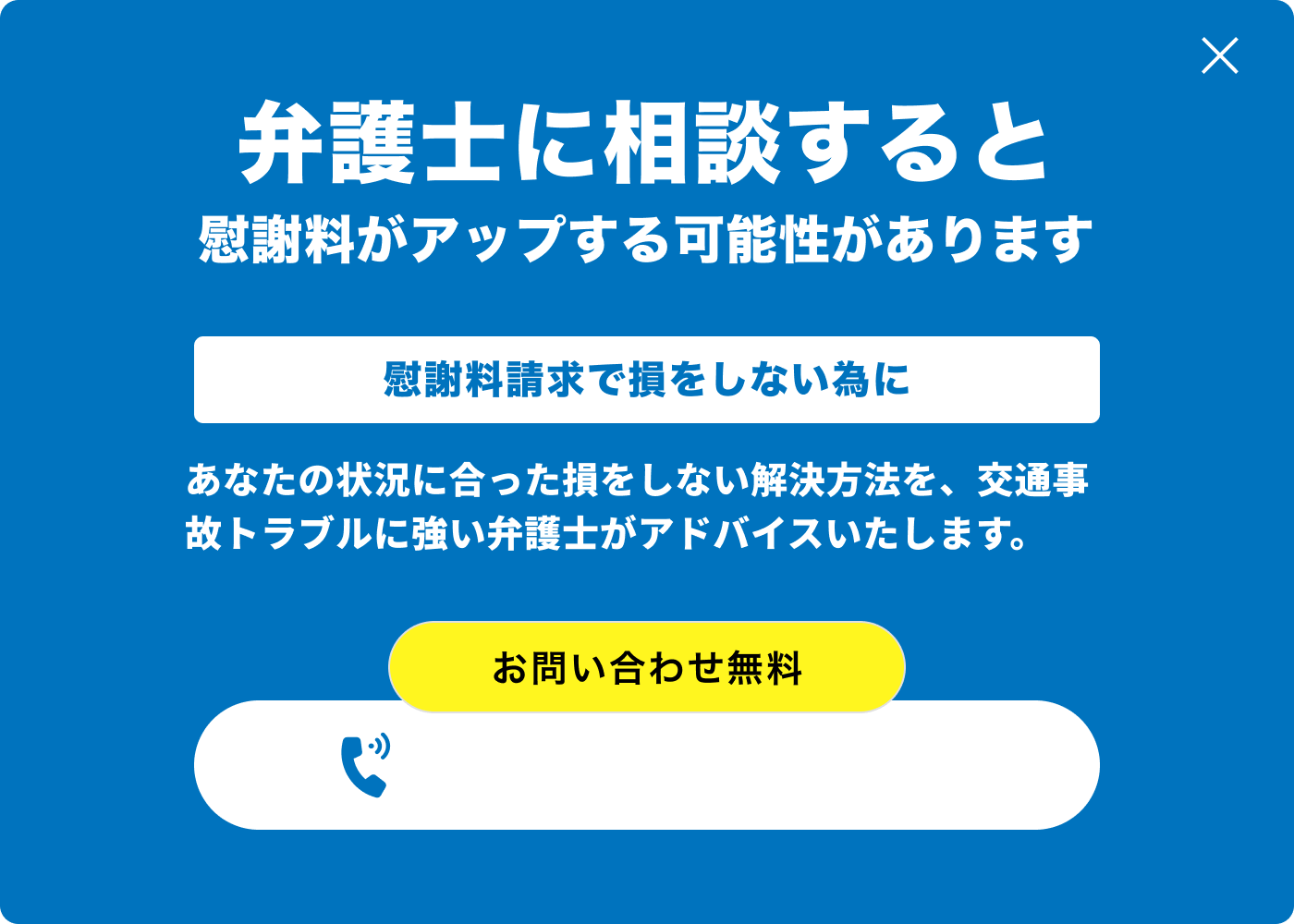交通事故や自転車事故など、事故はいつ起きてしまうか分からないものです。弁護士費用を用意できず泣き寝入りとなってしまうケースも少なくありません。
ベンナビ弁護士保険は、弁護士依頼で発生する着手金を補償する保険です。
交通事故だけでなく、自転車事故、労働問題、離婚、相続トラブルなど幅広い法的トラブルで利用することができます。
弁護士保険で法律トラブルに備える

交通事故の加害者である外国人が任意保険に加入していない場合、加害者本人の経済状況等により十分な金額を受け取れない恐れがあります。
このような場合、加害者が強制加入する自賠責保険やご自身の契約保険を活用することで、可能な限りの補償を受けるということも検討せざるを得ません。
この記事では、任意保険未加入の相手との交通事故について簡単に解説します。
交通事故の場合、相手が任意保険に加入していれば、任意保険会社が窓口となって、人身・物損両方の損害について適切に対応してくれます。他方、相手が任意保険に加入していない場合、このような保険会社を通じた対応を受けることはできません。
では、このような場合、被害者はどうすればよいのでしょうか。事故の加害者が任意保険に加入していなかった場合、以下のような対応が考えられます。
自動車運転者が加入する保険には、任意で契約する「任意保険」と法律上加入を強制される「自賠責保険」の2つがあります。相手運転者が任意保険に加入していなくても、通常は自賠責保険には必ず加入しているはずです。
そのため、交通事故の被害者は、加害者が加入する自賠責保険会社に対し一定の補償を求めて請求することができます(これを被害者請求といいます)。
しかし、自賠責保険への請求には注意が必要です。具体的には、自賠責保険に対する補償請求は人身損害に限定されます。そのため、物損事故の場合や人身・物損事故の場合には、物損についての損害(車両の修理費等)は自賠責保険に請求することはできません。
また、人身損害であっても自賠責保険からの補償には法律上の限度があります。自賠責保険はあくまで交通事故被害者について最低限の補償を行うことを趣旨とする保険制度ですので、被害全部が補償されるわけではないのです。
加害者が任意保険に加入しておらず、自賠責保険からも回収できない損害は、加害者側に直接請求するほかありません。加害者本人に対する請求ができることは当然ですが、以下のような場合では、加害者以外にも請求することができます。
加害者が仕事中に交通事故を起こしたような場合、被害者は加害者本人だけでなく、加害者の雇用主に対して損害賠償請求できる場合があります。具体的には、民法第715条に基づいて雇用主の使用者責任を問うことになります。なお、ここでいう雇用主とは、例えば、加害者を雇っている会社等がこれに該当します。
加害者の運転する車両が、他の所有者から借りていたような場合には、被害者は加害者本人だけでなく、その所有者に対しても損害賠償請求が可能です。具体的には、自動車損害賠償保障法第3条に基づいて車両の所有者の運行供用者責任を問うことになります。
なお、ここでいう運行供用者とは、車両の所有者で加害者にその使用を認めた者がこれに該当します。例えば「加害者の運転していた車がレンタカーだった」「友人の車を借りていた」というケースなどです。
もし被害者が人身傷害補償保険・搭乗者傷害保険・無保険車傷害保険などの保険に加入しているのであれば、加入先の保険会社から発生した損害について一定の補償を受けられる可能性があります。各保険の概要については以下の通りです。
もし被害者が仕事中や通勤中に事故に巻き込まれたのであれば、労働災害・通勤災害として行政から一定の補償を受けられる可能性があります。
労働災害・通勤災害と認定された場合、以下のような補償金の支払いを受けられますので、加害者側から支払いを受けることが困難なような場合には、積極的に利用するべきでしょう。
|
労災保険の保障内容 |
|
|
療養補償 |
事故により治療が必要な場合に支給 |
|
休業補償 |
休業せざるを得ない場合に支給 |
|
傷病補償 |
一定期間を過ぎても怪我が治癒しない場合に支給 |
|
障害補償 |
一定の後遺症が残った場合に支給 |
|
遺族補償 |
被害者が死亡した場合に支給 |
|
介護保障 |
常時または随時介護が必要な場合に支給 |
|
葬祭料 |
被害者が死亡した場合に支給 |
上記のとおり、加害者が任意保険に加入していなくても、強制加入の自賠責保険に対しては一定の補償を求めることができます。ここでは、自賠責保険に対して被害者請求を行う場合の請求方法・必要書類・補償範囲などを解説します。
請求時の主な流れとしては以下の通りです。
被害者としては、特に②の書類準備に大きな手間と労力が割かれるかと思います。もしスムーズに準備できるか不安であれば、弁護士に依頼することをおすすめします。弁護士であれば上記の請求手続きをすべて任せられますので、自力で行うよりも不備なくスムーズに済ませられるでしょう。
請求にあたっては、ケースに応じて以下のような書類が必要となります。
|
必要書類 |
入手先 |
|
保険金(共済金)・損害賠償額・仮渡金支払請求書 |
自賠責保険会社 |
|
交通事故証明書 |
自動車安全運転センター |
|
事故発生状況報告書 |
自賠責保険会社 |
|
医師の診断書・後遺障害診断書・死亡診断書 |
病院 |
|
納税証明書・課税証明書・確定申告書 |
税務署または市区町村役場 |
|
印鑑証明書 |
市区町村役場 |
|
委任状および委任者の印鑑証明 |
市区町村役場 |
|
戸籍謄本 |
市区町村役場 |
|
休業損害証明書 |
勤務先の会社 |
|
レントゲン写真等の検査結果 |
病院 |
|
診療報酬明細書 |
病院 |
|
通院交通費明細書 |
自賠責保険会社 |
|
付添看護自認書・看護料領収証 |
自賠責保険会社 |
自賠責保険では、事故により生じた以下のような損害について補償が受けられます。なお自賠責保険がカバーするのは人身損害に限定され、物的損害について補償を受けることはできませんので、注意しましょう。
|
自賠責保険の保障内容 |
|
|
治療費 |
怪我の治療のために実際にかかった金額 |
|
看護料 |
入院1日あたり4,200円 通院または自宅看護の場合は1日あたり2,100円 |
|
入院雑費 |
1日あたり1,100円 |
|
通院交通費 |
通院のために実際にかかった金額 |
|
装具・器具等の費用 |
入手のために実際にかかった金額 |
|
診断書等の費用 |
発行のために実際にかかった金額 |
|
文書料 |
発行のために実際にかかった金額 |
|
休業損害 |
原則1日あたり6,100円 |
|
慰謝料 |
1日あたり4,200円 |
自賠責保険は、事故の被害者に対して最低限の手助けを行うことを目的とした保険です。以下のように被害の程度に応じて限度額が設けられており、限度額を超える部分については別途請求手続きが必要となります。
|
自賠責保険の限度額 |
|
・傷害を負った場合:120万円(被害者1名につき) ・後遺障害が残った場合 ・常時介護を必要とする場合:4,000万円(第1級) (被害者1名につき) ・随時介護を必要とする場合:3,000万円(第2級) (被害者1名につき) ・上記以外の場合:3,000万円(第1級)~75万円(第14級) (被害者1名につき) ・被害者が死亡した場合:3,000万円(被害者1名につき) |
あまり考えられない事態ではありますが、相手運転者である外国人が車検切れの自動車に乗っており、「自賠責保険にすら加入していない」ということも考えられます。「相手が任意保険未加入の場合の補償請求について」で紹介したいずれの対応も望めず、加害者が何の保険にも加入していなければ、加害者本人に対して損害賠償請求する以外に全く方法はないのでしょうか。
実は、このような場合でも、被害者が加害者以外から補償を受ける方法があります。具体的には政府保障事業と呼ばれる制度を利用する方法です。
この制度は、加害者が自賠責保険に未加入の場合や加害者が不明であり請求先がないような場合に、被害者を自賠責保険と同じ水準で保護するための制度です。国土交通省HPに具体的な請求の手順が記載されていますので、もし制度利用を検討される場合にはこちらをご高覧ください。
加害者本人に十分な支払能力と支払意思があれば、加害者が保険に加入している・していないに拘らず、被害者は加害者から適正な補償を受けられます。
しかし、加害者本人に支払能力や支払意思があるかは、実際に事故が起きてみなければわかりません。相手運転者が十分な支払能力がなかったり、支払能力があっても支払意思がない場合において、保険制度が利用できなければ、実際に被害を補償してもらうことは困難な場合がほとんどでしょう。
特に外国人の場合、日本に定住していなければ本国に帰ってしまうリスクがあります。こうなった場合、事実上、加害者に補償を求めることは難しいと言わざるを得ません。この点は、外国人を相手とする場合に不可避的に生じるリスクと言えます。
外国人との事故で損害賠償請求する際は、弁護士に依頼することで心強いサポートが受けられますのでおすすめです。ここでは、損害賠償請求を弁護士に依頼するメリットについて解説します。
交通事故では「相手と協議しながら補償額について妥結する」という流れが通常です。また、このような協議がまとまらなければ訴訟提起も視野に入れなければなりません。このような煩雑な交渉や手続を自身で行うのは非常に煩雑です。
弁護士であればこのような煩雑な処理を一任することができますので、このメリットは大きいと言えます。
弁護士に依頼することで、慰謝料・治療費・休業損害・後遺障害逸失利益など、事故により発生した損害について適正な補償額を請求してもらうことができます。
特に慰謝料については、自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準という3つの計算基準が設けられており、どれが適用されるかで以下のように金額が異なります。
|
通院期間 |
自賠責基準(※1) |
任意保険基準(推定) |
弁護士基準(※2) |
|
1ヶ月間 |
8万6,000円 (8万4,000円) |
12万6,000円 |
28(19)万円 |
|
2ヶ月間 |
17万2,000円 (16万8,000円) |
25万2,000円 |
52(36)万円 |
|
3ヶ月間 |
25万8,000円 (25万2,000円) |
37万8,000円 |
73(53)万円 |
|
4ヶ月間 |
34万4,000円 (33万6,000円) |
47万8,000円 |
90(67) 万円 |
|
5ヶ月間 |
43万円 (42万円) |
56万8,000円 |
105(79) 万円 |
|
6ヶ月間 |
51万6,000円 (50万4,000円) |
64万2,000円 |
116(89) 万円 |
※1: 初診から治療終了日を21日とし実際の通入院は10日間だったと仮定し、2020年3月31日までは4,200円、2020年4月1日より後に発生した事故に関しては4,300円で計算しています。
※2:()内はむちうち等の他覚症状がない負傷の慰謝料
弁護士であれば、最も高額な弁護士基準での請求をスムーズに済ませることができ、結果的にもらえる賠償金を増額できる可能性があります。相手からできるだけ多くの金額を受け取りたいという方には、弁護士がおすすめです。
事故の加害者が任意保険に加入していない場合は、「加害者が自賠責保険に加入しているか」「自分が加入している任意保険や労災保険を利用できないか」など、ほかの手段で補償が受けられないか確認しましょう。それでも全ての損害が補償されなければ、加害者本人への損害賠償請求を検討することになるでしょう。
しかし加害者本人への請求対応をスムーズに済ませるには、交通事故トラブルに関する知識・経験が必要となります。その点、弁護士であればすべての請求対応を一任できますのでおすすめです。事務所によっては無料相談なども行っていますので、まずは相談だけでも利用してみると良いでしょう。
弁護士に相談するかお悩みの方へ
下のボタンからあなた当てはまるものを選んで悩みを解消しましょう。
弁護士費用特約があれば 実質0円で依頼できます!

多くの保険会社では、被害者1名につき最大300万円までの弁護士費用を負担してくれます。特約があるか分からない方でも、お気軽にご相談ください。弁護士と一緒にご確認した上で依頼の有無を決めて頂けます。
特約を利用して弁護士に相談する交通事故問題を依頼する弁護士の選び方にはポイントがあります。
等です。
詳しくは以下の記事を読んで、正しい弁護士の選び方を理解した上で弁護士に相談しましょう。
弁護士の選び方について詳しくみる
【来所不要・交通事故の被害者は初回相談料0円】◆豊富な解決実績◆示談金の大幅な増額実績多数◆交通事故専門チームが丁寧に対応します。まずは無料でご相談ください。【「錦糸町駅」南口から徒歩9分】
事務所詳細を見る
提示された賠償金に納得がいかない方は、アディーレへご相談を!適正な賠償金を受け取るためにサポートします◆自転車・バイク事故にも対応◆
事務所詳細を見る
【人身事故被害者の方へ】事故直後・通院中いずれの場合もまずはご相談ください。弁護士への依頼で、結果が大きく変わるかもしれません。【初回面談無料】【着手金無料プランあり】【オンラインで全国対応可能】
事務所詳細を見る
本記事では、自賠責保険の休業補償の受け取り方法や請求時のポイントを解説します。休業補償や休業損害は、相手方の保険会社と争いになりやすい部分でもあるため、ポイント...
自動車保険の契約をする際に、弁護士特約に加入するかどうか悩んでいる方も多いのではないでしょうか?本記事では、弁護士特約の加入率と加入するメリットなどについて詳し...
弁護士特約は、自動車保険のほか火災保険やクレジットカードなどにも付帯しているケースがあり、重複していること自体は一見無害にも見えます。しかし、弁護士特約が付帯し...
弁護士特約の利用を保険会社に嫌がられることはほとんどありません。しかし、なかには嫌がられるケースもあるので、適切な対応を知っておくことが大切です。本記事では、弁...
レンタカーを運転中に事故を起こしてしまい、多額の金額を支払わねばならないのではないかと不安に思っている方も多いのではないでしょうか。本記事では、レンタカーの交通...
自賠責保険は、交通事故の被害者に対して最低限の補償を提供することを目的としています。本記事では、自賠責保険による傷害補償の限度額(120万円)やその内訳、超過分...
この記事では、交通事故の加害者が任意保険を使わない場合の、示談金が振り込まれるまでの流れを解説します。示談金がなかなか振り込まれない場合の対処法も紹介するので、...
物損事故による車の修理代は、自腹で支払うほか対物賠償保険や車両保険で賄うこともできます。しかし、ケースによって異なるため、判断基準を知っておくと安心です。本記事...
業務中または通勤中に発生した交通事故については、労災保険と自賠責保険の両方によって補償の対象となることがあります。 労災保険給付と自賠責保険の保険金のうち、ど...
任意保険に入っていないと、多額の損害賠償責任を負うことがあります。反対に、無保険の相手と事故した場合は、十分な補償を受けられない可能性があるので注意が必要です。...
自賠責保険の慰謝料金額は、入通院慰謝料で日額4,300円、後遺障害慰謝料で32万円〜1,850万円、死亡慰謝料で400万円〜1,350万円となっています。本記事...
被害者請求とは、交通事故被害者が自賠責保険会社に対し、後遺障害等級認定の申請や保険金請求を行う手続きです。状況により被害者請求が適しているか異なりますので、この...
自賠責保険への加入は義務、民間の車保険(任意保険)への加入は自由と言われていますが、両者の違いが理解できていないと契約の判断が難しいのではないかと思います。この...
「自賠責保険の加入したい場合はどこに行けばいいの?」「更新時にはどんな手続きが必用?」など、自賠責保険の加入・更新をする方法をまとめました。自賠責保険の契約手続...
自賠責基準(じばいせききじゅん)とは、交通事故により負傷した被害者に対して、法令で決められた最低限の補償を行うことを目的とした基準のことです。
万が一の事故に備える為にはいろいろな方法がありますが、今回はその中でもかなりおすすめできる個人賠償責任保険をご紹介します。
他車運転特約(たしゃうんてんとくやく)とは、保険の対象となっている被保険者などが、他人の車を借りて運転している際に交通事故を起こした場合に、自分が契約している車...
任意保険基準とは、自動車保険会社が独自に設けている慰謝料の基準で、最低限の保障を行う自賠責保険基準と過去の判例を基に算出する弁護士基準の、丁度中間に設定されてい...
免責補償(めんせきほしょう)とは、レンタカーの運転で事故を起こした場合に、レンタカー会社が事故における負担額を契約内容に沿って補償してくれる制度です。
自動車損害賠償保障法とは、交通事故で死傷した被害者から加害者に対する責任追及を容易にするため、故意・過失の証明責任を加害者側に負わせる民事損害賠償責任の規定を記...
交通事故により未成年が死亡した場合、将来を考慮し高額になるケースがあります。逆に、未成年が死亡事故を起こした場合、たとえ被害者が死亡したとしても、加害者本人に慰...
本記事では、自動車事故の過失割合が、保険金額や被害者の自己負担額に対してどのように影響するのかを解説します。 自動車事故の被害に遭い、保険会社との示談交渉など...
交通事故被害の保険金をいつもらえるかは事故の状況や被害者の状態によってそれぞれです。この記事では自賠責保険の慰謝料を受け取れるタイミングや先払いを受ける方法など...
他車運転特約(たしゃうんてんとくやく)とは、保険の対象となっている被保険者などが、他人の車を借りて運転している際に交通事故を起こした場合に、自分が契約している車...
交通事故の加害者は、被害者に対して損害賠償責任を負うほか、自らもケガや車の破損などによって大きな損害を受けることがあります.。 交通事故を起こしてしまい、大き...
任意保険に入っていないと、多額の損害賠償責任を負うことがあります。反対に、無保険の相手と事故した場合は、十分な補償を受けられない可能性があるので注意が必要です。...
「自賠責保険の加入したい場合はどこに行けばいいの?」「更新時にはどんな手続きが必用?」など、自賠責保険の加入・更新をする方法をまとめました。自賠責保険の契約手続...
弁護士特約は、自動車保険のほか火災保険やクレジットカードなどにも付帯しているケースがあり、重複していること自体は一見無害にも見えます。しかし、弁護士特約が付帯し...
自動車保険の契約をする際に、弁護士特約に加入するかどうか悩んでいる方も多いのではないでしょうか?本記事では、弁護士特約の加入率と加入するメリットなどについて詳し...
交通事故の慰謝料を自賠責保険に請求する方法や流れ、補償される上限金額などの情報を解説しながら、十分な慰謝料を得るための方法を紹介していきます。
物損事故による車の修理代は、自腹で支払うほか対物賠償保険や車両保険で賄うこともできます。しかし、ケースによって異なるため、判断基準を知っておくと安心です。本記事...
自転車事故の多発が叫ばれるなか、自転車に乗る人が自転車保険に加入する事をおすすめしています。そこで今回は、自転車保険を選ぶ際のおすすめできる自転車保険をご紹介し...