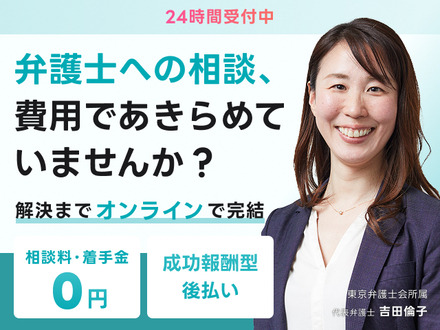交通事故は、いつ起きるのかわかりません。
突然事故に遭ってしまい、その後の流れがわからずに困っている方も多いでしょう。
事故が起きてから損害賠償金を獲得するまでにかかる期間は、怪我の程度にもよります。
たとえば、大怪我を負った事故では、2年程度通院してから示談交渉をおこなうケースもあります。
また、軽い打撲で後遺症もなく2週間程度で治った事故では、解決までに1ヵ月もかからないこともあり得るでしょう。
本記事では、交通事故が起きて慰謝料・賠償金が支払われるまでの流れについて解説します。
交通事故に遭ってしまった方へ
交通事故に遭った際、まずは以下の事故対応を心がけましょう。
- けが人の救出と警察への連絡
- 事故現場の確認と加害者情報の確認
- 目撃者の確保と保険会社への連絡
- なるべく早く病院で診察を受ける
事故対応を誤った場合、賠償金が低額になるなど、自身が損をする可能性があるので注意が必要です。
冷静な判断が困難な場合、弁護士へ依頼することで以下のメリットがあります。
-
事故直後の適切な対応を教えてくれる
-
示談交渉や面倒な手続きを一任できる
-
適切な額の損害賠償金を獲得できる
事故直後の段階で弁護士へ依頼することで、早期解決が望めます。
まずは、交通事故が得意な弁護士へご相談ください。
交通事故の流れ①|事故発生から警察が到着するまで
交通事故に遭ったらどうすればよいでしょうか。
まずは、交通事故直後の流れとやっておくべきことを解説します。
-
STEP1
警察に連絡する
- 連絡しないと、慰謝料や治療費を請求できなくなるリスクあり
-
STEP2
現場の情報を記録する
- 損害賠償請求の際に有効な証拠となる
-
STEP3
加害者の情報を記録する
- 感情的にならずに、冷静に対応することが重要
-
STEP4
自分の保険会社に連絡する
- 保険会社に「事故発生の日時・場所・事件の概要」を通知
1.警察に連絡する
まずは、なんといっても交通事故に遭ったら警察を呼んでください。
いざ事故当事者になってしまうと、事故処理や救急処置などで呼び忘れてしまうこともあるでしょう。
また、軽い交通事故だと、加害者から「警察は呼ばずに自分達だけで解決させましょう」などと提案されることもありますが、それに応じてしまうと、後日体の痛みが生じたりしても事故の証明ができずに慰謝料や治療費などを請求できないリスクが発生します。
「警察を呼ばないほうがすぐに解決しそう」などと思って通報せずにいると、被害者にとって不利益しかありません。
加害者から持ちかけられても決して応じずに、必ず警察を呼びましょう。
2.現場の情報を記録する
警察が到着するまでの間、2つのことをやってください。
まず1つ目が、現場の状況を記録することです。
警察が来れば後に現場検証をおこないますが、自分でも記録しておけば後の損害賠償請求で有効な材料になります。
特に抑えておくべき情報としては、以下があります。
- 事故車の損害箇所
- 事故現場や当日の状況
- 事故が起きるまでの経緯
- 第三者の目撃情報・住所・連絡先など
事故車の損害箇所など
被害に遭ったのは、自身の体だけではありません。
乗用車・自転車・バイクに乗って被害に遭ったのであれば、事故車の被害状況も把握しておきましょう。
スマートフォンを持っていれば、写真に撮っておくことが一番手っ取り早く確実です。
事故現場や当日の状況
事故現場の状況も抑えておきましょう。
事故現場の周囲の交差点や信号の位置関係、また事故当日の天候や路面の状況や交通量など、残せるものは全て写真やメモに残しましょう。
詳しくは警察の事情聴取で事細かに聞かれますが、時間が経つと細かいことは忘れてしまうものです。
加害者が少しでも自分に有利になるように嘘を付いた場合には反論材料になりますし、メモを取っておくことで加害者にいい加減なことを言わせないための牽制にもなります。
事故が起きるまでの経緯
事故が起きるまでの経緯も記録しておきましょう。
信号無視なのか、一時停止したのか、スピードはどれくらい出ていたのかなど、なぜ事故が起きたのかを記録してください。
第三者の目撃情報や住所・連絡先
第三者の目撃証言は非常に強力です。
もし事件直後に目撃者がいるようであれば、目撃証言を抑えておきましょう。
後に損害賠償請求をする際に証言してもらうこともあるため、連絡先や住所も聞いておくようにしてください。
3.加害者の情報を記録する
警察が来るまでにやってほしいことのもう一つが、加害者の情報を聞き出すことです。
なかには「なんであなたに話さないといけないんだ」などと非協力的な場合もありますが、感情的にならず冷静に対応しましょう。
ただし、最終的には警察を通じて情報を取得できるため、無理に聞き出す必要はありません。
圧倒的に有利な状況なのは被害者のほうです。
相手が非協力的な場合は「教えてくれないならば訴えることもできますよ」などと伝えるなどして、相手のことを聞いてください。
その際に抑えるべき情報は以下の3点です。
- 加害者の氏名・住所・連絡先
- 加害車両の登録番号・所有者
- 加害車両の保険内容など
加害者の氏名・住所・連絡先
氏名と住所は運転免許証とともに確認しましょう。
後ほど損害賠償のやり取りもあるので、あわせて連絡先も聞いておきましょう。
加害車両の登録番号・所有者
加害車両のナンバーに記載された登録番号をメモします。
また、加害車両が加害者本人のものとは限らないため、所有者も確認しましょう。
加害車両の保険内容等
加害車両の自賠責保険・任意保険の会社名、契約者名、契約番号を確認しましょう。
主に、これからの交渉は加害者側の保険会社とおこなうことになるため大切な情報です。
4.自分の保険会社に連絡する
これは後日でも構いません。
任意保険に加入している場合、保険会社に「事件発生の日時・場所・事故の概要」を通知しましょう。
保険金が下りるかどうかは事件の状況や契約内容によって変わりますが、この通知がないことには手続きには入れません。
交通事故の流れ②|警察が到着した際の対応
交通事故の被害者も警察から事情聴取を受けます。
もちろん怪我の程度が大きければそちらの回復が最優先ですが、警察の捜査には可能な限り協力しましょう。
被害者側の供述がなければ、加害者側の一方的な供述のみで捜査が進められる可能性も出てきます。
捜査が加害者有利に進められてしまうと、後の損害賠償請求にも影響が出てきます。
ここでは、警察が到着した際の対応について解説します。
警察の事情聴取に応える
警察からの事情聴取の際に作られるものが「供述調書」です。
これは、後の損害賠償請求にも重要になってきます。
対応にあたっては以下のポイントを押さえておくことが重要です。
わからないことは正直に伝えて真実を話す
わからないことはわからないと答えて、嘘はつかずに本当のことだけを堂々と話しましょう。
加害者が嘘の供述をしている場合は「それは違います」と真実を述べれば、嘘の供述を前提とした処理を防ぐことができます。
そこで非常に有効になるのが、上記で解説した事故後の現場での記録です。
この記録は捜査の際に役立ちます。
事故の証拠は全て提示する
事故後に集めた証拠は、警察から求められなくてもこちらから提示してください。
加害者の嘘を暴くきっかけになるかもしれませんし、損害賠償金の増額材料になることもあります。
ただし、警察に一度提出した証拠は長期間返還されないこともあるため、提出前には写しを取っておいてください。
供述調書の内容に誤りがなければ署名・押印をする
供述調書が作成されると最後に一通り読みあげられ、内容に不足や誤りがなければ署名・押印して完了します。
ただし、流れるようにおこなわれる警察の捜査に対して、ただ言われるがままに従っているだけだと、簡単な処理で済まされることもあります。
もし少しでも納得できないことがあれば署名・押印には簡単に応じず、十分に確認して納得したうえで対応しましょう。
少しでも怪我をしている場合は人身事故で届け出る
人身事故というと「車に轢かれた」「自動車が大破した」などのイメージがあるかもしれませんが、たとえ軽い怪我でも診断書があって警察が受領すれば人身事故として扱われます。
事故により身体的な被害があったと報告がなければ、物損事故として扱われます。
物損事故で扱われてしまうと「自賠責保険」は適用されない可能性があり、結果的に損害賠償金の回収ができないという問題が生じる可能性もあります。
※人身事故証明書入手不能理由書を提出した場合は請求可能です。
少しでも怪我をしたのであれば、診断書をもらって人身事故として処理してもらいましょう。
加害者に対して処分が科される
交通事故は「物損事故」と「人身事故」に分かれ、加害者にはそれぞれ以下のような処分が科されます。

物損事故の場合
人的被害の出ていない物損事故では、加害者が刑事罰に処せられることはありません。
「車を傷つけられたから器物損壊罪だ」と思う方もいるかもしれませんが、故意にやっていない過失犯の場合は適用されません。
物損事故の加害者が負う責任は民事責任となります。
なお、飲酒運転やスピード超過などのケースでは道路交通法違反で罰せられることもあります。
人身事故の場合
交通事故により人を傷つけたり死亡させたりした場合、加害者側は民事責任と刑事責任を問われます。
人身事故では過失運転致死傷罪に処され、刑罰は「7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金」です(自動車運転処罰法第5条)。
なお、飲酒運転・薬物使用運転・速度超過・信号無視などの悪質な原因があって人身事故を起こした場合、危険運転致死傷罪に処されます。
危険運転で傷害を負わせた場合は15年以下の懲役、危険運転で死亡させた場合は1年以上20年以下の懲役が科せられることになります(自動車運転処罰法第2条)。
ただし、人身事故で刑事責任が問われるといっても、よほど悪質なケースなどを除けば略式手続きで罰金刑になることがほとんどです。
略式手続きでの罰金刑とは、簡単にいうと「罰金を支払うことで、公開の裁判が行われず刑事手続きが終了する」というものです。
交通事故の流れ③|病院でけがの治療を受ける際の対応

交通事故の被害者は、目立った外傷がなくても病院で診察を受けてください。
脳内出血や骨折など、実は怪我をしていて、あとから痛みや痺れが出てくることもあります。
ここでは、病院でけがの治療を受ける際の対応について解説します。
診察・治療費の支払いをおこなう
交通事故のけがの治療でかかった病院での費用は、最終的に加害者・保険会社に請求できます。
病院によっては加害者の保険会社に直接請求してくれるところもありますが、一旦は費用を被害者本人が立て替えることもあります。
病院には「交通事故の被害者なのですが、費用の請求先を◯◯(加害者側の保険会社)にしてもらえませんか」と一度相談してみましょう。
被害者本人が立て替える場合は、必ず領収書を保管しておきましょう。
交通事故でも健康保険は利用できる
なかには「交通事故のけがでは健康保険を使えない」と勘違いしている方もいるかもしれませんが、交通事故でも健康保険は使えます。
しかし、交通事故で健康保険を使う際は「第三者行為による傷病届」を届け出る必要があります。
これは他人にけがをさせられた場合に健康保険に届け出て、後日加害者に対する求償を可能にしてもらうという手続きです。
もし病院に「健康保険は使えない」と言われた場合は、「第三者行為の届出中です」と伝えましょう。
詳しい手続きの方法は、健康保険組合や各都道府県の国民健康保険課などに問い合わせてみてください。
また、以下の記事でも解説しているので参考にしてください。
保険会社から治療費の打ち切りを告げられた場合は交渉する
一般的に、各保険会社では治療期間の基準があります。
なかには、治療途中の段階で保険会社から治療費の支払い打ち切りが告げられることもあります。
不当に打ち切られた場合には、のちの交渉や裁判などで打ち切り後の費用を受け取ることができます。
相手保険会社から治療費の打ち切りを告げられたら、一旦は健康保険を使って治療費を立て替えたりしながら治療を続けて、一度弁護士に相談してください。
症状固定と判断された場合は後遺障害申請をおこなう
交通事故のケガが完治せずに医師から症状固定と判断された場合は、後遺障害診断書などの必要書類を準備して後遺障害申請をおこないます。
症状固定とは「これ以上治療を続けても改善が困難」という状態のことで、医師によって判断されます。
後遺障害等級は第1級から第14級まであり、申請手続きをして損害保険料率算出機構から等級認定を受けることで、後遺障害に関する賠償金が請求できるようになります。
交通事故の流れ④|加害者・被害者間の示談交渉
交通事故の示談交渉は、事故による損害が確定したタイミングでおこないます。
ここでは、事故後の示談交渉について解説します。
基本的に示談交渉は相手保険会社とおこなう
示談交渉は、基本的に被害者と加害者の保険会社の間でおこなわれます。
ただし、相手保険会社は任意保険基準という独自の計算基準を用いて慰謝料などを計算するため、言われるがまま示談に応じてしまうと「もっともらえたはずだったのに」などと後悔することもあります。
提示された賠償金に納得できずに不信感がある場合は、一度弁護士に相談してみてください。
弁護士であれば「提示額は適切か」「増額できる余地はないか」などのアドバイスが望めます。
原則として示談成立後は撤回・やり直しできない
基本的に一度示談が成立すると、あとになってから合意内容を変更することはできません。
相手方の主張に対して少しでも疑問や不満がある場合は安易に応じず、納得のいくまで交渉を続けることが大切です。
示談が成立しなかった場合は裁判手続きに移行する
示談交渉が難航して解決が難しい場合は、以下のような手続きに移行します。
民事調停
民事調停とは、調停委員による仲介のもと、裁判所で話し合いをおこなって解決を図る手続きのことです。
調停委員会が双方の主張内容を聞き取って合意を目指しますが、あくまでも話し合いで解決を目指す手続きであり、裁判官による判決などはありません。
民事調停でも妥協点が見つからず解決が難しい場合は、民事訴訟に移行します。
損害賠償請求訴訟
民事訴訟では、裁判所で当事者双方が証拠などを用いて主張立証をおこないます。
十分に尽くされたところで、最終的には裁判官によって判決が下されます。
ただし、民事訴訟は民事調停よりも長期化しやすく手続きも複雑であるため、弁護士に依頼しておこなうのが一般的です。
示談交渉は弁護士に依頼するのがおすすめ
交通事故で示談交渉をおこなう際は、交通事故トラブルが得意な弁護士に依頼しましょう。
弁護士なら、依頼者の代理人として示談交渉や裁判などでのやり取りを一任でき、後遺障害申請などの事故手続きも代行してくれます。
相手方の提示額が不当に低い場合は的確に反論してくれるなど、依頼者が損を被らないように尽力してくれますし、法律知識や交渉ノウハウを活かしてスムーズな問題解決が望めます。
特に以下のような方には、弁護士への依頼をおすすめします。
- 慰謝料が妥当なのか知りたい
- 事故により後遺症が生じてしまった
- 後遺障害等級が認定されなかった
- 過失割合が妥当なのかわからない
- 被害者が亡くなっている
- 弁護士費用特約に加入している
用語解説
- 弁護士費用特約
- 弁護士費用特約とは、任意保険のオプションです。
- これがあると、弁護士費用を最大300万円、法律相談料を10万円まで保険会社が補償してくれます(上限は保険会社で異なります)。
- 弁護士費用特約は本人が加入していなくても、以下のような続柄の人が加入している場合、利用できます。


交通事故の流れ⑤|慰謝料・賠償金の支払い
相手方との示談が成立すれば、示談書の作成後に合意した金額が支払われて終了となります。
多くの場合、示談成立日の約1週間~2週間後に指定の銀行口座へ一括で振り込まれます。
交通事故の流れに関するよくある質問
ここでは、交通事故の流れに関するよくある質問について解説します。
交通事故にあったらまず何をしますか?
負傷者がいる場合は救護して、現場の安全を確保したのち110番通報しましょう。
なお、警察への通報は義務であり、もし怠った場合は報告義務違反として「3ヵ月以下の懲役または5万円以下の罰金」が科されるおそれがあります(道路交通法第119条1項10号)。
交通事故をした時の被害者の流れは?
被害者の場合も上記と同様の初期対応を済ませて、警察の到着を待つ間に事故現場や加害者の情報などを記録しましょう。
その後は警察による事情聴取に対応し、病院でけがの治療などを済ませたのち、相手方と示談交渉をおこなうというのが基本的な流れです。
軽い接触事故・物損事故の場合の流れは?
負傷者がいない事故の場合も基本的な流れは同じで、速やかに警察へ通報して加害者の連絡先などを記録しましょう。
警察とのやり取りを済ませたのち、車両の修理費用の見積もりなどを確認して損害額が確定すれば、相手方と示談交渉をおこなうことになります。
警察が交通事故のあとにおこなうことは何ですか?
通報を受けて到着した警察官は、事故現場にて事実確認や証拠保全をおこないます。
車両の破損状況などのチェック・当事者双方からの情報収集・目撃情報の収集などをおこない、事故情報などを実況見分調書にまとめます。
警察が作成する実況見分調書は示談交渉でも有効な証拠となるため、警察からの質問に対してはできるだけ丁寧かつ詳しく答えましょう。
まとめ|交通事故後に絶対押さえておきたい4つのポイント
ここでは、おさらいを兼ねて交通事故後に押さえておきたいポイントを4つ紹介します。
ここだけはしっかり覚えておきましょう。

1.交通事故に遭ったら必ず警察を呼ぶ
交通事故の当事者には警察を呼ぶ義務があります。
負傷者の確認や安全確保などが済んだら、速やかに通報しましょう。
2.余裕がある場合は自分でも現場の状況を記録する
警察が到着すれば現場検証がおこなわれますが、自分でも現場状況を記録しておくことで損害賠償請求する際に有効な材料になります。
可能であれば、自分でもスマートフォンなどで記録しておきましょう。
3.軽い怪我や違和感でも病院で診察を受けて、人身事故で処理してもらう
人身事故と物損事故では、受け取れる損害賠償額に大きな違いが生じます。
交通事故によって少しでも身体に違和感があれば必ず病院に行き、警察に人身事故として処理してもらうようにしましょう。
4.損害賠償請求で疑問を感じたら弁護士に相談する
交通事故での最終的な解決方法は金銭によるものです。
しかし、金銭が絡む場面ではトラブルが生じるおそれもあります。
加害者と揉めたりして難航している場合は、無料相談からでもよいので弁護士に相談しましょう。



























 慰謝料・損害賠償
慰謝料・損害賠償
 示談
示談
 過失割合
過失割合
 死亡事故
死亡事故
 後遺障害
後遺障害
 むちうち
むちうち
 自転車事故
自転車事故
 自動車事故
自動車事故
 人身事故
人身事故
 バイク事故
バイク事故