10対0の交通事故で代車費用は請求できる?5つの条件と代車利用のポイント

過失割合10対0の交通事故に遭った被害者は本来、加害者から車の修理費用や身体の治療費、そのほかかかった費用を全て支払ってもらう権利があります。
ただし、代車費用については、どのような条件下でも加害者側が請求に応じてくれるとは限りません。
事故車両よりも明らかにグレードが高い代車を使った場合、必要性がないのに代車をレンタルした場合、修理期間を超過して代車を使用し続けた場合などでは、代車費用をめぐって加害者側の保険会社との争訟に発展する可能性が高いです。
そこで本記事では、過失割合10対0の交通事故における代車費用の扱い、交通事故に巻き込まれたときに弁護士へ相談するメリットなどについてわかりやすく解説します。
ベンナビ交通事故では、代車費用をめぐる問題など交通事故でのトラブル解決に長けた弁護士を多数紹介中です。
初回相談無料などのサービスを提供している法律事務所も数多く掲載しているので、ぜひ一度弁護士に相談してみてください。
10対0の交通事故で代車費用は請求できるのか?
交通事故の被害に遭ったときには、自車両を修理工場に出したり、新しく車を購入したりする期間中、代車を使用せざるを得ないケースは少なくありません。
そして、過失割合10対0の交通事故では、発生した全ての損害について加害者側へ賠償請求できます。
ただし、これは「交通事故と法律上の因果関係が認められる限りの代車費用」に限られる点には注意が必要です。
そのため、「なかなか新車の購入手続きが進まないから何年も代車を使用したい」などの要望はとおりにくいでしょう。
以上を踏まえると、過失割合10対0の交通事故の代車費用については以下3点が重要だといえるでしょう。
- 過失割合10対0の交通事故では、不法行為に基づく損害賠償請求の一項目として代車費用を加害者側に請求できる
- 加害者側に請求できる代車費用は「交通事故と法律上の因果関係がある範囲」に限定される
- 自分が加入している任意保険会社の代車サービスを利用できる可能性がある
10対0の交通事故で代車費用を請求するための5つの条件
過失割合10対0の交通事故といえど、代車費用を無制限に請求できるわけではありません。
ここでは、過失割合10対0の交通事故において加害者側に代車費用を請求するための条件を5つ紹介します。
1.代車を使用していること
過失割合10対0の交通事故において代車費用を加害者側に請求するには、「実際に代車を使用した事実」が必要です。
不法行為に基づく損害賠償請求では、「実際に発生した損害」を前提に賠償額を算出します。
そのため、「代車を使用していれば〇〇万円かかったはず」という架空の事実を前提に、加害者側に仮定的代車費用を請求することはできません。
ただし、非常にまれなケースではあるものの、修理をおこなう必要があるのはほぼ確実であり、かつ代車費用がかかることが確実であるようなケースでは、代車を利用していない段階で将来の代車費用が認められる可能性もあります。
2.代車費用を支払っていること
過失割合10対0の交通事故で加害者側に代車費用を請求するには、「実際に代車費用を支出した事実」が要求されます。
というのも、代車を使用したにもかかわらず費用負担が発生していないのなら、不法行為責任における「損害」も存在しないと扱われるからです。
例えば、ディーラーから無償で代車を貸し出してもらえた場合、知人や親族に無料で代車を借りた場合には、被害者側は一切の費用負担なく代車を使用できているので、代車費用の請求は認められないでしょう。
3.代車費用が適切な金額であること
過失割合10対0の交通事故に遭ったときの代車費用は、「適切な金額」の範囲でしか加害者側に請求できません。
具体的には、「事故に遭った車両と同種・同年式の代車を使用したときの費用」が上限とされます。
例えば、軽自動車を運転中に交通事故に遭ったとき、高級車を代車として使ったとしても、加害者側に請求できるのは「代車として軽自動車を使用したときに生じる費用」に限られます。
事故車両が軽自動車なら代車も軽自動車、事故車両が国産普通車なら代車も同じグレードの国産普通車、といった基準で算定されます。
ただし、高級外車を運転中に交通事故に遭ったときの代車費用については注意が必要です。
一概には言えないものの、もし高級外車が交通事故で損傷しても、国産高級車の代車費用程度の賠償しか認めないのが通常です。
そもそも代車費用は、「代替的な交通手段を確保するために緊急的に要した車両費用」という性質の項目であり、「自家用車を保有している状態」自体を補填するものではありません。
国産軽自動車・国産普通車程度なら標準的な国民が使用している常識的な範囲なので代車費用が認められますが、ブランド的価値のある嗜好品としての車両についてはそのまま代車費用は請求しにくいでしょう。
4.代車を使用する必要性があること
過失割合10対0の交通事故で代車費用を請求できるのは、「実際に代車を使用する必要性があるとき」に限られます(代車使用の必要性)。
例えば、通勤・通学・通院などに自動車を欠かせない場合、営業車として自動車を使用していた場合、普段の買い物などで日常的にマイカーを使用していた場合などでは、代車の必要性があると判断されやすいでしょう。
これに対して、普段はまったく自動車を使用する機会がなく、レジャーの際などに自動車を使っていた程度であれば、代車費用の請求は認められない可能性が高いでしょう。
5.代車の使用期間が適切であること
過失割合10対0の交通事故で代車費用を加害者側に請求できるのは、「代車の必要性が認められる期間分」、つまり修理や買い替えに要する期間に限られます。
代車費用の請求が認められる目安となる期間は、修理の場合には約2週間、買い替えの場合には約1ヵ月間です。
もちろん、交換部品の調達に数週間を要する場合や、修理か買い替えの判断に迷うのが当然の場合には、代車の負担日数がさらに2週間前後増えてしまうことがあるようです。
代車を使用せざるを得ない事情が原因で使用期間が長期化しているにもかかわらず、加害者側の保険会社から代車費用の一部を認めない旨の主張がされたときには、速やかに弁護士へ相談・依頼をして加害者側の保険会社との間での協議を進めてもらいましょう。
10対0の交通事故で代車を利用する場合の3つのポイント
ここでは、過失割合10対0の交通事故で代車を利用するときのポイント3つを紹介します。
1.事前に保険会社に使用する代車や期間について確認しておく
実際に代車を使用したあとに、代車費用について加害者側とトラブルに発展するのは面倒なものです。
このようなトラブルを回避するためには、事前に加害者側の保険会社と代車の諸条件について話し合いを済ませておくとよいでしょう。
例えば、代車のグレード、代車の使用期間などについて事前に加害者側の保険会社から合意を得ておけば、代車費用の賠償について不安のない状態で代車を使用できるはずです。
特に、高級外車などのグレードの高い車両で事故に遭ったときには、どこまでの代車費用を任意で払ってくれるかについて加害者側の条件を確認しておきましょう。
2.代車の必要性や車種の妥当性などを証明できる証拠を確保しておく
代車費用についてあとから加害者側の保険会社とトラブルになったときに備えて、代車使用の必要性・代車種類の相当性・代車使用期間の相当性を根拠付ける証拠を確保しておくのがおすすめです。
証拠をあらかじめ確保しておけば、加害者側との示談交渉や民事訴訟でこちら側の主張を根拠付けるのに役立つでしょう。
例えば、通院のために代車を要したのなら治療費や薬代の明細、通勤のために代車を使用せざるを得ないなら自宅から会社に至るまでの経路を示す地図などを用意しておきましょう。
3.代車費用や修理費用などを請求する際は一度弁護士に相談しておく
過失割合10対0の交通事故で被害を受けたときには、弁護士へまずは一度相談することをおすすめします。
というのも、交通事故トラブルを得意とする弁護士へ相談することで以下のメリットを得られるからです。
- 代車費用を根拠付ける証拠を収集してくれる
- 治療通院などのために忙しい状況でも、加害者側保険会社との示談交渉や民事訴訟の手続きを全て代理してくれる
- 弁護士が代理人に就任したほうが加害者側保険会社から有利な条件を引き出しやすくなる
ベンナビ交通事故では、交通事故トラブルを得意とする弁護士を多数掲載中です。
法律事務所の所在地・具体的な相談内容・初回相談無料などのサービス面から弁護士を絞り込めるので、自身の希望にかなった弁護士を見つけることができるでしょう。
加害者に代車費用を請求できない場合は自分の代車特約を使うのもおすすめ
被害者側が加入している車両保険に代車費用特約が付帯されている場合には、代車費用特約を活用するのも選択肢のひとつです。
代車費用特約(レンタカー費用特約/事故・故障時代車費用特約)とは、交通事故によって自分の車両が使えなくなったときに、修理期間や買い替え期間中、契約者が代車を借りる費用を補償してくれるものです。
保険会社によって特約プラン内容は異なりますが、「日額7,000円、補償期間30日間」などの条件が設定されていることが多いです。
加害者側に対して代車費用を請求できないケースでは、自分が加入している保険会社の特約を使えば自己負担なく代車費用の補償を受けることができるでしょう。
ただし、自分の代車費用特約を使用するときには、以下の点に注意しましょう。
- 補償期間の起算点に注意する(事故発生日、工場入庫時など、プランによって異なる)
- 代車費用の補償期間に上限が設けられていることが多い
- 故意・重過失で交通事故を引き起こしたときには適用されない場合がある
- 特約が適用される代車は指定されたレンタカー会社の所有者に限られることが多い
- 過失割合10対0の交通事故のように車両保険を使用せずに特約のみを使うなら等級に影響するリスクは少ないが、保険会社の運用次第なので念のために事前確認が必要
- 毎年特約保険料の負担を強いられる
- 交通事故後に代車費用特約へ加入するのはほぼ不可能
加害者側の保険会社に対して代車費用を粘り強く請求するべきか、自分の契約する保険会社の特約を利用するべきかは、事案によって判断が分かれます。
ぜひ交通事故トラブルの経験豊富な弁護士のアドバイスを参考にしてください。
交通事故の代車費用に関するよくある質問
最後に、過失割合10対0の交通事故に遭った被害者側から寄せられる代車費用に関する質問を、Q&A形式で解説します。
Q.10対0以外の交通事故では代車費用を請求できないのか?
代車費用は不法行為に基づく損害賠償における「損害」の項目のひとつです。
そして、交通事故で発生した損害については、当事者双方の過失割合を確定したうえでそれぞれの過失割合にしたがって損害額を分担するのが決まりです。
例えば、過失割合10対0の交通事故の場合には、被害者側の過失割合は0、加害者側の過失割合が100%なので、加害者側が代車費用を含む全ての損害額を支払わなければいけません。
また、過失割合1対9の交通事故の場合には、自分の過失割合が10%、相手方の過失割合が90%なので、この割合にしたがって賠償額が振り分けられます(実際には、過失相殺をして金銭を授受する運用がとられています)。
ただし、悪質な保険会社のなかには、「過失割合10対0の交通事故以外では代車費用を支払わない」などの運用をとっている会社も存在する点に注意が必要です。
加害者側の保険会社の言いなりになると、本来であれば一部でも請求できたはずの代車費用を全額こちら側で負担しなければいけなくなってしまいます。
保険会社は、少しでも自社の損失を減らそうとする傾向にあります。
万が一、加害者の加入する保険会社から代車費用の支払いを拒絶されたときには、念のために弁護士へ相談し、本当に代車費用を請求できない事案なのか、代車費用以外にも損をしているポイントの有無について確認してもらうべきでしょう。
Q.代車費用は物損事故だけでなく人身事故でも請求できるか?
実際に代車を使用した事実があり、代車種類の相当性・代車使用の必要性・代車使用期間の相当性の要件を満たす限りにおいて、代車費用を加害者側に請求できます。
「人身事故だから代車費用を請求できない」「代車費用を請求できるのは物損事故だけ」など、物損事故か人身事故かは、代車費用の請求可否には一切影響しません。
さいごに|代車費用など交通事故の示談金に関することは弁護士に相談を
過失割合10対0の交通事故の場合、被害者側に生じた費用負担・損害額は全額加害者側に請求できるようにも思えます。
しかし、本記事で解説したように、「代車費用」というひとつの損害項目についても、代車使用の必要性などの要件を満たさない限り、加害者側に請求することはできません。
ほかにも、修理費用の範囲、過失割合の認定、後遺障害等級の問題など、交通事故に巻き込まれるとさまざまな事項について加害者側とのトラブルが生じかねません。
ベンナビ交通事故では、代車費用などの交通事故トラブルを得意とする弁護士を多数掲載中です。
弁護士に任せるだけで示談交渉や民事訴訟を有利に進めやすくなるので、この機会にぜひベンナビ交通事故から信頼できそうな弁護士へ相談してみてください。
弁護士に相談するかお悩みの方へ
下のボタンからあなた当てはまるものを選んで悩みを解消しましょう。
弁護士費用特約があれば 実質0円で依頼できます!

多くの保険会社では、被害者1名につき最大300万円までの弁護士費用を負担してくれます。特約があるか分からない方でも、お気軽にご相談ください。弁護士と一緒にご確認した上で依頼の有無を決めて頂けます。
特約を利用して弁護士に相談する交通事故問題を依頼する弁護士の選び方にはポイントがあります。
- 過去の解決事例を確認する
- 料金体系が明確である弁護士を選ぶ
- 交通事故問題が得意な弁護士から選ぶ
等です。
詳しくは以下の記事を読んで、正しい弁護士の選び方を理解した上で弁護士に相談しましょう。
弁護士の選び方について詳しくみる
【人身事故被害者の方へ】事故直後・通院中いずれの場合もまずはご相談ください。弁護士への依頼で、結果が大きく変わるかもしれません。【初回面談無料】【着手金無料プランあり】【オンラインで全国対応可能】
事務所詳細を見る
【元警察官(警部補)弁護士が経験を活かした交渉を】「怪我で通院している」「御家族が交通事故で亡くなった」など【LINE、WEB、電話で完結】【相談料無料】【着手金0円/365日対応】
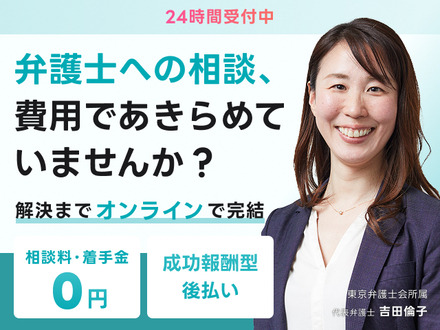
相談料・着手金0円、費用倒れの心配なし。大手より低価格な料金体系で増額実績多数。交通事故専門チームが後遺障害認定から交渉まで強力サポート。LINE完結・来所不要で全国対応。
事務所詳細を見る当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡

交通事故後の対応に関する新着コラム
-
本記事では、交通事故の被害に遭った方に向けて、交通事故用の示談書の簡単な書き方と流れ、交通事故用の示談書を簡単に書くために押さえておくべき4つのコツ、示談書の作...
-
本記事では、自転車と自動車間の過失割合がどのように設定されるかや、自転車と自動車間の交通事故が起きたときの対処法・注意点を解説します。
-
非接触事故で転倒がなくても、後で怪我に気づくことがあります。適切な対処法を理解せずに立ち去ると問題になる可能性があるため、本記事では転倒なしの非接触事故における...
-
交通事故トラブルを抱えるなかで、弁護士だけでなく行政書士にも対応してもらえることを知り、主に費用面が気になっている方も多いのではないでしょうか。本記事では、行政...
-
本記事では、レンタカーを運転していて交通事故に遭った場合、相手が100%悪くてもレンタカー会社へお金を支払わなければならない理由やレンタカー会社からお金を請求さ...
-
本記事では、交通事故の被害に遭った方に向けて、被害者が利用できる保険(自賠責保険・任意保険)の種類、加害者の自賠責保険と被害者の任意保険を使用する順番、加害者側...
-
交通事故によるけがで仕事を休む場合、いつ頃復帰するのが適切なのでしょうか?本記事では、交通事故が原因で仕事を休む場合の一般的な休業期間や、休業した場合にもらえる...
-
交通事故に遭った場合、会社から診断書の提出を求められることがあります。しかし、費用の問題などからためらっている方も多いのではないでしょうか。本記事では、交通事故...
-
本記事ではもらい事故でできる限り得したいと考えている方に向けて、もらい事故で得する(損しない)ための3つの基礎知識、もらい事故で得したい人が弁護士に依頼するメリ...
-
本記事では、交通事故の被害者の方に向けて、交通事故の示談が成立した場合、どのくらいに示談金が振り込まれるか説明しています。また、振り込みが遅れる場合のパターン、...
交通事故後の対応に関する人気コラム
-
当て逃げに遭ってしまった方へ、少しでも解決に近づけるための対処法をご紹介します。
-
物損事故とは、怪我人や死亡者がなく車両などに損害が出たにとどまる交通事故のことです。物損事故では相手方と示談交渉で揉めてしまう可能性もありますので、ポイントをお...
-
交通事故発生後は、警察に連絡・治療(人身事故の場合)・保険会社との交渉と進んでいきます。本記事では、各場面の詳しい対応や、いつ連絡が来るのかなどの期間についても...
-
交通事故が起きて被害者となった場合、「自分は被害者だから、待っているだけで何もする必要はない」と考えているなら、それは大きな間違いだと言えます。
-
交通事故が起きたら、物損事故・人身事故問わず警察へ届け出なければいけません。これは法律で義務付けられており、報告を怠ると法律違反として処罰を受ける可能性もありま...
-
交通事故のうち3割は駐車場で起こっているといわれています。駐車場は私有地になるため、事故が起こったあとの対処が一般道路とは異なる部分があります。本記事では、駐車...
-
事故後の対応や手続きを適切におこなうことで、その後の補償や示談交渉をスムーズに進められます。本記事では、交通事故にあった際に最初にとるべき行動、その後の手続きの...
-
車でおかまをほられた(後ろから追突された)ときに、どのように対処すればよいかご存知でしょうか。この記事では、車でおかまをほられた際の流れと対処法、示談金などを紹...
-
接触事故とは、走行中の自動車が車両・物・人などに接触して、損害や傷害が生じた事故のことです。接触事故では「怪我の有無」で賠償金の内容が異なりますので、事故後の流...
-
ひき逃げ事故は、その後の人生を大きく左右する重大な問題です。本記事では、ひき逃げ事故に遭われた被害者の方、そしてひき逃げ事故を起こしてしまった加害者の方が、事故...
交通事故後の対応の関連コラム
-
交通事故に怪我は付きものです。その際に治療先の治療院はどこを選べばいいのか?治療費は妥当なのか?が気になると思いますので、ご紹介していきます。
-
本記事ではもらい事故でできる限り得したいと考えている方に向けて、もらい事故で得する(損しない)ための3つの基礎知識、もらい事故で得したい人が弁護士に依頼するメリ...
-
交通事故の被害に遭った際は、加害者の情報を記録しておくことが大切です。適切な保険金や損害賠償を受け取るために必ず必要なものになってきますので、ぜひこの記事を参考...
-
事故後の対応や手続きを適切におこなうことで、その後の補償や示談交渉をスムーズに進められます。本記事では、交通事故にあった際に最初にとるべき行動、その後の手続きの...
-
非接触事故で転倒がなくても、後で怪我に気づくことがあります。適切な対処法を理解せずに立ち去ると問題になる可能性があるため、本記事では転倒なしの非接触事故における...
-
交通事故の被害者がさまざまな不満を抱いているなら、裁判を提起するのも選択肢のひとつです。 交通事故被害者が民事裁判を提起すべき事案や、交通事故裁判を弁護士に依...
-
本記事では、交通事故証明書の取得方法・取得場所を調べている方に向けて、交通事故証明書に関する基礎知識、交通事故証明書の4つの取得方法、交通事故証明書を取得できな...
-
本記事では、被害者の視点から当て逃げの被害届を出す理由・放置したときのリスク・やるべき手続き・加害者に対する損害賠償請求について、詳しく解説します。当て逃げで泣...
-
交通事故に巻き込まれた際は、できるだけ早く弁護士に相談することが大切です。支払ってもらえる保険金額や逸失利益を計算したい場合もあるでしょう。本記事では、後遺障害...
-
通勤中に交通事故に遭った場合、自動車保険だけでなく労災保険が使用できるケースもあります。十分な補償を受けるためにも、それぞれの中身を正しく理解しましょう。本記事...
-
日弁連交通事故相談センターは交通事故の民事上の紛争解決をサポートしてくれる専門機関です。事故直後から利用でき、電話相談、面接相談、示談あっ旋などに幅広く対応して...
-
後遺障害等級の認定に当たっては、後遺症の症状や交通事故との因果関係などが精査されます。本記事では、後遺障害等級の認定は厳しいのかどうかや認定されない理由、非該当...
交通事故後の対応コラム一覧へ戻る


























 慰謝料・損害賠償
慰謝料・損害賠償
 示談
示談
 過失割合
過失割合
 死亡事故
死亡事故
 後遺障害
後遺障害
 むちうち
むちうち
 自転車事故
自転車事故
 自動車事故
自動車事故
 人身事故
人身事故
 バイク事故
バイク事故






























