交通事故で弁護士特約を使ってみた感想 | 使うべきケースや使い方も解説

自動車保険を契約する際の弁護士特約について「よくわからないけど、付けた方がいいの?」と悩んでいる方も多いのではないでしょうか。
結論から言えば、弁護士特約は付けておいたほうがよいですし、事故の際には弁護士特約を使用したほうがメリットがあります。
本記事では、弁護士特約をつけることのメリットを、実際に弁護士特約を使ってみた人の感想とともに詳しく解説します。
交通事故で弁護士特約を使ってみた方の感想を紹介
任意保険で実際に弁護士特約を使った方の感想を紹介します。
体験談①:保険会社からの電話が一切なく、ストレスなく手続きを終えられた
弁護士費用特約を使ってからは保険会社からの電話は車の物損が終了してからは一切ありません。
仕事中も保険会社からの電話を気にしなくてよくなったので、ストレスがなくなりました。
弁護士特約を使って、弁護士に示談交渉を依頼すれば、相手方の保険会社とのやり取りは全て弁護士がおこなってくれます。
自分で示談交渉をおこなう場合には、仕事中などに保険会社から電話がかかってくることも多く、ストレスを感じる人も少なくありません。
弁護士特約を使うことによって、精神的に解放されて、ストレスがなくなる点は大きなメリットだといえるでしょう。
体験談②:適切な慰謝料を獲得できた
僕は今回、慰謝料に納得できずに弁護士特約を使いましたが、もちろん通院期間に納得できない場合も弁護士特約で解決できます。
法律相談費用が10万円に 弁護士費用が300万円までなので、早々オーバーすることはないので面倒くさいですが、必ず使うべきオプションだと思います。
何かあった時のために弁護士特約のオプションを付けて、使用しないでいる方も多数いるとは思いますが、事故こそ何かあった時で保険会社は自賠責基準の慰謝料しか出してくれません。
そんな時こそ正しく弁護士特約を使って、弁護士基準の適正な慰謝料をもらうべきだと思います。
慰謝料に納得できない場合も弁護士特約があることによって、適切な慰謝料を獲得できる可能性があります。
慰謝料の算定基準には、自賠責基準と任意保険基準と弁護士基準という3つの基準があります。
事故の被害者自ら慰謝料の示談交渉をおこなうと自賠責基準でしか慰謝料が支払われないことが一般的です。
しかし弁護士に示談を依頼すると、弁護士基準で慰謝料の請求がおこなわれます。
場合によっては慰謝料が2倍〜3倍になることもあるので、弁護士特約を使用して慰謝料請求をおこなったほうが受け取れる慰謝料が圧倒的に高くなります。
弁護士費用は安くはありませんが、弁護士特約をつけておけば、ほとんどのケースで相談料も弁護士費用も保険金の範囲内で受け取れます。
弁護士特約とは | ほんとうに必要、使ったほうがよいの?
弁護士特約とは、主に自動車保険に付帯される、弁護士費用を補償する特約です。
以下では、弁護士特約の特徴について詳しく解説します。
主に自動車保険に付帯する、弁護士費用を補償する特約
弁護士特約とは、主に自動車保険に付帯できる特約です。
弁護士に事故の示談などを依頼すると、通常は多額の費用が発生します。
料金は弁護士によって異なるものの、着手金と報酬を合わせると、100万円〜150万円程度の費用がかかるのが一般的です。
弁護士へ依頼するには高額なお金が必要になりますが、弁護士特約をつけておけば保険金から弁護士費用が支払われるため、弁護士費用の心配をすることなく弁護士へ示談交渉の依頼ができます。
弁護士特約で補償される弁護士費用の上限
弁護士特約には、補償費用の上限が設けられていることが一般的です。
詳細な内容は保険によって異なるものの、1回の事故で300万円というのが相場です。
1回の事故で300万円の弁護士費用が補償されれば、一般的な示談交渉であれば十分に弁護士特約からまかなうことができるでしょう。
また、司法書士や行政書士への書類作成依頼も弁護士特約でまかなうことができますが、この場合は1回の事故で10万円まで補償されるのが一般的です。
弁護士特約は交通事故と日常事故の補償が受けられるタイプがある
弁護士特約を利用できるのは交通事故だけではありません。日常の生活の中での事故も弁護士特約が利用できる場合があります。
日常生活の中で補償が受けられる事故には、次のようなものがあります。
- 歩行中に自転車にぶつけられてケガをした
- ひったくりにあった
- マンションの上階からの水漏れで家財が被害を受けた
このように、交通事故とは全く無関係の事故でも弁護士特約を利用できる場合があります。
日常生活でも利用できるため、弁護士特約をつけておけば、生活の中のさまざまなトラブルで活用できて安心です。
なお、保険によっては日常生活の事故には使用できず、交通事故のみをカバーしているものもあので、詳しくは保険会社へ確認してみましょう。
契約者のほか、契約者の家族も使える
弁護士特約を利用できるのは契約者本人だけではありません。
契約者の家族も利用できる保険が多く、一般的には次の範囲までが保険の対象となります。
- 契約者本人
- 契約者の配偶者
- 契約者の同居の家族(6親等内の血族・3親等内の婚族)
1人が弁護士特約付きの保険を契約しておけば、家族の交通事故の際にも弁護士を利用できるため、大きな安心を得られます。
物損事故でも弁護士特約を使うことは可能
弁護士特約は、人身事故に限らず物損事故でも利用可能です。
物損事故であっても相手の自動車が高級車などの場合、相手から法外な損害賠償を請求されることがあります。
弁護士特約に加入していれば、このような無茶な要求に対して弁護士が毅然と対応できるため安心です。
デメリットはほぼないので弁護士特約は使うのがおすすめ
弁護士特約にはデメリットがほとんどありません。
唯一のデメリットは年間2,000円から3,000円程度の保険料がかかることです。
通常、保険を使用すると等級が上がってしまいますが、弁護士特約を使っても等級が上がることはありません。
そのため、いくら弁護士特約を使用しても保険料が上がることはないのです。
弁護士特約に加入しているのであれば、難しいことは考えずに積極的に弁護士特約を使用し、示談交渉を弁護士へ依頼しましょう。
弁護士特約のメリット
弁護士特約には、以下6つのメリットがあります。
- 弁護士費用の負担をほぼゼロにできる
- 賠償金を増額できる可能性が高まる
- もらい事故でも示談交渉を任せることができる
- 精神的・肉体的な負担から解放される
- 迅速にもとの生活にもどれる
- 自分で依頼先の弁護士を選べる
それぞれのメリットについて、以下で詳しく解説します。
弁護士費用の負担をほぼゼロにできる
弁護士特約をつけておけば、1回あたり300万円まで弁護士費用が補償されます。
通常、交通事故の示談を弁護士に依頼した場合の費用は100万円〜150万円程度ですので、弁護士特約をつけておけば、ほとんどのケースで保険金で弁護士費用をまかなえます。
自己負担がほぼ0円なので、お金の心配をせずに弁護士へ依頼できるのは大きなメリットでしょう。
賠償金を増額できる可能性が高まる
交通事故の被害者が弁護士特約をつけて示談交渉を弁護士へ依頼すると、賠償金を増額できる可能性があります。
賠償金の算定基準には次の3つの種類があります。
- 自賠責基準
- 任意保険基準
- 弁護士基準
この3つの基準のうち、賠償額は自賠責基準が最も安く、弁護士基準が最も高くなります。
交通事故の被害者自ら示談交渉をおこなうと、保険会社は自賠責基準で慰謝料を算定するので受け取れる慰謝料は少なくなります。
一方、弁護士へ依頼すると弁護士基準で慰謝料を算定するので、受け取れる慰謝料は自賠責基準よりも多くなります。
場合によっては自賠責基準の2倍〜3倍の金額となることもあるので、弁護士特約をつけておけば慰謝料や賠償金をより多く受け取れるでしょう。
もらい事故でも示談交渉を任せることができる
もらい事故の場合、被害者側には過失がないので被害者側の保険を使えません。
そのため、交渉に被害者側の保険会社が介入できず、加害者側の保険会社と被害者が示談交渉するのが基本です。
その点、弁護士特約はもらい事故の被害者になった場合も利用できるので、示談交渉を任せることも可能です。
一般個人が加害者側の保険会社と交渉する場合には、交渉が加害者ペースで進み、受けとれる慰謝料が少なくなってしまうリスクがあります。
このような場合に弁護士特約を使用すれば、加害者側の保険会社と弁護士が交渉をおこなってくれるため、受けとれる慰謝料が高額になるでしょう。
精神的・肉体的な負担から解放される
弁護士特約を使用して弁護士を立てると、保険会社との示談交渉は弁護士がおこなってくれます。
自分で交渉すると、仕事中や休日に保険会社から電話がかかってくるため、仕事などに集中できません。
また、そもそも示談交渉そのものがストレスになってしまいます。
弁護士特約をすれば、保険会社から電話がくることは基本的にないので、精神的・肉体的な負担から解放される点もメリットです。
迅速にもとの生活にもどれる
弁護士特約を使用すれば、示談交渉を弁護士に任せられます。
そのため交通事故の当事者は示談交渉に時間を取られ、ストレスを抱えることなく、迅速にもとの生活に戻ることができます。
示談交渉を交通事故の当事者自らがおこなうと、交渉に時間を取られ、仕事に集中できず、仕事外でも休まりません。
一方で、弁護士特約を使用すれば、お金をかけずに日常生活に戻れるのはメリットでしょう。
自分で依頼先の弁護士を選べる
弁護士特約は自分で依頼先の弁護士を選べる点もメリットです。
弁護士特約を利用する際、保険会社はただ弁護士費用を負担するだけです。
そのため保険契約者は次のような流れで弁護士特約を利用して弁護士と契約します。
- 保険に弁護士特約が付いていることを確認
- 依頼する弁護士を探す
- 保険会社に弁護士特約を利用することを伝える
- 弁護士と委任契約を締結
- 保険会社から弁護士へ弁護士費用が支払われる
普段から自分が信頼している弁護士や、自宅近くの弁護士、交通事故問題に強いことで有名な弁護士など、自由に弁護士を選べる点はメリットといえます。
交通事故で弁護士費用特約を特に使うべきケース
交通事故の際に弁護士費用特約を使ったほうがよいケースは以下の4つです。
- もらい事故など被害者の過失割合が0%のケース
- 相手が提示する慰謝料の金額に納得できないケース
- 後遺症が出てしまった場合
- 相手から受け取れる金額より弁護士費用が高くなる費用倒れが不安な場合
弁護士が示談交渉を担当することで、示談交渉が有意に進むため、慰謝料や後遺障害の等級に納得できない場合には、弁護士特約を使用して示談交渉をしたほうがよいでしょう。
以下では、交通事故で弁護士費用特約を使ったほうがよいケースを詳しく解説していきます。
もらい事故など被害者の過失割合が0%のケース
もらい事故などの被害者の過失割合が0%のケースでは、弁護士特約を使用すべきです。
被害者の過失割合が0%の場合には、被害者側の保険を使うことがないので、被害者は加害者側の保険会社と自分で交渉しなければなりません。
保険会社は法律や判例について熟知しているので、被害者自ら交渉すると加害者側のペースで示談交渉が進んでしまい、本来受けとれるべき慰謝料などを受け取れない可能性があります。
そこで弁護士特約を使用すれば、弁護士ペースで交渉が進む可能性が高いため、本来受け取るべき金額をしっかりと受け取れるでしょう。
過失割合0%の事故ほど加害者有利で交渉が進むため、弁護士特約を使用し、弁護士に交渉を任せるのがベストです。
相手が提示する慰謝料の金額に納得できないケース
加害者側の保険会社が提示する慰謝料の金額に納得できない場合は、弁護士特約を使用し、弁護士が交渉することで金額が増える可能性があります。
事故の当事者自らが交渉すると、慰謝料の算定基準の中で最も低い自賠責基準で慰謝料が算定されます。
しかし、弁護士が交渉すると、慰謝料の算定基準の中で最も高額な弁護士基準で算定されるので、慰謝料の金額は高額になる傾向があるのです。
慰謝料の金額が納得できるものでないのであれば弁護士特約を使用し、弁護士基準の慰謝料を勝ち取りましょう。
後遺症が出てしまった場合
交通事故から時間が経ってから後遺症がでた場合も弁護士特約を使用して、弁護士に交渉を依頼するのがよいでしょう。
事故から時間が経ってからの後遺症は「事故との因果関係が証明できない」と加害者側が主張して、適切な慰謝料や後遺障害認定を受けられない可能性があります。
弁護士へ依頼することで、弁護士がしっかりと因果関係を証明し、適切な慰謝料や後遺障害認定を受けられる可能性は高まります。
事故から時間が経って後遺症と思われる症状が出た場合は、弁護士へ依頼したほうがよいでしょう。
相手から受け取れる金額より弁護士費用が高くなる費用倒れが不安な場合
事故の加害者側から受けとれる金額よりも弁護士費用が高くなる場合は、特約を使用したほうがよいでしょう。
一般的に交通事故の際の弁護士費用は100万円〜150万円程度といわれています。
そのため、交通事故の慰謝料が100万円〜150万円以下の場合、弁護士費用の支払いで受け取った慰謝料が無くなってしまいます。
その点、弁護士特約を利用すれば弁護士費用の負担がなくなるため、慰謝料を満額受け取れるでしょう。
弁護士特約を使えない主なケース
弁護士特約は以下のようなケースでは使用できません。
- 交通事故の後に弁護士特約に加入した
- 自転車同士や自転車と歩行者の事故
- 自然災害などによる事故
- 被保険者にも重大な過失があった
弁護士特約は事故の前からあらかじめ加入しておかなければ、事故の際の活用できません。
また、弁護士特約は基本的に車両に関連した事故でなければ使用できないので、自転車同士や自転車と歩行者の事故などには使用できないのが一般的です。
ただし、保険会社によっては車両とは無関係な日常生活の事故でも弁護士特約を使用できる場合があります。
そのほか、次のような自然災害を原因とした事故も弁護士特約を使用できない場合があります。
- 地震
- 噴火
- 台風
- 津波
- 洪水
- 戦争
- 暴動
以下のように、被害者側に重過失がある事故も弁護士特約は使用できないため注意しましょう。
- 無免許運転
- 飲酒運転
- 違法薬物を使用した状態の運転
弁護士特約を使う流れ
弁護士特約は以下の流れで使用します。
- まずは自分の保険契約に弁護士特約が付帯しているか確認する
- 保険会社に弁護士特約を使いたいことを連絡する
- 依頼先の弁護士を探す | 保険会社から紹介された弁護士以外でもOK
- 弁護士と委任契約を結ぶ
- 保険会社へ連絡して、弁護士と委任契約を結んだことを報告する
ここからは、それぞれの流れにおけるポイントや注意点について詳しく解説します。
①まずは自分の保険契約に弁護士特約が付帯しているか確認する
まずは、自分が加入している任意保険に弁護士特約がついているかどうかを確認してください。
任意保険に弁護士特約がついていなくても、次のような保険には弁護士特約がついており、交通事故に使用できる可能性があります。
- 医療保険
- 火災保険
- バイク保険
- 個人賠償責任保険
- クレジットカードの保険
弁護士特約がついていないかどうか、自動車保険以外のほかの保険契約も合わせて確認するようにしてください。
②保険会社に弁護士特約を使いたいことを連絡する
弁護士特約がついていることを確認したら、保険会社へ弁護士特約を使用する旨を伝えます。
あらかじめ保険会社へ伝えてから弁護士を探さないと、あとから「弁護士特約が使えない」と言われて、高額な弁護士費用を事故の当事者が負担しなければならないリスクも生じます。
そのため、必ず保険会社へ弁護士特約を使用したいことを連絡するようにしてください。
また、弁護士特約が使えないケースもあるため、今回の事故のケースでは弁護士特約を使用できるのかということも必ず確認しましょう。
➂依頼先の弁護士を探す | 保険会社から紹介された弁護士以外でもOK
弁護士特約が使用できることを確認したら、依頼する弁護士を探しましょう。
保険会社から弁護士を紹介されることもありますが、自分で弁護士を探しても問題ありません。
自分で弁護士を探す際には、次のポイントを重視するとよいでしょう。
- 交通事故分野に注力している
- 解決実績が豊富
弁護士特約では、相談料も10万円まで補償されます。
弁護士を選ぶ際には10万円の相談料補償をフル活用して複数の弁護士へ相談し、自分に合った弁護士を探してみるとよいでしょう。
④弁護士と委任契約を結ぶ
依頼する弁護士を決めたら、弁護士と委託契約を締結します。
委託契約締結後は、相手方の保険会社が本人へ連絡できなくなり、弁護士へ連絡しなければならないため、相手型の保険会社などから連絡がくることはありません。
⑤保険会社へ連絡して、弁護士と委任契約を結んだことを報告する
弁護士と委託契約を締結したら、再度保険会社へ連絡します。保険会社へは、以下の内容を伝えましょう。
- 依頼する弁護士の名前
- 法律事務所名
- 電話番号
- 住所
基本的には委託契約を締結すれば弁護士から契約内容を記載した書類を渡されるため、その書類を保険会社へ提出すれば問題ありません。
契約後に保険会社へ弁護士と委託契約を締結したことを伝えないと、弁護士特約で補償されない可能性があります。
そのため、契約後には速やかに保険会社へ連絡してください。
なお、弁護士にも「保険会社の弁護士特約を使用する」と伝えておくと、弁護士からも保険会社へ連絡するはずですので、手続きがスムーズに進みます。
交通事故の弁護士特約についてよくある質問
交通事故の弁護士特約についてよくある質問は次のとおりです。
- 自分に過失がないもらい事故でも弁護士特約が使えないケースはありますか?
- 弁護士特約の利用を保険会社が嫌がることはありますか?
- 弁護士特約を使うことができるタイミングに制限はありますか?
それぞれについて、以下で詳しくは回答します。
自分に過失がないもらい事故でも弁護士特約が使えないケースはありますか?
次のような事故は弁護士特約を使用できません。
- 故意や重過失による交通事故
- 自然災害による事故
- 事業用の車の運転中の事故
- 自分が賠償金を請求される側の場合
- 請求相手が親族
- 弁護士特約に加入する前におこった事故
これら以外の事故の場合には、基本的に弁護士特約を使用できますが、保険会社によって詳細な決まりは異なる可能性があるため、詳しくは保険会社へ確認してください。
弁護士特約の利用を保険会社が嫌がることはありますか?
次のようなケースでは、保険会社が弁護士特約の使用を嫌がる可能性があります。
- 事故の過失割合や損害賠償額の争いがない事故
- 被害額の小さい事故
- 被害者に過失がある事故
これらの事故は弁護士を使用しなくても当事者同士の話し合いで比較的簡単に解決したり、示談代行サービスを使用したりすることで解決できる場合があります。
そのため、保険会社は費用が高額になる弁護士特約の使用を嫌がる傾向があります。
しかし、当事者同士の話し合いで解決できるような事故でも、弁護士へ依頼するメリットは大きいため、保険会社が嫌がったとしても遠慮せずに弁護士特約を使用したほうがよいでしょう。
弁護士特約を使うことができるタイミングに制限はありますか?
弁護士特約を使用できるタイミングは「交通事故直後から示談交渉が成立するまで」と決まっています。
そのため、たとえ示談交渉中であっても、示談が成立する前であれば、弁護士特約を使用することができます。
一方、すでに示談が成立した事故については、弁護士特約の使用はできません。
示談成立前であれば、いつでも弁護士特約は使用できますが、後遺障害認定や慰謝料の金額算定が適切におこなわれるよう、なるべく事故発生から早いタイミングで弁護士特約を使用したほうがよいでしょう。
さいごに | 弁護士特約を適切に活用しよう
弁護士特約とは主に自動車保険に付帯される、弁護士費用が補償される特約です。
一般的には1回の事故につき300万円まで補償されます。
弁護士特約があれば、弁護士費用を気にすることなく、交通事故の示談交渉を弁護士に任せられ、使用したことによって等級が下がることもありません。
弁護士へ依頼することで、慰謝料の算定や後遺障害認定で有利になるだけでなく、示談交渉によるストレスからも解放されます。
そのため、任意保険などに弁護士特約がついているのであれば積極的に活用してください。
弁護士は自分で自由に選択できるので、交通事故問題に強く解決件数が多い弁護士を選びましょう。
弁護士に相談するかお悩みの方へ
下のボタンからあなた当てはまるものを選んで悩みを解消しましょう。
弁護士費用特約があれば 実質0円で依頼できます!

多くの保険会社では、被害者1名につき最大300万円までの弁護士費用を負担してくれます。特約があるか分からない方でも、お気軽にご相談ください。弁護士と一緒にご確認した上で依頼の有無を決めて頂けます。
特約を利用して弁護士に相談する交通事故問題を依頼する弁護士の選び方にはポイントがあります。
- 過去の解決事例を確認する
- 料金体系が明確である弁護士を選ぶ
- 交通事故問題が得意な弁護士から選ぶ
等です。
詳しくは以下の記事を読んで、正しい弁護士の選び方を理解した上で弁護士に相談しましょう。
弁護士の選び方について詳しくみる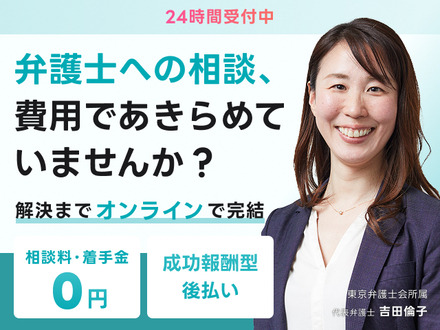
相談料・着手金0円、費用倒れの心配なし。大手より低価格な料金体系で増額実績多数。交通事故専門チームが後遺障害認定から交渉まで強力サポート。LINE完結・来所不要で全国対応。
事務所詳細を見る
【人身事故被害者の方へ】事故直後・通院中いずれの場合もまずはご相談ください。弁護士への依頼で、結果が大きく変わるかもしれません。【初回面談無料】【着手金無料プランあり】【オンラインで全国対応可能】
事務所詳細を見る
【元警察官(警部補)弁護士が経験を活かした交渉を】「怪我で通院している」「御家族が交通事故で亡くなった」など【LINE、WEB、電話で完結】【相談料無料】【着手金0円/365日対応】
当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡

交通事故後の対応に関する新着コラム
-
本記事では、交通事故の被害に遭った方に向けて、交通事故用の示談書の簡単な書き方と流れ、交通事故用の示談書を簡単に書くために押さえておくべき4つのコツ、示談書の作...
-
本記事では、自転車と自動車間の過失割合がどのように設定されるかや、自転車と自動車間の交通事故が起きたときの対処法・注意点を解説します。
-
非接触事故で転倒がなくても、後で怪我に気づくことがあります。適切な対処法を理解せずに立ち去ると問題になる可能性があるため、本記事では転倒なしの非接触事故における...
-
交通事故トラブルを抱えるなかで、弁護士だけでなく行政書士にも対応してもらえることを知り、主に費用面が気になっている方も多いのではないでしょうか。本記事では、行政...
-
本記事では、レンタカーを運転していて交通事故に遭った場合、相手が100%悪くてもレンタカー会社へお金を支払わなければならない理由やレンタカー会社からお金を請求さ...
-
本記事では、交通事故の被害に遭った方に向けて、被害者が利用できる保険(自賠責保険・任意保険)の種類、加害者の自賠責保険と被害者の任意保険を使用する順番、加害者側...
-
交通事故によるけがで仕事を休む場合、いつ頃復帰するのが適切なのでしょうか?本記事では、交通事故が原因で仕事を休む場合の一般的な休業期間や、休業した場合にもらえる...
-
交通事故に遭った場合、会社から診断書の提出を求められることがあります。しかし、費用の問題などからためらっている方も多いのではないでしょうか。本記事では、交通事故...
-
本記事ではもらい事故でできる限り得したいと考えている方に向けて、もらい事故で得する(損しない)ための3つの基礎知識、もらい事故で得したい人が弁護士に依頼するメリ...
-
本記事では、交通事故の被害者の方に向けて、交通事故の示談が成立した場合、どのくらいに示談金が振り込まれるか説明しています。また、振り込みが遅れる場合のパターン、...
交通事故後の対応に関する人気コラム
-
当て逃げに遭ってしまった方へ、少しでも解決に近づけるための対処法をご紹介します。
-
物損事故とは、怪我人や死亡者がなく車両などに損害が出たにとどまる交通事故のことです。物損事故では相手方と示談交渉で揉めてしまう可能性もありますので、ポイントをお...
-
交通事故発生後は、警察に連絡・治療(人身事故の場合)・保険会社との交渉と進んでいきます。本記事では、各場面の詳しい対応や、いつ連絡が来るのかなどの期間についても...
-
交通事故が起きて被害者となった場合、「自分は被害者だから、待っているだけで何もする必要はない」と考えているなら、それは大きな間違いだと言えます。
-
交通事故が起きたら、物損事故・人身事故問わず警察へ届け出なければいけません。これは法律で義務付けられており、報告を怠ると法律違反として処罰を受ける可能性もありま...
-
交通事故のうち3割は駐車場で起こっているといわれています。駐車場は私有地になるため、事故が起こったあとの対処が一般道路とは異なる部分があります。本記事では、駐車...
-
事故後の対応や手続きを適切におこなうことで、その後の補償や示談交渉をスムーズに進められます。本記事では、交通事故にあった際に最初にとるべき行動、その後の手続きの...
-
車でおかまをほられた(後ろから追突された)ときに、どのように対処すればよいかご存知でしょうか。この記事では、車でおかまをほられた際の流れと対処法、示談金などを紹...
-
接触事故とは、走行中の自動車が車両・物・人などに接触して、損害や傷害が生じた事故のことです。接触事故では「怪我の有無」で賠償金の内容が異なりますので、事故後の流...
-
ひき逃げ事故は、その後の人生を大きく左右する重大な問題です。本記事では、ひき逃げ事故に遭われた被害者の方、そしてひき逃げ事故を起こしてしまった加害者の方が、事故...
交通事故後の対応の関連コラム
-
本記事では、交通事故の被害に遭った方に向けて、交番では交通事故証明書をもらえないこと、交通事故証明書のもらい方・申請の流れ、インターネット上からの交通事故証明書...
-
交通事故が起きた際に警察へ電話をすることは法律で義務付けられており、これを怠ることによって様々なリスクが生じる恐れがあります。今回は、交通事故時に警察へ電話をす...
-
交通事故の被害者がさまざまな不満を抱いているなら、裁判を提起するのも選択肢のひとつです。 交通事故被害者が民事裁判を提起すべき事案や、交通事故裁判を弁護士に依...
-
本記事では、出勤中に交通事故の被害に遭った方や備えたい方に向けて、交通事故の被害に遭ったときにとるべき最初の対応、労災保険を請求する際の流れ、加害者や保険会社に...
-
接触事故とは、走行中の自動車が車両・物・人などに接触して、損害や傷害が生じた事故のことです。接触事故では「怪我の有無」で賠償金の内容が異なりますので、事故後の流...
-
交通事故の被害に遭い、軽傷だと思って病院に行かずに放置していたら、実は脳や内臓に強い衝撃を受けていて後日亡くなってしまった…という最悪のケースもあります。この記...
-
交通事故の被害者になってしまった場合、加害者がお見舞いに来ることが一般的ですが、その際に気になるのはお見舞い金の相場です。今回はお見舞い金の相場とお見舞いを受け...
-
交通事故の被害に遭った際は、加害者の情報を記録しておくことが大切です。適切な保険金や損害賠償を受け取るために必ず必要なものになってきますので、ぜひこの記事を参考...
-
通勤中に交通事故に遭った場合、自動車保険だけでなく労災保険が使用できるケースもあります。十分な補償を受けるためにも、それぞれの中身を正しく理解しましょう。本記事...
-
この記事では、事故車を買取に出すべきか、修理するべきか判断するための基準を5つお伝えします。事故車買取のメリットと注意点についてもお伝えするので、あわせてご確認...
-
自転車事故に遭った際は、必ず警察に報告しなければいけません。報告を怠ると、損害賠償請求で不利になる可能性があります。この記事では、自転車事故で警察を呼ばなかった...
-
労災保険給付は、労災の認定要件を満たしている限り、交通事故の被害者・加害者のいずれの立場でも受給可能です。 弁護士のアドバイスを受けながら、交通事故による損害...
交通事故後の対応コラム一覧へ戻る


























 慰謝料・損害賠償
慰謝料・損害賠償
 示談
示談
 過失割合
過失割合
 死亡事故
死亡事故
 後遺障害
後遺障害
 むちうち
むちうち
 自転車事故
自転車事故
 自動車事故
自動車事故
 人身事故
人身事故
 バイク事故
バイク事故
































