交通事故で加害者の治療費は被害者に請求できる?自分の治療費に保険は使える?

交通事故の加害者とされる側でも、治療費の全額が必ず自己負担になるとは限りません。
被害者側にも過失があれば自賠責保険から補償を受けられるほか、加害者自身が加入している人身傷害保険などから補償を受けられることもあります。
交通事故の加害者側が治療費などの補償を受けたい場合は、弁護士に相談しましょう。
本記事では、交通事故の加害者が治療費などの補償を受けられるケースや、保険会社に対して請求できる治療費の内訳などを解説します。
交通事故でけがをした加害者の治療費は誰が払うのか?
交通事故でけがをした加害者の治療費を誰が負担するかは、被害者との間の過失割合や、保険の加入状況などによって決まります。
過失割合10対0の場合、原則として治療費の全額が加害者の自己負担
交通事故について加害者に10割の過失がある場合は、原則として、治療費を含む損害の全額が加害者の自己負担となります。
過失割合が10対0の場合、被害者は一切損害賠償責任を負いません。
被害者が加入している自賠責保険や任意保険も、被害者自身が負う損害賠償責任をカバーするものなので、被害者に損害賠償責任が生じないケースでは保険金を請求することができません。
被害者にも過失がある場合は、被害者の自賠責保険から治療費の支払いを受けられる
交通事故について、被害者側にも何らかの過失がある場合(過失割合が9対1、8対2などの場合)には、被害者が加入している自賠責保険から治療費の支払いを受けることができます。
自賠責保険から支払われる保険金は、請求する当事者に重大な過失がある場合には、下表の割合による減額がおこなわれます。
|
請求する当事者の過失割合 |
減額割合(後遺障害・死亡) |
減額割合(傷害) |
|
7割未満 |
減額なし |
減額なし |
|
7割以上8割未満 |
2割減額 |
2割減額 |
|
8割以上9割未満 |
3割減額 |
2割減額 |
|
9割以上10割未満 |
5割減額 |
2割減額 |
治療費は「傷害」による損害に含まれます。
したがって、加害者の過失割合が7割以上10割未満であれば、積算した傷害による損害額(120万円以上となる場合は120万円)から2割減額されます。
加害者の過失割合が7割未満であれば、保険金の減額はおこなわれず、積算した傷害に係る損害額(120万円以上となる場合は120万円)の全額を受け取ることができます。
ただし、傷害による損害額が20万円未満の場合は減額がおこなわれません。
また、減額によって20万円以下となる場合には、20万円が支払われます。
なお本来であれば、交通事故によって加害者が受けた治療費などの損害は、過失割合に応じて被害者または任意保険会社に支払いを請求できます。
しかし、自賠責保険から支払われた保険金額は、被害者や任意保険会社に対して請求できる金額から控除されます。
自賠責保険の補償が比較的手厚いので、被害者や任意保険会社に対してさらに治療費を請求できるケースは少ないでしょう。
人身傷害保険などに加入していれば、過失割合にかかわらず治療費がカバーされる
交通事故の加害者が人身傷害保険などに加入していれば、自らの過失割合にかかわらず、その保険から治療費などをカバーする保険金を受け取ることができます。
自賠責保険の保険金は、過失割合が10割の場合は受け取れず、過失割合が7割以上の場合は減額されてしまいます。
これに対して、人身傷害保険などの保険金は、過失割合にかかわらず減額されないのが大きなメリットです。
ご自身の加入している保険の内容を問い合わせるなどして、治療費の補償として利用できる保険に加入しているかどうかを確認しましょう。
交通事故で保険会社に請求できる治療費の主な内訳
交通事故によるけがが保険による補償の対象となる場合、保険会社に対しては治療費として、医療機関や薬局に対して支払う費用全般の支払いを請求できます。
具体的には、以下のような治療費を保険会社に対して請求可能です。
- 診察料(初診料、再診料)
- 投薬料
- 検査料
- 入院費用
- 手術費用
- 薬剤の購入費用
- 差額ベッド代(治療に必要な場合に限る) など
治療費以外に、保険会社に請求できる費用の主な内訳
治療費以外にも、交通事故によって加害者が被った損害については、被害者が加入している自賠責保険や自ら加入している人身傷害保険などから補償を受けられることがあります。
具体的には、以下のような損害が補償の対象になります。
発生した損害を漏れなく積算して、適切な補償を受けましょう。
- 入院雑費
- 通院交通費
- 装具、器具の購入費
- 診断書などの費用
- 文書料
- 休業損害
- 入通院慰謝料
- 逸失利益
- 後遺障害慰謝料
- 葬儀費用
- 逸失利益
傷害による損害
交通事故によって加害者が負った傷害に関連して、以下の損害につき保険金を請求できることがあります。
なお損害の項目によっては、自賠責保険による補償の基準(=自賠責保険基準)によって計算される保険金額は、実際の損害額(=裁判所基準)よりも低く抑えられることがある点にご注意ください(後遺障害による損害、死亡による損害についても同様)。
入院雑費
入院中に要する日用品などの購入費用です。
自賠責保険基準では1日当たり1,100円、裁判所基準では1日当たり1,500円程度が認められます。
|
入院雑費 |
入院中に要する日用品などの購入費用です。 自賠責保険基準では1日当たり1,100円、裁判所基準では1日当たり1,500円程度が認められます。 |
|
通院交通費 |
通院時に要する交通費です。 必要かつ妥当な実費が支払われます。 |
|
装具、器具の購入費 |
義肢・義眼・眼鏡・補聴器・松葉杖・サポーターなどの購入費用です。 原則として必要かつ妥当な実費が支払われますが、自賠責保険基準では、眼鏡やコンタクトレンズの費用は5万円が限度とされています。 |
|
診断書などの費用 |
診断書や診療報酬明細書などの発行手数料です。 必要かつ妥当な実費が支払われます。 |
|
文書料 |
交通事故証明書・印鑑証明書・住民票などの発行手数料です。 必要かつ妥当な実費が支払われます。 |
|
休業損害 |
交通事故による傷害が原因で仕事を休んだことにより、減少した収入が補償の対象となります。 有給休暇を取得した場合も、その日数に対応する賃金が補償の対象です。 自賠責保険基準では、原則として1日当たり6,100円が補償されます。 ただし、さらに多額の収入減が生じたことを立証すれば、最大で1日当たり1万9,000円が補償されます。 裁判所基準では、事故当時の収入額を日割りしたうえで、休業日数を掛けた金額が補償されます。 |
|
入通院慰謝料 |
交通事故による傷害について生じた精神的・肉体的な苦痛に対する補償です。 対象日数は、被害者の傷害の状態や実治療日数などを勘案して、治療期間内で決められます。 裁判所基準では、入院期間と通院期間に応じて入通院慰謝料の金額を計算します。 |
自賠責保険では、傷害による損害の補償限度額は120万円です。加害者の過失割合が7割以上10割未満の場合は、積算した傷害による損害額(120万円上限)から2割減額されます。
加害者の過失割合が10割の場合は、自賠責保険による補償は受けられません。ただし、10対0の事故の加害者であっても、ご自身の人身傷害保険から入通院慰謝料を受け取れる可能性があります。
入通院慰謝料の相場
入通院慰謝料の相場は、請求する保険(ご自身の人身傷害保険か、相手方の自賠責保険・任意保険か)と、その計算基準によって大きく異なります。一般的に、相手方の保険に対し弁護士(裁判)基準で請求する場合が最も高額になる傾向があります。
入院慰謝料の相場(入院なし、週に3日通院した場合)
|
治療期間 |
人身傷害保険の目安 (※1) |
自賠責基準 (※2) |
弁護士基準(むちうちなど軽傷) |
弁護士基準(骨折など重傷) |
|
1ヵ月 |
4万円~10万円程度 |
8.6万円 |
19万円 |
28万円 |
|
3ヵ月 |
15万円~30万円程度 |
20.64万円 |
53万円 |
73万円 |
|
6ヵ月 |
30万円~60万円程度 |
41.28万円 (※3) |
89万円 |
116万円 |
- ※1 人身傷害保険の基準は保険会社や契約内容により異なります。あくまで一般的な目安です。
- ※2 自賠責保険の傷害慰謝料は、2020年3月31日以前の事故については1日4,200円、2020年4月1日以降の事故については1日4,300円で計算されます。上記は4,300円で計算した場合の最大額です(月30日計算)。
- ※3 自賠責保険の支払い基準では、傷害による損害の限度額は120万円と定められています。治療費や休業損害なども含めた総額がこの範囲内となります。
後遺障害による損害
交通事故によって加害者が負ったけがが完治せずに後遺症が残った場合は、以下の損害につき保険金を請求できることがあります。
|
逸失利益 |
後遺症によって労働能力が失われた場合に、将来にわたって生じる収入の減少に対する補償です。 事故当時の収入、認定される後遺障害等級(1級~14級)に応じた労働能力喪失率、年齢などから求められる労働能力喪失期間などによって金額を計算します。 |
|
後遺障害慰謝料 |
交通事故による後遺症について生じた精神的・肉体的な苦痛に対する補償です。 認定される後遺障害等級(要介護1級・2級、1級~14級)に応じて支払われます。 |
|
将来介護費 |
重度の後遺障害により、将来にわたって介護が必要となる場合に認められる費用です。 |
自賠責保険では、後遺障害による損害の補償限度額は4,000万円(要介護1級)、最低額は75万円(14級)です。加害者の過失割合が7割以上10割未満の場合は、積算した後遺障害による損害額から2割から5割減額されます。
加害者の過失割合が10割の場合は、自賠責保険による補償は受けられません。ただし、10対0の事故の加害者であっても、ご自身の人身傷害保険から入通院慰謝料を受け取れる可能性があります。
後遺障害慰謝料の相場
後遺障害慰謝料の相場は、認定された後遺障害等級と、請求する保険(ご自身の人身傷害保険か、相手方の自賠責保険・任意保険か)で決まります。入院慰謝料と同様に、弁護士(裁判)基準で請求する場合が最も高額になる傾向です。
|
後遺障害等級 |
人身傷害保険の目安 (※1) |
自賠責基準 |
弁護士基準 |
|
第14級 |
32万円~75万円程度 |
32万円 |
110万円 |
|
第12級 |
94万円~224万円程度 |
94万円 |
290万円 |
|
第9級 |
249万円~616万円程度 |
249万円 |
690万円 |
|
第7級 |
419万円~1,000万円程度 |
419万円 |
1,000万円 |
|
第1級 |
1,150万円~3,000万円程度 |
1,150万円 (※2) |
2,800万円 |
死亡による損害
交通事故によって加害者が死亡した場合には、以下の損害につき保険金を請求できることがあります。
|
葬儀費用 |
葬儀に要する、通夜・祭壇・火葬・墓石などの費用です。 墓地と香典返しは除きます。 自賠責保険基準では100万円、裁判所基準では150万円程度を上限とする実費相当額が認められます。 |
|
逸失利益 |
死亡によって得られなくなった将来の収入に対する補償です。 事故当時の収入や、年齢から求められる労働能力喪失期間などによって金額を計算します。 |
|
死亡慰謝料 |
交通事故によって死亡したことにより生じた精神的・肉体的な苦痛に対する補償です。 |
死亡慰謝料の相場
死亡慰謝料の相場は、弁護士を通じて交渉する(弁護士基準)場合や、人身傷害保険に請求する場合は、亡くなられた方の家庭内での立場(一家の支柱であったか、母親・配偶者であったかなど)によって大きく変動します。
一般的に、相手方の保険に対し弁護士(裁判)基準で請求する場合が最も高額になる傾向です。
|
対象・条件 |
人身傷害保険基準(※1) |
弁護士基準(裁判基準) |
|
一家の支柱(家計の主な担い手) |
1,500万円~2,000万円 |
2,800万円 |
|
母親・配偶者 |
1,300万円~1,600万円 |
2,500万円 |
|
その他(子ども、高齢者、独身者など) |
1,100万円~1,500万円 |
2,000万円~2,500万円 |
(※1) 人身傷害保険の死亡保険金は、慰謝料だけでなく逸失利益なども含む包括的な金額として契約時に定められていることが一般的です。
一方、自賠責保険では遺族の人数や被扶養者の有無によって算出されます。
|
対象・条件 |
自賠責保険基準 |
|
被害者本人の慰謝料 |
400万円 |
|
遺族の慰謝料(遺族一人) |
550万円 |
|
遺族の慰謝料(遺族二人) |
650万円 |
|
遺族の慰謝料(遺族三人以上) |
750万円 |
|
被扶養者がいた場合の加算 |
+200万円 |
|
合計支払い限度額(死亡による損害) |
上限3,000万円(慰謝料・逸失利益・葬儀費含む) |
(※2) 自賠責基準の金額は、本人分400万円に加え、遺族の人数に応じた金額が加算されます。
ご自身の過失が100%(10対0)の事故で、加害者ご自身が亡くなられたという場合には、ご遺族は加害者が加入していた人身傷害保険から死亡保険金を受け取ることができます。
もし、事故の状況を精査した結果、相手方にも過失が認められるようなケースであれば、上記の自賠責基準や弁護士基準を参考に、相手方の保険会社と交渉を進めることになります。このような場合は、法律や交渉の専門家である弁護士にご相談いただくことを強くおすすめします。
加害者のみがけがをした場合でも、人身事故として届け出るべきか?
交通事故の被害者がけがをしておらず、加害者のみけがをしているという場合、加害者としては以下の理由により、人身事故として警察に報告した方がよいと考えられます。
自賠責保険の保険金を請求する際には、人身事故の交通事故証明書の提出を求められます。
被害者側に何らかの過失があり、加害者が自賠責保険の保険金を請求できる場合には、人身事故として届け出た方がよいでしょう。
加害者自身のけがは、行政処分(運転免許の違反点数)や刑事処分(刑罰)との関係で、加害者の不利益に考慮されることはありません。
そのため被害者にけががなく、加害者のみけがをしている場合には、人身事故として届け出ることに不都合はないと考えられます。
さいごに|加害者でも治療費を請求したい場合は弁護士へ相談を
交通事故の加害者であっても、被害者に何らかの過失がある場合は、治療費などについて自賠責保険の保険金を請求できます。
また、加害者自身が加入している人身傷害保険などを利用すれば、過失割合にかかわらず治療費などの補償を受けることが可能です。
交通事故の加害者となってしまった方が、治療費などについて保険会社に適正な補償を請求したい場合には、弁護士へ相談することをおすすめします。
弁護士に相談すれば、各種保険の内容を確認したうえで、保険金の請求手続などをサポートしてもらえます。
「ベンナビ交通事故」には、交通事故事件を豊富に取り扱っている弁護士が多数登録されています。
相談内容や地域に応じて、スムーズに弁護士を検索可能です。
交通事故について無料相談を受け付けている弁護士も数多く登録されていますので、保険会社に治療費などを請求したい交通事故当事者の方は、「ベンナビ交通事故」を通じてお早めに弁護士へご相談ください。
弁護士に相談するかお悩みの方へ
下のボタンからあなた当てはまるものを選んで悩みを解消しましょう。
弁護士費用特約があれば 実質0円で依頼できます!

多くの保険会社では、被害者1名につき最大300万円までの弁護士費用を負担してくれます。特約があるか分からない方でも、お気軽にご相談ください。弁護士と一緒にご確認した上で依頼の有無を決めて頂けます。
特約を利用して弁護士に相談する交通事故問題を依頼する弁護士の選び方にはポイントがあります。
- 過去の解決事例を確認する
- 料金体系が明確である弁護士を選ぶ
- 交通事故問題が得意な弁護士から選ぶ
等です。
詳しくは以下の記事を読んで、正しい弁護士の選び方を理解した上で弁護士に相談しましょう。
弁護士の選び方について詳しくみる
【人身事故被害者の方へ】事故直後・通院中いずれの場合もまずはご相談ください。弁護士への依頼で、結果が大きく変わるかもしれません。【初回面談無料】【着手金無料プランあり】【オンラインで全国対応可能】
事務所詳細を見る
【元警察官(警部補)弁護士が経験を活かした交渉を】「怪我で通院している」「御家族が交通事故で亡くなった」など【LINE、WEB、電話で完結】【相談料無料】【着手金0円/365日対応】
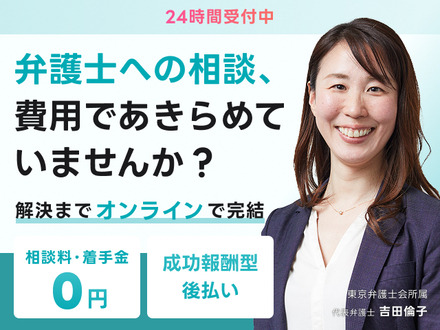
相談料・着手金0円、費用倒れの心配なし。大手より低価格な料金体系で増額実績多数。交通事故専門チームが後遺障害認定から交渉まで強力サポート。LINE完結・来所不要で全国対応。
事務所詳細を見る当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡

交通事故後の対応に関する新着コラム
-
本記事では、交通事故の被害に遭った方に向けて、交通事故用の示談書の簡単な書き方と流れ、交通事故用の示談書を簡単に書くために押さえておくべき4つのコツ、示談書の作...
-
本記事では、自転車と自動車間の過失割合がどのように設定されるかや、自転車と自動車間の交通事故が起きたときの対処法・注意点を解説します。
-
非接触事故で転倒がなくても、後で怪我に気づくことがあります。適切な対処法を理解せずに立ち去ると問題になる可能性があるため、本記事では転倒なしの非接触事故における...
-
交通事故トラブルを抱えるなかで、弁護士だけでなく行政書士にも対応してもらえることを知り、主に費用面が気になっている方も多いのではないでしょうか。本記事では、行政...
-
本記事では、レンタカーを運転していて交通事故に遭った場合、相手が100%悪くてもレンタカー会社へお金を支払わなければならない理由やレンタカー会社からお金を請求さ...
-
本記事では、交通事故の被害に遭った方に向けて、被害者が利用できる保険(自賠責保険・任意保険)の種類、加害者の自賠責保険と被害者の任意保険を使用する順番、加害者側...
-
交通事故によるけがで仕事を休む場合、いつ頃復帰するのが適切なのでしょうか?本記事では、交通事故が原因で仕事を休む場合の一般的な休業期間や、休業した場合にもらえる...
-
交通事故に遭った場合、会社から診断書の提出を求められることがあります。しかし、費用の問題などからためらっている方も多いのではないでしょうか。本記事では、交通事故...
-
本記事ではもらい事故でできる限り得したいと考えている方に向けて、もらい事故で得する(損しない)ための3つの基礎知識、もらい事故で得したい人が弁護士に依頼するメリ...
-
本記事では、交通事故の被害者の方に向けて、交通事故の示談が成立した場合、どのくらいに示談金が振り込まれるか説明しています。また、振り込みが遅れる場合のパターン、...
交通事故後の対応に関する人気コラム
-
当て逃げに遭ってしまった方へ、少しでも解決に近づけるための対処法をご紹介します。
-
物損事故とは、怪我人や死亡者がなく車両などに損害が出たにとどまる交通事故のことです。物損事故では相手方と示談交渉で揉めてしまう可能性もありますので、ポイントをお...
-
交通事故発生後は、警察に連絡・治療(人身事故の場合)・保険会社との交渉と進んでいきます。本記事では、各場面の詳しい対応や、いつ連絡が来るのかなどの期間についても...
-
交通事故が起きて被害者となった場合、「自分は被害者だから、待っているだけで何もする必要はない」と考えているなら、それは大きな間違いだと言えます。
-
交通事故が起きたら、物損事故・人身事故問わず警察へ届け出なければいけません。これは法律で義務付けられており、報告を怠ると法律違反として処罰を受ける可能性もありま...
-
交通事故のうち3割は駐車場で起こっているといわれています。駐車場は私有地になるため、事故が起こったあとの対処が一般道路とは異なる部分があります。本記事では、駐車...
-
事故後の対応や手続きを適切におこなうことで、その後の補償や示談交渉をスムーズに進められます。本記事では、交通事故にあった際に最初にとるべき行動、その後の手続きの...
-
車でおかまをほられた(後ろから追突された)ときに、どのように対処すればよいかご存知でしょうか。この記事では、車でおかまをほられた際の流れと対処法、示談金などを紹...
-
接触事故とは、走行中の自動車が車両・物・人などに接触して、損害や傷害が生じた事故のことです。接触事故では「怪我の有無」で賠償金の内容が異なりますので、事故後の流...
-
ひき逃げ事故は、その後の人生を大きく左右する重大な問題です。本記事では、ひき逃げ事故に遭われた被害者の方、そしてひき逃げ事故を起こしてしまった加害者の方が、事故...
交通事故後の対応の関連コラム
-
追突事故では被害者の過失が0になるケースが多く賠償金も高額になりやすいですが、事故後の対応を誤ると適正な金額を受け取れなくなる恐れがあるためご注意ください。この...
-
本記事では、交通事故の被害に遭った方に向けて、被害者が利用できる保険(自賠責保険・任意保険)の種類、加害者の自賠責保険と被害者の任意保険を使用する順番、加害者側...
-
交通事故が起きたら警察へその旨を報告をし、その後は現場検証が行われます。現場検証は、被害者と加害者の過失割合を決める重要なものになるので、知識をもって臨むことが...
-
交通事故が起きて被害者となった場合、「自分は被害者だから、待っているだけで何もする必要はない」と考えているなら、それは大きな間違いだと言えます。
-
交通事故に遭った場合、会社から診断書の提出を求められることがあります。しかし、費用の問題などからためらっている方も多いのではないでしょうか。本記事では、交通事故...
-
自転車事故で被害者が死亡した場合、残された遺族は加害者に対して「死亡慰謝料」や「死亡逸失利益」などの損害賠償を請求できます。納得のいく金額を受け取るためにも、示...
-
交通事故の相手が外国人でも、通常の交通事故と同様に損害賠償を請求することができます。しっかりと賠償金を受け取るためにも、事故時の対応方法について知っておきましょ...
-
本記事では、出勤中に交通事故の被害に遭った方や備えたい方に向けて、交通事故の被害に遭ったときにとるべき最初の対応、労災保険を請求する際の流れ、加害者や保険会社に...
-
交通事故の被害に遭い、軽傷だと思って病院に行かずに放置していたら、実は脳や内臓に強い衝撃を受けていて後日亡くなってしまった…という最悪のケースもあります。この記...
-
交通事故の被害に遭った際は、加害者の情報を記録しておくことが大切です。適切な保険金や損害賠償を受け取るために必ず必要なものになってきますので、ぜひこの記事を参考...
-
本記事では、治療費の打ち切りを打診されたり、実際に打ち切られたりしても、むちうちの治療を継続する方法や、MRIで異常がなくても後遺障害等級の認定を受けられる可能...
-
自損事故とは、被害者がおらず運転者が単独で起こした事故のことです。自損事故でも自動車保険を利用できますが、その前に警察への届け出などが必要です。この記事では、自...
交通事故後の対応コラム一覧へ戻る


























 慰謝料・損害賠償
慰謝料・損害賠償
 示談
示談
 過失割合
過失割合
 死亡事故
死亡事故
 後遺障害
後遺障害
 むちうち
むちうち
 自転車事故
自転車事故
 自動車事故
自動車事故
 人身事故
人身事故
 バイク事故
バイク事故




























