自転車事故で車と衝突!パターン別の過失割合や事故後の対処法を解説

- 「自動車と自転車の間で事故になった。過失割合はどうなるだろう。」
- 「自動車と自転車の交通事故が起きた場合、どのように対応すればいいのか。」
自動車・自転車間の交通事故では、自動車同士の事故とは異なる過失割合が設定されます。
交通事故の当事者になった場合、どのような過失割合になるかは気になるところでしょう。
また交通事故に慣れていないと対処方法がわからず、これからどうしていいか不安になるものです。
本記事では、自転車と自動車間の過失割合がどのように設定されるかや、自転車と自動車間の交通事故が起きたときの対処法・注意点を解説します。
交通事故の対応を誤ると、示談金の額が不当に低くなったり高くなったりなどして、大きな損をしてしまうことも少なくありません。
本記事を読んで交通事故の対応を適切にすすめれば、そういった損をしてしまうのを予防できます。
自転車と車の事故における過失割合の傾向
まずは、自転車と自動車の交通事故について、過失割合がどのように認定されるかを解説します。
自転車の過失割合は車に比べて低くなりやすい
自転車は自動車に比べると過失割合が低くなりやすい傾向です。
大前提として、道路交通法上、自動車も自転車も「車両」と扱われます。
ですから、自動車の運転者がさまざまな交通ルールを守らなければいけないのと同じように、自転車の運転者にも道路交通法に規定されている諸規制が適用されます。
ただし自転車は自動車に比べ、車体が小さいうえにスピードも出ず安定性もありません。
自動車の方が事故を回避しやすく、かつ事故になった場合は自転車側の方が大きなけがをしやすいです。
そのため自動車側が自転車を保護するべきと考えられ、交通事故では自動車の方が過失割合は大きくなる傾向にあります。
自転車の過失割合がゼロになることはほとんどない
自動車に比べ自転車の過失割合は小さくなる傾向にありますが、それでもゼロになることはほとんどありません。
道路交通法上は自転車も車両として扱われ、道路走行時にはルールを守り一定の注意をする義務があるためです。
また実際の事故では、自転車側にも法令違反が認められることが少なくありません。
「原則、車道を通行する」「道路の左側を通行する」「飲酒運転禁止」といったルールが守られていないケースがよくあります。
このような法令違反がみられるケースでは、当然ながら自転車側にも相応の過失割合が加算されるのです。
【パターン別】自転車と車の事故における基本過失割合
自転車と自動車の交通事故について、パターン別で基本過失割合を押さえていきましょう。
交差点での直進車同士の事故の基本過失割合
自転車(直進)と自動車(直進)が交差点で交通事故を起こしたときの基本過失割合は、信号機の有無や道幅、そのほか道路標識の状況によって異なります。
信号機のある交差点の場合
自転車(直進)と自動車(直進)が、信号機のある交差点で交通事故を起こしたときの基本過失割合は以下のとおりです。
| 事故の状況 | 過失割合(自転車:自動車) |
|---|---|
| 自転車側が赤信号、自動車側が青信号 | 80:20 |
| 自転車側が赤信号、自動車側が黄信号 | 60:40 |
| 自転車側が赤信号、自動車側が赤信号 | 30:70 |
| 自転車側が青信号、自動車側が赤信号 | 0:100 |
| 自転車側が黄信号、自動車側が赤信号 | 10:90 |
信号機のある交差点で自動車と自転車の交通事故がおきた場合、過失割合において上記表のとおり信号機の状況が重要です。
表をみてわかるように、過失割合は自転車側の方が低くなっています。
たとえば、自転車側が青信号で自動車側が赤信号の場合は自転車の過失割合がゼロです。
一方で自動車側が青信号で、自転車側が赤信号の場合、自動車の過失割合はゼロでなく20となります。
このように信号機の条件が同じでも、自動車側の過失割合が高くなるのです。
信号機のない交差点の場合
自転車(直進)と自動車(直進)が「信号機のない交差点」で交通事故を起こしたときの基本過失割合は以下のとおりです。
信号機が設置されていれば、信号機の色が基本過失割合を決定するときの重要な要素になりますが、交差点に信号機が設置されていない場合には、道幅・一時停止規制・優先道路・一方通行などの諸要素によって基本過失割合が決められます。
| 事故の状況 | 過失割合(自転車:自動車) | |
|---|---|---|
| 道幅 | 自転車と自動車の道幅が同程度 | 20:80 |
| 自転車側の道幅が広い | 10:90 | |
| 自動車側の道幅が広い | 30:70 | |
| 一時停止規制 | 自転車側に一時停止規制 | 40:60 |
| 自動車側に一時停止規制 | 10:90 | |
| 優先道路 | 自転車側が優先道路 | 10:90 |
| 自動車側が優先道路 | 50:50 | |
| 一方通行 | 自転車側が一方通行(自動車が違反) | 10:90 |
| 自動車側が一方通行(自転車が違反) | 50:50 | |
信号のない交差点での右折車と直進車の事故
信号機のない交差点で起きた右直事故の基本過失割合は以下のとおりです。
■対抗方向から侵入した場合
| 事故の状況 | 過失割合(自転車:自動車) |
|---|---|
| 自転車が右折・自動車が直進 | 40:60 |
| 自転車が直進・自動車が右折 | 10:90 |
直進する自転車と左折する車の事故
自転車が直進していたところ、左折する自動車に巻き込まれた場合の基本過失割合は以下のとおりです。
| 事故の状況 | 過失割合(自転車:自動車) |
|---|---|
| 自動車が自転車に先行して左折 | 10:90 |
| 自動車が自転車を追い越して左折 | 0:100 |
自転車よりも前方を走行していた自動車が左折をするタイミングで巻き込み事故が起きたパターンでは、自動車側が後方確認を怠ったという不注意があると同時に、自転車側にも、前方不注視や自動車の左折指示器の見落としなどの過失が存在します。
そのため、自転車側にも10%の過失があると扱われます。
これに対して、自動車が自転車を追い越して左折した際に接触した事案の場合、急に追い越されて目の前で左折をされた自転車側には交通事故の回避可能性がないと考えられます。
ですから、このパターンの巻き込み事故では、自転車側の過失割合は0 となるのです。
進路変更にともなう事故
進路変更時に自転車と自動車が交通事故を起こしたときの基本過失割合は以下のとおりです。
| 事故の状況 | 過失割合(自転車:自動車) |
|---|---|
| 自転車が進路変更(障害物あり) | 10:90 |
| 自転車が進路変更(障害物なし) | 20:80 |
| 自動車が進路変更 | 10:90 |
まず、進路変更をしたのが自動車側なら、自転車側の基本過失割合は10%です。
次に、進路変更をしたのが自転車側の場合、自転車の前方に障害物があったかどうかで基本過失割合が変わります。
前方に障害物がない状態で進路変更をしたケースでは、自転車側の基本過失割合は20%です。
これに対して、前方に障害物があり、それを避けるために進路変更をせざるを得ない状況なら、自転車側の基本過失割合は10%に引き下げられます。
直進する自転車と駐車場に出入りする車の事故
自転車が道路を走行していたところ、道路から駐車場に入ろうとした自動車や駐車場から道路に進入しようとした自動車と接触した場合、過失割合(自転車:自動車)は10:90です。
道路から駐車場に入ったり駐車場から道路へ出たりして、交通の流れを途切れさせる自動車側にはより大きな注意義務が問われます。
そのうえ自転車より自動車の方が重い注意義務が問われるため、過失割合が90となるのです。
自転車側に10%の過失割合が認められるのは、前方をしっかりと確認していれば、道路と駐車場を出入りしようとする自動車を認識して交通事故を回避できたと考えられるからです。
車のドアを開けたときの事故
自転車が道路を走行中、前方に駐停車していた自動車がドアを開けたところに衝突するといった事故も考えられます。
ただし過失割合を決める際に参照される別冊判タ38号や赤い本には、該当する例があげられていません。
一方で自転車でなくバイクだった場合の事例は掲載されており、これが参考になると考えられます。
別冊判タ38号や赤い本によれば、同様の事故が自動車とバイクの間で発生した場合の過失割合は、バイクが10で自動車が90です。
この過失割合がバイクでなく自転車だった場合も参考になると想定されます。
自転車と車の事故における過失割合の修正要素
交通事故の状況によっては、基本過失割合をそのままあてはめるのが適切でないケースも少なくありません。
たとえばスピード違反や酒気帯び運転など、基本過失割合以外に考慮すべき要素が多く存在するのです。
これら考慮すべき要素を総称して「修正要素」と言います。
交通事故ではまず基本過失割合を確認し、修正要素も加味して最終的な過失割合が決められるわけです。
具体的には「加害者側に+5」「被害者側に-10」のように、修正要素によって過失割合がかわります。
ここでは自転車と車の事故における、主な修正要素をみていきましょう。
自転車側の過失割合が大きくなるケース
自転車側の過失割合が大きくなる修正要素(自動車側の過失割合が小さくなる修正要素)の例として、以下が挙げられます。
- ︎自転車側の酒気帯び運転
- ︎夜間などで無灯火での運転
- ︎スマートフォンを注視しながらの運転
- ︎二人乗りやほかの自転車と並走しての運転
- ︎傘をさすなどしながら片手で運転
- ︎脇見運転など
これらが該当する場合、自転車側の過失割合が5%~15%程度加算されることになります。
自動車側の過失割合が大きくなるケース
自動車側の過失割合が大きくなる修正要素(自転車側の過失割合が小さくなる修正要素)として以下が挙げられます。
- ︎自転車を運転していたのが幼児、児童、高齢者、身体障害者など
- ︎自転車が自転車横断帯や横断歩道を走行していた
- ︎住宅街など道路幅が狭い場所を走行していた
- ︎大型の自動車と自転車の事故だった
- ︎酒気帯びなど自動車側に重過失があったなど
自転車と車の事故を起こした場合の対処法
自転車と自動車の交通事故が起きた場合の対処法やその後の流れについて解説します。
当事者双方の安全を確保する
交通事故を起こしてしまったら、まずは当事者双方の安全を確保します。
けが人がでているようなら、速やかに救急車を呼びましょう。
重傷者がでた場合、強引に動かすべきでないこともあります。
しかし道路上に倒れているなど、そのままにすると危険な場合は、安全な場所へ移動させることも必要です。
自転車・自動車なども道路上に放置すると、二次被害を招く可能性があります。
そのため必要に応じて、道路の隅など安全な場所へ移動させましょう。
けが人や自動車・自転車を移動させられないときは、発煙筒などを使い周囲に注意を促します。
警察に通報する
安全確保が終わったら、すぐに警察に通報してください。
「たいしたけがはないから通報しなくても大丈夫だろう」などの理由で警察に通報しないのは厳禁です。
交通事故が起きた場合には、運転手などに報告義務が課されているからです。
警察に通報を怠ると、3ヵ月以下の懲役刑または5万円以下の罰金の範囲で刑罰が下される可能性があります。
また、警察に通報しておかなければ、交通事故証明書が発行されないので、保険金の支払い手続きなどに支障が生じかねません。
警察が現場に到着したら、警察官からの質問に丁寧に答えましょう。
連絡先を交換し、事故状況を記録する
警察官が現場に到着する前や、警察官の現場対応が終わったら、交通事故の相手と連絡先などを交換してください。
交換するべき情報として、以下が挙げられます。
- ︎氏名
- ︎住所
- ︎電話番号
- ︎勤務先
- ︎加入している任意保険会社の名前、連絡先、保険証書の番号 など
また、交通事故の現場では、当事者自身でも事故の状況を記録しておくのも重要です。
あとから相手方が証言を翻したり事実とは異なる証言をしたりしたときに、客観的な証拠が必要になる場合があるからです。
交通事故の現場で押さえておくべき情報は以下のとおりです。
- ︎自転車や自動車、衣服や所持品が破損した場合にはその写真
- ︎交通事故当時の現場の様子(標識や街灯、監視カメラの有無など)
- ︎目撃者の連絡先、目撃者の証言
- ︎自動車のナンバープレートの数字 など
保険会社に連絡する
警察の聴取などが終わり、状況が落ち着いたらできるだけ早く自分の保険会社に連絡します。
連絡をする際は、保険証券など契約内容が確認できる資料と相手方の情報を用意しておきましょう。
なお保険会社によっては、保険会社の担当者が事故現場に来て対応してくれるサービスを提供しているようです。
こういったサービスが付与されている場合、警察への通報後、すぐに保険会社へ連絡するとよいでしょう。
病院で診察を受ける
交通事故後、少しでも身体に違和感があれば病院で診察を受けるべきです。
最初はたいしたことがないように思えても、時間が経過すると症状が悪化してしまうケースも少なくありません。
また事故発生後から病院診察までに時間が空くと、けがや症状が事故のためと証明しづらくなります。
その結果、相手から治療費の支払いなどを拒否されてしまうリスクが生じるのです。
治療終了後に示談交渉を進める
自転車事故のけが完治後、もしくは後遺障害認定の結果が出次第、損害賠償請求のための示談交渉を開始します。
加害者が任意保険に加入している場合、交渉の窓口になるのは一般的に保険会社の担当者です。
示談交渉で合意が得られない場合は、調停や裁判で解決を目指すことになります。
自転車と車の事故を起こした場合の注意点
さいごに、自転車と自動車の交通事故の事後処理をするときの注意事項を紹介します。
その場で示談を成立させない
交通事故直後に、その場で示談交渉をするべきではありません。
その場で示談を成立させた方が手間がないと思うかもしれませんが、一度示談を成立させるとあとで覆せません。
あとから、大きなけがが発覚したり休業を強いられるなどの損害が出たりしても、治療費や損害賠償の請求ができなくなるのです。
原則として示談交渉は、けがの完治や後遺障害の認定が完了し全ての損害が確定してから開始します。
保険会社の提案を鵜呑みにしない
自転車対自動車側の交通事故で自転車側が被害者とした場合、被害者側は加害者側の保険会社が提案する内容を鵜呑みにしてはいけません。
これまでみてきたように、自転車と自動車の交通事故では自転車側の過失割合が低くなる傾向にあります。
しかし、加害者側の保険会社は被害者にとって適切とは言えない過失割合を提示してくることが少なくないのです。
加害者側の保険会社が提案する内容をそのまま受け入れると、不当な過失割合で賠償金が大幅に少なくなってしまう可能性があります。
加害者側の提案に少しでも疑問があれば、弁護士に相談するなどしてその内容が適切か確認すべきです。
軽い接触事故でも、けがをしていれば人身事故として警察に届け出る
自転車に乗っていて自動車との交通事故に遭った場合、少しでもけがをしているようなら人身事故として届け出るべきです。
たいしたけがでないと思っていても、あとで痛みが大きくなり症状が重いとわかるケースもあります。
しかし人身事故でなく物損事故として届けてしまうと、治療費や慰謝料の請求ができなくなってしまう可能性があるのです。
あとから人身事故に切り替えるよう申請することもできますが、必ずしも認められるとは限りません。
けがの状況から、警察や加害者から物損事故として届けるようすすめられるケースもあります。
しかし少しでもけがをしていれば、人身事故として届けることが強く推奨されます。
けがなしの接触事故でも必ず警察を呼び、本当にけががないかも確認する
自転車と自動車が軽い接触事故を起こし、けがをしていなかった場合でも必ず警察を呼ばなくてはなりません。
「たいした事故でなかったから」と思うかもしれませんが、交通事故発生時に警察に届けるのは義務です。
違反すると、3ヵ月以下の懲役または5万円以下の罰金が科される可能性があります。
また、一見けががないようにみえても、本当にけがをしていないか確認するようにしましょう。
少しでも違和感があれば、病院へ行って診察を受けるべきです。
あとになって症状が重くなってしまう場合もあります。
交通事故による症状なのに、診断が遅れてしまうと治療費や賠償金を受け取れなくなってしまう可能性も否定できません。
あとからけがが発覚したら、人身事故へ切り替える
物損事故として届出をしてしまったあと、あとからけがが発覚した場合には、できるだけ早いタイミングで人身事故への切り替え手続きを進めましょう。
物損事故として処理されたままでは、治療費や慰謝料などを加害者側に請求できなくなる可能性があるのです。
物損事故から人身事故に切り替えるには、病院で診断書を作成してもらったうえでそれを警察へ提出します。
切り替え手続きの詳細や必要書類については、以下記事で紹介しておりますので、興味があればあわせて参照ください。
相手が無保険の場合はトラブルになりやすい
相手が無保険の場合、交通事故の対応でトラブルになりやすいので注意が必要です。
特に自転車は自動車に比べ無保険である可能性が高いと考えられます。
加害者側が無保険であれば、示談交渉は交通事故の当事者同士でおこなうのが一般的です。
この場合、以下のようなトラブルが想定されます。
- 加害者側が示談に応じない
- 加害者・被害者ともに示談交渉に慣れておらず、なかなか合意に至らない
- 示談交渉の場で互いに感情的となり、トラブルへと発展する
こういったトラブルを避けるには、弁護士に相談・依頼して交渉を代行してもらうことも推奨されます。
事故の当事者同士で話し合うよりストレスなく、スムーズに示談交渉で合意できるでしょう。
また弁護士に依頼すれば、示談金が不当に高くなったり安くなったりするのを避けることもできます。
さいごに|自転車と車の事故を起こしたときは弁護士に相談を!
自転車で走行中に自動車と接触事故などを起こしたときには、できるだけ早いタイミングで弁護士に相談することが推奨されます。
弁護士に依頼することで、相手との交渉を全て任せたり示談金が不当に高くなったり低くなったりすることを避けることが可能です。
また弁護士は依頼者の味方ですから、自分にとってできる限り有利な示談条件で合意しやすくなります。
ベンナビ交通事故では、自転車事故などの対応を得意とする弁護士を紹介しています。
法律事務所の所在地、具体的な相談内容、初回相談料無料などのサービス面から24時間無料で専門家を検索できるので、交通事故処理について少しでも不安・疑問があるときには、できるだけ早いタイミングで信頼できる弁護士までお問い合わせください。
弁護士に相談するかお悩みの方へ
下のボタンからあなた当てはまるものを選んで悩みを解消しましょう。
弁護士費用特約があれば 実質0円で依頼できます!

多くの保険会社では、被害者1名につき最大300万円までの弁護士費用を負担してくれます。特約があるか分からない方でも、お気軽にご相談ください。弁護士と一緒にご確認した上で依頼の有無を決めて頂けます。
特約を利用して弁護士に相談する交通事故問題を依頼する弁護士の選び方にはポイントがあります。
- 過去の解決事例を確認する
- 料金体系が明確である弁護士を選ぶ
- 交通事故問題が得意な弁護士から選ぶ
等です。
詳しくは以下の記事を読んで、正しい弁護士の選び方を理解した上で弁護士に相談しましょう。
弁護士の選び方について詳しくみる
【人身事故被害者の方へ】事故直後・通院中いずれの場合もまずはご相談ください。弁護士への依頼で、結果が大きく変わるかもしれません。【初回面談無料】【着手金無料プランあり】【オンラインで全国対応可能】
事務所詳細を見る
【元警察官(警部補)弁護士が経験を活かした交渉を】「怪我で通院している」「御家族が交通事故で亡くなった」など【LINE、WEB、電話で完結】【相談料無料】【着手金0円/365日対応】
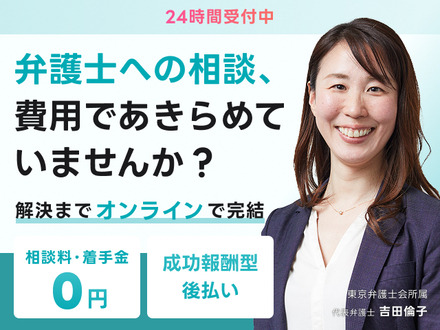
相談料・着手金0円、費用倒れの心配なし。大手より低価格な料金体系で増額実績多数。交通事故専門チームが後遺障害認定から交渉まで強力サポート。LINE完結・来所不要で全国対応。
事務所詳細を見る当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡

交通事故後の対応に関する新着コラム
-
接触がない「非接触事故」は、過失割合の判断が難しい事故です。非接触事故における過失割合の基本的な考え方、車対歩行者・車対車・車対バイクといった典型的なケース別の...
-
非接触事故で後日警察から連絡が来るかどうかは、一概には言えません。連絡が来る時期も、事故の種類や相手の診断書の提出時期、被害者のけがの程度により異なります。場合...
-
本記事では、交通事故の被害に遭った方に向けて、交通事故用の示談書の簡単な書き方と流れ、交通事故用の示談書を簡単に書くために押さえておくべき4つのコツ、示談書の作...
-
本記事では、自転車と自動車間の過失割合がどのように設定されるかや、自転車と自動車間の交通事故が起きたときの対処法・注意点を解説します。
-
非接触事故で転倒がなくても、後で怪我に気づくことがあります。適切な対処法を理解せずに立ち去ると問題になる可能性があるため、本記事では転倒なしの非接触事故における...
-
交通事故トラブルを抱えるなかで、弁護士だけでなく行政書士にも対応してもらえることを知り、主に費用面が気になっている方も多いのではないでしょうか。本記事では、行政...
-
本記事では、レンタカーを運転していて交通事故に遭った場合、相手が100%悪くてもレンタカー会社へお金を支払わなければならない理由やレンタカー会社からお金を請求さ...
-
本記事では、交通事故の被害に遭った方に向けて、被害者が利用できる保険(自賠責保険・任意保険)の種類、加害者の自賠責保険と被害者の任意保険を使用する順番、加害者側...
-
交通事故によるけがで仕事を休む場合、いつ頃復帰するのが適切なのでしょうか?本記事では、交通事故が原因で仕事を休む場合の一般的な休業期間や、休業した場合にもらえる...
-
交通事故に遭った場合、会社から診断書の提出を求められることがあります。しかし、費用の問題などからためらっている方も多いのではないでしょうか。本記事では、交通事故...
交通事故後の対応に関する人気コラム
-
当て逃げに遭ってしまった方へ、少しでも解決に近づけるための対処法をご紹介します。
-
物損事故とは、怪我人や死亡者がなく車両などに損害が出たにとどまる交通事故のことです。物損事故では相手方と示談交渉で揉めてしまう可能性もありますので、ポイントをお...
-
交通事故発生後は、警察に連絡・治療(人身事故の場合)・保険会社との交渉と進んでいきます。本記事では、各場面の詳しい対応や、いつ連絡が来るのかなどの期間についても...
-
交通事故が起きて被害者となった場合、「自分は被害者だから、待っているだけで何もする必要はない」と考えているなら、それは大きな間違いだと言えます。
-
交通事故が起きたら、物損事故・人身事故問わず警察へ届け出なければいけません。これは法律で義務付けられており、報告を怠ると法律違反として処罰を受ける可能性もありま...
-
交通事故のうち3割は駐車場で起こっているといわれています。駐車場は私有地になるため、事故が起こったあとの対処が一般道路とは異なる部分があります。本記事では、駐車...
-
事故後の対応や手続きを適切におこなうことで、その後の補償や示談交渉をスムーズに進められます。本記事では、交通事故にあった際に最初にとるべき行動、その後の手続きの...
-
車でおかまをほられた(後ろから追突された)ときに、どのように対処すればよいかご存知でしょうか。この記事では、車でおかまをほられた際の流れと対処法、示談金などを紹...
-
接触事故とは、走行中の自動車が車両・物・人などに接触して、損害や傷害が生じた事故のことです。接触事故では「怪我の有無」で賠償金の内容が異なりますので、事故後の流...
-
ひき逃げ事故は、その後の人生を大きく左右する重大な問題です。本記事では、ひき逃げ事故に遭われた被害者の方、そしてひき逃げ事故を起こしてしまった加害者の方が、事故...
交通事故後の対応の関連コラム
-
交通事故に怪我は付きものです。その際に治療先の治療院はどこを選べばいいのか?治療費は妥当なのか?が気になると思いますので、ご紹介していきます。
-
本記事では、交通事故の被害に遭った方に向けて、交番では交通事故証明書をもらえないこと、交通事故証明書のもらい方・申請の流れ、インターネット上からの交通事故証明書...
-
一時停止無視による事故に巻き込まれてしまったため、過失割合や罰則、違反点数の扱いがどうなるのか不安な方も多いのではないでしょうか。本記事では、一時停止無視による...
-
追突事故では被害者の過失が0になるケースが多く賠償金も高額になりやすいですが、事故後の対応を誤ると適正な金額を受け取れなくなる恐れがあるためご注意ください。この...
-
交通事故の治療は接骨院や整骨院でも受けられますが、保険会社に損害賠償を請求するための診断書は『正式な医師』でないと作成できないといった問題があります。交通事故の...
-
自転車事故で被害者が死亡した場合、残された遺族は加害者に対して「死亡慰謝料」や「死亡逸失利益」などの損害賠償を請求できます。納得のいく金額を受け取るためにも、示...
-
本記事では、過失割合10対0の交通事故における代車費用の扱い、交通事故に巻き込まれたときに弁護士へ相談するメリットなどについてわかりやすく解説します。
-
物損事故が発生した場合、加害者または任意保険会社に損害賠償請求することになります。物損事故の被害に遭った際に不利な状況にならないためにも、この記事にて示談成立ま...
-
交通事故の相手が外国人でも、通常の交通事故と同様に損害賠償を請求することができます。しっかりと賠償金を受け取るためにも、事故時の対応方法について知っておきましょ...
-
実況見分調書とは、事故状況について記載された書類のことで、過失割合を決定する際の重要な資料です。実況見分の内容に応じて記載内容も異なりますので、事故後は適切に対...
-
交通事故が起きたら、物損事故・人身事故問わず警察へ届け出なければいけません。これは法律で義務付けられており、報告を怠ると法律違反として処罰を受ける可能性もありま...
-
交通事故発生後は、警察に連絡・治療(人身事故の場合)・保険会社との交渉と進んでいきます。本記事では、各場面の詳しい対応や、いつ連絡が来るのかなどの期間についても...
交通事故後の対応コラム一覧へ戻る


























 慰謝料・損害賠償
慰謝料・損害賠償
 示談
示談
 過失割合
過失割合
 死亡事故
死亡事故
 後遺障害
後遺障害
 むちうち
むちうち
 自転車事故
自転車事故
 自動車事故
自動車事故
 人身事故
人身事故
 バイク事故
バイク事故




























