ひき逃げ事故とは?被害者・加害者がとるべき対応と損害賠償について解説

- 「突然車にひかれ、運転手は逃げてしまった…このようなときはどうすればいいの?」
- 「事故を起こしてその場から逃げてしまった…どうすれば最悪の事態を避けられるのか」
ひき逃げ事故は、被害者にとっても加害者にとっても、その後の人生を大きく左右する重大な問題です。
突然の事故に遭遇し、どう対応すれば良いのかわからず、不安や恐怖を感じている方もいるかもしれません。
本記事では、ひき逃げ事故に遭われた被害者の方、そしてひき逃げ事故を起こしてしまった加害者の方が、事故後にとるべき具体的な対応策・損害賠償請求・弁護士に相談するメリットなどについて、詳しく解説します。
交通事故は誰にでも起こりうるものですが、その後の対応が将来を大きく左右します。
ひき逃げに関する正しい知識を身につけ、万が一の際に適切な行動が取れるように備えましょう。
ひき逃げについての基礎知識
ひき逃げは、交通事故の中でも特に悪質な行為とされ、被害者だけでなく、加害者自身にも深刻な結果をもたらします。
ここでは、まずはひき逃げの基礎知識を解説します。
- ひき逃げとは?
- 運転手は事故発生時に負傷者を救護しなければならない
- ひき逃げ犯の検挙率は平均95%|加害者は比較的見つけやすい
それぞれについて詳しく見ていきましょう。
ひき逃げとは?
ひき逃げとは、一般的に自動車や自転車などで人を死傷させる事故を起こしたにもかかわらず、必要な措置を講じることなく現場から走り去る行為のことです。
法律上、「ひき逃げ」という直接的な罪名はありませんが、この行為は主に道路交通法第72条に定められた「救護義務違反」に該当します。
たとえば、以下のような行動はひき逃げに該当します。
- 車を運転中に歩行者と衝突し、けがをさせたけれど、そのまま現場から逃走した
- 自転車で歩行者と接触して転倒させたが、「大丈夫だろう」と判断し、声をかけただけでその場を去った
- 同乗者が負傷したにも関わらず、救護せずに現場を離れた
事故の大小に関わらず、人の死傷が関わる事故で現場を離れることは、法的な責任を問われる重大な行為なのです。
道路交通法第72条「救護義務」
交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。
この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。同項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置(第七十五条の二十三第一項及び第三項において「交通事故発生日時等」という。)を報告しなければならない。
運転手は事故発生時に負傷者を救護しなければならない
交通事故が発生した場合、運転手には法律によって主に以下の3つの義務が課せられています。(道路交通法第72条)
- 負傷者を救護する「救護義務」
- 事故の状況を速やかに警察に通報する「報告義務」
- 後続車による二次的な事故を防ぐ「危険防止措置義務」
中でも最も重要なのが「救護義務」です。
この義務により、運転手は事故後、負傷者に対して以下の行動を取る必要があります。
- 「大丈夫ですか?」と声をかけ、意識があるかを確認
- 必要であれば119番に通報し救急車を呼ぶ
- 安全な場所へ移動させ、可能な限り応急手当をおこなう など
これらの義務を怠り、負傷者がいるにも関わらず現場から逃走してしまうと、救護義務違反として「ひき逃げ」の罪に問われます。
救護義務は運転手だけでなく、車両の同乗者にも課せられる場合があります。
事故に関与した場合は、運転手や同乗者に関わらず、必ず負傷者の救護活動にあたるようにしましょう。
ひき逃げ犯の検挙率は90%超|加害者は見つかりやすい
公的なデータでは、死亡事件に限ると、検挙率はおおむね90%を超える高い水準で検挙されています。
ひき逃げをしてしまった場合、「逃げ切れるかもしれない」と考えてしまうかもしれませんが、現実はそう甘くありません。
法務省が公表している平成27年版「犯罪白書」によると、ひき逃げ事件の検挙率は全体で約52%ですが、死亡事故に限るとその検挙率は約102%にも上ります。
被害者のけがが重ければ重いほど、警察の捜査体制は強化され、目撃情報や防犯カメラ映像、車両の痕跡など、あらゆる手がかりをもとに捜査がおこなわれます。
その場では逃走できたとしても、後日逮捕される可能性は極めて高いといえるでしょう。
ひき逃げをした場合に適用される罰金や懲役
ここでは、ひき逃げに関連する主な法律と、それぞれの罰則について詳しく解説していきます。
- 道路交通法
- その他の法律
具体的にどのような法律に違反し、どのような罰金や懲役が科される可能性があるのかを理解しておくことは、加害者にとっても、被害者にとっても重要です。
それぞれについて詳しくみていきましょう。
道路交通法
先ほども述べた通り、交通事故が発生した際、運転手には主に以下3つの義務が課せられています。(道路交通法第72条)
- 負傷者を救護すること
- 警察へ事故を報告すること
- さらなる事故や被害の拡大を防ぐ措置をとること
人身事故(人が死傷する事故)を起こしたにも関わらず、これらの義務を果たさずに現場から立ち去った場合、道路交通法違反として以下の罰則や違反点数が科せられます。
違反の種別 罰則 違反点数 救護義務違反
5年以下の懲役または50万円以下の罰金(道路交通法117条1項) 35点
人の死傷が当該運転者の運転に起因する場合は10年以下の懲役または100万円以下の罰金(道路交通法117条2項) 報告義務違反 3か月以下の懲役または5万円以下の罰金(道路交通法119条1項17号) ー
交通事故とは、車両などの交通手段によって人が死傷したり、物が損壊したりすることを指しますが、ひき逃げが問題となるのは、その中でも「人の死傷」が発生した場合に限られます。
もし負傷者がおらず、車両やガードレールなどの物だけを損壊させて現場を離れた場合は、「当て逃げ」と呼ばれ、報告義務違反や危険防止措置義務違反に問われることになります。
当て逃げについては、「当て逃げをされたら?気づかなかった場合、泣き寝入りしないための対処法」で詳しく解説しています。
その他の法律
ひき逃げは、道路交通法違反だけでなく、以下のその他複数の法律に抵触し、科される刑罰も非常に重くなる可能性があります。
罪状 罰則 過失運転致死傷罪
(自動車運転過失致死傷罪)7年以下の懲役もしくは禁錮又は100万円以下の罰金
(自動車運転処罰法第5条)危険運転致死傷罪 負傷:15年以下の懲役
死亡:1年以下の有期懲役(自動車運転処罰法第2条)殺人罪 死刑・無期懲役・懲役5年以上(刑法第199条) 引用元:自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律 | e-Gov 法令検索、刑法 | e-Gov 法令検索
例えば、ひき逃げをすることで以下のような罪が想定されます。
- 飲酒運転で人をはねて死亡させ、そのまま逃走した場合は、危険運転致死罪および道路交通法違反(救護義務違反)に問われる
- スピード違反で人をはねてけがをさせ、警察に通報せずに逃走した場合は、過失運転致死傷罪と道路交通法違反の両方に問われる
【加害者】ひき逃げをした場合は速やかに自首するべき
万が一、ひき逃げをしてしまったら、速やかに警察へ自首しにいくことがベストな選択です。
通常、自動車運転中の不注意で他人を死傷させた場合、「過失運転致死傷罪」が適用されます(自動車運転処罰法第5条)。
しかし、ひき逃げをおこなうと、過失運転致死傷罪に加えて、救護義務違反や報告義務違反など、追加の罪が加わり、刑罰が重くなるリスクを自ら招くことになります。
| 罪名 | 刑罰 |
| 過失運転致死罪 | 7年以下の懲役または禁錮、または100万円以下の罰金 |
|
ひき逃げ |
5年以下の懲役または50万円以下の罰金 |
| 人の死傷が当該運転者の運転に起因する場合:10年以下の懲役または100万円以下の罰金 |
また、死亡事故のひき逃げにおける検挙率は約102%と非常に高く、逃走することはほぼ不可能です。
そのため、最寄りの警察署で正直に報告することが、結果的に自身の将来を守るための賢明な判断といえます。
自首したことは裁判で情状酌量の対象となり、刑が軽くなる可能性もあります。
ひき逃げは重大な犯罪であり、高確率で前科がつくため、さらなる罪を重ねて取り返しのつかない事態を招く前に、誠意ある対応をすることが重要です。
【被害者】ひき逃げに遭った場合にとるべき4つの行動

ひき逃げに遭うと、身体的なダメージだけでなく、加害者への怒り、治療費や収入減など精神的・経済的な不安も大きくなります。
そんな状況でも冷静さを保ち、自分の権利を守るために取るべき行動があります。
ここでは、ひき逃げの被害に遭った場合にまずおこなうべき重要な4つの対応を解説します。
- 加害車両のナンバーと連絡先をしっかり確認する
- すぐに警察を呼び事故証明を得る
- 救急車を呼び病院に行く
- 防犯カメラに写っている映像や目撃者を探す
加害車両のナンバーと連絡先をしっかり確認する
まず、ひき逃げをした車の情報をできる限り多く確認することが重要です。
事故直後は痛みや混乱で冷静に状況を確認するのが難しいかもしれません。
しかし、加害者の特定には、逃げた車の情報をできるだけ記録し、警察に提供することが極めて重要です。
たとえば、以下の情報が加害者特定の手がかりになります。
- 車両のナンバープレート(一部でも可)
- 車種
- 車の色
- 特徴(ステッカーや傷など)
ナンバープレートの一部でも覚えていれば、警察はそれを基に捜査を進めやすくなります。
また、事故が軽微で加害者と連絡先を交換して別れた場合でも、相手が嘘の連絡先を伝えている可能性もあります。
どんな些細な情報でも記録し、必ず警察に報告しましょう。
記録を取ると同時に自分の安全を確保することも忘れないでください。
道路に留まっていると、後続車による二次被害の危険があります。
できるだけ歩道の奥など安全な場所に移動するようにしましょう。
すぐに警察を呼び事故証明書を得る
ひき逃げの被害に遭った場合、必ず警察(110番)に連絡し、事故証明書を取得しましょう。
けがを軽く感じても、加害者の情報が不明でも、警察への連絡は必須です。
警察は現場を確認し、捜査を開始します。
届け出後、交通事故証明書が発行されます。
この証明書は、事故が発生したことを公的に証明する重要な書類で、後の治療費請求や損害賠償請求、保険金請求(自賠責保険や任意保険)などで必要となります。
もし警察に届け出なければ、事故の事実を証明することが難しくなり、保険会社からの補償を受けられなくなったり、法的手続きで不利になるリスクが高まります。
そのため、事故に遭った際は速やかに警察に連絡し、事故証明書の発行手続きをおこないましょう。
救急車を呼び病院に行く
ひき逃げ事故に遭った場合、けがの程度に関わらず、必ず医療機関を受診し、診断書を作成してもらってください。
事故の衝撃は、見た目以上に体にダメージを与えていることがあります。
事故直後は興奮状態で痛みを感じにくく、翌日以降にむちうちや体の痛みが出ることもあります。
症状が軽く感じても後遺症が残る可能性があるため、自己判断せずに医師の診察を受け、精密検査を受けることが重要です。
そして医師には必ず「交通事故に遭った」と伝え、診断書を作成してもらいましょう。
この診断書は、後の損害賠償請求や保険金請求に重要な証拠となります。
治療が始まったら、医師の指示に従い、症状が改善するまで継続的に治療を受けましょう。
途中で治療を中断せず、治療にかかる費用(診察料、薬代、通院費など)の領収書や通院記録は必ず保管してください。
防犯カメラに写っている映像や目撃者を探す
ひき逃げ事故では、加害者を特定するために、防犯カメラの映像や目撃者の証言を集めることが重要です。
警察も捜査をおこないますが、必ずしもすぐに加害者が特定されるわけではありません。
警察の到着を待っている間に、目撃者が立ち去ってしまう可能性もあるため、被害者自身が積極的に証拠を集めることが早期解決につながります。
加害車両の情報がわからなくても、周囲に目撃者がいないか聴き込みをおこない、目撃者がいれば連絡先を確認しましょう。
どんな些細な情報でも、加害者の特定や損害賠償請求に繋がる可能性があります。
諦めずに証拠を集め、積極的に行動することが大切です。
ひき逃げに遭った場合の損害賠償の請求はどうなる?
ひき逃げの被害に遭うと、身体的な治療費のほか、壊れた物の修理費や、治療のために休んだことによる収入減など、さまざまな損害が発生します。
ここでは、ひき逃げ事故における損害賠償請求について、加害者が特定できた場合と、加害者が特定できなかった場合の2つのケースに分けて、それぞれどのような対応が可能かを解説します。
加害者が特定できた場合|加害者に損害賠償を請求する
警察の捜査や目撃情報などにより、ひき逃げ事故の加害者が特定された場合、被害者はその加害者に対して、事故によって被った全ての損害の賠償を請求できます。
<請求できる項目>
- 治療費(入院費、手術費、通院費、薬代など)
- 通院のための交通費
- 事故による休業損害(仕事を休んだことによる収入減)
- 後遺障害が残った場合の逸失利益(将来得られたはずの収入の減少)
- 精神的な苦痛に対する慰謝料
保険会社は専門的な知識を持って対応してくるため、被害者自身で交渉をおこなうのが難しいと感じる場合は、弁護士に相談することも有効な手段です。
もし、加害者が任意保険に加入していなかった場合や、自賠責保険(強制保険)に加入していなかった場合は、自分が加入している任意保険や「政府保障事業制度」を利用することで保障を受けられます。
交通事故の損害賠償については、「交通事故の損害賠償金の基礎知識|項目、計算方法、相場などを解説」で詳しく解説しています。
加害者が特定できない場合|自分の任意保険で補償を受ける
残念ながら、警察の捜査によってもひき逃げの加害者が特定できなかった場合、自動車保険に加入していれば、「人身傷害保険」や「無保険車傷害保険」などを利用して一定の補償を受けられる可能性があります。
まずはご自身が加入している保険会社に連絡し、利用できる保険契約がないかを確認してみましょう。
これらの保険が契約に含まれているか、また、どのような場合に利用できるのか、補償の内容や限度額などを詳しく確認することが重要です。
人身傷害保険
人身傷害保険は、自動車事故によって死傷した場合に、加害者の過失割合に関係なく、実際の損害額(保険会社が定めた基準にもとづく)を保険金額の上限まで補償する保険です。
ひき逃げ事故のように加害者が不明な場合でも利用できます。
大きな特徴は、本人(被保険者)だけでなく、契約車両に同乗していた家族や友人も補償の対象となる点です。
また、加害者との示談交渉が成立するのを待つ必要がなく、損害額が確定すれば比較的速やかに保険金を受け取れます。これにより、治療費や生活費の不安を軽減できます。
補償される主な損害項目は、以下のとおりです。
- 医療費
- 通院費
- 仕事を休んだ場合の休業補償
- 逸失利益
- 精神的損害
- 後遺障害に対する補償 など
無保険車傷害特約(無保険車傷害保険)
無保険車傷害特約は、加害者が自動車保険に加入していない無保険車であった場合や、ひき逃げのように加害車両が特定できない場合に、治療費や慰謝料を補償してもらえる特約です。
ただし、補償の対象となるのは、原則として死亡または後遺障害が残った場合に限られ、傷害(けが)のみの場合は対象外となるのが一般的です。
また、支払われる保険金の額は、契約している保険の内容によって上限が定められています。
対人賠償保険の保険金額と同額か、一定額(例:2億円)が上限として設定されることが一般的です。
利用にあたっては、保険会社所定の条件を満たす必要があるため、事故に遭った際には、まず保険会社に連絡し、適用条件や具体的な補償内容、請求手続きについて詳しく確認しましょう。
加害者が不明・無保険でも「政府保障事業制度」で保障を受けられる
ひき逃げ事故で加害者が見つからない、または加害者が無保険の場合、被害者は損害賠償を受けられず途方に暮れてしまうかもしれません。
しかし、そんな状況を救済するために、国が設けた「政府保障事業制度」があります。
ここでは、この制度の概要や利用条件について詳しく解説します。
政府保障事業制度とは
政府保障事業制度とは、ひき逃げ事故で加害車両の所有者が不明な場合や、加害車両が無保険であるために被害者が自賠責保険などから損害補償を受けられない場合に、国が直接被害者に対して損害を補償する制度です。
自動車損害賠償保障法(自賠法)第72条に定められている公的な救済制度であり、被害者の保護を目的としています。
自賠法72条「自動車損害賠償保障事業」
政府は、ひき逃げ事故などによって被害者が自賠法3条の規定による損害賠償の請求をすることができない場合は、被害者からの請求によって、その受けた損害をてん補する。
保障される損害の範囲や限度額は、原則として自賠責保険の基準と同じです。
具体的には、以下のようになります。
- 傷害の場合は最高120万円まで
- 後遺障害の場合は、等級によって75万~4,000万円まで
- 死亡の場合には最高3,000万円まで
ただし、政府保障事業はあくまで最終的な救済措置であるため、自賠責保険の支払いとは異なる点もあることに注意が必要です。
たとえば、被害者自身の過失が大きい場合には、自賠責保険よりも厳しく過失相殺(損害額から過失分を減額)が適用されます。
過失相殺について詳しく知りたい方は、「過失相殺とは|被害者が知らないと損する過失相殺の全て」をあわせてお読みください。
政府保障事業の詳細については「損害賠償を受けるときは?|国土交通省」で確認できます。
政府保障事業制度を受けられる要件
政府保障事業制度を受けられる要件は以下のとおりです。
- 自動車にひき逃げされ、その車の保有者が明らかでない場合
- 無保険車との交通事故によって死傷した場合
- 公道における構内自動車との交通事故によって死傷した場合
- 盗難や無断運転など、保有者にまったく責任がない自動車との交通事故によって死傷した場合
無保険車とは自賠責保険に入っていない場合で、構内自動車とは一般道路上では運転できない自動車(運搬などに使われる車や、工場内の移動のみに使われる車)のことです。
ただし、被害者自身の重大な過失によって事故が発生した場合や、労災保険など他の社会保険からすでに給付を受けている場合(その給付額が損害額を上回る場合)など、保障の対象外となるケースもあります。
ご自身の状況が制度の対象となるか不明な場合は、損害保険会社などの請求受付窓口に相談してみるのがよいでしょう。
政府保障事業制度と自賠責保険の違い
政府保障事業制度と自賠責保険の違いは以下のとおりです。
これらの違いを理解したうえで、制度の利用を検討しましょう。
| 項目 | 政府保障事業 | 自賠責保険 |
| 適用対象 | 被害者が救済方法を持たない場合 | 事故による被害者 |
| 給付の順序 | 労災保険や健康保険の給付後、不足分をまかなう | 自賠責保険のみで支給される |
| 過失相殺 | 普通の過失でも過失相殺が考慮される | 重過失の場合のみ減額、その他の過失相殺はしない |
| 支払いまでの時間 | 事実関係の調査に時間がかかり、支払いまでに時間がかかる | 支払い請求後、比較的早期に支払いされる |
政府保障事業は、被害者を救済する手段がない場合に適用され、自賠責保険とは異なり、労災保険や健康保険などの社会保険の給付を先に受け、その不足分を政府保障事業でまかないます。
自賠責保険では、被害者に重過失がある場合のみ、過失に応じて5割・3割・2割の減額がおこなわれ、それ以外の過失相殺はおこないません。
一方、政府保障事業では、通常の過失でも過失相殺を考慮します。
また、政府保障事業は自賠責保険金の請求よりも調査に時間がかかり、実際に支払いを受けるまでにかなりの時間がかかることが一般的です。
事故の調査や損害額の確認など、遅滞の責任は負わないとされています。
政府保障事業に損害賠償を請求する手順
政府保障事業による保障請求は、保険会社あるいは責任共済の窓口でも受け付けてくれます。
ひき逃げで加害者がわからない場合は、申請書に所定の書類を添付して保険会社へ請求します。
ここでは、時効や請求限度額など、政府保障事業の請求に関して詳しく解説します。
請求の期限(時効)
政府保障事業の損害賠償請求には時効が決まっているので、期限を過ぎないように注意が必要です。
請求は被害の状況(傷害・後遺障害・死亡)によって区分され、損害保険会社(組合)の全国各支店等の窓口で受付します。
(1)事故発生日が令和2年4月1日以降の場合
| 傷害 | 治療を終えた日 | 事故発生日の翌日から5年以内 |
| 後遺障害 | 症状固定日 | 症状固定日の翌日から5年以内 |
| 死亡 | 死亡日 | 死亡日の翌日から5年以内 |
(2)事故発生日が令和2年3月31日以前の場合
| 傷害 | 治療を終えた日 | 事故発生日の翌日か3年以内 |
| 後遺障害 | 症状固定日 | 症状固定日の翌日から3年以内 |
| 死亡 | 死亡日 | 死亡日の翌日から3年以内 |
請求できる法定保障限度額
請求できる法定保障限度額について、被害の状況別に解説します。
傷害事故の法定補償限度額:120万円
損害の範囲 内容 基準 治療費 診察料・入院料・投薬料・手術料・処置料・通院費・柔道整復等の費用など 必要かつ妥当な実費 看護料 ・入院中の看護料(原則として12歳以下の小学生に近親者等が付き添った場合)
・自宅看護料又は通院看護料(医師が看護の必要性を認めた場合又は12歳以下の小学生の通院等に近親者等が付き添った場合)・入院1日につき4,200円。
・自宅看護料又は通院1日につき2,100円。
・近親者以外の場合、地域の家政婦料金を限度として、その実額。諸雑費 入院中の諸雑費 原則として入院1日1,100円 義肢等の費用 義肢・歯科補てつ・義眼・眼鏡・補聴器・松葉杖などの費用 必要かつ妥当な実費。
眼鏡の費用は、50,000円が限度文書料 交通事故証明書・印鑑証明書・住民票等の発行手数料 必要かつ妥当な実費 治療費 診察料・入院料・投薬料・手術料・処置料・通院費・柔道整復等の費用など 必要かつ妥当な実費 休業損害 事故による傷害のために発生した収入の減少(有給休暇を使用した場合、家事従事者の場合を含む) ・1日につき6,100円
・これ以上に収入減の立証がある場合は、19,000円を限度としてその実額慰謝料 精神的・肉体的な苦痛に対する補償 1日につき4,300円
対象となる日数は、治療期間の範囲内引用元:国土交通省|限度額と補償額
後遺障害を残した事の法定補償限度額:4,000万円
- 法定限度額:4,000万円(第1級)、3,000万円(第2級)
- 法定限度額:3,000万円(第1級)、~75万円(第14級)
損害の範囲 内容 基準 逸失利益 身体に障害を残し、労働能力が減少したために、将来発生するであろう収入減。 収入及び各等級(第1~第14級)に応じた労働能力喪失率、喪失期間等により計算します。 慰謝料等 精神的・肉体的な苦痛に対する補償等。 別表Ⅰの後遺障害
1,650万円(第1級)、1,203万円(第2級)。なお、初期費用等として500万円(第1級)、205万円(第2級)が加算されます。
別表Ⅱの後遺障害
1,150万円(第1級)~32万円(第14級) 上記1.及び2.の後遺障害において、第1~第3級で被扶養者がいるときは増額されます。
死亡事故の法定保障限度額:3,000万円
損害の範囲 内容 基準 葬儀費 通夜・祭壇・火葬・埋葬・墓石などに要する費用。
墓地・香典返しなどは含まれません。
100万円。 逸失利益 被害者が死亡しなければ将来得られたと考えられる収入額から、本人の生活費を控除したもの。 収入及び就労可能期間、被扶養者の有無等を考慮の上、計算します。 慰謝料 被害者本人の慰謝料 400万円 慰謝料 遺族の慰謝料。
遺族慰謝料請求権者(被害者の配偶者・子及び父母)の人数により金額が異なります。
請求者1名の場合550万円(500万円)、2名の場合650万円、3名以上の場合750万円。
被害者に被扶養者がいるときは、更に200万円が加算されます。
請求に必要な書類
書類名 作成者
(発行者)請求区分 傷害 後遺障害 死亡 政府保障事業への損害のてん補請求書 請求者 ◎ ◎ ◎ 請求者本人の印鑑登録証明書 市区町村 ◎ ◎ ◎ 交通事故証明書 自動車安全運転センター ◎ ◎ ◎ 事故発生状況報告書 事故の当事者等 ◎ ◎ ◎ 診断書 病院 ◎ ◎ ◎ 後遺障害診断書 病院 ◎ 死体検案書又は死亡診断書 病院 ◎ 診療報酬明細書 病院 ◎ 〇 ◎ 通院交通費明細書
請求者 ◎ ◎ 健康保険等の被保険者証(写し) 請求者 〇 〇 戸籍(除籍)謄本(注1) 市区町村 ◎ 休業損害証明書(給与所得者の場合) 雇用主 〇 〇 〇 その他損害を立証する書類、領収書等 〇 〇 〇 振込依頼書 請求者 ◎ ◎ ◎
(注1)亡くなられたご本人について、出生から死亡までの省略のない連続した戸籍(除籍)謄本を提出してください。
ひき逃げ事故については早急に弁護士に相談を
ひき逃げをしてしまった・ひき逃げされた場合は、すぐに弁護士に相談することが重要です。
ひき逃げ事故の被害者・加害者ともに、弁護士に相談することで、適切な対応策や、今後の見通しについてアドバイスを受けられます。
- 自首に同行してくれる
- 逮捕・勾留された場合、早期釈放に向けて弁護活動をしてくれる
- 被害者との示談交渉を代行してくれる
- 逮捕後の取り調べに対する適切なアドバイスを受け、早期釈放を目指せる
- 事故後に取るべき対応をアドバイスしてくれる
- 加害者が見つかった場合は複雑な損害賠償請求を一任できる
- 保険会社との交渉を有利に進めてくれる
- 交通事故被害者のための補償制度について教えてくれる
できるだけ速やかに弁護士に依頼することで、事故による負担が抑えられるでしょう。
一人で悩まずに、まずはお近くの弁護士に相談ください。
交通事故問題に強い弁護士を探すなら「ベンナビ交通事故」
「ベンナビ交通事故」は、交通事故問題に特化した弁護士を簡単に検索できるポータルサイトです。
地域・相談内容・得意分野など、さまざまな条件で絞り込み検索できるため、あなたにぴったりの弁護士を手間なく見つけられます。
また、夜間・土日祝に対応の事務所も多数掲載されているため、緊急で相談したい場合でも安心です。
さらに、初回相談無料や電話・オンライン相談可能な弁護士も豊富に登録されており、気軽に相談を始められます。
特に、後遺障害が残るケースや過失割合に争いがある場合など、複雑な事案では弁護士のサポートが不可欠です。弁護士に相談することで、法的観点から適切な解決策を得られるだけでなく、将来的なトラブルを未然に防ぐことも可能です。
「ベンナビ交通事故」を活用して信頼できる弁護士を見つけ、交通事故についてのお悩みを早期に解決しましょう。
解決事例①示談交渉により990万円から3,210万円に損害賠償を増額
「ベンナビ交通事故」で解決できた代表的な事例をいくつかご紹介します。
交通事故後の対応にお困りの方は、ぜひ参考にしてください。
まずは、示談交渉により賠償金が990万円から3,210万円増額された事例です。
| 当初の賠償額 | 示談交渉後の賠償額 | 賠償額の増減 |
| 990万円 | 3,210万円 | 2,220万円の増額 |
【事故の状況】 この事例は、歩道で停止中の歩行者に車両が衝突した事故です。歩行者(依頼者)の顔には大きな傷跡が残り、後遺障害として外貌醜状のみが認定されていました。保険会社は逸失利益を完全に否定したことから弁護士に依頼したケースです。
【対応と結果】接客業において外貌醜状が大きく影響を与えることを主張し立証した結果、保険会社はこちらの主張を受け入れ、示談が成立しました。
この事例から、事故後の適切な対応と専門的な知識が、最終的な賠償額に大きな違いをもたらすことが分かります。
引用元:ベンナビ交通事故
解決事例②裁判により4975万円から9475万円に損害賠償を増額
続いて、加害者が任意保険に加入していなかったものの4500万円の増額が認められた事例です。
| 当初の賠償額 | 裁判後の賠償額 | 賠償額の増減 |
| 4975万円 | 9475万円 | 4,475万円の増額 |
【事故の状況】 被害女性は歩道を通行中、縁石を飛び越えて歩道に乗り上げてきた自動車にひかれ、命を落としました。加害者が任意保険に未加入であったため、ご遺族は十分な補償を受けられない恐れがありました。
【対応と結果】被害者の任意保険に無保険車傷害特約が付帯していることを確認し、保険会社から慰謝料等の全額を回収可能であることを見つけました。
加害者と保険会社を相手に民事裁判を起こし、外国人被害者の将来の逸失利益や通貨問題など難しい問題をクリア。最終的には4500万円の増額が認められ、9475万円で和解が成立しました。この事例から、無保険車による事故でも、適切な保険の特約を活用することで、補償を得られる可能性があることが分かります。
引用元:ベンナビ交通事故
ひき逃げに関するよくある質問
最後に、ひき逃げに関して多くの方が疑問に思われる点について、よくある質問とその回答をまとめました。
ご自身の状況に近い質問や、気になる点があれば、ぜひチェックしてみてください。
- ひき逃げは指名手配される?
- ひき逃げに時効はある?
- 事故直後にひき逃げしたことに気づかなかった場合はどうなる?
- ひき逃げされた直後は「大丈夫」と言ってしまったが、後から痛みが出たときはどうしたらいい?
ひき逃げは指名手配される?
ひき逃げ事件では、加害者が特定できない場合や逃走した場合、警察が指名手配をおこなうことがあります。
特に被害者が重傷を負ったり死亡した場合には、指名手配がおこなわれることが多く、社会的な関心も高まるケースです。
指名手配された場合、加害者は逮捕されるリスクが高まり、逃げ続けることは困難になります。
このため、自首をすることが賢明といえるでしょう。
ひき逃げに時効はある?
ひき逃げ事件の公訴時効は、加害者がどのような罪に問われるかによって異なります。
具体的には以下の通りです。
- 救護義務違反(ひき逃げ):時効は7年
- 過失運転致死罪:時効は10年
- 危険運転致死罪:時効は20年
これらの時効は、犯罪が発生した日から計算されます。
つまり、ひき逃げ事件が発生した日が起算点となります。
また、民事の損害賠償請求権については、以下の通りです。
- 被害者が加害者を知った日から5年、または事故発生から20年
- 加害者が不明な場合、20年間は請求権が消滅しない
事故直後にひき逃げしたことに気づかなかった場合はどうなる?
事故に気づかなかった場合、以下のような法律が適用される可能性があります。
- 救護義務違反:故意でなくても適用されることがあります。
- 報告義務違反:3か月以下の懲役または5万円以下の罰金が科されることがあります。
もし事故の結果、他者が負傷または死亡した場合、過失運転致死傷罪が適用されることがあります。
過失運転致死傷罪に問われると、7年以下の懲役または禁錮、または100万円以下の罰金が科される可能性があります。
事故に気づかなかった場合、弁護人を通じて「気づかなかった」という主張をおこなうことが重要です。
また、弁護士に相談し、適切な法的アドバイスを受けることをおすすめします。
ひき逃げされた直後は「大丈夫」と言ってしまったが、後から痛みが出たときはどうしたらいい?
事故後に痛みが出た場合は、すぐに病院で診察を受け、診断書を取得することが重要です。
また、警察にも必ず連絡し、事故の詳細を報告する必要があります。
痛みが出たことを保険会社にも報告し、適切な手続きをおこないましょう。
ひき逃げ事故の場合、加害者が不明なことが多く、賠償請求が難しい場合があります。
このような状況では、交通事故に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士に相談することで、今後の対応をスムーズに進められ、適切な法的手続きを踏みやすくなります。
まとめ
本記事では、ひき逃げ事故に遭われた被害者の方、そしてひき逃げ事故を起こしてしまった加害者の方が、事故後にとるべき具体的な対応策・損害賠償請求・弁護士に相談するメリットなどについて解説しました。
ひき逃げ事故は、法的な手続きや交渉が複雑になるケースが多く、精神的な負担も大きいものです。
加害者、被害者いずれの立場であっても、一人で悩まず、できるだけ早い段階で交通事故問題に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。
専門家のアドバイスを受けることで、ご自身の権利を守り、未来への不安を少しでも軽減できるでしょう。
弁護士に相談するかお悩みの方へ
下のボタンからあなた当てはまるものを選んで悩みを解消しましょう。
弁護士費用特約があれば 実質0円で依頼できます!

多くの保険会社では、被害者1名につき最大300万円までの弁護士費用を負担してくれます。特約があるか分からない方でも、お気軽にご相談ください。弁護士と一緒にご確認した上で依頼の有無を決めて頂けます。
特約を利用して弁護士に相談する交通事故問題を依頼する弁護士の選び方にはポイントがあります。
- 過去の解決事例を確認する
- 料金体系が明確である弁護士を選ぶ
- 交通事故問題が得意な弁護士から選ぶ
等です。
詳しくは以下の記事を読んで、正しい弁護士の選び方を理解した上で弁護士に相談しましょう。
弁護士の選び方について詳しくみる
【元警察官(警部補)弁護士が経験を活かした交渉を】「怪我で通院している」「御家族が交通事故で亡くなった」など【LINE、WEB、電話で完結】【相談料無料】【着手金0円/365日対応】
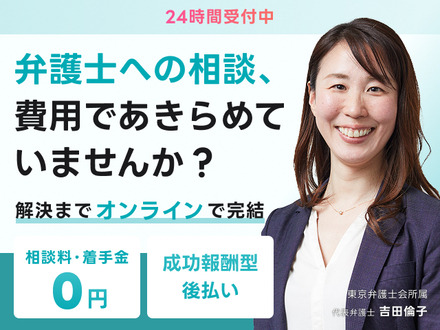
相談料・着手金0円、費用倒れの心配なし。大手より低価格な料金体系で増額実績多数。交通事故専門チームが後遺障害認定から交渉まで強力サポート。LINE完結・来所不要で全国対応。
事務所詳細を見る
【人身事故被害者の方へ】事故直後・通院中いずれの場合もまずはご相談ください。弁護士への依頼で、結果が大きく変わるかもしれません。【初回面談無料】【着手金無料プランあり】【オンラインで全国対応可能】
事務所詳細を見る当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
ひき逃げ被害に遭った方は弁護士へ相談することで加害者の特定や損害賠償がスムーズに進みます。
一部ではありますが、弁護士に依頼することで以下のようなメリットがあります。
・ひき逃げ犯の特定ができる可能性が高い
・損害賠償の請求もスムーズになる
・慰謝料の増額が見込める
・過失割合の是正が見込める
・弁護士が面倒な手続きなどを代行してくれる
依頼するしないは別として、ご自身の場合、弁護士に依頼するとどのようなメリットがあるのかを具体的に相談してみることをオススメします。
当サイト『ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)』は交通事故を得意とする弁護士を掲載しており、事務所への電話は【通話料無料】、電話相談や面談相談が無料の事務所や、着手金が必要ない事務所もあります。
まずは下記よりお近くの弁護士を探して相談してみましょう。

交通事故後の対応に関する新着コラム
-
接触がない「非接触事故」は、過失割合の判断が難しい事故です。非接触事故における過失割合の基本的な考え方、車対歩行者・車対車・車対バイクといった典型的なケース別の...
-
非接触事故で後日警察から連絡が来るかどうかは、一概には言えません。連絡が来る時期も、事故の種類や相手の診断書の提出時期、被害者のけがの程度により異なります。場合...
-
本記事では、交通事故の被害に遭った方に向けて、交通事故用の示談書の簡単な書き方と流れ、交通事故用の示談書を簡単に書くために押さえておくべき4つのコツ、示談書の作...
-
本記事では、自転車と自動車間の過失割合がどのように設定されるかや、自転車と自動車間の交通事故が起きたときの対処法・注意点を解説します。
-
非接触事故で転倒がなくても、後で怪我に気づくことがあります。適切な対処法を理解せずに立ち去ると問題になる可能性があるため、本記事では転倒なしの非接触事故における...
-
交通事故トラブルを抱えるなかで、弁護士だけでなく行政書士にも対応してもらえることを知り、主に費用面が気になっている方も多いのではないでしょうか。本記事では、行政...
-
本記事では、レンタカーを運転していて交通事故に遭った場合、相手が100%悪くてもレンタカー会社へお金を支払わなければならない理由やレンタカー会社からお金を請求さ...
-
本記事では、交通事故の被害に遭った方に向けて、被害者が利用できる保険(自賠責保険・任意保険)の種類、加害者の自賠責保険と被害者の任意保険を使用する順番、加害者側...
-
交通事故によるけがで仕事を休む場合、いつ頃復帰するのが適切なのでしょうか?本記事では、交通事故が原因で仕事を休む場合の一般的な休業期間や、休業した場合にもらえる...
-
交通事故に遭った場合、会社から診断書の提出を求められることがあります。しかし、費用の問題などからためらっている方も多いのではないでしょうか。本記事では、交通事故...
交通事故後の対応に関する人気コラム
-
当て逃げに遭ってしまった方へ、少しでも解決に近づけるための対処法をご紹介します。
-
物損事故とは、怪我人や死亡者がなく車両などに損害が出たにとどまる交通事故のことです。物損事故では相手方と示談交渉で揉めてしまう可能性もありますので、ポイントをお...
-
交通事故発生後は、警察に連絡・治療(人身事故の場合)・保険会社との交渉と進んでいきます。本記事では、各場面の詳しい対応や、いつ連絡が来るのかなどの期間についても...
-
交通事故が起きて被害者となった場合、「自分は被害者だから、待っているだけで何もする必要はない」と考えているなら、それは大きな間違いだと言えます。
-
交通事故が起きたら、物損事故・人身事故問わず警察へ届け出なければいけません。これは法律で義務付けられており、報告を怠ると法律違反として処罰を受ける可能性もありま...
-
交通事故のうち3割は駐車場で起こっているといわれています。駐車場は私有地になるため、事故が起こったあとの対処が一般道路とは異なる部分があります。本記事では、駐車...
-
事故後の対応や手続きを適切におこなうことで、その後の補償や示談交渉をスムーズに進められます。本記事では、交通事故にあった際に最初にとるべき行動、その後の手続きの...
-
車でおかまをほられた(後ろから追突された)ときに、どのように対処すればよいかご存知でしょうか。この記事では、車でおかまをほられた際の流れと対処法、示談金などを紹...
-
接触事故とは、走行中の自動車が車両・物・人などに接触して、損害や傷害が生じた事故のことです。接触事故では「怪我の有無」で賠償金の内容が異なりますので、事故後の流...
-
ひき逃げ事故は、その後の人生を大きく左右する重大な問題です。本記事では、ひき逃げ事故に遭われた被害者の方、そしてひき逃げ事故を起こしてしまった加害者の方が、事故...
交通事故後の対応の関連コラム
-
一時停止無視による事故に巻き込まれてしまったため、過失割合や罰則、違反点数の扱いがどうなるのか不安な方も多いのではないでしょうか。本記事では、一時停止無視による...
-
本記事では、交通事故の被害に遭った方に向けて、被害者が利用できる保険(自賠責保険・任意保険)の種類、加害者の自賠責保険と被害者の任意保険を使用する順番、加害者側...
-
追突事故では被害者の過失が0になるケースが多く賠償金も高額になりやすいですが、事故後の対応を誤ると適正な金額を受け取れなくなる恐れがあるためご注意ください。この...
-
自動車保険を契約する際の弁護士特約について「よくわからないけど、付けた方がいいの?」と悩んでいる方も多いのではないでしょうか。本記事では、弁護士特約をつけること...
-
実況見分調書の内容に納得がいかない場合、やり直しを求めることはできるのでしょうか。今回は、実況見分調書の内容に納得がいかない場合の対処法について、解説していきま...
-
交通事故に怪我は付きものです。その際に治療先の治療院はどこを選べばいいのか?治療費は妥当なのか?が気になると思いますので、ご紹介していきます。
-
追突事故に遭い、示談交渉がスムーズに進まずに悩んでいる方も多いのではないでしょうか。自力で解決しようとしても、問題の複雑化を招くおそれがあるので、まずは弁護士に...
-
交通事故発生後は、警察に連絡・治療(人身事故の場合)・保険会社との交渉と進んでいきます。本記事では、各場面の詳しい対応や、いつ連絡が来るのかなどの期間についても...
-
本記事では、過失割合10対0の交通事故における代車費用の扱い、交通事故に巻き込まれたときに弁護士へ相談するメリットなどについてわかりやすく解説します。
-
交通事故の加害者は、被害者に対して損害賠償責任を負うほか、自らもケガや車の破損などによって大きな損害を受けることがあります.。 交通事故を起こしてしまい、大き...
-
非接触事故で後日警察から連絡が来るかどうかは、一概には言えません。連絡が来る時期も、事故の種類や相手の診断書の提出時期、被害者のけがの程度により異なります。場合...
-
飲酒事故とは、酒を飲んだ状態で発生した交通事故のことです。飲酒事故の場合、通常の交通事故よりも重い罰則が科されて、賠償金が高額になることもあります。この記事では...
交通事故後の対応コラム一覧へ戻る


























 慰謝料・損害賠償
慰謝料・損害賠償
 示談
示談
 過失割合
過失割合
 死亡事故
死亡事故
 後遺障害
後遺障害
 むちうち
むちうち
 自転車事故
自転車事故
 自動車事故
自動車事故
 人身事故
人身事故
 バイク事故
バイク事故





























