交通事故にあったらどうする?事故後の対応6ステップと注意点を解説

- 「もし交通事故にあったときの初期対応は?」
- 「交通事故にあったら示談までの流れはどのように進める?」
突然交通事故にあってしまったら、誰でもパニックになってしまうものです。
しかし、事故後の対応や手続きを適切におこなうことで、その後の補償や示談交渉をスムーズに進められます。
そこで本記事では、交通事故にあった際に最初にとるべき行動、その後の手続きの流れ、そして注意すべきポイントをわかりやすく解説します。
事故直後の対応を事前に理解し、注意点を抑えておくことで、万が一の事態にも冷静に対処できます。
これから解説する6つのステップと注意点を理解すれば、冷静に行動するための準備が整うでしょう。
ぜひ最後までお読みください。
交通事故にあったら?|直後の対応6つのステップ

交通事故は、誰もが予期せず遭遇する可能性があります。
万が一、交通事故にあってしまった場合、落ち着いて適切な対応をとることが重要です。
ここでは、事故直後の対応を6つのステップで解説します。
これらのステップを踏むことで、自身と周囲の安全を確保し、その後の手続きをスムーズに進められます。
- 自身の安全を確保し負傷者がいる場合は救護する
- 警察へ連絡する(110番通報)
- 相手の情報や事故の状況を確認・記録する
- 自身の保険会社へ連絡する
- 医療機関を受診する
- 交通事故証明書の交付を受ける
①自身の安全を確保し負傷者がいる場合は救護する

まずは自分自身の安全を確保してください。
事故車両や周囲の状況を確認し、二次的な事故を防ぐために可能であれば安全な場所に移動しましょう。
次に、負傷者がいる場合は直ちに応急処置をおこないます。
負傷者の意識や呼吸、出血の有無などを確認し、必要に応じて119番通報で救急車を要請します。
救急車が到着するまでの間、可能な範囲で止血や気道確保などの応急手当を行ってください。
また、発煙筒や三角停止板を使用して、後続車に事故の発生を知らせることも大切です。
②警察へ連絡する(110番通報)

事故現場では、必ず警察に連絡し、110番通報をしてください。
警察への報告は道路交通法上の義務であり、報告を怠ると3ヵ月以下の懲役又は5万円以下の罰金に処される可能性があります。(道路交通法第72条・第119条)
道路交通法第72条 警察への報告義務
交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。
この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。同項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置(第七十五条の二十三第一項及び第三項において「交通事故発生日時等」という。)を報告しなければならない。
道路交通法第119条 報告を怠った場合の罰則
次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。
また、警察への報告を怠ると、保険金請求に必要な「交通事故証明書」が発行されません。
交通事故証明書がないと、事故の事実が確認できず、自賠責保険や任意保険から必要な補償を受けられない可能性があります。
通報時には、以下の内容を落ち着いて簡潔かつ明確に情報を伝えましょう。
- 事故の発生場所
- 事故の規模
- 負傷者の状況 など
交通事故の現場では相手から「警察を呼ばずに穏便に処理したい」といわれることがありますが、これは避けるべきです。
警察への報告は、事故の当事者間で後々のトラブルを防ぐためにも、必ずおこなうようにしましょう。
③相手の情報や事故の状況を確認・記録する

相手の情報や事故の状況を正確に記録することも重要です。
まず、以下の情報を確認しましょう。
- 氏名・住所・電話番号
- 相手の保険会社名・保険契約番号
- 車両ナンバー
- 勤務先および雇用主情報(氏名・住所・連絡先)
相手の勤務先の情報を確認する理由は、業務中の交通事故については、原則として雇用主に責任があるためです。
もしメモ用紙やペンがない場合は、名刺を受け取るか、相手の許可を得てスマートフォンで免許証などを撮影させてもらう方法でも構いません。
次に、事故の状況を記録することも大切です。
以下の情報をメモや写真、動画で記録しましょう。
事故の記録は、過失割合の判断や損害賠償請求の重要な根拠となります。
- 事故が発生した日時・事故現場
- 事故が発生した経緯
- 車両の損傷箇所
- 事故が起きた状況(天候・道路状況・信号の有無など)
事故の記録にはドライブレコーダーの映像を残しておくことも有効です。
データが上書きされないよう、SDカードを抜いて保管しましょう。
さらに、目撃者がいる場合は連絡先を確認し、証言をもらっておくとあとで証拠として役立ちます。
④自身の保険会社へ連絡する

事故発生あとはできるだけ早く自分の加入している保険会社に連絡し、事故の詳細を報告しましょう。
保険会社への連絡は、事故後のサポートを受けるために不可欠です。
保険会社には、以下の情報を伝えましょう。
| 伝える情報 | 内容 |
| 契約内容 | 証券番号・契約者・住所・連絡先など |
| 事故の状況 | 事故発生日時・場所・関係者の情報・事故の原因や状況など |
| 損害の有無 | 車両や人への損害の有無・どのような損害が発生したかなど |
| 事故後の対応 | 警察への連絡・医療機関への受診・相手と話した内容など |
保険会社に事故の手続きを依頼すると、修理費や医療費、賠償金などの支援が受けられます。
事故報告書や必要書類を提出した後、保険会社からの指示に従い、手続きを進めていきましょう。
⑤医療機関を受診する

事故後、症状がない場合でも必ず病院で診察を受け、診断書を取得するようにしましょう。
事故によるけがは、あとから症状が現れることがあるためです。
たとえば、目に見える傷がなくても、内出血やむちうち症などの症状が後に現れることがあります。
診断書は損害賠償請求の際に重要な証拠となります。
受診が遅れると、交通事故によるけがであることが証明できなくなり、治療費などの賠償を受けられなくなる可能性があります。
整形外科や脳神経外科など、適切な診療科で受診してください。
なお、診断書には、以下の内容を記載してもらいましょう。
| 項目 | 内容 |
| 傷病者の情報 | 患者の氏名や生年月日などの基本情報 |
| 傷病名 | 事故によって負ったけがの名称(例:打撲、骨折など) |
| 症状の詳細 | 現在の症状や痛みの程度、受傷部位など |
| 治療開始日 | 事故後、治療を開始した日付 |
| 治療期間 | どのくらいの期間治療が必要とされるかの見込み |
| 作成年月日 | 診断書が作成された日付 |
| 病院名および医師名 | 診断書を発行した医療機関の名称と担当医師の名前 |
| 今後の見通し | 治療の経過や今後の予想される治療内容、後遺症の可能性など |
診断書が損害賠償請求や示談交渉において重要な証拠となるため、正確に記載されることが求められます。
診断書を受け取った際には、記載内容に誤りがないかを確認することも重要です。
⑥交通事故証明書の交付を受ける

事故後、必ず交通事故証明書を交付してもらうことが重要です。
交通事故証明書は、交通事故の発生を公的に証明する書類です。
事故証明書には、事故の日時・場所・関係者などの詳細情報が記載されており、今後の保険請求や法的手続きにおいて重要な証拠となります。
特に後の賠償請求や裁判で必要となるため、忘れずに手続きをおこないましょう。
交通事故証明書を取得するためには、まず事故を警察に届け出る必要があります。
警察が現場確認をおこなった後、その結果をもとに自動車安全運転センターが証明書を発行します。
事故後すぐに取得し、大切に保管しておきましょう。
交通事故にあって医療機関を受診した後の手続きと流れ
交通事故にあってけがを負った場合、適切な治療を受けて損害賠償請求をおこなうためには、以下の手続きが必要です。
- 「交通事故証明書」を取得したり、後遺症が残った場合には「後遺障害等級認定」を受ける
- 示談交渉をおこなう
- 必要に応じて弁護士へ相談する
これらの手続きを適切におこなうことで、自身の権利を守り、適正な補償を受けられます。
それぞれの内容について詳しく見ていきましょう。
①「交通事故証明書」を取得したり、後遺症が残った場合には「後遺障害等級認定」を受ける

示談交渉をスムーズに進めるためには、まず「交通事故証明書」や「後遺障害等級認定」など、重要な証拠となる書類を用意することが大切です。
- 交通事故証明書
- 事故の事実を公的に証明するもので、保険金の請求や損害賠償請求の際に必要となります。
- 事故直後に警察に事故を届け出てから、自動車安全運転センターに発行してもらいます。
- 後遺障害等級認定
- 治療を続けても症状が改善せず、後遺症が残ってしまった場合は、後遺障害等級認定を受けましょう。
- 認定されれば、後遺障害に対する賠償金(後遺障害慰謝料や逸失利益)を請求できます。
後遺障害等級認定を受けるためには、専門医による「後遺障害診断書」が必要です。
症状を正確に評価してもらうために、医師とよく相談しましょう。
②示談交渉をおこなう

次に、けがの治療が完了した後、または後遺障害等級の認定を受けた時点で、事故の加害者やその保険会社と示談交渉をおこないます。
示談内容は、大きく分けて「人に関する損害」と「物に関する損害」の2つがあります。
どちらも漏れなく示談交渉の際の交渉材料にするようにしましょう。
| 人に関する損害 | 物に関する損害 |
|
|
示談交渉の際は、自分の症状や後遺症について正確に伝え、過小評価されないように注意しましょう。
示談が成立すると、基本的にその内容の変更や修正はできなくなります。
示談内容に不満がある場合は交渉を続けるか、弁護士に相談することをおすすめします。
相手が提示する内容に合意すれば、示談が成立となり損害賠償額が正式に確定します。
示談が成立したら、後のトラブルを避けるために、必ず書面(示談書)に残しておくのも大切です。
示談交渉のタイミングや有利に進める方法については、「交通事故の示談交渉時期とタイミング|示談を有利に進める方法」で詳しく解説しています。
③必要に応じて弁護士へ相談する

示談交渉に不満がある場合や、交渉が上手くいかない場合は、弁護士への相談も検討しましょう。
交通事故の手続きや示談交渉が複雑な場合、弁護士に相談することで、適切なアドバイスを受けられます。
たとえば、賠償金額の増額を目指す交渉や、法的手続きを進めるサポートをおこなってくれます。
特に後遺障害が残った場合や、相手の保険会社との交渉が難航する場合には、弁護士の助けを借りることが重要です。
なお、弁護士に相談することで得られる具体的な利益(慰謝料の増加・交渉のスムーズ化など)については、のちほど「解決事例」の見出しで詳しく紹介します。
交通事故にあったら注意すべき3つのポイント
交通事故は予期せぬ出来事であり、冷静な判断が難しい状況に陥ることがあります。
ここでは、交通事故にあったときに注意すべきポイントを3つ解説します。
- 事故現場では当事者同士で交渉や賠償金の取り決めをおこなわない
- 治療費として支払われる損害賠償金は、事故によるけがに対してのみ適用される
- 示談を締結する前に必ず疑問や不安を解消する
これらのポイントを理解しておくことで、後のトラブルを防ぎ、適切な対応をとれます。
事故現場では当事者同士で交渉や賠償金の取り決めをおこなわない
事故現場でその場で賠償金の取り決めをすることは避けるべきです。
口頭であっても、一度成立した示談は基本的に取り消せないためです。
事故直後は、どのような負傷が生じているか、正確な状況を把握できません。
そのため、現場で示談した金額では、損害が適正にカバーされていない可能性があります。
また、事故直後は動揺して感情的になっている可能性があり、冷静な判断ができないこともあります。
そのため、交渉は保険会社や弁護士を通じておこない、後々のトラブルを避けるためにも、現場では話し合わないようにしましょう。
事故後の適切な賠償金を見極めるためには、医師の診断結果や事故の詳細を踏まえた正当な手続きをおこなうことが重要です。
治療費として支払われる損害賠償金は、事故によるけがに対してのみ適用される
事故による治療費は、事故が原因で発生したけがに対するものであり、事故とは直接関係のない病状や治療は賠償金として認められません。
たとえば、事故前から持病で通院しており、事故で同じ部位を負傷した場合、通院が持病によるものか事故によるものかが問題になることがあります。
補償が対象となるか不安な場合は、保険会社に相談することをおすすめします。
医療機関で診断書を取得し、治療が事故によるものであることを証明することも重要です。
これにより、適切な治療費が賠償されることになります。
示談を締結する前に必ず疑問や不安を解消する
示談交渉は慎重におこない、示談書にサインする前に内容を十分に確認しましょう。
疑問点や不安があれば、弁護士に相談して確認することが重要です。
示談書に署名すると、あとで追加請求や異議を申し立てることが難しくなります。
そのため、賠償金額や契約内容が正当なものであるかを慎重に確認することが重要です。
相手から提示された示談金に違和感がある場合は、弁護士による無料相談を活用するのがおすすめです。
弁護士は示談金が適正な金額かどうか、専門的なアドバイスをしてくれます。
交通事故問題に特化した弁護士を簡単に検索できる「ベンナビ交通事故」なら、初回相談が無料の弁護士が多数登録されています。
また、電話やオンライン相談が可能な弁護士も多いため、示談金に関する不安を解消したい方は、まずは無料相談を活用してみてはいかがでしょうか。
交通事故にあったときに相談できる窓口
交通事故にあったときに相談できる窓口は以下のとおりです。
無料で相談できる窓口もあるため、事故でけがをした・賠償に関して不安があるなどの場合はぜひ活用してみてください。
| 相談窓口 | 内容 | 料金 | 特徴 |
| 弁護士 | 交通事故に関する法的なサポート全般 (法律相談・示談交渉の代理・訴訟の代理など) |
有料 (一部で初回無料) |
・専門的なアドバイスを受けられる |
| 法テラス | 経済的に余裕がない方を対象に、無料の法律相談や弁護士費用の立て替え制度を提供 | 無料 | ・経済的な負担が少ない ・利用には条件があり、すぐに利用できない場合がある |
| 日弁連交通事故相談センター | 弁護士による無料の電話相談や面談相談 | 無料 | ・無料で相談できるため気軽に利用できる ・相談内容や日時が限られている場合がある |
| 自治体の相談窓口 | 交通事故に関する一般的な相談 | 無料 | ・交通事故の基本的な情報やアドバイスを得られる ・複雑な案件には対応できない場合がある |
| 交通事故紛争処理センター | 中立・公正な立場で、法律相談や和解あっせん、審査手続きなど | 無料 | ・中立的な立場で公正に解決を目指しているため、信頼性が高い ・対応に時間がかかる場合があり、和解に至らない可能性もある |
被害者向けの無料相談窓口については「交通事故の相談窓口|被害者向け・無料相談窓口を紹介」で詳しく解説しているため、あわせてお読みください。
交通事故にあったら弁護士に相談すべき3つの理由
交通事故にあったら弁護士に相談することを強くおすすめします。
ここでは、交通事故にあったときに弁護士に依頼すべき理由を3つのポイントに分けて解説します。
- 相手方との交渉を代理しておこなってくれる
- 慰謝料が増加する可能性がある
- 後遺障害等級の認定手続きのサポートをしてくれる
それぞれの理由について詳しく見ていきましょう。
相手方との交渉を代理しておこなってくれる
弁護士に依頼することで、相手方との複雑な交渉を代行してもらえ、精神的な負担を大幅に軽減できます。
交通事故の知識や経験がない被害者にとって、加害者側と補償について交渉するのは大きな負担となります。
特に、複雑な事案の場合、交渉が難航することも少なくありません。
しかし、弁護士に依頼すれば、被害者自身が交渉する必要がなくなり、負担を軽減できます。
けがを負っている場合でも、治療に専念できるため安心です。
弁護士は、法的な知識や豊富な経験を活かし、被害者が不利な状況に陥らないよう適切に交渉を進め、適正な補償を受けられるようサポートしてくれます。
慰謝料が増加する可能性がある
弁護士に依頼することで、当初保険会社から提示された金額よりも、慰謝料が大幅に増額されるケースは少なくありません。
なかには、2~3倍以上に増額された事例もあります。
慰謝料の算定には3つの基準があり、弁護士は最も高額な「裁判所基準」を用いて交渉をおこなってくれるためです。
| 算定基準 | 内容 |
| 自賠責保険基準 | ・被害者の最低限の補償を目的とした国の基準 ・慰謝料や損害賠償額は最も低く設定されている |
| 任意保険基準 | ・各保険会社が独自に定める基準 ・自賠責保険基準よりは高いが、裁判所基準より低いことが一般的 |
| 裁判所基準(弁護士基準) | ・過去の裁判例をもとに算定される最も高額な基準 ・弁護士が交渉することで適用される可能性が高まる |
示談交渉では、加害者側の保険会社は通常、「任意保険基準」を提示してきます。
しかし、「裁判所基準(弁護士基準)」は過去の裁判例に基づき、被害者が実際に受け取るべき金額に近い最も高額な基準です。
弁護士が交渉をおこなうことで、この裁判所基準が適用される可能性が高まるのです。
後遺障害等級の認定手続きのサポートをしてくれる
後遺障害等級認定の手続きをサポートしてくれる点も大きなメリットです。
「後遺障害等級認定」とは、交通事故による後遺症の程度を公的に認定する手続きのこと。
後遺障害慰謝料や逸失利益(事故がなければ得られたであろう収入)の請求で必要です。
認定された等級によって補償額が大きく変わり、等級が低くなる(数字が大きくなる)ほど慰謝料の相場も減少します。
| 等級 | 慰謝料の相場(弁護士基準の場合) |
| 1級 | 約2800万円 |
| 2級 | 約2370万円 |
| 3級 | 約1990万円 |
| 4級 | 約1670万円 |
| 5級 | 約1400万円 |
等級認定は主に書類審査ですが、事故の因果関係を証明するのは、交通事故に詳しくない被害者にとって難しいものです。
弁護士に依頼すれば、診断書作成のサポートや適切な検査のアドバイスが受けられ、認定手続きが有利に進む可能性が高まります。
後遺障害認定についてより詳しく知りたい方は、下記の記事もあわせてお読みください。
弁護士へ相談するタイミングはいつがいい?
弁護士に相談する最適なタイミングは、交通事故が発生したすぐあとです。
加害者とのやり取りに不安がある場合や、保険会社の対応に疑問を感じる場合は、早めに弁護士に相談することで、問題を早期に解決できる可能性が高まります。
弁護士は事故直あとから証拠の収集や、その後の手続きについてアドバイスをしてくれます。
また、弁護士に依頼することで慰謝料の増額や適正な保険金の請求につながるケースも多くあります。
早い段階で専門家のアドバイスを受けることが、よりよい解決への近道となるでしょう。
交通事故問題に強い弁護士を探すなら「ベンナビ交通事故」
「ベンナビ交通事故」は、交通事故問題に特化した弁護士を簡単に検索できるポータルサイトです。
地域・相談内容・得意分野など、さまざまな条件で絞り込み検索できるため、あなたにぴったりの弁護士を手間なく見つけられます。
また、夜間・土日祝に対応の事務所も多数掲載されているため、緊急で相談したい場合でも安心です。
さらに、初回相談無料や電話・オンライン相談可能な弁護士も豊富に登録されており、気軽に相談を始められます。
特に、後遺障害が残るケースや過失割合に争いがある場合など、複雑な事案では弁護士のサポートが不可欠です。
弁護士に相談することで、法的観点から適切な解決策を得られるだけでなく、将来的なトラブルを未然に防ぐことも可能です。
「ベンナビ交通事故」を活用して信頼できる弁護士を見つけ、交通事故についてのお悩みを早期に解決しましょう。
解決事例①示談交渉により990万円から3,210万円に損害賠償を増額
「ベンナビ交通事故」で解決できた代表的な事例をいくつか紹介します。
交通事故後の対応にお困りの方は、ぜひ参考にしてください。
まずは、示談交渉により賠償金が990万円から3,210万円増額された事例です。
| 当初の賠償額 | 示談交渉後の賠償額 | 賠償額の増減 |
| 990万円 | 3,210万円 | 2,220万円の増額 |
- 事故の状況
- この事例は、歩道で停止中の歩行者に車両が衝突した事故です。
- 歩行者(依頼者)の顔には大きな傷跡が残り、後遺障害として外貌醜状のみが認定されていました。
- 保険会社は逸失利益を完全に否定したことから弁護士に依頼したケースです。
- 対応と結果
- 接客業において外貌醜状が大きく影響を与えることを主張し立証した結果、保険会社はこちらの主張を受け入れ、示談が成立しました。
- 考察
- この事例から、事故後の適切な対応と専門的な知識が、最終的な賠償額に大きな違いをもたらすことがわかります。
解決事例②後遺障害等級9級が認定、慰謝料1500万から3000万に増額
続いて、後遺障害認定の申請が認められ、当初の賠償額より1,500万円増額できた事例です。
| 当初の賠償額 | 示談交渉後の賠償額 | 賠償額の増減 |
| 1,500万円 | 3,000万円 | 1,500万円の増額 |
- 事故の状況
- 横断歩道を歩行中に車にひかれ、左足を複雑骨折しました。
- 入院は3ヵ月、その後1年半の通院治療を経て弁護士に依頼。
- 症状が重く、治療にも長期間を要したため、損害保険会社との交渉が難航するのではないかと不安に感じ、弁護士に依頼したケースです。
- 対応と結果
- 弁護士が後遺障害認定申請をおこない、9級が認められました。
- その結果、賠償額は将来の治療費も含めて約3,000万円に増加しました。
- 考察
- この事例から分かることは、後遺障害等級の認定が賠償額に大きな影響を与えることです。
- また、弁護士による専門的な対応が、保険会社との交渉を有利に進める大きな力になることも示されています。
交通事故にあったら覚えておきたい被害者救済制度
交通事故の被害にあわれた方は、心身ともに大きな負担を抱えることになります。
ここでは、そのような被害者を救済するための制度を2つ紹介します。
- 政府保障事業(国土交通省)
- NASVA(自動車事故対策機構)
これらの制度を知っておくことで、万が一の際に、より適切な対応をとれるでしょう。
それぞれの制度について詳しく解説します。
政府保障事業(国土交通省)
政府保障事業は、加害者が無保険またはひき逃げ事故で加害者が特定できない場合など、加害者に損害賠償責任を問えない被害者を救済するための制度です。
国土交通省が運営しています。
交通事故の被害にあっても加害者から十分な賠償を受けられない場合、政府が加害者の代わりに損害を補償し、被害者の生活を守ることを目的としています。
具体的には、傷害事故に対しては最大120万円、死亡事故に対しては最大3,000万円の補償がおこなわれます。
政府保障事業への請求は、損害保険会社(共済組合)の窓口で受け付けています。
詳細については、各損害保険会社または共済組合にお問い合わせください。
NASVA(自動車事故対策機構)
NASVA(自動車事故対策機構)は、自動車事故の発生防止と、事故被害者の支援を目的とする独立行政法人です。
全国50か所に支所を置き、被害者やその家族に対して、さまざまな支援活動をおこなっています。
NASVAの主な支援内容は以下のとおりです。
- 療養施設の案内
- 事故による重度の後遺障害を負った方に対して、専門的な治療やリハビリテーションを受けられる施設を紹介する
- 介護料の支援
- 介護が必要な被害者に対して、介護費用の助成をおこなう
- 生活資金の無利息貸付
- 勝訴判決を得たにもかかわらず、加害者から支払いを受けられない被害者などに対して、生活資金の無利息貸付をおこなう
NASVAは、交通事故被害者の経済的・精神的な負担を軽減し、社会復帰をサポートするための重要な役割を担っています。
さらに詳しい情報については、「自動車事故対策機構とは?業務内容・被害者が利用できる支援制度などを解説」や下記の公式サイトをご確認ください。
まとめ
本記事では、交通事故にあった際に最初にとるべき行動、その後の手続きの流れ、そして注意すべきポイントについて解説しました。
交通事故にあった際は、冷静に対応し、適切な手続きをおこなうことが重要です。
事故にあわないことが理想ですが、万が一のときに備えて、本記事の内容を参考に正しい知識を身につけておきましょう。
また、疑問・不安がある場合や、専門的な知識が必要な場面では、弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士は、あなたの強い味方となり、最善の結果へと導いてくれるでしょう。
弁護士に相談するかお悩みの方へ
下のボタンからあなた当てはまるものを選んで悩みを解消しましょう。
弁護士費用特約があれば 実質0円で依頼できます!

多くの保険会社では、被害者1名につき最大300万円までの弁護士費用を負担してくれます。特約があるか分からない方でも、お気軽にご相談ください。弁護士と一緒にご確認した上で依頼の有無を決めて頂けます。
特約を利用して弁護士に相談する交通事故問題を依頼する弁護士の選び方にはポイントがあります。
- 過去の解決事例を確認する
- 料金体系が明確である弁護士を選ぶ
- 交通事故問題が得意な弁護士から選ぶ
等です。
詳しくは以下の記事を読んで、正しい弁護士の選び方を理解した上で弁護士に相談しましょう。
弁護士の選び方について詳しくみる
【全国対応│初回相談無料◎】大手法律事務所の交通事故専門部にて交通事故の部門長の経験あり!豊富な実績を用いて示談金や賠償金、後遺障害や過失割合の問題を迅速な解決に向けて代理対応します!
事務所詳細を見る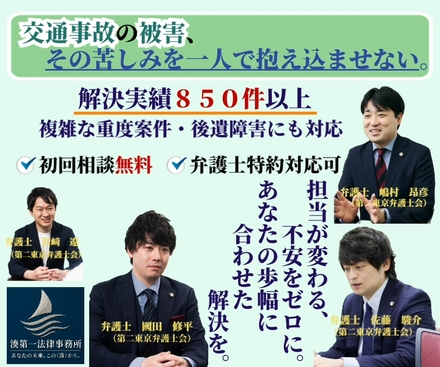
【初回相談無料】解決件数850件以上の弁護士が直接対応/賠償金の大幅増額の実績あり/後遺障害・交渉はお任せください/むち打ち・骨折〜死亡事故など幅広く親身にお話伺います<オンライン相談可・全国対応可>
事務所詳細を見る
【賠償金獲得まで費用は0円!】これまでの解決実績は26,000件以上。賠償金額・後遺障害・むちうちなどのご相談は、増額実績多数の当事務所へご相談ください。諦めるのはまだ早いかもしれません!
事務所詳細を見る当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡

交通事故後の対応に関する新着コラム
-
接触がない「非接触事故」は、過失割合の判断が難しい事故です。非接触事故における過失割合の基本的な考え方、車対歩行者・車対車・車対バイクといった典型的なケース別の...
-
非接触事故で後日警察から連絡が来るかどうかは、一概には言えません。連絡が来る時期も、事故の種類や相手の診断書の提出時期、被害者のけがの程度により異なります。場合...
-
本記事では、交通事故の被害に遭った方に向けて、交通事故用の示談書の簡単な書き方と流れ、交通事故用の示談書を簡単に書くために押さえておくべき4つのコツ、示談書の作...
-
本記事では、自転車と自動車間の過失割合がどのように設定されるかや、自転車と自動車間の交通事故が起きたときの対処法・注意点を解説します。
-
非接触事故で転倒がなくても、後で怪我に気づくことがあります。適切な対処法を理解せずに立ち去ると問題になる可能性があるため、本記事では転倒なしの非接触事故における...
-
交通事故トラブルを抱えるなかで、弁護士だけでなく行政書士にも対応してもらえることを知り、主に費用面が気になっている方も多いのではないでしょうか。本記事では、行政...
-
本記事では、レンタカーを運転していて交通事故に遭った場合、相手が100%悪くてもレンタカー会社へお金を支払わなければならない理由やレンタカー会社からお金を請求さ...
-
本記事では、交通事故の被害に遭った方に向けて、被害者が利用できる保険(自賠責保険・任意保険)の種類、加害者の自賠責保険と被害者の任意保険を使用する順番、加害者側...
-
交通事故によるけがで仕事を休む場合、いつ頃復帰するのが適切なのでしょうか?本記事では、交通事故が原因で仕事を休む場合の一般的な休業期間や、休業した場合にもらえる...
-
交通事故に遭った場合、会社から診断書の提出を求められることがあります。しかし、費用の問題などからためらっている方も多いのではないでしょうか。本記事では、交通事故...
交通事故後の対応に関する人気コラム
-
当て逃げに遭ってしまった方へ、少しでも解決に近づけるための対処法をご紹介します。
-
物損事故とは、怪我人や死亡者がなく車両などに損害が出たにとどまる交通事故のことです。物損事故では相手方と示談交渉で揉めてしまう可能性もありますので、ポイントをお...
-
交通事故発生後は、警察に連絡・治療(人身事故の場合)・保険会社との交渉と進んでいきます。本記事では、各場面の詳しい対応や、いつ連絡が来るのかなどの期間についても...
-
交通事故が起きて被害者となった場合、「自分は被害者だから、待っているだけで何もする必要はない」と考えているなら、それは大きな間違いだと言えます。
-
交通事故が起きたら、物損事故・人身事故問わず警察へ届け出なければいけません。これは法律で義務付けられており、報告を怠ると法律違反として処罰を受ける可能性もありま...
-
交通事故のうち3割は駐車場で起こっているといわれています。駐車場は私有地になるため、事故が起こったあとの対処が一般道路とは異なる部分があります。本記事では、駐車...
-
事故後の対応や手続きを適切におこなうことで、その後の補償や示談交渉をスムーズに進められます。本記事では、交通事故にあった際に最初にとるべき行動、その後の手続きの...
-
車でおかまをほられた(後ろから追突された)ときに、どのように対処すればよいかご存知でしょうか。この記事では、車でおかまをほられた際の流れと対処法、示談金などを紹...
-
接触事故とは、走行中の自動車が車両・物・人などに接触して、損害や傷害が生じた事故のことです。接触事故では「怪我の有無」で賠償金の内容が異なりますので、事故後の流...
-
ひき逃げ事故は、その後の人生を大きく左右する重大な問題です。本記事では、ひき逃げ事故に遭われた被害者の方、そしてひき逃げ事故を起こしてしまった加害者の方が、事故...
交通事故後の対応の関連コラム
-
交通事故の加害者は、被害者に対して損害賠償責任を負うほか、自らもケガや車の破損などによって大きな損害を受けることがあります.。 交通事故を起こしてしまい、大き...
-
事故で車が廃車になった際、車の時価額や買い替え諸費用を相手方に請求できる場合があります。本記事では、事故で廃車になった際の車の時価額や買い替え諸費用を相手方に請...
-
通勤中に交通事故に遭った場合、自動車保険だけでなく労災保険が使用できるケースもあります。十分な補償を受けるためにも、それぞれの中身を正しく理解しましょう。本記事...
-
物損事故とは、怪我人や死亡者がなく車両などに損害が出たにとどまる交通事故のことです。物損事故では相手方と示談交渉で揉めてしまう可能性もありますので、ポイントをお...
-
交通事故発生後は、警察に連絡・治療(人身事故の場合)・保険会社との交渉と進んでいきます。本記事では、各場面の詳しい対応や、いつ連絡が来るのかなどの期間についても...
-
タクシーとの交通事故は、誰にとっても突然の出来事。しかし、事故直後の行動次第で、その後の示談や補償に大きな影響が出ます。 本記事では、タクシー事故時に取るべき...
-
交通事故における供述調書(きょうじゅつちょうしょ)とは、警察が事故の様子を記録する為に作成する書類のことで、事故の状況を明らかにする実況見分書とセットで作成され...
-
交通事故のうち3割は駐車場で起こっているといわれています。駐車場は私有地になるため、事故が起こったあとの対処が一般道路とは異なる部分があります。本記事では、駐車...
-
物損事故の場合、慰謝料は請求できないケースが大半です。車の修理費など、請求が認められる損害の賠償を漏れなく請求しましょう。本記事では、物損事故で慰謝料は請求でき...
-
交通事故トラブルを抱えるなかで、弁護士だけでなく行政書士にも対応してもらえることを知り、主に費用面が気になっている方も多いのではないでしょうか。本記事では、行政...
-
交通事故に遭った場合、会社から診断書の提出を求められることがあります。しかし、費用の問題などからためらっている方も多いのではないでしょうか。本記事では、交通事故...
-
交通事故が起きたら、物損事故・人身事故問わず警察へ届け出なければいけません。これは法律で義務付けられており、報告を怠ると法律違反として処罰を受ける可能性もありま...
交通事故後の対応コラム一覧へ戻る


























 慰謝料・損害賠償
慰謝料・損害賠償
 示談
示談
 過失割合
過失割合
 死亡事故
死亡事故
 後遺障害
後遺障害
 むちうち
むちうち
 自転車事故
自転車事故
 自動車事故
自動車事故
 人身事故
人身事故
 バイク事故
バイク事故

























