後遺障害14級に該当する症状とは?認定率を上げるポイントや慰謝料相場を解説

交通事故の後遺障害には、第1級から第14級までの等級が設定されています。
後遺障害14級は最も軽度であり、代表的なけがとしては「むちうち」があります。
後遺障害等級が認定されるかどうかで受け取れる損害賠償額は大きく変わるため、後遺症が残った場合には等級獲得に向けて適切に手続きを進めていくことが大切です。
本記事では、交通事故で後遺障害14級が認定される症状の具体例や認定条件、認定を受けるためのポイントや慰謝料相場などを解説します。
後遺障害14級の症状
後遺障害等級14級は1号から9号まであり、それぞれの主な症状は以下のとおりです。
| 等級 | 後遺障害の症状 |
|---|---|
| 14級1号 | 片方のまぶたが一部欠損したもの・まつげはげを残すもの |
| 14級2号 | 三歯以上に対し歯科補てつを加えたもの |
| 14級3号 | 片方の耳が1m以上の距離で小声を聴き取れない程度に聴力が落ちたもの |
| 14級4号 | 上半身の露出面にてのひらサイズの醜いあとを残すもの |
| 14級5号 | 下半身の露出面にてのひらサイズの醜いあとを残すもの |
| 14級6号 | 片手の親指以外の指骨の一部を失ったもの |
| 14級7号 | 片手の親指以外の指の第一関節を曲げ伸ばしできなくなったもの |
| 14級8号 | 片足の中指から小指のうち1本~2本の用を廃したもの |
| 14級9号 | 身体の一部に神経症状を残すもの |
ここでは、後遺障害14級が認定される主な症状について解説します。
14級1号:片方のまぶたが一部欠損したもの・まつげはげを残すもの
後遺障害14級1号が認定されるのは、「片方のまぶたが一部欠損したもの・まつげはげを残すもの」です。
具体的には、目を閉じた際に角膜を完全に覆うことはできるものの、白目が露出している程度の状態を指します。
ここでいう「まつげはげ」とは、まつげの生えている周縁の2分の1以上にわたって、まつげがなくなってしまう症状のことです。
14級2号:三歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
後遺障害14級2号が認定されるのは、「三歯以上に対し歯科補てつを加えたもの」です。
歯科補てつとは、完全に無くしている、または著しく欠損した歯を被せものや入れ歯などの人工物で補うことを指します。
14級3号:片方の耳が1m以上の距離で小声を聴き取れない程度に聴力が落ちたもの
後遺障害14級3号が認定されるのは、「片方の耳が1m以上の距離で小声を聴き取れない程度に聴力が落ちたもの」です。
具体的には、一耳の平均純音聴力レベルが40db以上70db未満の状態をいいます。
簡単にいうと、小声でささやかれる程度では聞こえない状態です。
14級4号:上半身の露出面にてのひらサイズの醜いあとを残すもの
後遺障害14級4号が認定されるのは、「上半身の露出面にてのひらサイズの醜いあとを残すもの」です。
「醜いあと」の明確な基準はありませんが、誰が見てもひどい状態と考えてください。
14級5号:下半身の露出面にてのひらサイズの醜いあとを残すもの
後遺障害14級5号が認定されるのは、「下半身の露出面にてのひらサイズの醜いあとを残すもの」です。
「醜いあと」の定義については、4号と同様に誰が見てもひどい状態と考えてください。
14級6号:片手の親指以外の指骨の一部を失ったもの
後遺障害14級6号が認定されるのは、「片手の親指以外の指骨の一部を失ったもの」です。
片手の指の骨の一部を失っていることが、X線写真などで確認できる状態をいいます。
14級7号:片手の親指以外の指の第一関節を曲げ伸ばしできなくなったもの
後遺障害14級7号が認定されるのは、「片手の親指以外の指の第一関節を曲げ伸ばしできなくなったもの」です。
なお、麻痺が第二関節に及んでいる場合は、等級が上がることもあります。
14級8号:片足の中指から小指のうち1本~2本の用を廃したもの
後遺障害14級8号が認定されるのは、「片足の中指から小指のうち1本~2本の用を廃したもの」です。
具体的には次のような症状が該当します。
- 片足の指の末節骨の長さの2分の1以上を失ったもの
- 片足の指を切断したもの
- 片足の指の第1関節または第2関節がなくなったもの
- 足の指の付け根の関節または第2関節の可動域が腱側の可動域角度の2分の1以下に制限されるもの など
大まかにいうと、足の指が切断される、あるいは半分しか動かない状態であると考えてください。
14級9号:身体の一部に神経症状を残すもの
後遺障害14級9号が認定されるのは、「身体の一部に神経症状を残すもの」です。
具体的には、痛み・痺れ・めまい・吐き気・頭痛・耳鳴りなどの症状が続いている場合などが該当します。
一般的には、むちうちによって後遺症が残ったケースでは14級9号が認定される可能性が高いといえるでしょう。
後遺障害14級の認定条件
次に、後遺障害14級の認定条件について詳しく見ていきましょう。
1.事故が症状を発生させる程度のものであること
後遺障害として認められるのは、後遺症の発症が事故によるものと認められる場合です。
そのため、極めて低速で追突されたり、事故自体の規模が小さかったりする場合には、たとえ症状を発症していたとしても非該当とされることがあります。
2.事故当初から病院への通院を継続していること
後遺障害として等級認定を受けるためには、受傷直後から症状固定になるまで、整形外科などの医師の治療を継続して受けている必要があります。
たとえば、事故直後から1ヵ月ほど一切通院していなかったり、整骨院の通院のみで医師の治療を受けていなかったりする場合は、等級認定を受けられない可能性があります。
3.事故当初からの症状の訴えが一貫して継続していること
後遺障害14級の認定を受けるためには、事故直後から症状固定まで症状が一貫・連続していることが必要です。
たとえば、事故当初は左足の関節が痛んでいたものの、事故から5ヵ月経つと右足の痛みを訴えるようになったり、1ヵ月おきに別の箇所に痛みが出ていることを訴えたりしている場合などは非該当となることがあります。
4.症状がそれなりに重篤であり、常時性が認められること
そもそも「後遺障害」というくらいなので、等級認定を受けるためには残った症状がそれなりに重いことも必要になります。
たとえば、頚部の「コリ」「違和感」「だるさ」などの症状では、後遺障害として認められない可能性があります。
また、後遺障害は一過性のものではなく、慢性症状であることが基本です。
これらを総合的に考慮したうえで、後遺障害等級14級に該当するかどうかが判断されます。
後遺障害14級が認定された場合の慰謝料相場・計算方法
交通事故で後遺障害として等級認定を受けた場合、「後遺障害慰謝料」や「後遺障害逸失利益」といった後遺障害に関する賠償金を請求することができます。
ここでは、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益の相場・計算方法を解説します。
後遺障害慰謝料の計算基準は3種類ある
交通事故の慰謝料については、以下のような3種類の計算基準があります。
- 自賠責基準:自賠責保険が用いる計算基準で、最も低額になりやすい
- 任意保険基準:各任意保険会社が用いる計算基準で、自賠責保険よりも高額になりやすい
- 弁護士基準:弁護士や裁判所が用いる計算基準で、最も高額になりやすい
相手方が任意保険に加入していない場合は自賠責基準、任意保険に加入している場合は任意保険基準、慰謝料請求を弁護士に依頼する場合は弁護士基準が適用されるのが一般的です。
以下では、各計算基準の慰謝料相場について解説します。
自賠責基準
自賠責基準で算定した場合、後遺障害14級での慰謝料は32万円となります。
なお、当該金額は後遺障害14級の適正な慰謝料額を検討するうえでの「最低基準」と考えられています。
自賠責基準に基づく慰謝料額は、3つの計算基準の中でも最も低額になるということを覚えておきましょう。
任意保険基準
任意保険基準については、各保険会社によって算定方法が異なるため、具体的な金額を示すことはできません。
基本的には、自賠責基準とほぼ同額か若干高い程度が相場といえるでしょう。
弁護士基準
弁護士基準の慰謝料額に関しては、通称「赤い本」と呼ばれる日弁連が発行する「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」に記載があり、110万円となります。
自賠責基準と弁護士基準では3倍以上の差があり、後遺症が残った場合は交通事故問題を得意とする弁護士にサポートしてもらうことをおすすめします。
後遺障害逸失利益の計算方法
後遺障害逸失利益とは、交通事故による後遺障害がなければ本来受け取れるはずだった将来分の収入のことを指します。
後遺障害逸失利益については、以下のような式で算出します。
- 後遺障害逸失利益=収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に応じたライプニッツ係数
後遺障害14級では、労働能力喪失率は5%、労働能力喪失期間は5年程度に制限されてライプニッツ係数は4.58で計算するケースが一般的です。
後遺障害14級の認定を受けるための申請方法
後遺障害として等級認定を受けるためには、損害保険料率算出機構による審査を受けなければなりません。
以下のとおり、申請方法は「事前認定」と「被害者請求」の2種類あります。
| 後遺障害等級の申請方法 | |
|---|---|
| 事前認定 | 加害者側の保険会社に一括して手続きを任せる方法 |
| 被害者請求 | 被害者自らが手続きをおこなう方法 |
それぞれメリット・デメリットがあるので、以下で詳しく見ていきましょう。
事前認定
事前認定は、加害者の任意保険会社に後遺障害等級認定の申請手続きを一任する方法です。
後遺障害診断書や診療報酬明細書などを保険会社に提出するだけで済むので、手間がかからないのがメリットです。
しかし、相手保険会社には後遺障害の有無を立証する責任はないため、必ずしも等級獲得のために尽力してくれるとは限りません。
後遺障害として等級認定されると相手保険会社の負担額は増加するため、相手保険会社は積極的に対応してくれないというのが通常です。
被害者請求
被害者請求は、被害者自身が自ら後遺障害等級認定の申請手続きをおこなう方法です。
等級認定のために必要だと思う資料を自分で用意して送付できるため、事前認定に比べて等級認定の可能性が高いというのがメリットです。
ただし、どのような資料が必要か判断して集めるには医学的知識なども必要であり、準備に時間がかかるのも難点といえます。
十分な立証活動をして後遺障害として等級認定を受けたい場合は、弁護士にサポートしてもらうのがよいでしょう。
後遺障害14級の認定を受けるためのポイント
ここでは、後遺障害14級の認定率を上げるためのポイントを3つ紹介します。
症状固定になるまで適切な頻度で通院を続ける
後遺障害14級の認定率を上げるためには、症状固定になるまで適切な頻度で通院を続けることが大切です。
明確な基準はありませんが、通院期間6ヵ月以上・通院日数60日以上がひとつの目安となります。
通院日数・通院期間が十分でなければ「後遺障害が残るほどの状態ではない」と判断されるおそれがあるため、自己判断で通院頻度を減らしたり通院を止めたりすることは控えましょう。
ただし、必要以上に通院していると過剰診療とみなされ、不利益を被る場合もあるため注意してください。
医師には自覚症状を正確に申告する
医師に対して、自覚症状を正確に申告することも重要です。
後遺障害等級の認定審査では、医師によって作成される診断書の記載内容が特に重視されます。
そして、その診断書には患者自身が申告した自覚症状なども記載されます。
担当医の診察を受ける際には、「痛みがある」「痺れている」といった感覚的なことだけでなく、症状がみられる部位や日常生活への影響などもできるだけ詳しく説明するようにしましょう。
弁護士に相談する
後遺障害14級の獲得を目指すのであれば、弁護士に相談するのが有効です。
交通事故に強い弁護士であれば、等級認定を受けるために必要な資料を集めてくれて、依頼者の代理人としてスムーズに申請手続きを進めてくれます。
場合によっては、後遺障害診断書の作成方法などについて医師とやり取りして、等級認定の必要性を医学的・法的観点から主張してもらうこともでき、自力で対応するよりも等級認定の可能性が高まります。
ほかにも、弁護士なら慰謝料請求なども依頼でき、弁護士基準が適用されることで当初の提示額よりも大幅に増額できる可能性もあります。
特に後遺障害が残る事故では、弁護士費用よりも弁護士の介入による増額分のほうが大きくなりやすいため、まずは相談だけでも検討してみることをおすすめします。
後遺障害14級が認定されなかった場合の対処法
後遺障害14級が認定されなかった場合は、損害保険料率算出機構に対して異議申立てを検討しましょう。
新たな証拠書類を追加したり、主張の組み立て方を変えたりすれば、再審査のうえで後遺障害14級が認定されることもあります。
ただし、一度出された結果を覆すことは簡単ではありません。
知識や経験のない素人が自力で対応するのは現実的ではないため、異議申立てをおこなう場合は弁護士のサポートが必要不可欠といえるでしょう。
後遺障害14級に関するよくある質問
ここでは、後遺障害14級に関するよくある質問について解説します。
後遺障害14級の認定率は?
後遺障害14級の認定率は約2.5%です。
損害保険料率算出機構の統計によると、2022年度における自賠責保険の総支払件数は84万2,035件にのぼり、そのうち後遺障害14級の認定を受けたのは2万1,310件です。
なお、後遺障害1級~14級全体の認定件数は3万7,728件で、14級については2万1,310件で全体の約56%を占めており、多くのケースで14級が認定されています。
むちうちなら後遺障害14級になる?もらえる金額はいくら?
交通事故で頚椎捻挫・むちうちになった場合は、後遺障害14級9号または12級13号が認められる可能性があります。
たとえば、MRI・CT・レントゲンなどで異常が医学的に証明できる場合には、他覚的所見があるものとして12級13号が認められる可能性が高いといえます。
後遺障害慰謝料の相場としては、後遺障害14級では32万円(自賠責基準)・110万円(弁護士基準)、後遺障害12級では94万円(自賠責基準)・290万円(弁護士基準)です。
後遺障害14級では75万円しかもらえない?
相手方の自賠責保険に請求する場合は、後遺障害14級では後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益を合わせて75万円が上限額となります。
ただし、これはあくまでも自賠責保険から支払われる金額であり、弁護士に請求対応を依頼したりすれば75万円を大きく上回る可能性があります。
さいごに|交通事故で後遺障害が残ったらまずは弁護士に相談を
後遺障害14級は最も軽度な後遺障害等級ですが、認定を受けることで後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益などを請求できるようになります。
後遺障害等級の申請方法としては事前認定や被害者請求の2種類があり、等級認定の可能性を高めたい場合は被害者請求がおすすめです。
弁護士なら、依頼者の代理人として適切に申請手続きを進めてくれるだけでなく、慰謝料請求なども依頼することで賠償金の増額も期待できます。
当サイト「ベンナビ交通事故」では、交通事故に強い全国の法律事務所を掲載しており、地域ごとに一括検索できるので、弁護士を探す際は利用してみましょう。
弁護士に相談するかお悩みの方へ
下のボタンからあなた当てはまるものを選んで悩みを解消しましょう。
弁護士費用特約があれば 実質0円で依頼できます!

多くの保険会社では、被害者1名につき最大300万円までの弁護士費用を負担してくれます。特約があるか分からない方でも、お気軽にご相談ください。弁護士と一緒にご確認した上で依頼の有無を決めて頂けます。
特約を利用して弁護士に相談する交通事故問題を依頼する弁護士の選び方にはポイントがあります。
- 過去の解決事例を確認する
- 料金体系が明確である弁護士を選ぶ
- 交通事故問題が得意な弁護士から選ぶ
等です。
詳しくは以下の記事を読んで、正しい弁護士の選び方を理解した上で弁護士に相談しましょう。
弁護士の選び方について詳しくみる
「事故の損害賠償を求めたい」「保険会社との交渉を任せたい」「後遺症に悩まされている」等、自己負担なく、保険会社との交渉や慰謝料額のチェックを弁護士に依頼できるかもしれません【示談に応じてしまう前に、使える権利がないか一度ご確認ください】
事務所詳細を見る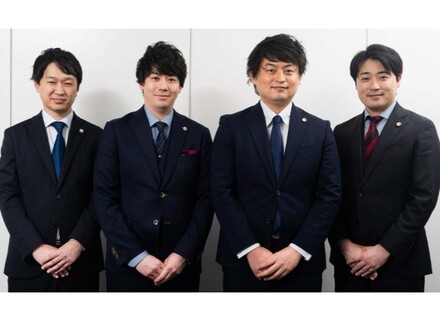
【初回相談無料】解決件数850件以上の弁護士が直接対応/賠償金の大幅増額の実績あり/後遺障害・交渉はお任せください/むち打ち・骨折〜死亡事故など幅広く親身にお話伺います<オンライン相談可・全国対応可>
事務所詳細を見る
【初回相談0円】【オンライン相談対応◎】【来所せずご依頼可能】事故直後や治療中のお悩み/保険会社との交渉など、実績豊富な弁護士が迅速かつ丁寧に対応いたします◆弁護士特約対応◆お気軽にご相談ください
事務所詳細を見る当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡

後遺障害等級・申請方法に関する新着コラム
-
本記事では交通事故で後遺症が残った場合に決める後遺障害等級について誰が決めるのかや後遺障害等級の認定に当たっては弁護士に早期に相談することで後遺障害等級の認定を...
-
本記事では、交通事故の被害に遭い橈骨頭骨折を負った方に向けて、橈骨橈骨折の症状や後遺症に関する基礎知識、橈骨橈骨折で認められる後遺障害等級の目安、適切な後遺障害...
-
交通事故で頚椎を損傷すると、どのような症状が出るのでしょうか?本記事では、頚椎損傷の主な症状や考えられる後遺症、加害者に請求できるお金について解説します。少しで...
-
交通事故による後遺症が残ったときは、後遺障害等級認定の手続きが必要です。等級認定を受けることができれば、賠償金の大幅な増額が期待できます。本記事では、後遺障害等...
-
交通事故に遭ったことが原因でけがを負い、後遺症が残った場合は、後遺障害等級認定を受けることで保険会社から損害賠償を受け取れる可能性があります。交通事故による後遺...
-
交通事故に遭ってしまい腰椎圧迫骨折の治療を続けたものの、後遺障害等級が認定されず、不安を感じている方もいるのではないでしょうか。本記事では、腰椎圧迫骨折で後遺障...
-
本記事では交通事故の被害に遭った方に向けて、後遺障害等級認定の定義、仕組み、認定機関、調査期間などの基礎知識、事前認定と被害者請求の大まかな流れ、後遺障害等級が...
-
事故で受けたケガが完治しない場合「後遺障害等級認定を受けるかどうか悩んでいる」という方もいるでしょう。この記事では、「後遺障害等級認定を受けることにはデメリット...
-
交通事故に巻き込まれた際は、できるだけ早く弁護士に相談することが大切です。支払ってもらえる保険金額や逸失利益を計算したい場合もあるでしょう。本記事では、後遺障害...
-
後遺障害等級と障害者手帳の交付を受けるための等級は別物であり、必ずしも障害者手帳が交付されるわけではありません。本記事では、後遺障害11級に認定された方に向けて...
後遺障害等級・申請方法に関する人気コラム
-
後遺障害14級は最も軽症の後遺障害等級で、たとえばむちうち・聴力の低下・歯の欠損などがあった場合に認定されます。本記事では、交通事故で後遺障害14級が認定される...
-
後遺障害診断書の概要や入手方法、書き方と記入例、後遺障害の等級認定を獲得するためのポイントのほか、医師が診断書を書いてくれない場合とその対処法、後遺障害診断書の...
-
今回お伝えする内容は、後遺障害等級12級に該当する症状と認定の方法、そして、後遺障害等級12級の適切な慰謝料を獲得する7つの知識をご紹介します。
-
交通事故における症状固定とは、むちうちなどのような後遺障害等級の獲得や示談時期などを決める際に重要な意味があります。安易に保険会社から症状固定日の提案に同意する...
-
交通事故トラブルを弁護士に相談すれば、自身に有利な条件で問題解決できる可能性が高くなります。しかし、費用面が気がかりで躊躇している方もいるのではないでしょうか。...
-
高次脳機能障害(こうじのうきのうしょうがい)とは、主に脳に損傷を負ったことで起こる様々な神経心理学的障害(記憶障害、注意障害、遂行機能障害、社会的行動障害など)...
-
後遺障害等級13級に該当する症状と後遺障害等級13級を獲得する手順をご紹介していきます。
-
後遺障害の認定が非該当になった場合に、異議申し立てを行うための方法と、成功させるコツをご紹介します。
-
後遺障害等級10級に認定された場合、その後遺障害が与える労働能力喪失率は27%と設定されており、後遺症が残った場合はいよいよ実生活にも多大な影響を与える症状が多...
-
今回は、後遺障害11級と認定される症状や、後遺障害等級11級となった場合に、どの程度の損害賠償になるのかなどをご紹介します。
後遺障害等級・申請方法の関連コラム
-
後遺障害の等級で14級9号が認定された場合の、示談金(慰謝料)請求事例をご紹介します。保険会社が提示する示談の条件が必ず適正とは限りません。示談の内容に納得でき...
-
脊髄損傷とは、交通事故や高いところからの落下事故の際に起こり得るものです。身体の機能に大きく関係している脊髄が損傷するため、後遺症が残り後遺障害等級が認定される...
-
後遺障害等級第2級は労働能力100%失ったと判断される非常に重い障害です。働けなくなるだけでなく、症状によっては日常生活でも介護が必要になる場合もあります。この...
-
交通事故に遭ってしまい腰椎圧迫骨折の治療を続けたものの、後遺障害等級が認定されず、不安を感じている方もいるのではないでしょうか。本記事では、腰椎圧迫骨折で後遺障...
-
医療機関を受診する必要性を認識するために、症状や後遺症などについて確認しておきましょう。ここでは、慢性硬膜下血腫の症状や検査方法、治療法などについてご紹介します...
-
交通事故により重度の後遺障害を負った場合、加害者や保険会社から受け取る損害賠償とは別に、国より「障害年金」を受給することが可能です。この記事では障害年金の制度や...
-
自賠責基準の後遺障害慰謝料の相場や、請求できる保険金の限度額などをご紹介します。後遺障害申請手続きの注意事項や弁護士を雇うメリットなども解説していますので、後遺...
-
高次脳機能障害は、症状の程度によって1級から9級の後遺障害等級に該当します。ただし、必ず認定されるわけではありません。適切な等級に認定してもらうポイントや条件に...
-
本記事では交通事故で後遺症が残った場合に決める後遺障害等級について誰が決めるのかや後遺障害等級の認定に当たっては弁護士に早期に相談することで後遺障害等級の認定を...
-
骨折による後遺症が残った場合は、後遺障害等級認定を受けられるか、どの等級に認定されるかによって損害賠償額が大きく変わってきます。本記事では、骨折による後遺症の種...
-
後遺障害第1級に該当する遷延性意識障害とは「植物状態」となってしまった症状をいいます。今回は、遷延性意識障害になった場合に獲得できる慰謝料などを見ていきましょう...
-
交通事故における後遺障害9級は、眼・耳・鼻・口・手足・内臓機能などに障害が残った場合に認定されます。1号から17号まであり、どのようなものが該当するのか押さえて...
後遺障害等級・申請方法コラム一覧へ戻る


























 慰謝料・損害賠償
慰謝料・損害賠償
 示談
示談
 過失割合
過失割合
 死亡事故
死亡事故
 後遺障害
後遺障害
 むちうち
むちうち
 自転車事故
自転車事故
 自動車事故
自動車事故
 人身事故
人身事故
 バイク事故
バイク事故
































