- 交通事故の慰謝料がいくら貰えるか不安…
- 慰謝料をできるだけ多くもらいたい!
- 慰謝料の計算方法が難しくて分からない…
そんな方にオススメなのが、ベンナビ交通事故の『慰謝料計算ツール』です。
【実際の利用画面】

適切な慰謝料額を簡単に計算できる上、近くの弁護士を探してくれるので、事故の被害にあって困っている方にぴったりのサービスなんです。
交通事故で損をしないためにも、まずは適正な慰謝料を調べてみましょう。
\弁護士にも相談できる!/
今すぐ適正な慰謝料を調べてみる▶

交通事故で口を負傷すると、「歯」が無くなってしまうケースが多々あります。
ものを噛んで飲み込んだり、言葉を発したりするのが難しくなる方もおられます。
そのような場合、後遺障害認定を受けて慰謝料や逸失利益を請求できる可能性があります。
以下では、交通事故の歯の後遺障害で認定される等級や請求できる慰謝料について解説します。


まずは、交通事故で歯に損傷を受けた場合にどういった後遺障害が認定される可能性があるのか、見てみましょう。
交通事故で歯を失った場合、「歯牙障害」として後遺障害認定されます。
歯牙障害は、歯が著しく欠損してクラウンやブリッジ、インプラントなどの歯科治療を受けた後に、治療を施した歯の本数によって判定されます。
この歯科治療のことを「歯科補綴」と言います。歯科補綴によって歯が修復されて使える状態に戻っていても、後遺障害認定されます。
|
後遺障害 |
等級 |
|
14歯以上に対し歯科補綴を加えた |
10級4号 |
|
10歯以上に対し歯科補綴を加えた |
11級4号 |
|
7歯以上に対し歯科補綴を加えた |
12級3号 |
|
5歯以上に対し歯科補綴を加えた |
13級5号 |
|
3歯以上に対し歯科補綴を加えた |
14級2号 |
交通事故で口を負傷すると、その後ものを飲み込んだり話したりすることが困難になるケースがあります。
その場合、「咀嚼(ものを噛んで飲み込む能力)」「言語(言葉を発する能力)」の後遺障害が認定されます。
後遺障害認定基準は以下のとおりです。
|
症状 |
等級 |
|
咀嚼と言語の機能を廃した場合 |
1級2号 |
|
咀嚼または言語のどちらか一方の機能を廃した |
3級2号 |
|
咀嚼及び言語の機能に著しい障害が残った |
4級2号 |
|
咀嚼又は言語の機能に著しい障害が残った |
6級2号 |
|
咀嚼及び言語の機能に障害が残った |
9級6号 |
|
咀嚼又は言語の機能に障害が残った |
10級3号 |
|
用語 |
解説 |
| 咀嚼機能を廃した | 流動食しか摂取できない状態 |
| 咀嚼機能に著しい障害を残す | お粥程度のものしか食べられない状態 |
| 咀嚼機能に障害を残す | 固いものを食べられない状態 |
| 言語機能を廃した | 人間の発する4種類の発音のうち3種以上発音できなくなった状態 |
| 言語機能に著しい障害を残す | 4種の発音のうち2種の発音ができなくなった場合か、綴音(ある音と別の音とが結合している音)の機能に障害があって言葉のコミュニケーションをとりにくい場合 |
| 言語機能に障害を残す | 4種の発音のうち1種を発音できなくなった状態 |

後遺障害認定を受けるとどのような賠償金を請求できるのか、見てみましょう。
交通事故で後遺障害認定を受けると、後遺障害慰謝料を請求できます。
後遺障害慰謝料は、後遺障害が残ったことによる被害者の精神的苦痛を賠償するためのお金です。
認定された等級が高いほど慰謝料の金額が上がります。等級ごとの後遺障害慰謝料の相場は以下のとおりです。
|
等級 |
慰謝料の相場 |
|
1級 |
2,800万円 |
|
2級 |
2,370万円 |
|
3級 |
1,990万円 |
|
4級 |
1,670万円 |
|
5級 |
1,400万円 |
|
6級 |
1,180万円 |
|
7級 |
1,000万円 |
|
8級 |
830万円 |
|
9級 |
690万円 |
|
10級 |
550万円 |
|
11級 |
420万円 |
|
12級 |
290万円 |
|
13級 |
180万円 |
|
14級 |
110万円 |
後遺障害逸失利益は、後遺障害が残ったことによって、労働能力が低下するため得られなくなった将来の収入です。
つまり、後遺障害が残ったことによる減収分を相手に請求できるのです。
逸失利益は、以下の計算式によって求めます。
|
逸失利益=事故前の基礎収入×労働能力喪失率×就労可能年数に対応するライプニッツ係数 |
ライプニッツ係数とは、将来の収入を先に一括で受けとることによって、発生する差額を調整するための特殊な係数です。
以下で計算例を2つご紹介します。
事故前の年収500万円、事故当時30歳の男性が咀嚼言語の後遺障害で1級(労働能力喪失率100%)に認定されたとします。
この場合、500万円×100%×16.711=8,355万5,000円の逸失利益が認められます。
事故前の年収が400万円、事故当時40歳の女性が咀嚼障害で9級(労働能力喪失率35%)となったとします。
この場合、400万円×35%×14.643=2,050万200円の逸失利益が認められます。
そんな方にオススメなのが、ベンナビ交通事故の『慰謝料計算ツール』です。
【実際の利用画面】

適切な慰謝料額を簡単に計算できる上、近くの弁護士を探してくれるので、事故の被害にあって困っている方にぴったりのサービスなんです。
交通事故で損をしないためにも、まずは適正な慰謝料を調べてみましょう。
\弁護士にも相談できる!/
今すぐ適正な慰謝料を調べてみる▶

交通事故で歯の後遺障害が認められるためには、「歯科補綴」したことが要件となります。
具体的には、「歯の喪失」あるいは「歯の著しい欠損」が生じて治療した場合に、「歯科補綴」と認められます。
「歯の喪失」には、交通事故で直接歯を失った場合だけではなく、治療のために抜歯した場合も含まれます。
「歯の著しい欠損」と言うためには、歯の体積の4分の3以上が欠けたことが必要です。
ヒビが入った場合でも、治療のために抜歯が必要となったり、4分の3以上削ってクラウンをしたりすると、「歯牙障害」となります。
神経を抜く場合、通常は抜歯するので、歯牙障害と認定されるでしょう。
歯牙障害は、3本以上の歯に「歯科補綴」した場合に認定されます。
ただ、歯が2本折れたときにも「ブリッジ治療」をするケースがあります。
ブリッジを架ける際には隣の健康な歯も削ることになるので、その歯も含めて「歯科補綴」の本数を計算します。
ブリッジを架けた歯を足すと3本以上になる場合には、折れた歯が2本であっても後遺障害認定されます。
歯牙障害の後遺障害診断書は歯科医に作成してもらいます。
歯牙障害については、通常の後遺障害診断書とは異なる専門の書式があるので、保険会社から取り寄せて歯科医に渡し、作成を依頼しましょう。
交通事故でけがをして後遺障害認定の申請をするときには、以下の流れで進めましょう。
まずは、「症状固定」するまで治療を続けることが重要です。
症状固定とは、それ以上治療を続けても改善しなくなった状態です。
歯牙障害では、症状固定時期があまり問題になりませんが、言語や咀嚼の後遺障害の場合、リハビリによってある程度回復する可能性もあるので、医師が「症状固定」と判断するまで根気強く通院治療を続けましょう。
症状固定したら、歯牙障害の場合には歯科医、言語や咀嚼の障害の場合には医師に後遺障害診断書の書式を渡して、後遺障害診断書を作成してもらいます。
自賠責の後遺障害認定では、後遺障害診断書の内容が非常に重要です。
医師や歯科医によっては後遺障害診断書の書き方を把握しておらず、間違った記載をされて被害者が不利益を受けるケースもあり、注意が必要です。
交通事故に詳しい弁護士に対応を依頼して、医師や歯科医と連絡を取り合って適切な方法で書類作成してもらいましょう。
後遺障害診断書ができたら、相手の保険会社に後遺障害診断書を送るか(事前認定)、自分で書類をそろえて自賠責保険へ提出するか(被害者請求)のどちらかの方法で後遺障害認定申請をします。
どちらの方法が適切かはケースによって異なります。
自分で判断がつかないなら、弁護士にアドバイスを求めるのが良いでしょう。

交通事故で後遺障害が残ったら、弁護士に依頼することをおすすめします。
弁護士が示談交渉をすると、被害者が自分で交渉するより大幅に慰謝料が増額されます。
「弁護士基準」という高額な基準によって、慰謝料が計算されるためです。
特に等級が高くなった場合の差額が大きくなる傾向にあるようです。
後遺障害が残ったら、弁護士に示談交渉を依頼するようにしましょう。
交通事故後の対応は被害者にとって非常に煩雑でストレスのかかるものです。
いろいろな書類を集めたり、さまざまな機関と連絡を取り合ったり、書類を取り寄せ作成したり提出したりしなければなりません。
相手の保険会社とのやり取りにも労力を使い、神経がすり減ります。
弁護士にすべて任せてしまえば、ほとんどの対応は弁護士がしてくれます。
相手の保険会社との交渉窓口も弁護士になって、自分で直接話をする必要はなくなります。
このように交通事故に関する手続きを一任できて、労力を削減しストレスを軽減できるのも弁護士に依頼する大きなメリットとなります。
交通事故で口にけがをしたら、後遺障害が残るケースも多々あります。
まずは弁護士に相談をして、後遺障害認定を含めた事故対応をまとめて任せてしまうのが良いでしょう。

弁護士に相談するかお悩みの方へ
下のボタンからあなた当てはまるものを選んで悩みを解消しましょう。
弁護士費用特約があれば 実質0円で依頼できます!

多くの保険会社では、被害者1名につき最大300万円までの弁護士費用を負担してくれます。特約があるか分からない方でも、お気軽にご相談ください。弁護士と一緒にご確認した上で依頼の有無を決めて頂けます。
特約を利用して弁護士に相談する交通事故問題を依頼する弁護士の選び方にはポイントがあります。
等です。
詳しくは以下の記事を読んで、正しい弁護士の選び方を理解した上で弁護士に相談しましょう。
弁護士の選び方について詳しくみる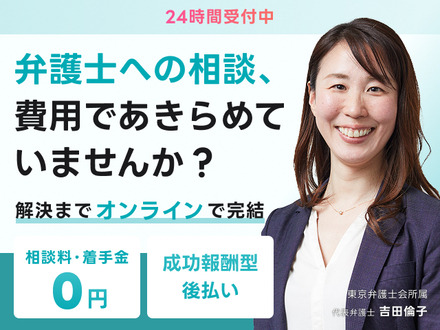
相談料・着手金0円、費用倒れの心配なし。大手より低価格な料金体系で増額実績多数。交通事故専門チームが後遺障害認定から交渉まで強力サポート。LINE完結・来所不要で全国対応。
事務所詳細を見る
【相談実績60,000件以上/解決実績7900件以上】【東京都相談窓口】交通事故の対応・示談交渉に豊富な経験を持つ弁護士が慰謝料増額に向け、徹底してサポートいたします【着手金0円/365日対応】
事務所詳細を見る
【1万件以上の実績◎】保険会社からの慰謝料・治療費や後遺障害認定に納得がいかないなどのお悩みに寄り添います!医療知識に知見あり!保険会社との交渉はお任せください<全国対応>【夜間・休日の相談◎】
事務所詳細を見る
本記事では交通事故で後遺症が残った場合に決める後遺障害等級について誰が決めるのかや後遺障害等級の認定に当たっては弁護士に早期に相談することで後遺障害等級の認定を...
本記事では、交通事故の被害に遭い橈骨頭骨折を負った方に向けて、橈骨橈骨折の症状や後遺症に関する基礎知識、橈骨橈骨折で認められる後遺障害等級の目安、適切な後遺障害...
交通事故で頚椎を損傷すると、どのような症状が出るのでしょうか?本記事では、頚椎損傷の主な症状や考えられる後遺症、加害者に請求できるお金について解説します。少しで...
交通事故による後遺症が残ったときは、後遺障害等級認定の手続きが必要です。等級認定を受けることができれば、賠償金の大幅な増額が期待できます。本記事では、後遺障害等...
交通事故に遭ったことが原因でけがを負い、後遺症が残った場合は、後遺障害等級認定を受けることで保険会社から損害賠償を受け取れる可能性があります。交通事故による後遺...
交通事故に遭ってしまい腰椎圧迫骨折の治療を続けたものの、後遺障害等級が認定されず、不安を感じている方もいるのではないでしょうか。本記事では、腰椎圧迫骨折で後遺障...
本記事では交通事故の被害に遭った方に向けて、後遺障害等級認定の定義、仕組み、認定機関、調査期間などの基礎知識、事前認定と被害者請求の大まかな流れ、後遺障害等級が...
事故で受けたケガが完治しない場合「後遺障害等級認定を受けるかどうか悩んでいる」という方もいるでしょう。この記事では、「後遺障害等級認定を受けることにはデメリット...
交通事故に巻き込まれた際は、できるだけ早く弁護士に相談することが大切です。支払ってもらえる保険金額や逸失利益を計算したい場合もあるでしょう。本記事では、後遺障害...
後遺障害等級と障害者手帳の交付を受けるための等級は別物であり、必ずしも障害者手帳が交付されるわけではありません。本記事では、後遺障害11級に認定された方に向けて...
後遺障害14級は最も軽症の後遺障害等級で、たとえばむちうち・聴力の低下・歯の欠損などがあった場合に認定されます。本記事では、交通事故で後遺障害14級が認定される...
後遺障害診断書の概要や入手方法、書き方と記入例、後遺障害の等級認定を獲得するためのポイントのほか、医師が診断書を書いてくれない場合とその対処法、後遺障害診断書の...
今回お伝えする内容は、後遺障害等級12級に該当する症状と認定の方法、そして、後遺障害等級12級の適切な慰謝料を獲得する7つの知識をご紹介します。
交通事故における症状固定とは、むちうちなどのような後遺障害等級の獲得や示談時期などを決める際に重要な意味があります。安易に保険会社から症状固定日の提案に同意する...
交通事故トラブルを弁護士に相談すれば、自身に有利な条件で問題解決できる可能性が高くなります。しかし、費用面が気がかりで躊躇している方もいるのではないでしょうか。...
高次脳機能障害(こうじのうきのうしょうがい)とは、主に脳に損傷を負ったことで起こる様々な神経心理学的障害(記憶障害、注意障害、遂行機能障害、社会的行動障害など)...
後遺障害等級13級に該当する症状と後遺障害等級13級を獲得する手順をご紹介していきます。
後遺障害の認定が非該当になった場合に、異議申し立てを行うための方法と、成功させるコツをご紹介します。
後遺障害等級10級に認定された場合、その後遺障害が与える労働能力喪失率は27%と設定されており、後遺症が残った場合はいよいよ実生活にも多大な影響を与える症状が多...
今回は、後遺障害11級と認定される症状や、後遺障害等級11級となった場合に、どの程度の損害賠償になるのかなどをご紹介します。
後遺障害等級の認定に当たっては、後遺症の症状や交通事故との因果関係などが精査されます。本記事では、後遺障害等級の認定は厳しいのかどうかや認定されない理由、非該当...
後遺障害認定の結果に納得がいかない場合は、異議申し立てをすることで再審査を受けられます。しかし、手続きの進め方がわからず、悩んでいる方も多いのではないでしょうか...
骨折による後遺症が残った場合は、後遺障害等級認定を受けられるか、どの等級に認定されるかによって損害賠償額が大きく変わってきます。本記事では、骨折による後遺症の種...
後遺障害等級が認められないと、慰謝料などの獲得はもちろんできませんし、治療費なども自分で負担していくことになりますので、適切な後遺障害等級を獲得できるように、ご...
後遺障害等級13級に該当する症状と後遺障害等級13級を獲得する手順をご紹介していきます。
交通事故で発症した手や足のしびれは、症状が後遺症として残るケースがあります。そのような場合は後遺症に関する損害賠償を請求するため、後遺障害認定を受けなければいけ...
交通事故の被害に遭い後遺障害が生じた場合、適切な後遺障害等級を得ることで損害賠償が大きく変わります。より簡単に負担を少なく後遺障害等級を獲得し、適切な損害賠償を...
後遺障害が認定されない原因と非該当になった時の対処法をご紹介します。後遺障害が認定されるか否かで、保険金の額に100万円以上の差額が生じるケースは珍しくありませ...
後遺障害認定されたら具体的に何がどうなるのでしょうか。この記事では、後遺障害認定されたら発生する慰謝料や逸失利益などのお金の知識や、後遺障害認定前と認定後の流れ...
医療機関を受診する必要性を認識するために、症状や後遺症などについて確認しておきましょう。ここでは、慢性硬膜下血腫の症状や検査方法、治療法などについてご紹介します...
後遺障害の認定が非該当になった場合に、異議申し立てを行うための方法と、成功させるコツをご紹介します。
交通事故に遭った家族が1ヵ月以上意識不明の場合は、将来的に「遷延性意識障害」の診断を受ける可能性があります。 本記事では、家族が交通事故に遭って1ヵ月以上意識...

