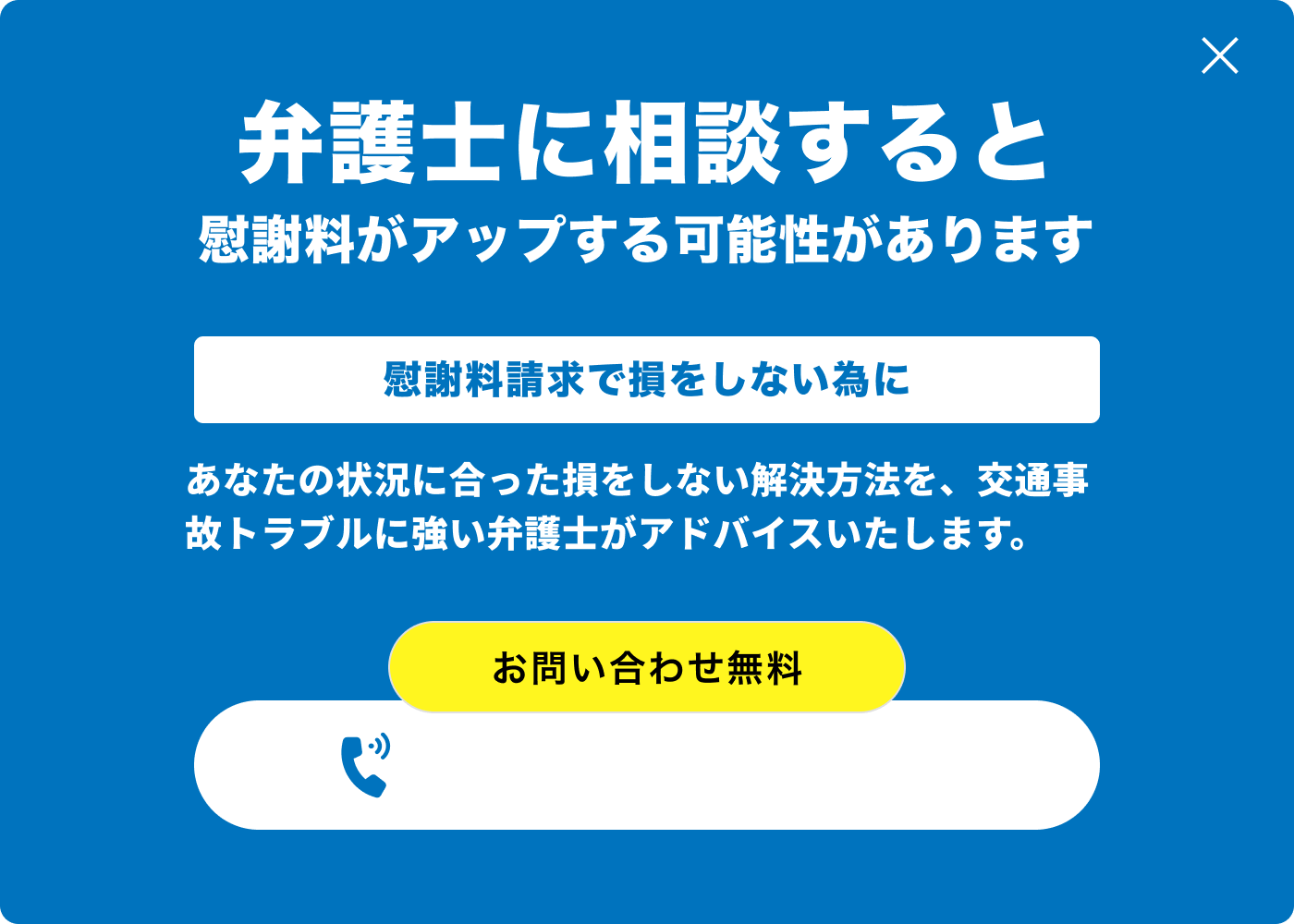交通事故や自転車事故など、事故はいつ起きてしまうか分からないものです。弁護士費用を用意できず泣き寝入りとなってしまうケースも少なくありません。
ベンナビ弁護士保険は、弁護士依頼で発生する着手金を補償する保険です。
交通事故だけでなく、自転車事故、労働問題、離婚、相続トラブルなど幅広い法的トラブルで利用することができます。
弁護士保険で法律トラブルに備える

後遺障害等級9級となる症状には、部位によって1号から17号に分類されており、労働能力喪失率は35%に設定されています。今回は、後遺障害等級9級に認定される症状と、後遺障害等級9級で獲得できる慰謝料を100万円以上増額させる方法をご紹介します。
下記の表に後遺障害等級9級となる後遺障害をまとめましたので、ますはどんな症状が該当するのかをご確認ください。
|
等級 |
後 遺 障 害 |
自賠責保険(共済)金額 |
労働能力喪失率 |
|
第9級 |
1号:両眼の視力が0.6以下になったもの |
616万円 |
35% |
|
2号:1眼の視力が0.06以下になったもの |
|||
|
3号:両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの |
|||
|
4号:両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの |
|||
|
5号:鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの |
|||
|
6号:咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの |
|||
|
7号:両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの |
|||
|
8号:1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話し声を解することが困難である程度になったもの |
|||
|
9号:1耳の聴力を全く失ったもの |
|||
|
10号:神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの |
|||
|
11号:胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの |
|||
|
12号:1手のおや指又はおや指以外の2の手指を失ったもの |
|||
|
13号:1手のおや指を含み2の手指の用を廃したもの又はおや指以外の3の手指の用を廃したもの |
|||
|
14号:1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの |
|||
|
15号:1足の足指の全部の用を廃したもの |
|||
|
16号:外貌に相当程度の醜状を残すもの |
|||
|
17号:生殖器に著しい障害を残すもの |
両眼の視力が0.6以下になってしまった場合に後遺障害等級9級1号に認定されます。後遺症認定で定められた視力は矯正視力ですので、メガネなどの視力矯正をしても、一般的な視力に届かない場合に後遺障害とされます。
片眼の視力が0.06以下になってしまった場合に後遺障害等級9級2号に認定されます。
今までの視界の右半分あるいは左半分が見えなくなる症状。
文字通り視野が狭くなってしまった症状を言います。
見えている景色の中にボツボツと穴が空いて見えない部分が出てきてしまう症状と言われています。
瞼を閉じても角膜が完全に隠れない状態で認定されます。
鼻は顔の中心にあるモノですので、外見に大きく影響することを考慮して、後遺障害等級7 級 12 号が認定される可能性が高くなります。
固形物が一切食べられないほどであれば、後遺障害等級はさらに上がります。
第9級7号:両耳の聴力が純音聴力レベル60dB以上または50dB以上で、なおかつ明瞭度が最高70%以下
第9級8号:大声も聞こえない程度の聴力で、残った片耳も1m以上離れると厳しい状態
第9級9号:片耳だけ完全に聴力が失われた場合
具体的に認定される症状は以下のようなものがあります。
高次脳機能障害によくある症状はこちらの記事をご覧ください。
脳の損傷によって、文字が書けない、歩行障害が残れば認定されます。
「うつ」などの精神的な障害で労働能力が失われたケースです。客観的な判断が難しい症状なので、必ず専門医による診断と、後遺障害の原因が交通事故であることを証明する必要があります。
該当する主な症状は部位によってことなり、だいたいは以下の通りです。
肺の機能が低下してしまったケースなど。
心臓機能が低下し、ペースメーカーをつける事になってしまった場合。
大きな食事制限や食事後のめまいなどがあれば認定されます。
立ち仕事を止められているなどした場合に認定されます。
腎臓や膀胱など泌尿器系の内臓に後遺障害が残った場合でも、症状が重い場合には認定されます。
具体的な症状としては・・・
末節骨がその長さの2分の1以上失われた場合
指の根元か第二関節の可動域が2分の1以下になった場合
親指の橈側外転または掌側外転(親指をてのひらにつける動作)の動く範囲のいずれかが2分の1以下になった状態
神経麻痺の影響で指の存在感覚が無くなった場合
物に触れる触角や温度感覚、痛感などが完全に失われた場合 など
片足の親指の第1関節を切断し、長さが2分の1以下になった場合
片足の親指以外の指を全て第一関節から根元まで切断してしまった場合
片足の指が根元から第一関節にかけて、稼働範囲が2分の1以下になった場合
“外貌(がいぼう)”とは、衣服などで隠さず露出している部分のことですが、問題なるのは「顔」で、顔に傷跡が残ってしまった場合、後遺障害の第9級16号に認定されます。
確実に後遺障害9級に認定されるためにも、「後遺障害等級の認定基準」も合わせてご確認ください。
次に、後遺障害等級9級に認定された際の損害賠償額がどの程度もらえるのか見ていきましょう。
|
項目 |
金額 |
|---|---|
|
自賠責保険の保険金上限額 |
616万円 |
|
自賠責保険の後遺障害慰謝料額 |
245万円 |
|
弁護士基準の後遺障害慰謝料額 |
690万円 |
|
労働能力喪失率 |
35/100 |
|
請求項目 |
内容と慰謝料の相場 |
|
入通院慰謝料 |
1日あたり4,200円 |
|
後遺障害慰謝料 |
自賠責保険の後遺障害等級第9級では245万円 |
|
死亡慰謝料 |
一家の大黒柱:2,600~3,000万円 |
|
第1級 |
第2級 |
第3級 |
第4級 |
第5級 |
第6級 |
第7級 |
|
1,100万円 |
958万円 |
829万円 |
712万円 |
599万円 |
498万円 |
409万円 |
|
第8級 |
第9級 |
第10級 |
第11級 |
第12級 |
第13級 |
第14級 |
|
324万円 |
245万円 |
187万円 |
135万円 |
93万円 |
57万円 |
32万円 |
|
治療関係費 |
治療費や入院費が該当 |
|
看護料 |
通院付添費:2050円/日 |
|
入通院慰謝料 |
4200円/日 |
|
入院雑費 |
1500円/日 |
|
通院交通費 |
通院に要した交通費など |
|
その他 |
将来介護費・装具購入費・学費・家庭教師代など |
|
休業損害 |
5700円/日 |
|
傷害慰謝料 |
入通院期間に基づいて算定(あまりにも入院などが長い場合) |
|
逸失利益 |
後遺障害が残ったことで失われた利益 |
|
後遺障害慰謝料 |
後遺障害が認定された場合に請求 |
今回はモデルとして以下の人物を想定し、損害賠償金を計算していきます。
<<モデルケース>>
30歳の会社員が交通事故に遭遇。
入院100日。通院日数200日間(実際は100日)
事故前の年収500万円
後遺障害等級9級に該当
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・入通院治療費・・・・・・400万円
・後遺障害慰謝料・・・・・245万円(自賠責基準)
・後遺障害診断書作成料・・1万5000円
・入通院慰謝料・・・・・・84万円
1:入院期間+通院期間
2:実通院日数(入院期間+実際に通院した日数)×2
この2つの計算式を比べて日数が少ない方を採用します。
1:100+200=300
2:100×2=200
=200×4200=840,000円
・付き添い看護料・・・・・20万5000円
2050円×100=205,000円
・入院中雑貨・・・・・・・15万円(1500円×100日)
・休業損害・・・・・・・・168万円
500万円÷12=約42万円、42万円×4ヶ月=168万円
・逸失利益・・・・・・・・2895万7075円【逸失利益の計算例】
・入通院交通費・・・・・・2万円(必要なバス・電車代など)
・衣料損害費・・・・・・・3万円(購入時の時価)
合計:3834万7075円
これまで説明してきた慰謝料や損害賠償金はあくまで自賠責保険という最低限の基準ですので、ここから適切な基準で後遺障害の慰謝料を求めることで、100万円以上の増額が見込めます。
後遺障害等級の認定には、3つの基準がありますが、弁護士基準で計算するだけで、慰謝料や損害賠償金は大幅にアップします。
表:基準別の後遺障害慰謝料の違い(上:自賠責、下:弁護士)
|
第1級 |
第2級 |
第3級 |
第4級 |
第5級 |
第6級 |
第7級 |
|
1,100万円 |
958万円 |
829万円 |
712万円 |
599万円 |
498万円 |
409万円 |
|
2,800万円 |
2,370万円 |
1,990万円 |
1,670万円 |
1,400万円 |
1,180万円 |
1,000万円 |
|
第8級 |
第9級 |
第10級 |
第11級 |
第12級 |
第13級 |
第14級 |
|
324万円 |
245万円 |
187万円 |
135万円 |
93万円 |
57万円 |
32万円 |
|
830万円 |
690万円 |
550万円 |
420万円 |
290万円 |
180万円 |
110万円 |
・後遺障害慰謝料:245万円 → 690万
表:通常の弁護士基準による入通院慰謝料の表(単位:万円)

表:むち打ち症で他覚症状がない場合に適用される入通院慰謝料表(単位:万円)

・入通院慰謝料 :84万円 → 217万円(152万円)
被害者請求とは、交通事故にあった被害者自身が自分で後遺障害などの被害を請求する、自賠責保険のカギとなる請求方法です(自賠法16条)。保険会社に後遺障害等級などの手続きを任せる事前認定とは異なり、自らが動いて請求するので透明性が高く、等級に応じた自賠責限度額を保険会社との示談を待たずに先取りできるなどのメリットがあります。
後遺障害の申請を「被害者請求で行う」ことです。これがもっとも有効な方法と言えます。通常は相手方の保険会社が後遺障害の申請手続きなどのすべてを行ってくれますが、相手の保険会社はあなたに支払う保険金をできるだけ定額にしたい、もっといえば払いたくはないと考えているので、望む結果が出るとは限りません。
その対策としてできるのが「被害者請求」です。
後遺障害等級9級に該当する症状と、獲得できる慰謝料の相場及び増額の方法になります。後遺障害等級に認定は交通事故で怪我を負った際の肝になる部分ですので、少しでも獲得に不安があるようでしたら、一度弁護士に相談されるのが良いと思います。
9級以外の後遺障害等級について知りたい方は、下記の該当する等級より、ご確認ください。
弁護士に相談するかお悩みの方へ
下のボタンからあなた当てはまるものを選んで悩みを解消しましょう。
弁護士費用特約があれば 実質0円で依頼できます!

多くの保険会社では、被害者1名につき最大300万円までの弁護士費用を負担してくれます。特約があるか分からない方でも、お気軽にご相談ください。弁護士と一緒にご確認した上で依頼の有無を決めて頂けます。
特約を利用して弁護士に相談する交通事故問題を依頼する弁護士の選び方にはポイントがあります。
等です。
詳しくは以下の記事を読んで、正しい弁護士の選び方を理解した上で弁護士に相談しましょう。
弁護士の選び方について詳しくみる
【来所不要・交通事故の被害者は初回相談料0円】◆豊富な解決実績◆示談金の大幅な増額実績多数◆交通事故専門チームが丁寧に対応します。まずは無料でご相談ください。【「立川」駅北口より徒歩6分】
事務所詳細を見る
【人身事故被害者の方へ】事故直後・通院中いずれの場合もまずはご相談ください。弁護士への依頼で、結果が大きく変わるかもしれません。【初回面談無料】【着手金無料プランあり】【オンラインで全国対応可能】
事務所詳細を見る
【来所不要・交通事故の被害者は初回相談料0円】◆豊富な解決実績◆示談金の大幅な増額実績多数◆交通事故専門チームが丁寧に対応します。まずは無料でご相談ください。【「六本木一丁目」駅より徒歩3分】
事務所詳細を見る
交通事故に遭ったことが原因でけがを負い、後遺症が残った場合は、後遺障害等級認定を受けることで保険会社から損害賠償を受け取れる可能性があります。交通事故による後遺...
交通事故に遭ってしまい腰椎圧迫骨折の治療を続けたものの、後遺障害等級が認定されず、不安を感じている方もいるのではないでしょうか。本記事では、腰椎圧迫骨折で後遺障...
本記事では交通事故の被害に遭った方に向けて、後遺障害等級認定の定義、仕組み、認定機関、調査期間などの基礎知識、事前認定と被害者請求の大まかな流れ、後遺障害等級が...
事故で受けたケガが完治しない場合「後遺障害等級認定を受けるかどうか悩んでいる」という方もいるでしょう。この記事では、「後遺障害等級認定を受けることにはデメリット...
交通事故に巻き込まれた際は、できるだけ早く弁護士に相談することが大切です。支払ってもらえる保険金額や逸失利益を計算したい場合もあるでしょう。本記事では、後遺障害...
後遺障害等級と障害者手帳の交付を受けるための等級は別物であり、必ずしも障害者手帳が交付されるわけではありません。本記事では、後遺障害11級に認定された方に向けて...
後遺障害10級には、肩・腕・手や股関節・膝・足を骨折して可動域が2分の1以下に制限された場合が含まれます。本記事では、後遺障害10級の具体的な症状や認定基準、後...
後遺障害等級の認定に当たっては、後遺症の症状や交通事故との因果関係などが精査されます。本記事では、後遺障害等級の認定は厳しいのかどうかや認定されない理由、非該当...
交通事故に遭った家族が1ヵ月以上意識不明の場合は、将来的に「遷延性意識障害」の診断を受ける可能性があります。 本記事では、家族が交通事故に遭って1ヵ月以上意識...
交通事故により重度の後遺障害を負った場合、加害者や保険会社から受け取る損害賠償とは別に、国より「障害年金」を受給することが可能です。この記事では障害年金の制度や...
【弁護士監修】交通事故で後遺障害となり第14級と認定された場合、後遺障害慰謝料の相場がいくらになるのか、計算方法や示談金額、第14級の認定基準などを徹底解説。正...
後遺障害診断書の概要や入手方法、書き方と記入例、後遺障害の等級認定を獲得するためのポイントのほか、医師が診断書を書いてくれない場合とその対処法、後遺障害診断書の...
今回お伝えする内容は、後遺障害等級12級に該当する症状と認定の方法、そして、後遺障害等級12級の適切な慰謝料を獲得する7つの知識をご紹介します。
交通事故に遭った被害者のために、後遺障害の基礎・基本を解説します。適切な治療やリハビリを受けている場合でも、後遺障害を負ってしまうかもしれません。そのようなとき...
交通事故における症状固定とは、むちうちなどのような後遺障害等級の獲得や示談時期などを決める際に重要な意味があります。安易に保険会社から症状固定日の提案に同意する...
交通事故トラブルを弁護士に相談すれば、自身に有利な条件で問題解決できる可能性が高くなります。しかし、費用面が気がかりで躊躇している方もいるのではないでしょうか。...
高次脳機能障害(こうじのうきのうしょうがい)とは、主に脳に損傷を負ったことで起こる様々な神経心理学的障害(記憶障害、注意障害、遂行機能障害、社会的行動障害など)...
後遺障害等級13級に該当する症状と後遺障害等級13級を獲得する手順をご紹介していきます。
後遺障害の認定が非該当になった場合に、異議申し立てを行うための方法と、成功させるコツをご紹介します。
後遺障害等級10級に認定された場合、その後遺障害が与える労働能力喪失率は27%と設定されており、後遺症が残った場合はいよいよ実生活にも多大な影響を与える症状が多...
交通事故が原因の腰痛で請求できる慰謝料は、症状の程度により異なります。腰痛の場合、後遺障害等級12級・14級が認定される可能性がありますが、そのためには申請手続...
交通事故に遭ってしまい腰椎圧迫骨折の治療を続けたものの、後遺障害等級が認定されず、不安を感じている方もいるのではないでしょうか。本記事では、腰椎圧迫骨折で後遺障...
後遺障害の等級で14級9号が認定された場合の、示談金(慰謝料)請求事例をご紹介します。保険会社が提示する示談の条件が必ず適正とは限りません。示談の内容に納得でき...
後遺障害等級第3級は労務に服することができない(障害のせいで働けない)状態に認定される等級です。被害者の今後の人生に大きな支障をきたす障害であるため、高額な慰謝...
後遺障害等級第2級は日常生活にまで支障をきたす非常に重い障害です。状況によりけりですが、損害賠償の合計額が数千万単位になる可能性はかなり高いでしょう。この記事で...
後遺障害等級5級に認定される症状は、労働能力喪質率79%という非常に大きな損害が残るもので、今後の人生においてほぼ確実に介護が必要となるものとなります。
後遺障害等級の認定に当たっては、後遺症の症状や交通事故との因果関係などが精査されます。本記事では、後遺障害等級の認定は厳しいのかどうかや認定されない理由、非該当...
バイクは運転者の体が丸出しになっている乗り物です。そのため、交通事故では重症を負ってしまう可能性が高く、後遺症が残るケースも珍しくありません。この記事では、後遺...
後遺障害の申請方法には、被害者請求と事前認定の2種類があります。本記事では、両者のメリット・デメリットとともに被害者請求で申請したほうがよい状況を解説していきま...
この記事では、骨盤骨折で骨折は治ったものの、痛みがのこった、骨が変形してしまった、股関節が動かなくなったなどの症状がある場合の後遺障害等級や、慰謝料相場を紹介し...
後遺障害等級の12級13号は、局部に頑固な神経症状が残った際に認定される後遺障害です。この記事では、12級13号は具体的にどのような状態で認定されるのかや14級...
後遺障害認定されたら具体的に何がどうなるのでしょうか。この記事では、後遺障害認定されたら発生する慰謝料や逸失利益などのお金の知識や、後遺障害認定前と認定後の流れ...