後遺障害の被害者請求とは|必要書類や手続きの流れやメリットを解説

後遺障害の申請方法には、被害者請求と事前認定の2種類があります。
手続きの流れに大きな違いはありませんが、後遺障害申請においては、被害者請求が推奨されるケースが多いです。
ただし、どちらの申請方法にもそれぞれメリットとデメリットがあります。
必ずしも被害者請求で申請をするべきとはかぎりません。
自身の状況に合わせて、申請方法を判断するべきでしょう。
本記事では、被害者請求と事前認定の違いや被害者請求の方法について紹介します。
被害者請求での後遺障害申請を検討している場合は、参考にしてみてください。
被害者請求と事前認定の違い
被害者請求と事前認定の違いは、加害者側の保険会社と被害者本人のどちらが手続きをおこなうかです。
|
申請方法 |
概要 |
|
加害者側の保険会社に後遺障害申請の手続きを一任する方法 |
|
|
被害者本人が後遺障害申請の手続きをおこなう方法(弁護士に代行を依頼することもできる) |
後遺障害の審査は書面を参考におこなわれます。
そのため、どちらの申請方法でも提出書類が同じであれば、後遺障害の認定結果が変わることはありません。
事前認定のメリット・デメリット

事前認定のメリットは、手間が一切かからないことです。
被害者は担当医が作成した診断書を提出するだけで済むので、手続きに時間と労力を割く必要がありません。
しかし、加害者側の保険会社は、あくまで手続きの代行をしているだけです。
後遺障害が認定されやすいよう、特別な配慮をしてくれるわけではありません。
そのため、むちうちや高次脳機能障害などの他者からは見えにくい後遺症を申請する場合、加害者側の保険会社が用意した最低限の資料だけでは、後遺障害が認定されないケースも少なからずあります。
被害者請求のメリット・デメリット

被害者請求のメリットは、被害者が自ら後遺症の症状を証明するための資料を用意できることです。
後遺症の証拠資料が充実しやすく、適切な後遺障害が認定される確率が高まる可能性があります。
「事前認定では非該当になったけれど、被害者請求で再申請をしたら後遺障害が認定された」というケースも多々あります。
ただし、被害者自身が等級認定のために必要書類を集める必要があるので、事故後の負担が増えてしまうのがデメリットです。
知識不足な場合は十分に書類を集めきれず、適正な後遺障害等級を獲得できない恐れもあります。
また、診断書やレントゲン資料などを発行する費用も自己負担になるため、お金がかかる点にも注意しなければいけません。
被害者請求で後遺障害申請をしたほうがよい状況
事前認定よりも被害者請求での申請が適している状況は、他人からは見えにくい後遺症を申請する場合です。
上記のとおり、事前認定ではそのような後遺症を証明するのが難しいので、被害者請求での申請を検討するべきでしょう。
また、事前認定で受けた認定結果に納得がいかなかった場合にも、被害者請求での再申請が有効です。
証拠書類を十分に揃えて申請し直すことで、最初とは違う認定結果が出る可能性もあります。
誰から見ても後遺症があることが明らかな状態であれば、手間も費用もかからない事前認定で問題ないでしょう。
その場合は、加害者側の保険会社に手続きの代行を依頼してください。
被害者請求で後遺障害等級認定されるまでの流れ
ここでは、被害者請求での等級認定までの流れを解説します。
- 病院で症状固定の診断を受ける
- 必要書類を準備する
- 加害者側の自賠責保険会社に書類を提出する
- 損害保険料率算出機構によって審査がおこなわれる
1.病院で症状固定の診断を受ける
まずは病院で治療を受けて、医師から症状固定の診断を受けます。
症状固定とは「これ以上治療を続けても症状の改善が望めない状態」を指します。
場合によっては加害者側の保険会社から症状固定の催促を受けることもありますが、あくまでも判断するのは医師です。
もし催促を受けた場合は、言われるがまま対応せずに医師と相談しましょう。
2.必要書類を準備する
症状固定の診断を受けたあとは、後遺障害診断書などの必要書類を集めます。
具体的な必要書類や入手先などについては「被害者請求で後遺障害申請する場合の必要書類」で後述します。
3.加害者側の自賠責保険会社に書類を提出する
必要書類を準備できたら、加害者側の自賠責保険会社に提出します。
4.損害保険料率算出機構によって審査がおこなわれる
書類提出後は、損害保険料率算出機構によって「等級に該当するのかどうか」「該当する場合は何級が適切なのか」などの審査がおこなわれます。
場合によっては追加で書類提出を求められることもあり、その際はすみやかに対応しましょう。
5.加害者側の自賠責保険会社を介して審査結果が通知される
審査が完了したら、加害者側の自賠責保険会社から審査結果が知らされます。
もし審査結果に納得いかない場合は、異議申立てをすることもできます。
ただし、同じ書類を提出しても基本的に結果は変わりませんので、新たに説得力のある証拠を集めたうえでおこなう必要があります。
被害者請求で後遺障害申請する場合の必要書類
被害者請求での後遺障害申請に必要な書類は、以下のとおりです。
|
必要書類 |
入手先 |
|
交通事故証明書 |
自動車安全センター |
|
保険金・損害賠償の請求書 |
自賠責保険会社 |
|
請求者の印鑑証明書 |
市区町村の役場 |
|
事故発生状況報告書 |
自賠責保険会社 |
|
休業損害証明書(仕事を休んで休業損害が発生した場合) |
勤務先 |
|
診断書(事故発生〜症状固定まで) |
病院 |
|
後遺障害診断書 |
病院 |
|
レントゲンなど |
病院 |
なお、交通事故証明書や保険金の請求書、休業損害証明書に関しては、加害者側の任意保険会社から交付してもらえる場合があります。
まずは、加害者側の任意保険会社に書類の取り寄せが可能か確認してみるとよいでしょう。
必要な書類を全て揃えて自賠責保険会社に書類の送付を済ませたら、あとは認定結果が出るのを待つだけです。
後遺障害診断書の確認は入念におこなう
後遺障害診断書とは、事故でどのような後遺症を負ったのかを記載した、担当医による診断書のことです。
後遺障害の認定結果はこの書類の内容を重視して判断されるので、後遺障害申請において特に重要な書類といえるでしょう。
この書類は通院先の担当医が作成してくれますが、医師は交通事故トラブルの専門家ではありません。
そのため、担当医が後遺障害の手続きに不慣れだと、診断書の内容に不備や不足が生じることもあるので注意してください。
後遺障害診断書の作成には、いくつかのポイントがあります。
医師から診断書を受け取ったら、正しい形式で作成されているかどうか、確認を怠らないようにしましょう。
弁護士であれば診断書のチェックなどもしてくれるので、もし不安な方は相談してみましょう。
その他の書類
目に見えにくい後遺症を申請する際には、症状の有無を確認するための検査を受けて結果を提出することで、後遺障害が認定される可能性を高めることができます。
外傷がなく他人からわかりにくい後遺症の場合には、担当医に相談をして、症状の有無を調べられる検査がないか確認してみるとよいでしょう。
また、レントゲンやCTなどの画像資料も症状の存在を証明するのに有効です。
担当医に確認して証拠として役立ちそうであれば、証拠資料として一緒に提出することをおすすめします。
後遺障害が認定される期間の目安
必要書類を提出して後遺障害の認定結果が出るまでの目安は1ヵ月~2ヵ月です。
審査が3ヵ月以上長引くケースもまれにありますが、2023年度の統計によると80%以上の申請は2ヵ月以内に終了しています。
|
認定までにかかる期間 |
申請件数に占める割合 |
|
30日以内 |
73.7% |
|
31日~60日以内 |
14.0% |
|
61日~90日以内 |
6.7% |
|
91日を超える |
5.6% |
なお、自賠責保険の被害者請求権には「症状固定日の翌日から3年」の時効があります。
ただし、そこまで後遺障害の手続きが難航することはまれなので、特別気をつける必要はないでしょう。
被害者請求で後遺障害申請する場合は弁護士への依頼がおすすめ
交通事故問題で弁護士を雇った場合、被害者請求の手続きを弁護士に一任することができます。
ここでは、被害者請求を弁護士に依頼するメリットを2つ紹介します。
1. 適切な等級が認定される可能性が高まる
交通事故問題の解決経験が豊富な弁護士であれば、後遺障害が認定されやすい後遺障害診断書の書き方や、症状を証明するために受けておいたほうがよい検査などを熟知しています。
必要書類の準備や確認もしてもらえるので、申請に不備が生じるリスクを極限まで抑えることができるでしょう。
弁護士が被害者請求をおこなうのが、最も適切な等級が認定される可能性が高い申請方法といえるでしょう。
自身で手続きに臨むことに不安を感じるのであれば、弁護士に任せることをおすすめします。
2. 慰謝料の大幅な増額を見込める
交通事故の慰謝料は、加害者側の保険会社の基準(任意保険基準)で算出されるケースが一般的です。
しかし、弁護士を選任することで、過去の裁判結果を基にした基準(弁護士基準・裁判所基準)での慰謝料請求が望めます。
各基準の慰謝料額は以下のように異なります。
|
等級 |
任意基準(推定) |
弁護士基準 |
|
1,600万円 |
2,800万円 |
|
|
1,300万円 |
2,370万円 |
|
|
1,100万円 |
1,990万円 |
|
|
900万円 |
1,670万円 |
|
|
750万円 |
1,400万円 |
|
|
600万円 |
1,180万円 |
|
|
500万円 |
1,000万円 |
|
|
400万円 |
830万円 |
|
|
300万円 |
690万円 |
|
|
200万円 |
550万円 |
|
|
150万円 |
420万円 |
|
|
100万円 |
290万円 |
|
|
60万円 |
180万円 |
|
|
40万円 |
110万円 |
後遺障害の慰謝料相場は、弁護士の有無で約2倍の差額が生じます。
後遺障害が関わる事故では、弁護士に依頼する費用よりも弁護士基準への切り替えによる増額分のほうが大きくなる可能性が高いです。
弁護士に依頼した方が得になるかどうかは、法律事務所の法律相談を利用することで確認できます。
最近では、無料相談を受け付けている法律事務所も増えてきているので、自分の場合はどうなのか確認してみましょう。
まとめ
被害者請求と事前認定の違いは、以下のとおりです。
|
申請方法 |
メリット |
デメリット |
|
事前認定 |
手続きの手間がかからない |
相手保険会社は後遺障害認定されやすいように特別な配慮はしてくれない |
|
被害者請求 |
被害者本人が後遺障害を証明する証拠資料を用意できる(後遺症を証明しやすい) |
手続きの手間と書類を用意するための費用が発生する |
後遺障害の認定結果によって、受け取ることのできる保険金の額が大きく変わります。
後遺障害の申請は、損害賠償請求において非常に重要な手続きですので、わからないことは放置せず、担当医や弁護士に相談しながら臨みましょう。
弁護士であれば、納得のいく審査結果を得るための書類収集のアドバイスや、損害賠償金の示談交渉や裁判などのサポートもしてくれます。
初回の法律相談無料の法律事務所もあるので、まずは一度話を聞いてみることをおすすめします。
弁護士に相談するかお悩みの方へ
下のボタンからあなた当てはまるものを選んで悩みを解消しましょう。
弁護士費用特約があれば 実質0円で依頼できます!

多くの保険会社では、被害者1名につき最大300万円までの弁護士費用を負担してくれます。特約があるか分からない方でも、お気軽にご相談ください。弁護士と一緒にご確認した上で依頼の有無を決めて頂けます。
特約を利用して弁護士に相談する交通事故問題を依頼する弁護士の選び方にはポイントがあります。
- 過去の解決事例を確認する
- 料金体系が明確である弁護士を選ぶ
- 交通事故問題が得意な弁護士から選ぶ
等です。
詳しくは以下の記事を読んで、正しい弁護士の選び方を理解した上で弁護士に相談しましょう。
弁護士の選び方について詳しくみる
「事故の損害賠償を求めたい」「保険会社との交渉を任せたい」「後遺症に悩まされている」等、自己負担なく、保険会社との交渉や慰謝料額のチェックを弁護士に依頼できるかもしれません【示談に応じてしまう前に、使える権利がないか一度ご確認ください】
事務所詳細を見る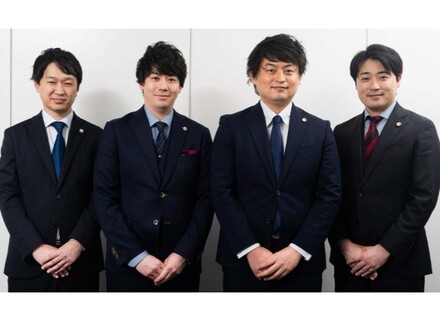
【初回相談無料】解決件数850件以上の弁護士が直接対応/賠償金の大幅増額の実績あり/後遺障害・交渉はお任せください/むち打ち・骨折〜死亡事故など幅広く親身にお話伺います<オンライン相談可・全国対応可>
事務所詳細を見る
【初回相談0円】【オンライン相談対応◎】【来所せずご依頼可能】事故直後や治療中のお悩み/保険会社との交渉など、実績豊富な弁護士が迅速かつ丁寧に対応いたします◆弁護士特約対応◆お気軽にご相談ください
事務所詳細を見る当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡

後遺障害等級・申請方法に関する新着コラム
-
本記事では交通事故で後遺症が残った場合に決める後遺障害等級について誰が決めるのかや後遺障害等級の認定に当たっては弁護士に早期に相談することで後遺障害等級の認定を...
-
本記事では、交通事故の被害に遭い橈骨頭骨折を負った方に向けて、橈骨橈骨折の症状や後遺症に関する基礎知識、橈骨橈骨折で認められる後遺障害等級の目安、適切な後遺障害...
-
交通事故で頚椎を損傷すると、どのような症状が出るのでしょうか?本記事では、頚椎損傷の主な症状や考えられる後遺症、加害者に請求できるお金について解説します。少しで...
-
交通事故による後遺症が残ったときは、後遺障害等級認定の手続きが必要です。等級認定を受けることができれば、賠償金の大幅な増額が期待できます。本記事では、後遺障害等...
-
交通事故に遭ったことが原因でけがを負い、後遺症が残った場合は、後遺障害等級認定を受けることで保険会社から損害賠償を受け取れる可能性があります。交通事故による後遺...
-
交通事故に遭ってしまい腰椎圧迫骨折の治療を続けたものの、後遺障害等級が認定されず、不安を感じている方もいるのではないでしょうか。本記事では、腰椎圧迫骨折で後遺障...
-
本記事では交通事故の被害に遭った方に向けて、後遺障害等級認定の定義、仕組み、認定機関、調査期間などの基礎知識、事前認定と被害者請求の大まかな流れ、後遺障害等級が...
-
事故で受けたケガが完治しない場合「後遺障害等級認定を受けるかどうか悩んでいる」という方もいるでしょう。この記事では、「後遺障害等級認定を受けることにはデメリット...
-
交通事故に巻き込まれた際は、できるだけ早く弁護士に相談することが大切です。支払ってもらえる保険金額や逸失利益を計算したい場合もあるでしょう。本記事では、後遺障害...
-
後遺障害等級と障害者手帳の交付を受けるための等級は別物であり、必ずしも障害者手帳が交付されるわけではありません。本記事では、後遺障害11級に認定された方に向けて...
後遺障害等級・申請方法に関する人気コラム
-
後遺障害14級は最も軽症の後遺障害等級で、たとえばむちうち・聴力の低下・歯の欠損などがあった場合に認定されます。本記事では、交通事故で後遺障害14級が認定される...
-
後遺障害診断書の概要や入手方法、書き方と記入例、後遺障害の等級認定を獲得するためのポイントのほか、医師が診断書を書いてくれない場合とその対処法、後遺障害診断書の...
-
今回お伝えする内容は、後遺障害等級12級に該当する症状と認定の方法、そして、後遺障害等級12級の適切な慰謝料を獲得する7つの知識をご紹介します。
-
交通事故における症状固定とは、むちうちなどのような後遺障害等級の獲得や示談時期などを決める際に重要な意味があります。安易に保険会社から症状固定日の提案に同意する...
-
交通事故トラブルを弁護士に相談すれば、自身に有利な条件で問題解決できる可能性が高くなります。しかし、費用面が気がかりで躊躇している方もいるのではないでしょうか。...
-
高次脳機能障害(こうじのうきのうしょうがい)とは、主に脳に損傷を負ったことで起こる様々な神経心理学的障害(記憶障害、注意障害、遂行機能障害、社会的行動障害など)...
-
後遺障害等級13級に該当する症状と後遺障害等級13級を獲得する手順をご紹介していきます。
-
後遺障害の認定が非該当になった場合に、異議申し立てを行うための方法と、成功させるコツをご紹介します。
-
後遺障害等級10級に認定された場合、その後遺障害が与える労働能力喪失率は27%と設定されており、後遺症が残った場合はいよいよ実生活にも多大な影響を与える症状が多...
-
今回は、後遺障害11級と認定される症状や、後遺障害等級11級となった場合に、どの程度の損害賠償になるのかなどをご紹介します。
後遺障害等級・申請方法の関連コラム
-
交通事故で負ったケガが原因でめまいが起こっている場合、症状によっては後遺障害が認定され、高額な損害賠償を受けられる可能性があります。本記事では、交通事故によるめ...
-
今回お伝えする内容は、後遺障害等級12級に該当する症状と認定の方法、そして、後遺障害等級12級の適切な慰謝料を獲得する7つの知識をご紹介します。
-
交通事故により眼球やまぶたが傷ついたり、機能障害を負ったりします。この記事では、眼球やまぶたに関する後遺障害について、該当する症状や後遺障害等級、慰謝料相場をす...
-
後遺障害診断書の概要や入手方法、書き方と記入例、後遺障害の等級認定を獲得するためのポイントのほか、医師が診断書を書いてくれない場合とその対処法、後遺障害診断書の...
-
交通事故に遭ってしまい腰椎圧迫骨折の治療を続けたものの、後遺障害等級が認定されず、不安を感じている方もいるのではないでしょうか。本記事では、腰椎圧迫骨折で後遺障...
-
交通事故の被害を弁護士に相談するべき時期はケースバイケースです。この記事では、後遺障害を弁護士に相談するのに最も適したタイミングを解説します。弁護士への相談を検...
-
自賠責基準の後遺障害慰謝料の相場や、請求できる保険金の限度額などをご紹介します。後遺障害申請手続きの注意事項や弁護士を雇うメリットなども解説していますので、後遺...
-
後遺障害等級の12級14号は、外貌に醜状が残った際に認定される障害です。この記事では、12級14号とは具体的にどのような後遺障害なのか、請求できる損害賠償(慰謝...
-
後遺障害には第1級〜第14級までの等級が設定されていますが、その中でも第1級〜第3級は家事や学業も含めた社会復帰が事実上不可能とされる症状も多く含まれています。...
-
後遺障害10級には、肩・腕・手や股関節・膝・足を骨折して可動域が2分の1以下に制限された場合が含まれます。本記事では、後遺障害10級の具体的な症状や認定基準、後...
-
後遺障害の慰謝料とは、交通事故に被害で負った後遺症が、後遺障害等級認定をされた際に請求できる慰謝料のことで、交通事故の損害賠償の中でも相場を引き上げる要因にもな...
-
交通事故トラブルを弁護士に相談すれば、自身に有利な条件で問題解決できる可能性が高くなります。しかし、費用面が気がかりで躊躇している方もいるのではないでしょうか。...
後遺障害等級・申請方法コラム一覧へ戻る


























 慰謝料・損害賠償
慰謝料・損害賠償
 示談
示談
 過失割合
過失割合
 死亡事故
死亡事故
 後遺障害
後遺障害
 むちうち
むちうち
 自転車事故
自転車事故
 自動車事故
自動車事故
 人身事故
人身事故
 バイク事故
バイク事故
































