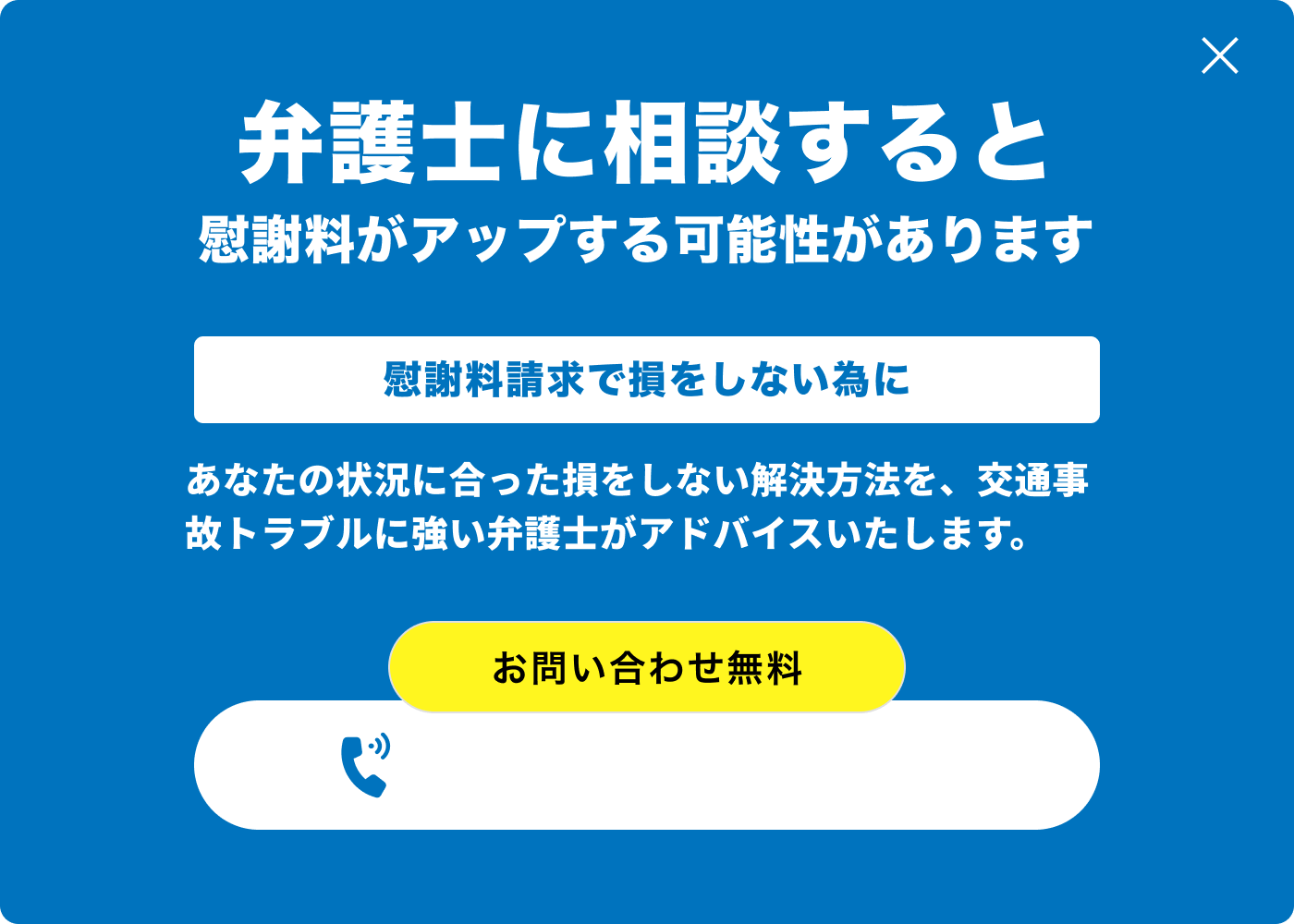交通事故や自転車事故など、事故はいつ起きてしまうか分からないものです。弁護士費用を用意できず泣き寝入りとなってしまうケースも少なくありません。
ベンナビ弁護士保険は、弁護士依頼で発生する着手金を補償する保険です。
交通事故だけでなく、自転車事故、労働問題、離婚、相続トラブルなど幅広い法的トラブルで利用することができます。
弁護士保険で法律トラブルに備える

あなたが歩行者で事故に遭った場合には、加害者に対して慰謝料を請求できる可能性があります。
ただ、「どれくらい請求可能なのか」「請求するにはどういった方法を取ればよいか」などについて疑問に思っている方も少なくないでしょう。
本記事では、歩行中に事故に遭ってしまった方に向けて、加害者に対して請求できる慰謝料額や慰謝料以外に損害賠償として請求できるもの、慰謝料請求までの流れなどについて解説します。
この記事を参考に、慰謝料に対する理解を深めてください。
交通事故の歩行者が受け取れる慰謝料には、次の3種類があります。
慰謝料は精神的な苦痛に対する損害賠償金ですが、治療費や物損のように発生した損害を金銭的に表すのが困難です。
そのため、慰謝料額の算定のためには一定の基準を用いることが通常です。
この基準には「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準」の3種類があります。
|
自賠責基準 |
自賠責保険を用いる際に用いられる基準で、3つの中で最も慰謝料額が低いです。「最低限の補償額」という意味合いをもちます。 |
|
任意保険基準 |
各保険会社が独自に設定している基準です。慰謝料額は、自賠責基準と同程度か少し高い程度です。保険会社と示談をする際に、保険会社から提示される金額になります。 |
|
弁護士基準 |
裁判をした場合に支払われる基準で、「裁判基準」とも呼ばれます。「民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準(通称:赤い本)」、「交通事故損害額算定基準(通称:青本)」にも記載があり、弁護士が示談を代理した場合や裁判をした場合に用いられる基準です。 |
示談は加害者も被害者も金額に納得していれば成立しますので、どの基準が適用されているかには十分な注意が必要です。
では、どういった慰謝料が請求できるかについてみていきましょう。
入通院慰謝料とは、けがの治療のために、入院や通院をしたことに対して支払われる慰謝料です。
金額は入院日数や通院日数に応じて決まり、日数が長くなると慰謝料額も高くなります。
自賠責基準の入通院慰謝料は、次の2つの計算をおこない、金額が少ないほうが適用されます。
※かっこ内は2020年4月1日以前の事故の場合
仮に、15日の通院期間で5日の通院をした場合には、次の計算のような計算をおこないます。
➀と②では②のほうが少ないですので、上記のケースでの自賠責基準の慰謝料額は43,000円です。
任意保険基準の入通院慰謝料は概ね次の図のとおりです。

(単位:万円)
なお、各保険会社が独自に定めている基準であるため正確な金額は不明ですが、自賠責基準よりは若干高めに設定していることが通常です。
弁護士基準の入通院慰謝料は、むちうち症で他覚所見がない場合や軽い打撲などのケースと、その他のケースで別れます。
弁護士基準の入通院慰謝料は次のとおりです。

(単位:万円)

(単位:万円)
後遺障害慰謝料は、交通事故の被害によって後遺障害が残ってしまったときに支払われる慰謝料です。
後遺障害とは、症状固定後(治療をしてもそれ以上改善が認められない状態)も障害が残っており、その程度が自過失法施工令の等級に該当することをいいます。
後遺障害慰謝料は認定された等級によって金額が異なり、それぞれの基準での慰謝料額は次のとおりです。
|
等級 |
自賠責基準 (2020年3月31日までに発生した事故) |
任意基準(推定) |
弁護士基準 |
|
1,150万円 (1,100万円) |
1,600万円程度 |
2,800万円 |
|
|
998万円 (958万円) |
1,300万円程度 |
2,370万円 |
|
|
861万円 (829万円) |
1,100万円程度 |
1,990万円 |
|
|
737万円 (712万円) |
900万円程度 |
1,670万円 |
|
|
618万円 (599万円) |
750万円程度 |
1,400万円 |
|
|
512万円 (498万円) |
600万円程度 |
1,180万円 |
|
|
419万円 (409万円) |
500万円程度 |
1,000万円 |
|
|
331万円 (324万円) |
400万円程度 |
830万円 |
|
|
249万円 (245万円) |
300万円程度 |
690万円 |
|
|
190万円 (187万円) |
200万円程度 |
550万円 |
|
|
136万円 (135万円) |
150万円程度 |
420万円 |
|
|
94万円 (93万円) |
100万円程度 |
290万円 |
|
|
57万円 |
60万円程度 |
180万円 |
|
|
32万円 |
40万円程度 |
110万円 |
死亡慰謝料とは、被害者が亡くなってしまった場合に請求できる慰謝料のことです。
なお、死亡慰謝料は事故と死亡に因果関係があれば請求可能ですので、事故から一定期間経過した後に被害者が亡くなってしまった場合でも請求可能なケースがあります。
死亡慰謝料は事故被害者本人の精神的苦痛と、遺族が背負う精神的苦痛の2要素が含まれています。
自賠責基準の死亡慰謝料のうち、被害者本人に対する金額は一律で400万円です。
一方、ご遺族の金額は請求者(慰謝料を請求する権利のある人)の人数によって変わります。
請求者の範囲は民法711条で定められており、原則として被害者の両親・配偶者・子供です。
加えて、被害者の収入で生計を立てている扶養家族がいた場合には200万円が追加されます。
表にまとめると次のとおりとなります。
|
被害者本人の慰謝料 |
400万円(2020年4月1日以前に発生した事故に関しては350万円) |
|
請求者が1人の遺族の慰謝料 |
550万円 |
|
請求者が2人の遺族の慰謝料 |
650万円 |
|
請求者が3人以上の遺族の慰謝料 |
750万円 |
|
扶養されていた場合の慰謝料 |
200万円 |
仮に請求者が1人で、亡くなった本人に扶養家族がいない場合、400万円と550万円の合計の950万円が自賠責基準での慰謝料額です。
一方、請求者が1人で、亡くなった本人に扶養家族がいた場合、400万円と550万円と200万円の合計1,150万円が自賠責基準の慰謝料額です。
任意保険基準の死亡慰謝料額は、被害者本人と遺族の分を合計したもので、亡くなった方の家庭内での立場によって変わります。
任意保険基準の死亡慰謝料額は次の表のとおりです(公表されていないため、推定値です)。
|
死亡者の立場 |
任意保険基準 |
|
一家の支柱 |
1,500万〜2,000万円程度 |
|
配偶者、母親 |
1,500万〜2,000万円程度 |
|
上記以外 |
1,200万〜1,500万円程度 |
弁護士基準の死亡慰謝料額も、被害者本人と遺族の分の両方を含んでいます。
任意保険基準と同様、慰謝料額は亡くなった方の家庭内の立場で変わります。
|
死亡者の立場 |
任意保険基準 |
|
一家の支柱 |
2,800万円 |
|
配偶者、母親 |
2,500万円 |
|
上記以外 |
2,000万~2,500万円 |
歩行者で交通事故に遭った方の中には、慰謝料額が高額になるのではと考えている方もいるかもしれません。
しかし死亡慰謝料額には一定の基準があり、金額が基準から大きく変わることはあまりありません。
ここからは、歩行者で交通事故に遭った際の慰謝料について解説します。
交通事故の慰謝料は、被害状況に応じて請求が可能です。
入通院期間や後遺障害の等級、被害者が亡くなったかどうかにより金額が決まります。
過失割合の認定においては、歩行者であることは相当程度考慮されます。
過失割合とは、交通事故の発生に対してどの程度の過失があるかを、被害者と加害者について割合で表したもので、上限が100、下限が0です。
過失割合は判例によってある程度類型的に決められており、被害者が歩行者である事故類型の過失割合が認定されています。
そして、過失割合に応じて慰謝料を含めた損害賠償額が減額されます(過失相殺)。
たとえば損害賠償額が1,000万円で、過失割合が被害者:加害者=10:90であった場合、10%が減額された900万円が損害賠償として支払われるのです。
3つの慰謝料額と過失割合について説明してきましたが、過失割合が修正されたり、慰謝料額そのものが修正されたりして、受け取れる賠償金額が変わるケースがあります。
加害者に重過失がある場合には、過失割合が加害者に重く修正される結果、受け取れる賠償金額が増加する可能性があります。
重過失が認められ得るケースとしては、無免許運転、著しいスピード違反、殊更な赤信号無視、飲酒運転、脱法ドラッグを吸引しての運転などが該当します。
事故を目撃した際のショックや、被害者が亡くなったことによって、家族がうつ病や適応障害などの精神疾患を患った場合などには、家族に対する慰謝料が認められる可能性があります。
身体に大きな傷跡が残ってしまった場合や味覚・嗅覚などに異常が残ってしまった場合など、重度な後遺障害が残ってしまうと重い後遺障害等級が認定されます。
認定されると、高額な後遺障害慰謝料が認められる可能性があります。
素因減額とは、被害者に既往症(以前かかったことがある病気のこと)があった場合に、それを原因として損害が拡大した部分について、慰謝料を含む損害賠償金を減額することをいいます。
たとえば、椎間板ヘルニアなどの身体的病気を患っている場合には、それがなかった場合に比べて事故によるけがの程度が大きくなることが考えられます。
上記のような場合には、素因減額によって賠償額を減額して、損害拡大部分について被害者も負担することで、公平な分担を図ります。
通院慰謝料は、通院日数が少ない場合に減額される可能性があります。
具体的には1ヵ月の通院日数が10日を切った場合、通院期間ではなく実際に通院した日数の3倍の日数を基準に慰謝料額を算出することがあります。
たとえば、通院期間が1年であったとしても、実際の通院日数が20日であった場合、通院慰謝料は20日×3のおよそ2ヵ月分とされる可能性があります。
歩行者にも過失割合がある場合、慰謝料を含む損害賠償額は相当程度減額されます。
これを過失相殺といいます。
過失割合は、事故態様によって類型的に決まります。
その根拠となるのは警察が作成する実況見分調書で、実務的には加害者が加入する保険会社によって提示されます。
日常会話やドラマなどで、被害者側が「慰謝料を請求する」という言葉を耳にするかもしれません。
しかし、加害者に対して請求できるのは慰謝料に限ったものだけではありません。
繰り返しになりますが、被害者は交通事故で発生した損害をすべて加害者に請求できます。
慰謝料請求は加害者に対して請求できる損害賠償請求の一部です。
そもそも、一般に、被害者が加害者に対して金銭を請求できるのは、民法の709条と710条を根拠にしています。
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
(財産以外の損害の賠償)
第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。引用元:民法第709条 第710条
そして、慰謝料とは精神的な部分についての損害賠償をいいます。
被害者は事故により発生した損害をすべて支払ってもらえますので、精神的な損害だけでなく、当然財産的な損害についても賠償してもらえるのです。
精神的な部分と財産的な部分を合わせた金額が、請求すべき損害賠償金であると理解しておいてください。
では、慰謝料以外に損害賠償として請求できる金銭にはどういったものがあるのでしょうか。
ここで確認しておきましょう。
積極損害とは、交通事故に遭わなければ支払う必要がなかった費用のことをいいます。
治療費や入院費はイメージしやすいかと思いますが、以下も積極損害として認められる可能性があります。
|
積極損害 |
内容 |
|
入院費・治療費 |
入院や治療に発生した費用 |
|
整骨院・温泉治療・マッサージ・針灸代 |
むちうち等で医師の指示がある場合 |
|
付添看護費 |
一人で通院できない場合の「通院付添費」入院に付き添いが必要な場合の「入院付添費」介護が必要な場合の「自宅介護費」 |
|
将来看護費 |
後遺障害を負うことで将来にわたって介護が必要になったときの費用 |
|
身体を補うものの費用 |
義足・義歯・車椅子、補聴器、入れ歯、義眼、かつら、めがね、コンタクトレンズ、身障者用ワープロ、パソコン等 |
|
雑費 |
入院や通院中の雑費 |
|
交通費 |
入院や通院の交通費 |
|
通院のための宿泊費 |
通院のために宿泊が必要になった場合の費用 |
|
家屋の改造費 |
後遺障害が残り、家屋を改造する必要がある場合の費用 |
|
学習費 |
ケガの治療の影響で学習の遅れを取り戻す場合や、留年した場合の費用 |
|
弁護士費用 |
訴訟となった場合の弁護士費用 |
|
葬儀関係費 |
事故で被害者が亡くなった場合の葬儀費用 |
|
その他 |
旅行のキャンセル料金や成年後見申立費用など |
消極損害とは、事故に遭うことで失われてしまった利益(収入)のことをいいます。
治療のため休業した期間の利益減少分である「休業損害」と、後遺障害や死亡によって将来にわたる利益減少分である「逸失利益」にわけられます。
代表的な休業損害の計算式は次のとおりです。
|
給与所得者 事故前3ヵ月間の収入÷90×休業日数 個人事業主 事故前年の所得税確定申告所得 ÷ 365 × 休業日数 主婦(夫) 賃金センサスの平均賃金1日分の収入 × 休業日数 |
後遺障害や死亡による逸失利益の計算方法は次のとおりです。
|
【後遺障害の逸失利益】 基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数 【死亡逸失利益】 基礎収入×(1-生活費控除率)×労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数 |
ここからは、慰謝料額のシミュレーションをみてみましょう。
なお、弁護士基準での慰謝料算定とします。
仮にけがを負って1ヵ月入院・3ヵ月通院した場合、弁護士基準での慰謝料額は上の表に照らし合わせると、115万円となります。
後遺障害が残ったケースでは、入通院慰謝料と後遺障害慰謝料の2つを合計したものを請求できます。
仮に入院が3ヵ月・通院が5ヵ月、後遺障害が12級だとした場合の慰謝料額は次のとおりです。
|
慰謝料額=入通院慰謝料+後遺障害慰謝料 =204万円+420万円 =624万円 |
交通事故により亡くなってしまった場合の慰謝料額は、家庭内の立場によって異なってくるのはすでにお伝えしたとおりです。
仮に一家の支柱の方が亡くなった場合の慰謝料シミュレーション額は、2,800万円です。
最後に、事故に遭った時点から慰謝料を請求するまでの以下4つの流れを紹介します。
事前に全体像を把握しておくことで、落ち着いて対処できるようになるため、参考にしてみてください。
事故発生後には、警察が対応します。
このとき、人身事故扱いになっているか確認する必要があります。
仮に物損事故の扱いになってしまった場合、人身事故であることを証明するための手続きなどが必要になり手間が発生するからです。
もし物損事故として扱われた場合は、医師の診断書を警察署に持っていき、人身事故扱いに切り替えてもらうようにしてください。
けががあった場合には、必ず病院を受診しあなたの症状をしっかりと伝えるようにしてください。
病院では、必要な検査は必ずおこない、その証拠を残し定期的に受診するようにしてください。
事故直後の診断だけでなく、治療経過なども損害賠償額に影響を与えるからです。
症状固定とは、治療を継続してもそれ以上けがの症状がよくならないことをいいます。
入院費や治療費などは、症状固定までの分が損害賠償として支払われますので、症状固定のタイミングは非常に重要です。
治療中に保険会社から「そろそろ症状固定にしませんか」と打診を受けることがありますが、症状固定の判断をするのは医師です。
保険会社の意見をそのまま素直にきく必要はありません。
症状固定後にも残っている症状に関しては「後遺障害」となります。
後遺障害に関する損害賠償を請求する場合には後遺障害等級の認定を受ける必要がありますので、医師に診断書を作成してもらいましょう。
後遺障害の申請の方法は、加害者の保険会社に申請してもらう「事前認定」と、被害者自身で申請する「被害者請求」の2種類がありますが、被害者請求での認定をおすすめします。
事前認定の場合には、提出書類が被害者自身でコントロールできなくなる結果、本来あるべき等級よりも低くなってしまう可能性があるからです。
症状固定や後遺障害の等級が決まったあとは、加害者の加入する保険会社と示談交渉をおこないます。
保険会社が提示する損害賠償額は、適正価格よりも低い可能性がありますので、十分な注意が必要です。
示談は一度おこなってしまうと、あとからやり直したり別途損害を請求したりすることは非常に困難です。
損害賠償額が提示された場合には、弁護士にチェックしてもらうことをおすすめします。
慰謝料には「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準」の3種類があります。
そして、保険会社と示談する場合には、「任意保険基準」での慰謝料額を最初に提示されることが通常です。
しかし、任意保険基準は各保険会社が独自に決定したものですので、その金額が弁護士基準でない場合には、慰謝料額は適正なものではないと評価できるでしょう。
事故によって被害を受けた場合、大変な思いをすることになるのが通常です。
できるだけ多くの慰謝料額を獲得したいと考えているのであれば、弁護士に依頼してください。
弁護士は保険会社と「弁護士基準」を用いて慰謝料額を交渉しますので、あなた自身で交渉をおこなった場合に比べて慰謝料が増額する可能性があります。
また、加害者に請求できるものは慰謝料だけに限りません。
積極損害や消極損害なども請求可能です。
保険会社が提示する示談金のなかに、もしかすると漏れがあるかもしれません。
弁護士に依頼すれば、あなたの示談金が最大化するように交渉してもらえますので、本来であれば請求できたのに、自分自身で交渉をしたために示談金が少なくなってしまったといった事態も避けられます。
ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)では、交通事故に注力している弁護士のみを紹介しています。
都道府県別に弁護士事務所を検索できますので、お近くの弁護士事務所を探してみましょう。
歩行者で交通事故に遭ってしまった場合の慰謝料について解説しました。
慰謝料には「入通院慰謝料」「後遺障害慰謝料」「死亡慰謝料」の3種類があり、受けた被害に応じて請求が可能です。
慰謝料額は精神的な苦痛に対する損害を補償するものであるため、基準が設けられています。
「弁護士基準」が最も高額となるため、損害賠償額が提示された場合にはどの基準が採用されているのかしっかりと確認しておきましょう。
また、保険会社が提示する基準はほとんどのケースでは「任意保険基準」となっています。
「弁護士基準」で支払ってもらうには、あなた自身での交渉では難しいケースがほとんどであるため、弁護士に依頼することをおすすめします。
弁護士に相談するかお悩みの方へ
下のボタンからあなた当てはまるものを選んで悩みを解消しましょう。
弁護士費用特約があれば 実質0円で依頼できます!

多くの保険会社では、被害者1名につき最大300万円までの弁護士費用を負担してくれます。特約があるか分からない方でも、お気軽にご相談ください。弁護士と一緒にご確認した上で依頼の有無を決めて頂けます。
特約を利用して弁護士に相談する交通事故問題を依頼する弁護士の選び方にはポイントがあります。
等です。
詳しくは以下の記事を読んで、正しい弁護士の選び方を理解した上で弁護士に相談しましょう。
弁護士の選び方について詳しくみる
提示された賠償金に納得がいかない方は、アディーレへご相談を!適正な賠償金を受け取るためにサポートします◆自転車・バイク事故にも対応◆
事務所詳細を見る
提示された賠償金に納得がいかない方は、アディーレへご相談を!適正な賠償金を受け取るためにサポートします◆自転車・バイク事故にも対応◆
事務所詳細を見る
提示された賠償金に納得がいかない方は、アディーレへご相談を!適正な賠償金を受け取るためにサポートします◆自転車・バイク事故にも対応◆
事務所詳細を見る
交通事故にあうと加害者から見舞金が支払われることがあります。労災の場合は会社から支払われることもありますが、必ず支給されるわけではないため注意が必要です。本記事...
もらい事故で全損した場合は相手に買い替え費用を請求できます。ただし、新車購入金額の100%を請求できるとは限らないため注意が必要です。本記事では、もらい事故で車...
自賠責保険は、交通事故の被害者に対して最低限の補償を提供することを目的としています。本記事では、自賠責保険による傷害補償の限度額(120万円)やその内訳、超過分...
物損事故の場合、慰謝料は請求できないケースが大半です。車の修理費など、請求が認められる損害の賠償を漏れなく請求しましょう。本記事では、物損事故で慰謝料は請求でき...
交通事故の過失割合は、事故の客観的な状況に応じて決まります。本記事では、「動いている車同士の事故に過失割合100:0はありえない」が本当なのかどうかについて解説...
本記事では、交通事故による全治6ヵ月のけががどの程度重症であるのか、および請求できる損害賠償の内訳や対応時の注意点などを解説します。
本記事では、運転中に追突されたもののけががなかったケースにおいて、請求できる損害賠償の項目や利用できる保険の種類などを解説します。
交通事故に遭った家族が1ヵ月以上意識不明の場合は、将来的に「遷延性意識障害」の診断を受ける可能性があります。 本記事では、家族が交通事故に遭って1ヵ月以上意識...
この記事では、交通事故の加害者が任意保険を使わない場合の、示談金が振り込まれるまでの流れを解説します。示談金がなかなか振り込まれない場合の対処法も紹介するので、...
交通事故を起こした際は、損害賠償の内容を示談書にまとめておくことが大切です。しかし、具体的な記載事項や書き方がわからず、悩んでいる方も多いのではないでしょうか。...
交通事故で負傷した場合は、その肉体的・精神的苦痛に対して慰謝料を請求できます。本記事では、慰謝料の基礎知識から相場、増額方法について解説しています。
交通事故の被害に遭った際に、損害賠償請求ができる項目や相場を知らないと、加害者側保険会社の提示金額を鵜呑みにしてしまい適正な金額の賠償を受けられない恐れがありま...
人身事故と物損事故ではそれぞれ手続の流れが異なります。けがをしているのに物損事故で処理すると、十分な補償が受けられないなどのデメリットがあります。本記事では、人...
慰謝料とは、精神的苦痛に対して支払われる賠償金です。交通事故の場合だと、事故被害で怪我を負った(または死亡事故)の場合に請求可能です。この記事では、交通事故の慰...
「休業損害証明書の書き方について知りたい」「休業損害の相場を把握したい」などの悩みを抱えている交通事故被害者の方に向けて、本記事では休業損害証明書の書き方やパタ...
交通事故によるけがや病気などで会社を休んだ場合に受けられるのが休業補償ですが、休業損害や休業手当と混合されるケースが多くあります。本記事では、会社を休んだ場合の...
「追突事故の慰謝料について知りたい」「慰謝料を増額したい」などのお悩みを抱えている交通事故の被害者に向けて、本記事では追突事故の慰謝料の種類や相場を解説します。...
保険金は事故被害から早く立ち直るための大切なお金です。いつどのくらいもらえるのか気になる方が多いのではないでしょうか。この記事では交通事故の保険金の算出方法や相...
休業損害とは、交通事故により仕事を休んだことで減収したことに対する損害のことを呼びます。職業や請求方法などにより金額は大きく変わりますので、適切な額を受け取るた...
逸失利益とは、交通事故による後遺障害や死亡がなければ、将来得られるはずだった収入の減少分に対する補償のことです。特に逸失利益は高額になるケースが多いため、詳しい...
同乗していた車が交通事故に遭ってしまった場合、事故の状況に応じて同乗者が取るべき対応は変わります。慰謝料の請求先やご自身が受けられる保険の補償範囲など、正確に把...
交通事故の傷跡が残った場合、後遺障害慰謝料を請求できる可能性があります。なお後遺障害等級は14段階に分かれており、何級が認定されるかによって慰謝料の金額は大きく...
交通事故で負傷した場合は、その肉体的・精神的苦痛に対して慰謝料を請求できます。本記事では、慰謝料の基礎知識から相場、増額方法について解説しています。
人身事故と物損事故ではそれぞれ手続の流れが異なります。けがをしているのに物損事故で処理すると、十分な補償が受けられないなどのデメリットがあります。本記事では、人...
「慰謝料どれくらいもらった?」と聞きたくても交通事故の慰謝料請求をした経験のある人なんて周囲にいないのが通常です。そこで、この記事では実際にあった慰謝料請求事例...
交通事故によるけがや病気などで会社を休んだ場合に受けられるのが休業補償ですが、休業損害や休業手当と混合されるケースが多くあります。本記事では、会社を休んだ場合の...
交通事故の示談金は、事故や怪我の状況などに応じて細かく異なります。交通事故の知識なく示談交渉を進めてしまうと、結果的に損をしてしまうこともあるため注意しましょう...
交通事故の慰謝料は、弁護士基準で請求することで高額になる可能性があります。弁護士基準での慰謝料請求を成功させるためにも、請求時のポイントについて知っておきましょ...
この記事では、全損事故に遭った際の補償について説明しています。交通事故の被害者は加害者に対し、慰謝料などの損害賠償金の請求ができます。全損ならではの状況に起因す...
慰謝料とは、精神的苦痛に対して支払われる賠償金です。交通事故の場合だと、事故被害で怪我を負った(または死亡事故)の場合に請求可能です。この記事では、交通事故の慰...
交通事故でむち打ち被害に遭った際は、適切な手順に則って対処する必要があります。対処が適切でない場合、加害者から補償が受けられない可能性もありますので注意しましょ...
少しでも高額の休業損害を請求したいなら弁護士への依頼は不可欠です。ベンナビ交通事故では交通事故案件の実績豊富な専門家を多数掲載しているので、信頼できる弁護士まで...