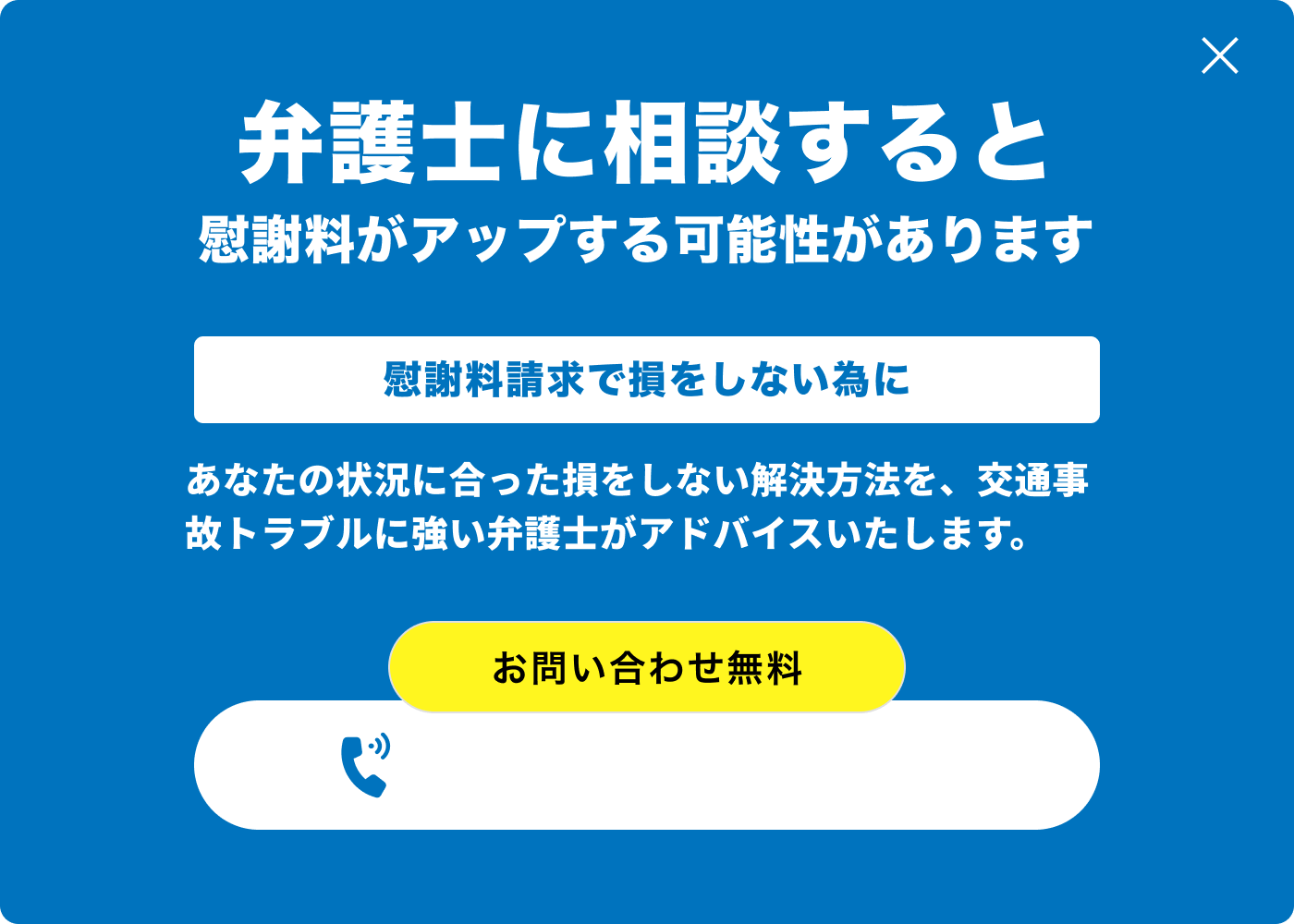交通事故や自転車事故など、事故はいつ起きてしまうか分からないものです。弁護士費用を用意できず泣き寝入りとなってしまうケースも少なくありません。
ベンナビ弁護士保険は、弁護士依頼で発生する着手金を補償する保険です。
交通事故だけでなく、自転車事故、労働問題、離婚、相続トラブルなど幅広い法的トラブルで利用することができます。
弁護士保険で法律トラブルに備える

交差点で起こる事故の代表例として、直進車と右折車による右直事故が挙げられます。直進車と右折車では直進車のほうが優先であることが基本であり、右折車の過失割合が高くなることが多いです。しかし、具体的な過失割合は、信号の色や双方の位置関係のほか事故車両が自動車、単車、自転車のいずれであるかなど諸々の事情で変わってきます。
事故の相手に対しては、慰謝料・消極損害・積極損害などの損害賠償を請求することになりますが、請求できる金額は過失割合により左右されます。事故対応にあたっては、過失割合をどのように取り決めるかが一つの大きなポイントとなるでしょう。
この記事では、交差点における直進車と右折車の事故での過失割合や賠償金の内訳、損害賠償請求時のポイントや過失割合でお悩みの方の相談先などについて解説します。
ここでは過失割合の目安をご紹介します。まずは「四輪車と四輪車による事故」というケースです。

|
同一道路を対方向から進入 |
過失割合(%) |
||
|
四輪車A |
四輪車B |
||
|
信号機が設置されている |
直進車A、右折車Bともに青で進入 |
20 |
80 |
|
直進車A黄で進入、右折車B青で進入黄で右折 |
70 |
30 |
|
|
直進車A、右折車Bともに黄で進入 |
40 |
60 |
|
|
直進車A赤で進入、右折車B青で進入赤で右折 |
90 |
10 |
|
|
直進車A赤で進入、右折車B黄で進入赤で右折 |
70 |
30 |
|
|
直進車A赤で進入、右折車B青矢印の右折か信号で右折 |
100 |
0 |
|
|
直進車A、右折車Bともに赤で進入 |
50 |
50 |
|
|
信号機が設置されていない |
直進車Aと右折車B |
20 |
80 |

過失割合(%)|【A:40】【B:60】

|
交差道路から進入 |
過失割合(%) |
|||
|
四輪車A |
四輪車B |
|||
|
直進車Aが広路を進行、右折車Bが狭路から広路へ右折:図1 |
20 |
80 |
||
|
直進車Aが優先道路を進行、右折車Bが劣後路から優先道路へ右折:図1 |
10 |
90 |
||
|
交差道路から進入 |
過失割合(%) |
|||
|
四輪車A |
四輪車B |
|||
|
右折車B①が広路・優先路から直進車Aの進行してきた狭路へ右折(対向方向右折):図2 |
60 |
40 |
||
|
80 |
20 |
|||
|
右折車B②が広路・優先路から直進車Aの向かう狭路へ右折(同一方向右折):図2 |
50 |
50 |
||
|
70 |
30 |
|||

過失割合(%)|【A:15】【B:85】
・BがAの対向方向に右折
過失割合(%)|【A:70】【B:30】
・BがAと同一方向に右折
過失割合(%)|【A:60】【B:40】

・Bが中央(左側端)に寄るのに支障なし:図1
過失割合(%)|【A:20】【B:80】
・Bが中央(左側端)に寄るのに支障あり:図2
過失割合(%)|【A:40】【B:60】

過失割合(%)|【A:30】【B:70】
過失割合(%)|【A:40】【B:60】
次は「四輪車と単車による事故」というケースです。

|
信号機が設置されている |
過失割合(%) |
|||
|
単車 |
四輪車 |
|||
|
単車直進、四輪車右折(左図) |
直進車、右折車双方とも青で進入 |
15 |
85 |
|
|
直進黄で進入、右折車青進入黄右折 |
60 |
40 |
||
|
直進車、右折車双方とも黄で進入 |
30 |
70 |
||
|
直進車は赤、右折車は青で進入赤で右折 |
80 |
20 |
||
|
直進車は赤、右折車は黄で進入赤で右折 |
60 |
40 |
||
|
右折車に青矢印による右折可の信号、直進車は赤 |
100 |
0 |
||
|
双方とも赤で進入 |
40 |
60 |
||
|
信号機が設置されていない |
過失割合(%) |
|||
|
単車 |
四輪車 |
|||
|
単車直進、四輪車右折(右図) |
単車直進、四輪車右折 |
15 |
85 |
|

|
信号機が設置されている |
過失割合(%) |
|||
|
単車 |
四輪車 |
|||
|
単車右折、四輪車直進(左図) |
直進車、右折車双方とも青で進入 |
70 |
30 |
|
|
直進黄で進入、右折車青進入黄右折 |
25 |
75 |
||
|
直進車、右折車双方とも黄で進入 |
50 |
50 |
||
|
直進車は赤、右折車は青で進入赤で右折 |
10 |
90 |
||
|
直進車は赤、右折車は黄で進入赤で右折 |
20 |
80 |
||
|
右折車に青矢印による右折可の信号、直進車は赤 |
0 |
100 |
||
|
双方とも赤で進入 |
40 |
60 |
||
|
信号機が設置されていない |
過失割合(%) |
|||
|
単車 |
四輪車 |
|||
|
単車右折、四輪車直進(右図) |
単車右折、四輪車直進 |
70 |
30 |
|

過失割合(%)|【単車:30】【四輪車:70】
過失割合(%)|【単車:20】【四輪車:80】

過失割合(%)|【単車:50】【四輪車:50】
過失割合(%)|【単車:60】【四輪車:40】

|
一方が明らかに広い道路又は優先道路・一方に一時停止標識あり |
過失割合(%) |
||
|
単車 |
四輪車 |
||
|
単車直進、四輪車右折 |
一時停止規制車直進、右折車同一方向右折 |
45 |
55 |
|
一時停止規制車直進、右折車対向方向右折 |
55 |
45 |
|
|
一時停止規制車右折 |
15 |
85 |
|
|
狭路車右折、広路車直進 |
15 |
85 |
|
|
劣後車右折、優先車直進 |
10 |
90 |
|
|
狭路(劣後)車直進 |
60 |
40 |
|
|
狭路(劣後)車直進 |
40 |
60 |
|

|
一方が明らかに広い道路又は優先道路・一方に一時停止標識あり |
過失割合(%) |
||
|
単車 |
四輪車 |
||
|
単車右折、四輪車直進 |
一時停止規制車直進、右折車同一方向右折 |
35 |
65 |
|
一時停止規制車直進、右折車対向方向右折 |
25 |
75 |
|
|
一時停止規制車右折 |
65 |
35 |
|
|
単車右折、四輪車直進 |
狭路車右折、広路車直進 |
65 |
35 |
|
劣後車右折、優先車直進 |
70 |
30 |
|
|
狭路(劣後)車直進 |
20 |
80 |
|
|
狭路(劣後)車直進 |
30 |
70 |
|

過失割合(%)|【単車:20】【四輪車:80】
過失割合(%)|【単車:30】【四輪車:70】
最後に「四輪車と自転車による事故」というケースです。


|
同一道路を対向方向から進入 |
過失割合(%) |
|||
|
四輪車 |
自転車 |
|||
|
信号機 設置あり |
自転車右折、四輪車直進(自転車は道路交通法違反) |
直進車、右折車双方とも青で進入 |
50 |
50 |
|
直進車黄で進入右折車青で進入黄で右折 |
80 |
20 |
||
|
直進車、右折車双方とも黄で進入 |
60 |
40 |
||
|
直進車、右折車双方とも赤で進入 |
70 |
30 |
||
|
自転車直進、四輪車右折 |
直進車、右折車双方とも青で進入 |
90 |
10 |
|
|
直進車黄で進入右折車青で進入黄で右折 |
60 |
40 |
||
|
直進車、双方車とも黄で進入 |
80 |
20 |
||
|
直進車赤で進入右折車青で進入赤で右折 |
30 |
70 |
||
|
直進車赤で進入右折車黄で進入赤で右折 |
50 |
50 |
||
|
直進車赤で進入右折車青矢印で右折可の信号で右折 |
20 |
80 |
||
|
直進車、右折車双方とも赤で進入 |
70 |
30 |
||
|
信号機 設置なし |
自転車直進、四輪車右折 |
90 |
10 |
|
|
自転車右折、四輪車直進(自転車は道交法違反) |
50 |
50 |
||

|
交差道路から侵入 |
過失割合(%) |
|
|
四輪車 |
自転車 |
|
|
自転車直進、四輪車右折 |
80 |
20 |
|
自転車右折、四輪車直進 |
70 |
30 |


|
自転車直進、四輪車右折 |
過失割合(%) |
|||
|
四輪車 |
自転車 |
|||
|
一方が明らかに広い道路 |
広路車直進、狭路車右折(図1) |
90 |
10 |
|
|
狭路車直進、広路車右折(図2) |
対向方向 |
70 |
30 |
|
|
同一方向 |
||||
|
一方が優先道路 |
優先道路進行車直進、非優先側右折(図1) |
90 |
10 |
|
|
優先道路通行車右折、非優先側直進(図2) |
対向方向 |
50 |
50 |
|
|
同一方向 |
60 |
40 |
||
|
一方に一時停止標識あり |
一時停止規制側、直進非規制側右折(図3) |
対向方向 |
60 |
40 |
|
同一方向 |
65 |
35 |
||
|
一時停止規制側右折、非規制側直進(図4) |
90 |
10 |
||


|
自転車右折、四輪車直進 |
過失割合(%) |
|||
|
四輪車 |
自転車 |
|||
|
一方が明らかに広い道路 |
広路車直進、狭路車右折(図5) |
60 |
40 |
|
|
狭路車直進、広路車右折(図6) |
対向方向 |
80 |
20 |
|
|
同一方向 |
70 |
30 |
||
|
一方が優先道路 |
優先道路進行車直進、非優先側右折(図5) |
50 |
50 |
|
|
優先道路通行車、 |
対向方向 |
80 |
20 |
|
|
同一方向 |
70 |
30 |
||
|
一方に一時停止標識あり |
一時停止規制側直進、非規制側右折(図7) |
対向方向 |
80 |
20 |
|
同一方向 |
70 |
30 |
||
|
一時停止規制側右折、非規制側直進(図8) |
65 |
45 |
||

過失割合(%)|【四輪車:90】【自転車:10】
交通事故での損害賠償請求にあたっては、何点か知っておくべきポイントがあります。以下では各ポイントについて解説します。
過失割合は上記の内容に加えて「曲がる際にウインカーを付けていなかった」「徐行をしていなかった」など、具体的な事情も踏まえた上で決められます。このような過失割合に影響を及ぼす要素のことを修正要素と呼び、一例としては以下のようなものがあります。
以下のいずれかに当てはまる際、5~20%の範囲で過失割合が修正される場合があります。
|
修正要素 |
概要 |
|
早回り右折 (右折車に加算) |
交差点中心の直近の内側を通過せずに右折すること。 |
|
大回り右折 (右折車に加算) |
右折前に道路中央に寄らずに右折すること。 |
|
直近右折 (右折車に加算) |
右折前に直進車が交差点に侵入しており、直進車が近くにいる状態で右折すること。 |
|
既右折 (右折車が減算) |
右折車が右折を終了した状態で直進車とぶつかること。 |
|
明らかな先入り (狭路車が減算) |
先に狭路車が交差点に侵入している状態で広路車とぶつかること。 |
|
合図なし (合図無しの車に加算) |
右左折する前にウインカーを付けないこと。 |
|
徐行なし (徐行無しの車に加算) |
徐行が必要な状況で徐行しないこと。 |
事故被害者は自身が負った損害を相手に請求することになりますが、その際に請求できる金額は過失割合によって大きく変わります。過失割合で100:0とならないケースは珍しいことではありません。当事者双方に過失がある場合は「相手側の過失割合分」しか請求することができません。
例として「事故によって自身が200万円の損害を被った」と仮定します。この場合、相手の過失割合が100%であれば損害分200万円を全額請求できます。一方、相手の過失割合が50%という場合、損害分の50%にあたる100万円しか請求できず、残りの100万円については自身が負担しなければなりません。
特に損害の大きいケースでは、過失割合が変わることで動く金額も大きくなります。過失割合の交渉を有利に進められるかどうかで得られる結果も大きく変わりますので、もし不安な場合は弁護士のサポートを得ることも検討すべきでしょう。
事故の相手と示談が成立した場合、それは双方が損害賠償について合意したということを意味します。したがって、あとになってから示談のやり直しを一方的に求めたところで、基本的に認められることはありません。
相手によっては示談成立を急かしてくることもあるかもしれませんが、安易に応じることは避け、納得のいくまで交渉を重ねましょう。また詳しくは「交差点事故で請求できる賠償金の内訳」で後述しますが、交通事故で請求できる賠償金はさまざまなものがありますので、請求漏れや計算ミスなどにも注意が必要です。
事故の相手に請求できる賠償金としては、慰謝料・消極損害・積極損害があります。以下で賠償金の内訳について確認していきましょう。
慰謝料には入通院慰謝料・後遺障害慰謝料・死亡慰謝料の3種類があり、どれを請求できるかは被害状況によって異なります。また慰謝料の計算にあたっては以下のような基準があり、なかでも弁護士基準が高額になりやすい傾向にあります。
|
交通事故慰謝料の計算基準 |
|
|
自賠責保険で用いる基準 |
|
|
加入先保険会社が独自で用いる基準 |
|
|
裁判所での判例をもとにした基準 |
|

事故に遭って入院・通院した場合に請求できるのが入通院慰謝料です。治療にかかった期間・入院や通院した日数などに応じて算出され、計算基準ごとの計算式としては以下の通りです。
なお弁護士基準については「客観的にみて症状を確認できるかどうか(他覚症状の有無)」で請求すべき金額が変わる可能性があります。
|
自賠責基準の計算式 |
|
※①・②のうち少ない額が適用されます。



事故の怪我について治療を尽くしたものの完治せず、後遺症が残って後遺障害等級が認定された場合に請求できるのが後遺障害慰謝料です。症状の重さによって等級は決められ、以下のように等級の高さに応じて請求額が異なります。
|
等級 |
自賠責基準 (2020年3月31日までに発生した事故) |
任意保険基準(推定) |
弁護士基準 |
|
1,150万円 (1,100万円) |
1,600万円程度 |
2,800万円 |
|
|
998万円 (958万円) |
1,300万円程度 |
2,370万円 |
|
|
861万円 (829万円) |
1,100万円程度 |
1,990万円 |
|
|
737万円 (712万円) |
900万円程度 |
1,670万円 |
|
|
618万円 (599万円) |
750万円程度 |
1,400万円 |
|
|
512万円 (498万円) |
600万円程度 |
1,180万円 |
|
|
419万円 (409万円) |
500万円程度 |
1,000万円 |
|
|
331万円 (324万円) |
400万円程度 |
830万円 |
|
|
249万円 (245万円) |
300万円程度 |
690万円 |
|
|
190万円 (187万円) |
200万円程度 |
550万円 |
|
|
136万円 (135万円) |
150万円程度 |
420万円 |
|
|
94万円 (93万円) |
100万円程度 |
290万円 |
|
|
57万円 |
60万円程度 |
180万円 |
|
|
32万円 |
40万円程度 |
110万円 |
事故に遭って被害者が亡くなってしまった場合に請求できるのが死亡慰謝料です。被害者の家族構成・生前の家庭内での立場などに応じて算出され、計算基準ごとの請求額としては以下の通りです。
|
請求する要項 |
慰謝料額 |
|
死者本人に対する慰謝料 |
400万円(2020年4月1日以前に発生した事故に関しては350万円) |
|
死亡者に扶養されていた場合(※) |
200万円 |
|
慰謝料を請求する遺族が1人の場合 |
550万円 |
|
慰謝料を請求する遺族が2人の場合 |
650万円 |
|
慰謝料を請求する遺族が3人の場合 |
750万円 |
※遺族が死亡した被害者本人に扶養されていた場合のみ200万円が加算されます。(遺族が1人で扶養されている場合:400万円+200万円+550万円=1,150万円)
|
死亡者の立場 |
任意保険基準(推定) |
弁護士基準 |
|
一家の支柱 |
1,500万~2,000万円 |
2,800万円 |
|
配偶者、母親 |
1,500万~2,000万円 |
2,500万円 |
|
上記以外 |
1,200万~1,500万円 |
2,000万~2,500万円 |
消極損害とは事故によって失ってしまった将来分の収入のことを呼び、休業損害・後遺障害逸失利益・死亡逸失利益の3種類があります。こちらも慰謝料と同様、被害状況によって請求できるものは異なります。
事故に遭って仕事を休まざるをえなくなり、普段通り働いていれば受け取れたであろう収入が受け取れなくなった場合に請求できるのが休業損害です。被害者の収入や仕事を休んだ期間などに応じて算出され、会社勤めの方に限らず専業主婦・就職活動中などの方でも請求可能です。
|
休業損害=1日あたりの基礎収入(※)×休業日数 |
※会社員・アルバイトなどの場合:「直近3ヵ月の収入÷90」
※自営業・個人事業主などの場合:「(前年度の所得+固定費)÷365」
事故の怪我について治療を尽くしたものの完治せず、後遺症が残って後遺障害等級と認定された場合に請求できるのが後遺障害逸失利益です。収入・等級の高さ・年齢などに応じて算出され、計算式は以下の通りです。
|
後遺障害逸失利益=基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数 |
※基礎収入:事故前の被害者の年収
※労働能力喪失率:後遺障害による労働能力喪失の割合をパーセンテージで表したもの
※労働能力喪失期間:後遺症により労働能力が失われたと評価できる期間
※ライプニッツ係数:将来付与分の利息を割り引く際の係数
事故に遭って被害者が亡くなってしまった場合に請求できるのが死亡逸失利益です。収入・生前の家庭内での立場などに応じて算出され、計算式は以下の通りです。
|
死亡逸失利益=基礎収入額×(1-生活費控除率)×中間利息控除係数 |
※生活費控除率:生存していた場合に生活のために支出したものと考えられる一定割合(実際には調整的意味合いが強い)
積極損害とは事故が原因で被害者が支払った費用のことを呼びます。費用ごとの請求額については被害状況に応じてそれぞれ異なりますが、ここでは一例をまとめて紹介します。
|
項目 |
内容 |
|
修理代 |
事故で傷ついた車両を修理する際に支払った費用 |
|
治療費 |
病院で治療を受けるにあたって支払った費用 |
|
入院雑費 |
日用品雑貨・電話代・テレビカード代など、入院時に支払った諸雑費 |
|
通院費用 |
通院のために電車・バス・タクシーなどを利用した際に支払った費用 |
|
付添看護費 |
事故が原因で介護や介助が必要な場合に請求可能な項目 |
|
将来の看護費 |
事故が原因で後遺症が残り、今後介護が必要と見込まれる場合に請求可能な項目 |
|
児童の学費等 |
入院などによって勉学が遅れてしまい、遅れ分を回収するために支払った学費など |
|
葬儀関係費 |
葬儀を行うにあたって支払った費用 |
弁護士は、交通事故の被害者のためにさまざまなサポートを行っています。以下では、弁護士への依頼をおすすめする理由や実際の解決事例などを紹介します。
なお以下の各項目で紹介する解決事例は、当サイトに掲載している弁護士の解決事例を簡略化したものです。
過失割合を取り決めるには、事故態様や修正要素などを評価・検討しなければなりません。記事内では過失割合の目安を紹介しましたが、実際のところはケースに応じての判断となりますので、交通事故に関する知識を持っていない素人では判断が難しいでしょう。
弁護士に依頼すれば、交通事故の知識を活かして過去の裁判例なども参考にしながら、妥当な過失割合を判断してもらえます。また相手から極端に不利な内容を提示されているようなケースでは、弁護士が介入して交渉することで過失割合を引き下げられる可能性もあります。
タクシーに乗っていた被害者が車両事故に巻き込まれ、右距骨背内側骨折骨軟骨骨折や右距骨壊死などの怪我を負った事例です。この事故で被害者は後遺障害等級12級の認定を受け、相手保険会社からは賠償金:約460万円、被害者の過失割合:20%を提示されていました。
まず弁護士は依頼内容と状況が似た判例を探し、それをもとに交渉を進めた結果、過失割合を5%にまで下げることに成功しました。そして入通院慰謝料・後遺障害慰謝料・後遺障害逸失利益などの各損害を改めて算出して請求し、約1,050万円にまで増額することができました。
賠償金のうち慰謝料は、弁護士基準で請求することによって高額になりやすい傾向にあります。弁護士基準で請求する際、十分な法律知識がなければ相手保険会社から対応を渋られることも多々あるようですが、弁護士に依頼すれば速やかに応じてもらえる可能性が高まります。
入通院慰謝料を例にとると、以下のように弁護士基準で請求することで金額が倍増する可能性もあります。
|
通院期間 |
自賠責基準(※1) |
任意保険基準(推定) |
弁護士基準(※2) |
|
1ヶ月間 |
8万6,000円 (8万4,000円) |
12万6,000円 |
28(19)万円 |
|
2ヶ月間 |
17万2,000円 (16万8,000円) |
25万2,000円 |
52(36)万円 |
|
3ヶ月間 |
25万8,000円 (25万2,000円) |
37万8,000円 |
73(53)万円 |
|
4ヶ月間 |
34万4,000円 (33万6,000円) |
47万8,000円 |
90(67) 万円 |
|
5ヶ月間 |
43万円 (42万円) |
56万8,000円 |
105(79) 万円 |
|
6ヶ月間 |
51万6,000円 (50万4,000円) |
64万2,000円 |
116(89) 万円 |
※1: 初診から治療終了日を21日とし実際の通入院は10日間だったと仮定し、2020年3月31日までは4,200円、2020年4月1日より後に発生した事故に関しては4,300円で計算しています。
※2:()内はむちうち等の他覚症状がない負傷の慰謝料
停車中の被害者が加害者の車両に追突され、腰椎捻挫や頚椎捻挫などの怪我を負った事例です。この事故で被害者は後遺障害等級14級の認定を受け、相手保険会社からは賠償金として約170万円を提示されていました。
依頼を受けた弁護士が賠償金の内訳について弁護士基準と比較したところ、入通院慰謝料と後遺障害慰謝料は各25万円ほど、後遺障害逸失利益は70万円低額であることがわかりました。そこで弁護士基準に直した金額で交渉を進めていった結果、こちらの請求が認められて約292万円に増額することに成功しました。
交通事故では過失割合の取り決めが一つのポイントとなりますが、事故後に必要な手続きはそれだけではありません。まず各損害を算出して相手への請求額を確定する必要がありますし、後遺症が残った際は後遺障害等級の申請なども検討することになります。
しかし弁護士であれば、依頼者の代わりに事故手続きをすべて対応してくれます。依頼後は弁護士が対応窓口となってくれますので、相手方と顔を合わせる必要もありません。依頼者は面倒な事故手続きから解放され、生活の立て直しに集中できます。
自動車運転中の被害者が、センターラインを越えてきた加害者の車両と正面衝突し、TFCC損傷などの怪我を負った事例です。この事故で、相手保険会社からは賠償金として約80万円を提示されていました。また後遺症が残ったことから後遺障害申請を行ったものの、結果は非該当とのことでした。
まず弁護士は治療状況や症状に関する資料を取り寄せて、後遺障害等級の認定結果について異議申立てを行った結果、14級へと判断が覆りました。それを受けて後遺障害慰謝料・後遺障害逸失利益を請求したところ主張が認められ、最終的に約300万円にまで増額することに成功しました。
交通事故で支払われる賠償金には相場がありません。また過失割合についてもケースバイケースでの判断となるため、少しでも納得のいく形で示談を済ませるには交通事故問題に注力する弁護士のサポートを得るのが効果的でしょう。
また事務所によっては無料相談なども実施しています。相談後に契約を迫られるようなこともありませんので、「適切な額の賠償金を受け取りたい」「事故対応を代わってもらいたい」などの方はお気軽にご相談ください。
弁護士に相談するかお悩みの方へ
下のボタンからあなた当てはまるものを選んで悩みを解消しましょう。
弁護士費用特約があれば 実質0円で依頼できます!

多くの保険会社では、被害者1名につき最大300万円までの弁護士費用を負担してくれます。特約があるか分からない方でも、お気軽にご相談ください。弁護士と一緒にご確認した上で依頼の有無を決めて頂けます。
特約を利用して弁護士に相談する交通事故問題を依頼する弁護士の選び方にはポイントがあります。
等です。
詳しくは以下の記事を読んで、正しい弁護士の選び方を理解した上で弁護士に相談しましょう。
弁護士の選び方について詳しくみる
【人身事故被害者の方へ】事故直後・通院中いずれの場合もまずはご相談ください。弁護士への依頼で、結果が大きく変わるかもしれません。【初回面談無料】【着手金無料プランあり】【オンラインで全国対応可能】
事務所詳細を見る
【来所不要・交通事故の被害者は初回相談料0円】◆豊富な解決実績◆示談金の大幅な増額実績多数◆交通事故専門チームが丁寧に対応します。まずは無料でご相談ください。【「立川」駅北口より徒歩6分】
事務所詳細を見る
【相談料/着手金0円&電話相談◎】賠償額が妥当か判断してほしいならご相談を!交渉での解決で早期解決と負担軽減を目指します|来所せずに電話で依頼完了!|弁護士費用特約に対応|土日祝
事務所詳細を見る
交通事故トラブルに巻き込まれ、車の修理費や慰謝料はいくらくらいもらえるのか知りたいものの、詳細などがわからず、踏みとどまっている方も多いのではないでしょうか。本...
「追い抜き事故を起こしてしまった…過失割合はどうなるのだろう」と気になる方は、追い越し事故なのかを確認することをおすすめします。本記事では、追い越し事故のケース...
交通事故の過失割合が8対2の場合は、被害者が支出した修理代のうち、2割を被害者が自己負担しなければなりません。 本記事では、交通事故の過失割合が8対2の場合に...
一時停止無視による事故に巻き込まれてしまったため、過失割合や罰則、違反点数の扱いがどうなるのか不安な方も多いのではないでしょうか。本記事では、一時停止無視による...
交通事故による修理費請求は、加害者側と交渉しなければならないケースがほとんどです。そのため、早い段階で弁護士に相談して、交渉をスムーズに進めるのがおすすめです。...
交通事故の相手方が過失を認めない場合の対処法、過失割合の決め方や注意点、相手方との交渉にあたって準備しておくこと、相手方との交渉を弁護士に依頼するメリットなどに...
交通事故の過失割合が9対1というケースでは、1の過失が認められた被害者側は得られる賠償金の額が減ってしまうため、納得いかない方も多いでしょう。本記事では、交通事...
交通事故に遭った場合、過失割合によって損害賠償額は大きく変わります。そのため、自身に過失がないときは、過失割合10対0を主張することが大切です。本記事では、交通...
交通事故の過失割合は、弁護士に交渉してもらうことで変わる可能性があります。自分の過失割合を下げることができれば、慰謝料増額につながります。本記事では、弁護士が交...
バック事故の過失割合の解説だけでなく、『過失割合』と『損害賠償金の関係』、『よくあるトラブルと対処法』などを紹介していきます。
交通事故の損害賠償では過失割合も重要な要素です。そこで交通事故の被害者になってしまった人に向けて、過失割合の基本や決め方、注意点などを解説します。また、過失割合...
先頭の車に非がないことはなんとなく想像がつきますが、2台目、3台目の車に乗っていた運転手にはどういった過失割合が定められるのか、また、損害賠償は誰に請求すればい...
交通事故のうち3割は駐車場で起こっているといわれています。駐車場は私有地になるため、事故が起こったあとの対処が一般道路とは異なる部分があります。本記事では、駐車...
過失相殺を決める際、警察が行う現場検証の実況見分調書が最重要資料となります。この過失相殺について、その意義や過失相殺後の補償金に納得がいかない時、弁護士に相談す...
自転車事故の過失割合(じてんしゃじこのかしつわりあい)とは、自転車事故の当事者間におけるお互いの不注意(過失)の程度を数値化したものです。
バック事故の過失割合の解説だけでなく、『過失割合』と『損害賠償金の関係』、『よくあるトラブルと対処法』などを紹介していきます。
巻き込み事故(まきこみじこ)とは、主に交差点を右左折する自動車が、交差点を直進しようとした二輪車(バイクや自転車)と接触した場合の交通事故のことを言います。
子供の飛び出し事故の過失(責任)を判断する基準は、明確には決められておらず、事故当時に状況によって考えていく必要があります。この記事では、状況別の過失割合や損害...
追突事故の過失割合は「被害者0:加害者100」と判断されるケースが一般的です。ただし、被害者の立場でも絶対に過失を問われないとは限りません。本記事では、追突事故...
横断歩道の横断中に交通事故に遭った場合、多くのケースでは歩行者より自動車の過失割合が高くなります。この記事では、歩行者と自動車の過失割合についてご紹介します。
後遺障害診断書は後遺障害認定を受けるために必須の書類です。しかし、医師が診断書を書いてくれないトラブルが時折生じます。この記事では、医師が後遺障害診断書の作成を...
被害者なのに損害賠償責任を負うことになる無過失責任。そうならない為の対策などをご紹介していきます。
アイスバーン(路面凍結)や雨などで車がスリップしてしまい、交通事故に巻き込まれた場合、過失割合はどのように変化するのでしょうか。この記事では、状況別の過失割合や...
信号無視の事故で被害者となってしまった場合の過失割合の算定方法について記載します。
交通事故トラブルに巻き込まれ、車の修理費や慰謝料はいくらくらいもらえるのか知りたいものの、詳細などがわからず、踏みとどまっている方も多いのではないでしょうか。本...
飛び出し事故によって死亡した場合、被害者にも一定の過失が認められる可能性があります。請求可能な賠償金としては死亡慰謝料や死亡逸失利益などがありますが、過失割合に...
交通事故による修理費請求は、加害者側と交渉しなければならないケースがほとんどです。そのため、早い段階で弁護士に相談して、交渉をスムーズに進めるのがおすすめです。...
サンキュー事故(さんきゅーじこ)とは、優先権のある車両が優先権のない車両に通行を優先させた際に起きる交通事故で、対向車が右折時に直進車と同方向の左側を通過する二...
自転車事故の過失割合(じてんしゃじこのかしつわりあい)とは、自転車事故の当事者間におけるお互いの不注意(過失)の程度を数値化したものです。
「信号機の有無」や「事故の相手がバイク」など、右直事故での過失割合はケースごとに大きく変わります。また場合によっては、過失割合が加算・減算されるケースもあります...
一時停止無視による事故に巻き込まれてしまったため、過失割合や罰則、違反点数の扱いがどうなるのか不安な方も多いのではないでしょうか。本記事では、一時停止無視による...
横断歩道の横断中に交通事故に遭った場合、多くのケースでは歩行者より自動車の過失割合が高くなります。この記事では、歩行者と自動車の過失割合についてご紹介します。